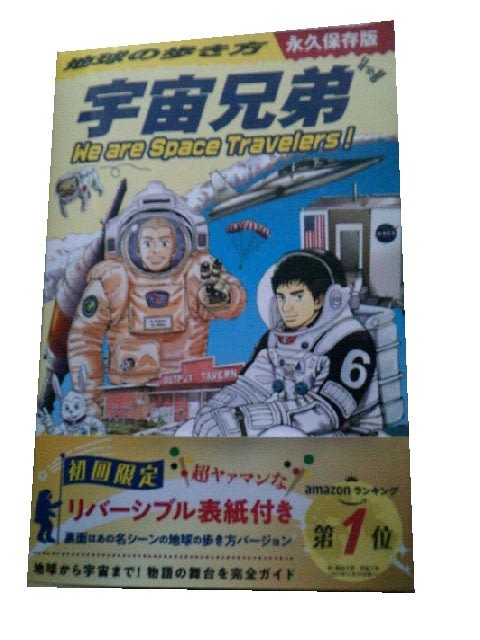世界で初めて月の裏側から持ち帰った試料を分析して明らかにしたでつ。
月の起源を解明する上で重要な手掛かりになるでつ。
月裏側の南半球にかけて広がる南極エイトケン盆地の一角に着陸。
土壌サンプルや岩石を採取。
この盆地は40億年以上前に巨大な隕石が衝突してできたとされ、月内部が最も深くまで
えぐられた場所として知られるでつ。。
研究チームは、持ち帰った試料のうち、月のマントルの一部が溶けてできた玄武岩を調べたでつ。
水分量を分析したところ、1グラム当たり1〜1.5マイクログラムと推定できたでつ。
米航空宇宙局によるアポロ計画などで月の表側から持ち帰った玄武岩に含まれる水分量は、
1グラム当たり1〜200マイクログラムだったでつ。
月は表側と裏側で地形や地質などが大きく異なる二分性と呼ばれる特徴を持つでつ。
月が形成される過程と深く関係していると考えられているでつ。
月裏側の他の場所から採取した試料も分析しなければならないでつが、月のマントルに含まれる水分量にも二分性が
ある可能性が示唆されたでつ。
研究チームは今後、月の表側と裏側とで水分量に違いがみられた要因を詳しく調べるでつ。
今回の成果について、月の裏側を代表するデータなのか慎重に見る必要はあるでつが、
月の二分性を巡る議論を活発にする貴重な成果。
月の謎も解明されていくでつなぁ~