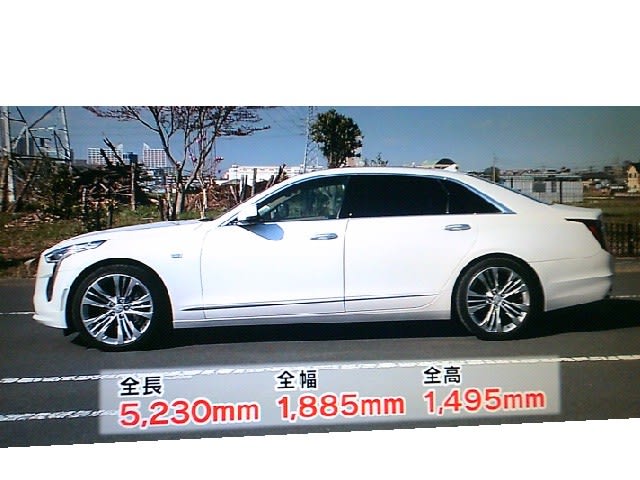この間、車検の時に代車を用意していただいたのが、ホンダのフィット。
走りのホンダということと久々のホンダサウンドを期待。
だけど80年代のような加速時のフィールもサウンドも全くなかったでつ。
静かな感じというか…
なんとなくホンダ車の乗ってる高揚感がなかったでつ。
ホンダ車の最近のインプレ見ると静かさを強調されてるでつ。
次期新車を購入するにあたっては、基準は今のマイカー カムリが基準。
燃費と走りを両立した車となるとホンダのアコードかインサイドということになるでつ。
車格的には、インサイトにはなるでつ。
だけど、パワーでは明らかにカムリ。
インサイトはプリウス基準だから、プリウスよりは数段上だけど、ちょっと中途半端。
1.5Lのエンジンでは車体が重たい分パワーウエイトレシオ的にカムリより不利だから
実燃費も怪しい…
そうなるとアコードとなるでつ。
性能ではカムリと互角かそれ以上ではあるんだけど…
アコードはとかくデカクて価格が高い。
車幅の1860は何とかなるにしても、全長4900はカムリWSと同じサイズ。
カムリの4885より15ミリだけど、この大きさで15ミリは微妙。
そいとインサイトはまだエンジンとモータのハイブリット走行はあるけど
アコードは完全にモータとエンジンが分かれているでつ。
相当な回転数を上げないとエンジンがかからない…
ということはホンダサウンドがおがめない…
静かなホンダ車に乗るのはクリープを入れないコーヒーみたいなもの…
だけどハリアに450万出すなら、アコードの465万は安い。
まぁ~インサイトもカムリと同価格帯だけど、走りの性能を考えると
カムリが数段上だから同じ価格で買うと損する感じがするでつ。
そりならシビックとなるけど…
ハッチバックはなぁ~となるでつ。
ホンダ車となると今の日本のラインアップから考えると駒不足というとこでつ。
まぁ~カムリのローンが後1年あるからじっくりと考えてというとこなんだけど…
ただ今のホンダ車には走りのスピリッツがないのが残念だなぁ~
あの吹き上がりの良さとサウンドがホンダ車の一番の魅力。
NーBOXが売れてるのも他の軽より走りがいいからなんでつなぁ~
そいとホンダもトヨタもセダンも含めてたけど、販売価格が高すぎる感じ。
こりも改善しないと…
同じ価格帯や若干の価格差なら欧州車へ流れてしまうでつ。
う~ん…
カムリに匹敵する走りと燃費、価格を考えるとホンダ車では役不足だなぁ~
かつてのホンダならトヨタより数段上の車が多かったんだけどなぁ~
走りのホンダということと久々のホンダサウンドを期待。
だけど80年代のような加速時のフィールもサウンドも全くなかったでつ。
静かな感じというか…
なんとなくホンダ車の乗ってる高揚感がなかったでつ。
ホンダ車の最近のインプレ見ると静かさを強調されてるでつ。
次期新車を購入するにあたっては、基準は今のマイカー カムリが基準。
燃費と走りを両立した車となるとホンダのアコードかインサイドということになるでつ。
車格的には、インサイトにはなるでつ。
だけど、パワーでは明らかにカムリ。
インサイトはプリウス基準だから、プリウスよりは数段上だけど、ちょっと中途半端。
1.5Lのエンジンでは車体が重たい分パワーウエイトレシオ的にカムリより不利だから
実燃費も怪しい…
そうなるとアコードとなるでつ。
性能ではカムリと互角かそれ以上ではあるんだけど…
アコードはとかくデカクて価格が高い。
車幅の1860は何とかなるにしても、全長4900はカムリWSと同じサイズ。
カムリの4885より15ミリだけど、この大きさで15ミリは微妙。
そいとインサイトはまだエンジンとモータのハイブリット走行はあるけど
アコードは完全にモータとエンジンが分かれているでつ。
相当な回転数を上げないとエンジンがかからない…
ということはホンダサウンドがおがめない…
静かなホンダ車に乗るのはクリープを入れないコーヒーみたいなもの…
だけどハリアに450万出すなら、アコードの465万は安い。
まぁ~インサイトもカムリと同価格帯だけど、走りの性能を考えると
カムリが数段上だから同じ価格で買うと損する感じがするでつ。
そりならシビックとなるけど…
ハッチバックはなぁ~となるでつ。
ホンダ車となると今の日本のラインアップから考えると駒不足というとこでつ。
まぁ~カムリのローンが後1年あるからじっくりと考えてというとこなんだけど…
ただ今のホンダ車には走りのスピリッツがないのが残念だなぁ~
あの吹き上がりの良さとサウンドがホンダ車の一番の魅力。
NーBOXが売れてるのも他の軽より走りがいいからなんでつなぁ~
そいとホンダもトヨタもセダンも含めてたけど、販売価格が高すぎる感じ。
こりも改善しないと…
同じ価格帯や若干の価格差なら欧州車へ流れてしまうでつ。
う~ん…
カムリに匹敵する走りと燃費、価格を考えるとホンダ車では役不足だなぁ~
かつてのホンダならトヨタより数段上の車が多かったんだけどなぁ~