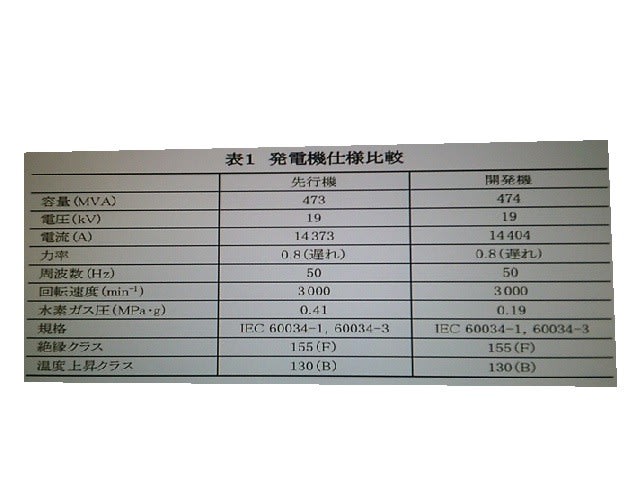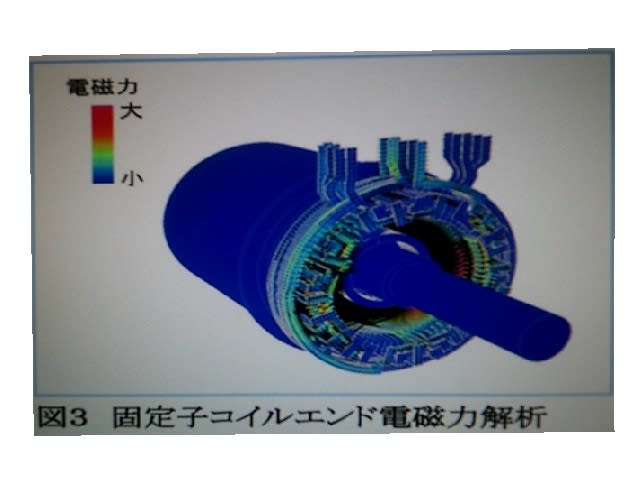主要国が温室効果ガスのカーボンニュートラル(排出実質ゼロ)を打ち出し、世界が脱炭素に向け大きく動き出したでつ。
目標達成には電源の脱炭素技術が鍵を握るでつ。
技術開発の最新動向が、どう進んでいるかということでつ。
国土の4分の1が海抜ゼロメートルのオランダは、温暖化によって極地の氷が溶ければ国土の一部が消失しかねないでつ。
脱炭素への関心は高く、温室効果ガス排出削減に向けて、新たなプロジェクトが動き出しているでつ。

最北部フローニンゲン州にあるエームスハーヴェン地区は、エムス川の河口付近に位置する港で、数多くの風力発電の風車が立ち並ぶでつ。
オランダのマグナム発電所は、天然ガスを燃料とする火力発電所で、発電設備が3系列あり、そのうちの1系列を2027年に
100%水素で運用する計画を進めているでつ。
重要な役割を担うのが大型ガスタービン技術。
火力発電は石炭、天然ガスなどの化石燃料を燃やし、蒸気やガスでタービンを回転させて発電するでつが、その過程では
大量の二酸化炭素を発生するでつ。
そこで注目されているのが、燃やしてもCO2を排出しない水素を燃料とするガスタービン。
1990年代から国の水素利用の研究に参画し、開発を進めてきたでつ。
2015年頃に欧州の電力会社からの問い合わせが増え、本格的に実用化に乗り出したでつ。
水素発電でも基礎となる高効率なガスタービン開発が重要。
高砂工場に、次世代ガスタービン・コンバインド・サイクル発電の実証設備を完成し、稼働させたでつ。
発電効率は64%台で世界最高水準を誇るでつ。
その実現の源泉は高砂工場にあるでつ。
約92万平方メートルにも及ぶ工場内には研究開発、設計、製造、実証の施設があり、約1000人が働いているでつ。
世界でガスタービンの開発・設計、製造、実証を三位一体で行えるのは高砂工場だけでつ。
すぐに実証発電設備で検証できるでつ。
三位一体の検証で高い信頼性を確立しているのが強み。
試験設備などをそろえるには多額の投資が必要な上、使いこなすまでにはかなりの時間を要するでつ。
計測ノウハウも必要で高砂工場には30~40年の経験を持つベテランも少なくないでつ。
中国や韓国メーカーが参入できない理由がここにあるでつ。
現在、力を入れているのが水素ガスタービンの開発。
既存の火力発電所を大規模に改修するのでは多額のコストがかかり、水素発電への転換が進まないでつ。
このため「燃焼器だけを交換する形にしているでつ。
現在は3つのタイプの燃焼器の開発を進めているでつ。
マグナム発電所に導入を目指しているのは「拡散燃焼方式」と呼ばれるタイプ。
水素と空気を別々に燃焼器内に噴射するこの方式は、窒素酸化物(NOx)の発生が増え、
それを抑える対策が必要となるが、既に100%水素だけで燃焼させる試験に成功しているでつ。
あらかじめ燃料と空気を混合して燃焼器に入れる「予混合燃焼方式」を採用すれば、NOxを低減できるでつが、
燃焼器内の火炎が投入される燃料を伝って逆戻りする「逆火」が起こりやすくなるでつ。
水素は燃焼速度が速く、燃焼器に水素を投入すると火炎の進む速度が空気の流体の速度よりも速くなるため。
逆火によって燃料を供給するノズルまで火が達してしまうと、ノズルが破損する恐れが高まるでつ。
このため、燃焼器内の燃料や空気の流れを変えるため、燃料を供給するノズルの形状を改良。
これによりノズルの中心部にできる流速の遅い部分を解消し、逆火を防止できるようになったでつ。
天然ガスに水素を30%混焼するタイプではこの予混合燃焼器を採用。
18年に燃焼試験を終えたこのタイプは70万キロワット相当の出力に対応し、従来のコンバインドサイクル型の
ガス火力と比べ、発電時のCO2排出量を約10%削減できるでつ。
こうした環境性能が認められ、米国で水素ガスタービン2台の受注が決まっているでつ。
さらに現在、開発を進めているのが水素だけを燃料にできるタイプ。
数多くのノズルがついた「マルチクラスター型」で、それぞれのノズルの穴を小さくして安定的な燃焼を実現。
2025年3月に燃焼試験の完了を目指しているでつ。
水素ガスタービンへの関心は高まってて、数十件の話が来ているでつ。
商談件数は20年1月に比べ、10月には約3割増えたでつ。
石炭火力の転換を進める米国で需要が高く、欧州でも改造工事が多いでつ。
今後は日本や東南アジア、中東での需要増も見込んでいるでつ。
水素だけでなく、やはりCO2を排出しないアンモニアを燃料としたガスタービンの開発にも着手したでつ。
火力発電の脱炭素化のトップランナーとしての地歩を固める構えでつ。
さらに、水素の製造や輸送・貯蔵、利用の技術を磨き、エコシステムの構築に取り組むでつ。
発電所から発生するCO2を回収し、輸送・貯蔵、燃料に転換利用する事業の拡大も目指しているでつ。
原子力発電も脱炭素に貢献する技術と捉え、世界最高水準の次世代軽水炉の30年代後半の投入を計画。
火力発電の脱炭素化と水素・CO2エコシステムの構築を同時並行で迅速に推進するでつ。
技術開発を強化し、世界の脱炭素化を後押しするでつ。
水素ガスタービンがこりから世界の主流になるでつ。
この技術だけは国産でやってほしいでつ。
技術の海外流出は避けてほしいでつ。
目標達成には電源の脱炭素技術が鍵を握るでつ。
技術開発の最新動向が、どう進んでいるかということでつ。
国土の4分の1が海抜ゼロメートルのオランダは、温暖化によって極地の氷が溶ければ国土の一部が消失しかねないでつ。
脱炭素への関心は高く、温室効果ガス排出削減に向けて、新たなプロジェクトが動き出しているでつ。

最北部フローニンゲン州にあるエームスハーヴェン地区は、エムス川の河口付近に位置する港で、数多くの風力発電の風車が立ち並ぶでつ。
オランダのマグナム発電所は、天然ガスを燃料とする火力発電所で、発電設備が3系列あり、そのうちの1系列を2027年に
100%水素で運用する計画を進めているでつ。
重要な役割を担うのが大型ガスタービン技術。
火力発電は石炭、天然ガスなどの化石燃料を燃やし、蒸気やガスでタービンを回転させて発電するでつが、その過程では
大量の二酸化炭素を発生するでつ。
そこで注目されているのが、燃やしてもCO2を排出しない水素を燃料とするガスタービン。
1990年代から国の水素利用の研究に参画し、開発を進めてきたでつ。
2015年頃に欧州の電力会社からの問い合わせが増え、本格的に実用化に乗り出したでつ。
水素発電でも基礎となる高効率なガスタービン開発が重要。
高砂工場に、次世代ガスタービン・コンバインド・サイクル発電の実証設備を完成し、稼働させたでつ。
発電効率は64%台で世界最高水準を誇るでつ。
その実現の源泉は高砂工場にあるでつ。
約92万平方メートルにも及ぶ工場内には研究開発、設計、製造、実証の施設があり、約1000人が働いているでつ。
世界でガスタービンの開発・設計、製造、実証を三位一体で行えるのは高砂工場だけでつ。
すぐに実証発電設備で検証できるでつ。
三位一体の検証で高い信頼性を確立しているのが強み。
試験設備などをそろえるには多額の投資が必要な上、使いこなすまでにはかなりの時間を要するでつ。
計測ノウハウも必要で高砂工場には30~40年の経験を持つベテランも少なくないでつ。
中国や韓国メーカーが参入できない理由がここにあるでつ。
現在、力を入れているのが水素ガスタービンの開発。
既存の火力発電所を大規模に改修するのでは多額のコストがかかり、水素発電への転換が進まないでつ。
このため「燃焼器だけを交換する形にしているでつ。
現在は3つのタイプの燃焼器の開発を進めているでつ。
マグナム発電所に導入を目指しているのは「拡散燃焼方式」と呼ばれるタイプ。
水素と空気を別々に燃焼器内に噴射するこの方式は、窒素酸化物(NOx)の発生が増え、
それを抑える対策が必要となるが、既に100%水素だけで燃焼させる試験に成功しているでつ。
あらかじめ燃料と空気を混合して燃焼器に入れる「予混合燃焼方式」を採用すれば、NOxを低減できるでつが、
燃焼器内の火炎が投入される燃料を伝って逆戻りする「逆火」が起こりやすくなるでつ。
水素は燃焼速度が速く、燃焼器に水素を投入すると火炎の進む速度が空気の流体の速度よりも速くなるため。
逆火によって燃料を供給するノズルまで火が達してしまうと、ノズルが破損する恐れが高まるでつ。
このため、燃焼器内の燃料や空気の流れを変えるため、燃料を供給するノズルの形状を改良。
これによりノズルの中心部にできる流速の遅い部分を解消し、逆火を防止できるようになったでつ。
天然ガスに水素を30%混焼するタイプではこの予混合燃焼器を採用。
18年に燃焼試験を終えたこのタイプは70万キロワット相当の出力に対応し、従来のコンバインドサイクル型の
ガス火力と比べ、発電時のCO2排出量を約10%削減できるでつ。
こうした環境性能が認められ、米国で水素ガスタービン2台の受注が決まっているでつ。
さらに現在、開発を進めているのが水素だけを燃料にできるタイプ。
数多くのノズルがついた「マルチクラスター型」で、それぞれのノズルの穴を小さくして安定的な燃焼を実現。
2025年3月に燃焼試験の完了を目指しているでつ。
水素ガスタービンへの関心は高まってて、数十件の話が来ているでつ。
商談件数は20年1月に比べ、10月には約3割増えたでつ。
石炭火力の転換を進める米国で需要が高く、欧州でも改造工事が多いでつ。
今後は日本や東南アジア、中東での需要増も見込んでいるでつ。
水素だけでなく、やはりCO2を排出しないアンモニアを燃料としたガスタービンの開発にも着手したでつ。
火力発電の脱炭素化のトップランナーとしての地歩を固める構えでつ。
さらに、水素の製造や輸送・貯蔵、利用の技術を磨き、エコシステムの構築に取り組むでつ。
発電所から発生するCO2を回収し、輸送・貯蔵、燃料に転換利用する事業の拡大も目指しているでつ。
原子力発電も脱炭素に貢献する技術と捉え、世界最高水準の次世代軽水炉の30年代後半の投入を計画。
火力発電の脱炭素化と水素・CO2エコシステムの構築を同時並行で迅速に推進するでつ。
技術開発を強化し、世界の脱炭素化を後押しするでつ。
水素ガスタービンがこりから世界の主流になるでつ。
この技術だけは国産でやってほしいでつ。
技術の海外流出は避けてほしいでつ。