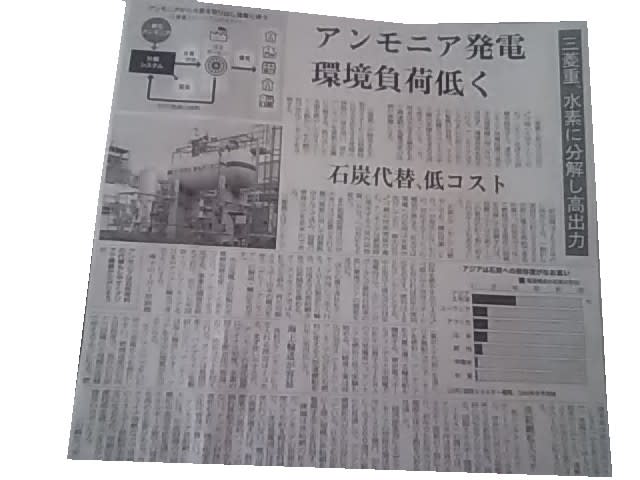脱炭素社会に向けた動きが世界で加速する中,水素焚き・アンモニア焚きのガスタービン複合発電の
開発を継続して取り組んでいるでつ。
現在,大型ガスタービンで天然ガスに水素を 30vol%混ぜて使用できるガスタービン燃焼器の
開発を完了。
水素専焼方式の開発も鋭意進めているでつ。

また,水素のエネルギーキャリアとして有望なアンモニアを利用する GTCC 開発にも取り組み,
カーボンフリー発電システムのラインアップを更に拡充するでつ。
これらの技術で,ヨーロッパ,北米をはじめとする水素焚き GTCC プロジェクトに参画。
2020 年代半ばからの実用化を目指す。大容量・高効率 GTCC による大規模な水素需要を
喚起することで,国際的な水素サプライチェーン構築を牽引し,脱炭素社会の実現するでつ。
2015 年,COP21 で採択された地球温暖化防止の国際的枠組み“パリ協定”により,世界各国の
政府や金融機関,投資家,企業が次々と脱炭素化への取組みを表明。
2020 年からは協定の実運用がいよいよ始まり,CO2 排出量の削減目標達成に向けた動きが
更に活発になっているでつ。
北欧の環境先進地域を含む EU は,2050 年のカーボンニュートラルに向けた指針を既に表明。
CO2 排出量世界第1位,2位の中国,アメリカは両国が温暖化対策で協力していく共同声明を
近頃発表。
エネルギーの消費大国であり,その大部分を輸入に依存する日本も,2050年までに
カーボンニュートラルを目指すことを宣言。
日本の一次エネルギーの主な変換先は電力で全体の 44%を占めるでつ。
その中で CO2 を発生する火力発電は約8割を占め、再生可能エネルギーの普及が進む中においても,
特に 2011 年の東日本大震災以降,その依存度は依然として高いでつ。
脱炭素社会の実現に向けて,火力発電設備の中で CO2排出量が最も少なく,
かつ高効率な発電方式である GTCC は,今後も旺盛なエネルギー需要に対応する一方
再生可能エネルギーの導入・普及に対する加速と,環境負荷に配慮した化石燃料の
有効活用が求められているでつ。
火力発電の脱炭素化技術に継続して取り組んでいるでつ。
その中で GTCC 発電設備については,その特徴を活かして,
①燃焼ガス温度の高温化をはじめとする更なる高効率化・大容量化を進めて
CO2削減を図ること。
②増大する再生可能エネルギーによる発電量の変動に迅速・柔軟に対応できるように
ガスタービンの運用性を高める技術開発を進めること。
さらに,③燃焼しても CO2 を排出しない水素や,アンモニアを燃料とする
ガスタービンの技術開発を進めることで,来るべき 2050 年の脱炭素社会の実現を目指しているでつ。
折しも,日本では脱炭素社会に向けた水素基本戦略として 2030 年頃に水素発電の商用化を
目指すことを掲げてるでつ。
この先10 年ほどの短期間で,技術開発・商品化から電力事業者への設備導入を進める必要。
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構に支援を頂き,発電用大型ガスタービンにおいて,
燃料の天然ガスに水素を体積比で 30%混ぜて使用することができる燃焼器の開発に成功。
これにより水素発電の社会実装へのハードルを下げ,水素社会へのスムーズな移行を促すことが
期待できるでつ。
また,引き続き NEDO の支援を受け、水素 100%専焼に対応する燃焼器の開発を進めているでつ。
さらに,水素のエネルギーキャリアとしての活用が期待されるアンモニアを利用した GTCC システムの
研究開発も進めているでつ。
水素,アンモニアを利用した当社の発電用ガスタービンの検討状況,世界の水素発電プロジェクトへの
参画状況を中心に脱炭素社会実現に向けた取組みを下記に示すでつ。
脱炭素社会実現のため風力発電や太陽光発電に代表される再エネ発電の普及・拡大が今後も世界的に
進むと見られるでつ。
2060 年には再エネ利用による CO2 削減が全体量の約3割になる試算もあるでつ。
気候や気象条件による出力変動が大きい再エネ発電は,余剰電力の有効利用が課題。
蓄電池や水素等への変換によるエネルギー貯蔵が必要とされ,変動周期が長く,多くのエネルギー容量が
必要とされる場合は,水素等に変換して利用することが特に有効。
GTCC 発電は,再エネの急激な出力変動に追従する能力・運用性を有し,電力需要と再エネのギャップを
柔軟に埋めることが可能。
また,水素を燃料とすることで大量かつ安定な水素需要を生むことから,その期待はますます高まっているでつ。
将来の脱炭素化に向けた当社シナリオを図1に示すでつ。

中期的には,CO2回収を活用した化石燃料由来のブルー水素の普及が見込まれるでつ。
GTCC は,これまでの安価で,安全で,安定的な化石燃料による発電を続けながら,
発電効率を高めて CO2 の排出量を減らすこと。
また,ブルー水素の利用を推進し,CO2 を発生しない水素燃料やアンモニア燃料の混焼による発電を行う
シナリオが考えられるでつ。
更に長期的には,コスト削減と技術革新により再生可能エネルギー由来のグリーン水素が主流となり,
それを利用した水素専焼発電により,排出 CO2 ゼロを達成するシナリオが考えられるでつ。
大容量・高効率の発電用ガスタービンにおける水素利用には以下に示す環境的・経済的メリットがあるでつ(図2)。

1つは,既設のガスタービン設備を最小限の改造で,低炭素化あるいは脱炭素化することが可能なこと。
ガスタービン用燃焼器と燃料供給系統以外の大規模なリニューアルを必要とせず投資コストを抑制でき,
水素転換へのコストのハードルを下げて水素社会へのスムーズなシフトを促すことが期待されるでつ。
次に,液体水素のみの利用にとどまらず,メチルシクロヘキサンやアンモニアといった水素キャリアで
輸送されたものを水素化し,燃料として利用できるため,キャリアへの柔軟性があることや燃料電池車等に比べて,
低純度な水素の利用が可能であり,水素コストの低減できるでつ。
最後に,水素焚きガスタービンは1つの発電設備で燃料電池車 200 万台相当の水素を必要とするため,
大規模な水素需要が喚起され,サプライチェーンの拡大,水素コストの削減を促進することも期待されるでつ。
以上のように,大容量・高効率の発電用ガスタービンにおける水素利用には脱炭素社会を実現するために,
欠かすことのできない重要な役割があるでつ。
水素焚きガスタービンの開発におけるキーポイントは,ガスタービンの心臓部である燃焼器,燃焼技術の開発。
発電用大型ガスタービンの高効率化に伴うタービン入口温度の上昇は NOx 排出量の指数関数的な増加につながるでつ。
このため,大型ガスタービン用燃焼器は,燃料と空気をあらかじめ混合して燃焼器内に投入する
予混合燃焼方式である Dry LowNOx(DLN)燃焼器を採用し,NOx 排出量の低減を図っているでつ。
この方式は,従来の拡散燃焼方式に比べて燃焼器内の火炎温度を低減できるため,
蒸気・水噴射による NOx 低減手法を用いることなく,サイクル効率の低下もないでつ。
一方で,安定燃焼範囲が狭く,燃焼振動や逆火(フラッシュバック)の発生リスクがあり,
未燃分も排出しやすい傾向があるでつ。
水素は天然ガスと比較して燃焼速度が速い特性があるでつ。
そのため,予混合燃焼器にて天然ガスと水素を混焼,あるいは水素専焼させた場合,
天然ガスのみを燃焼させた場合よりも逆火の発生リスクが高くなるでつ。
逆火により火炎が燃焼器の上流に遡上し,当該部が焼損する可能性があるため,
水素焚きガスタービン用の燃焼器は逆火発生の防止に向けた改良を中心に,低 NOx 化や安定燃焼化を
図る必要があるでつ。
図3に,当社の水素混焼・専焼に対応する水素ガスタービン用燃焼器の概要を示すでつ。

水素混焼用 Dry Low NOx(DLN)マルチノズル燃焼器水素混焼による逆火発生リスクの上昇を防ぐことを目的として,
従来の DLN 燃焼器をベースとして新たに開発された水素混焼燃焼器の概要を図4に示すでつ。

圧縮機から燃焼器内部に供給された空気は,旋回翼(スワラー)を通過して,旋回流となるでつ。
燃料はスワラーの表面に設けられた小さな孔より供給され,旋回流により周囲の空気と急速に混合されるでつ。
一方,旋回流の中心部(以下渦芯)には,流速の低い領域が存在し,ここを火炎が遡上することで
逆火が発生すると考えられるでつ。
そこで新型燃焼器ではノズルの先端から空気を噴射して渦芯の流速を上昇させ,渦芯の低流速領域を補うことで
逆火の発生を防止しているでつ。
ガスタービン燃焼器の燃焼特性に関する代表的な項目として,NOx,燃焼振動があげられ,燃焼圧力条件の影響を受けるため,
実機相当の圧力条件での検証が必要となるでつ。
そこで,フルスケールの水素混焼燃焼器1本(実機では 16 本ないし 20 本の燃焼器を配置)を
使用した実機圧力燃焼試験(以下,実圧燃焼試験)を実施。
水素混焼が燃焼特性に与える影響を確認試験における空気条件及び燃料条件を,
タービン入口温度 1600℃級ガスタービンの定格負荷相当に合わせた条件における,
水素混合割合に対する NOx の変化を図5に示すでつ。

水素混合割合の増加に伴って,NOx が僅かに上昇する傾向が確認。
これは,燃料中に水素が混合することにより,燃焼速度が上昇して燃焼器中の火炎位置が上流へ移動し,
燃料と空気の混合が不十分な状態で燃焼するためと考えられるでつ。
だけど,水素 30vol%を混合した条件においても,天然ガスでの運転時(=水素 0vol%)とほぼ同等であり,
運用可能な範囲内にあることが確認。
同じ条件における燃焼振動圧力レベルの変化を図6に示すでつ。

燃焼振動圧力レベルについても,天然ガスでの運転時と比較し同等以下で,水素混合割合の変化に対して,
あまり影響を受けないことが確認。
また水素 30vol%混焼において逆火は確認されなかったでつ。
以上の結果より,逆火の発生や燃焼振動の著しい上昇を伴わずに運用できる目途を得たでつ。
水素専焼用マルチクラスタ燃焼器を示すでつ(図7)。

水素が更に高濃度になると,前項の水素混焼燃焼器に採用される旋回流による燃料と空気の混合方式では,
渦芯部の低流速域で発生する逆火のリスクが更に高くなるでつ。
そこで旋回流を利用せず,より小さなスケールで空気と水素を混合できる混合方式が,逆火への耐性があると
考えられるでつ。
水素専焼燃焼器は,大崎クールジェンに適用されている IGCC 用マルチクラスタ燃焼器をベースとして
開発を進めているでつ。
水素混焼燃焼器の燃料供給ノズル(8本)に対して,より数多くのノズルを有し,1本のノズルの孔を小さくし,
空気を送るとともに,そこに水素を吹いて小さなスケールで混合させ,火炎を分散することで,高い逆火耐性と
低 NOx 燃焼が両立する可能性を有するでつ。
拡散燃焼器は,燃料と燃焼用空気を別々に燃焼器内に噴射。
予混合燃焼方式に比べて火炎温度が高く NOx 排出量が増えるため,蒸気・水噴射による NOx 低減対策が
必要になるでつ。
一方で,比較的,安定燃焼範囲が広く,燃料性状変動への許容範囲も大きいでつ。
拡散燃焼器を図8に示すでつ。

これまで,小型から中型のガスタービン発電設備においてオフガス(製油プラント等で発生する排ガス)の燃料利用により
幅広い水素含有割合(~90vol%)の燃料に関する実績を有するとともに,
水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術研究開発プロジェクトへの参画の際に,水素専焼による燃焼試験にも成功。
本拡散燃焼器をオランダのバッテンフォール・マグナム発電所の水素焚き転換プロジェクトに適用することを
検討しているでつ。
発電用ガスタービンで必要となる大量の水素を安定に利用するためには,水素の製造・運搬・貯蔵等を
担うサプライチェーンの構築が前提。
このため,水素を運搬・貯蔵するためのキャリアとして液化水素だけでなく,アンモニアや
メチルシクロヘキサン等を活用することが検討されているでつ。
その中で,アンモニアは,液体水素やメチルシクロヘキサンに比べて体積あたりの水素密度が大きく,
水素を効率良く運搬・貯蔵できるキャリア。
また,液化石油ガスなどの既存の運搬・貯蔵インフラの転用が可能であり,インフラ整備のハードルが
比較的低く,大規模な水素インフラ整備が難しい地域、例えば離島での利用可能性があるなどの
特徴があるでつ。
更に,カーボンフリーな燃料として直接燃焼することも可能であることから,電力会社や IPPなどの
発電設備へ早期に導入することにより,将来のカーボンフリー燃料としての活用が期待されるでつ。
ガスタービン発電の燃料としてアンモニアを専焼できる中小型4万 kW 級ガスタービンシステムの開発に着手。
アンモニアの直接燃焼では,燃料中の窒素が燃焼により酸化することで発生する窒素酸化物の課題があり,
図9に示す当社の H-25 形ガスタービン(出力4万 kW 級)を対象に,NOx 排出量を低減する燃焼器の開発と
脱硝装置を組み合わせたガスタービンシステムを構築し,実用化を目指しているでつ。
過去,このような大出力ガスタービンにアンモニア直接燃焼を適用した例はなく,
大規模な水素・アンモニアの需要を喚起して脱炭素化に貢献できるでつ。

一方,大型ガスタービンでアンモニアを燃焼させる際は,表1に示す点を考慮する必要。

図 10 に示すガスタービンの排熱でアンモニアを水素と窒素に再変換し,開発済みの水素混焼用燃焼器。
又は,開発中の水素専焼燃焼器により燃焼させる GTCC システムの検討を進めているでつ。

アンモニア分解にはアンモニア 1mol あたり約 46kJ の熱が必要であるがでつ,投入した熱は,
アンモニアが水素になることで,燃料の発熱量の1.14倍の増加として化学再生されるでつ。
したがって,アンモニア分解器の下流側に設置するガス処理装置でのエネルギー損失以外には
原理的な熱効率低下はないでつ。
アンモニア分解ガスの燃焼では,アンモニア分解時に若干量残留するアンモニアの一部が燃焼器内で
フューエル NOx として変換されることに留意する必要。
これらは燃焼器内で元々生成されるNOxに上乗せされて排出されるものと予想。
NOxの排出規制値を満足するための残留アンモニア量による NOx の増加量を把握する必要。
そこで,分解ガス中に微量含まれる残留アンモニアが NOx に及ぼす影響の確認。
また、燃焼の安定性を確認することを目的とし,1650℃級の水素混焼用ガスタービン燃焼器を用いて
実圧燃焼試験を行ったでつ。
図 11 に,タービン入口温度 1650℃(定格条件),天然ガスとアンモニア分解ガスの
混焼時(燃料組成:水素20vol%,窒素 6.7vol%,天然ガス 73.3vol%,微量のアンモニア)の,
アンモニア濃度と排ガス中のNOx濃度の関係を示す。燃料中のアンモニア濃度が増加するとともに
NOx濃度が線形で増加する結果となり(図中●印),アンモニアの NOx への
転換率(図中 CR: Conversion ratio)は,約90%。

また,燃料中のアンモニア濃度を変化させても燃焼振動の圧力レベルに大きな変化はなく,
管理値に対して十分な裕度があり,フラッシュバックは発生せず燃焼の安定性が確認されたでつ。
以上,これらアンモニアを利用したガスタービンシステムの開発により,カーボンフリー発電システムのラ
インアップを更に拡充するでつ。
海外では,大規模な再エネ由来のグリーン水素の生産から利用までのシステム開発,あるいは,
化石燃料由来のブルー水素の生産・利用において水素製造時に発生する CO2 を CCS で処理することも
含めたシステム開発など,水素の製造,輸送,貯蔵そして利用までを視野に入れた包括的な水素利用プランが
多く示されているでつ。
水素の利活用を通して,その地域におけるエネルギーの信頼性と独立性を高め,雇用を創出するとともに,
不経済なグリッド構築の回避,既存インフラの再利用,複数の産業セクターにおける燃料の多様化な
ど様々な効果が期待され,国境を越え,国家,自治体,企業共同体が連携してプロジェクトが
進められているでつ。
ここでは,その中で,参画するヨーロッパ,及び米国での水素ガスタービンプロジェクトを3件あるでつ。
まず,1件目は,スウェーデンのエネルギー企業が運営する出力 132 万 kW 級の天然ガス焚き GTCC を
水素焚きに転換するプロジェクト。
同プロジェクトは,図 12 に示すオランダ最北部のフローニンゲン(Groningen)州に位置する
バッテンフォール・マグナム(発電所に,当社が納入した M701F 形ガスタービンを中核とする
発電設備3系列のうち1系列を 2027 年までに 100%水素専焼の発電設備へと切り替えるもの。

これまでに初期フィージビリティスタディーを実施。
既存技術である拡散燃焼器の適用を検討し,水素燃焼への転換が可能であることを確認。
天然ガス焚きでは 44 万 kW の GTCC 発電設備1系列につき年間約 130 万トンの CO2 を排出するでつが,
水素焚きへの転換によりそのほとんどを削減することができるでつ。
引き続きガスタービン技術領域にて具体的な改造範囲の計画,設計等,同プロジェクトの
実現に向けて検討を続けるでつ。
2件目は,イギリス東海岸のハンバー川流域の三角州地帯における同国内最大規模の産業クラスタの
脱炭素化事業のプロジェクト。
ここでは,グローバルに事業展開する脱炭素化関連産業の企業・機関が連携し,
天然ガスから製造したブルー水素の活用や,二酸化炭素の回収・除去技術を適用し,
2040 年までに二酸化炭素の排出実質ゼロ達成を目指すでつ。
このプロジェクトにおいて,産業クラスタ内にあるソルトエンド発電所(図 13)に納入した
天然ガス焚き GTCC 発電設備の M701F 形ガスタービンを水素焚きに
転換する技術検討・フィージビリティスタディーに着手し,水素混焼率 30vol%から始め
将来的に水素専焼を視野に入れて検討を進めているでつ。

3件目は,米国ユタ州のインターマウンテン電力が計画する水素を利用した GTCC 発電プロジェクト。
84 万 kW 級の M501JAC 形ガスタービン2基を中核とする GTCC 発電設備を受注し,
2025 年に 30vol%の水素混焼,2045 年までに水素専焼での発電を目指すでつ。
本プロジェクトは,石炭火力発電所の設備更新により建設されるもので,
水素混焼率 30vol%GTCC への更新により,最大で年間 460 万トンの CO2排出量削減に
寄与できる見込み。
燃料の水素は,参画するユタ州内の再生可能エネルギー由来電力によるエネルギー貯蔵事業からの
活用が期待されてて,発電された電力は,インターマウンテン発電所からロッキー山脈を
またいで,カリフォルニア州,及びユタ州に幅広く供給されるでつ。
これらを含めた国内外での水素利用発電のプロジェクト参画を通じて,グループが掲げる
エナジートランジッションちまり、低環境負荷エネルギーへの転換への動きに弾みをつけ,火力発電への
水素利活用の需要を喚起していくとともに,水素の供給・輸送・貯蔵に関する国際的な水素バリューチェーンの
構築にも関わることで,脱炭素社会の実現するでつ。
2020 年代半ばからの水素発電の具体的な導入時期に向けて,今後数年間で,これまでの要素開発の結果をもとに
実機ガスタービンを用いた実証を進めるでつ。
ガスタービン開発は,基本設計の段階で各要素の検証試験を実施。
その結果を詳細設計に反映,最終的に実機を用いた実証を行うでつ。
この開発サイクルを同一工場内で実施することで,より迅速かつ確実な開発・製品化を進めてきたでつ。
水素ガスタービンについても実用化に向けて図 14 に示すとおり,大型ガスタービン水素混焼(30vol%)の
実証を行い,商用化を開始。

その後,大型ガスタービン水素専焼の米国ユタ州 PJ での商用化。
中小型ガスタービン水素専焼についても,H-25 ガスタービンを用いた実証を行うでつ。
アンモニア焚きについても,同様に中小型 H-25 ガスタービンで実証を行い,実用化。
水素,アンモニアを利用した発電用ガスタービンの検討状況,世界の水素発電プロジェクトへの
参画状況を中心に脱炭素社会実現に向けた取り組んでいるでつ。
こりは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成事業(水素社会構築技術開発事業 : JPNP14026)の
成果の一部。
同助成事業において水素・天然ガス混焼方式のガスタービンの燃焼器の開発に取り組み,30vol%の混焼条件において
ガスタービンの運転が可能なことが確認できたでつ。
引き続き,水素専焼方式の開発を進めいくでつ。
また,本報の第4章に記載したアンモニア分解ガスによる GTCC の開発は,
内閣府戦略的イノベーション創造プログラム“エネルギーキャリア”,並びに
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成事業により進められたでつ。
2020 年半ば頃から始まるであろう CCS を組み合わせた化石燃料由来の水素利用,
2050 年の再生可能エネルギー由来の水素利用が主流になる社会に向けて,
開発する水素・アンモニア焚きガスタービンを通して,国際的な水素サプライチェーン構築を牽引し,
脱炭素社会の実現を進めていくでつ。
だけどほぼ日立の技術でつなぁ~
三菱重工にとっては、火力を日立と統合してお得したでつ。