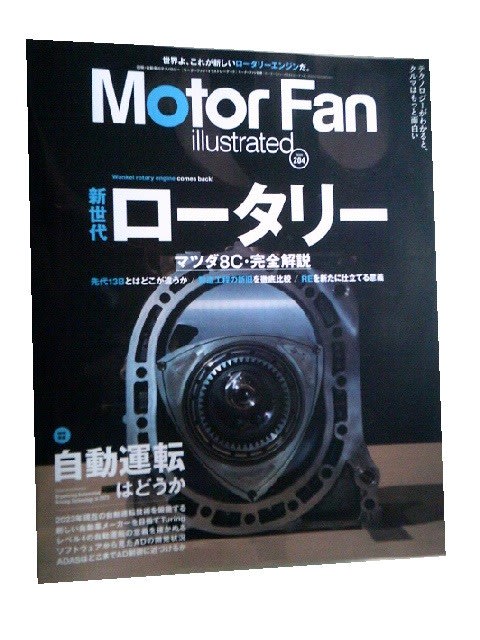フィットにハイブリッドが追加されたのが3代目。
ようやくというか電動化に関しては、ホンダのスタートダッシュは遅いなぁ~
トヨタがアクアやSAIを出して、HV化が加速してる中でホンダHVへの期待は高かったでつ。
ということで…
正式発表を前にすでに1万台以上の予約注文が入っていたというから、その注目度の高ったことで証明してるでつ。
ポイントは…
まずコンパクトカーの定番であるフィットをベースとしていること、ハイブリッドで160万円を切るという価格、30km/Lという燃費性能。
特にトヨタがHVは全チャンネル展開してるから価格と燃費は重要なポイント。
3代目フィットは、.3Lエンジンと薄型電気モーターを小さなボンネット内にすっぽり収め、駆動用ニッケル水素バッテリーも薄型にして
ラゲッジルームのフロア下にコンパクトに収納。
まるでなにごともなかったかのようにハイブリッド化に成功しているでつ。
とはいっても簡単ではなかったでつ。
バッテリーの搭載などによる重量増は約100kgほどガソリン車より重い。
重量配分変化については、ボディ、足まわり、ブッシュなどを基本から見直したでつ。
ガソリン車よりも多くの部分でコストがかかっているでつ。
10・15モード燃費30km/Lを実現するにも苦労があったでつ。
そりは、テレビの特集でもやってたでつなぁ~
とにかく燃費№1譲れないとこだったでつ。
インサイトよりボディが小さいので車重は60kgほど軽いでつが、空気抵抗が大きく、さらに全長が短いため空力的に不利となるでつ。
そのため、ライトまわりのデザイン変更、ドアミラーの形状変更、リアのディフューザーまわりの変更、エンジンのフリクション低減、
低転がり抵抗タイヤ採用、CVTフルードウオーマーの追加など…
ただ心配な点もいくつかあるでつ。
インサイトのようなハイブリッド専用車ではないので、ハイブリッドらしい演出に乏しく、ユーザーに強くアピールできるのかということ。
1.3Lエンジン+電気モーターによる走りは、出足の良さがとくに印象的。
モーターアシストによってトルクがぐいっと押し上げられ、アクセルペダルを軽く踏んだだけで前に押し出されるように加速していくでつ。
1.3Lモデルとは明らかに異なるでつ。
深く踏み込む必要がないのでエンジン回転が抑えられ、とても静かなのも特徴。
ホンダのIMAはエンジンを動力源とし、モーターは補助動力のためハイブリッドであることを強く意識させることはなく、
静かでトルクフルなエンジン。
回生ブレーキもそれほど強くはなく、ごく自然な感じで、通常のブレーキの感覚で運転することができるでつ。
このあたりになるとハイブリッドであることを強調する時代ではなくなってきてるとこでつなぁ~
ハイブリッドらしい演出よりも実性能が重要。
そう考えると、コンパクトカーとしての資質に加え、ハイブリッドという付加性能を加えられた、このモデルの実力は相当に高いでつ。
ハイブリッドで、この性能が159万円から手に入るのはやはり凄い。
このトルクフルで快適な走りが、この価格で手に入るのならば、ハイブリッドになるでつ。
居住性や使い勝手、実用性など、むしろインサイトより優っているのが、フィットハイブリッド。
ということを考えると2代目のインサイトの立ち位置がなくなってきたでつなぁ~
ここらへんは、同じタイプではなく、もう少し差を漬けてもよかった気がするでつ。
スポーツハイブリット的な感じでね。
ようやくというか電動化に関しては、ホンダのスタートダッシュは遅いなぁ~
トヨタがアクアやSAIを出して、HV化が加速してる中でホンダHVへの期待は高かったでつ。
ということで…
正式発表を前にすでに1万台以上の予約注文が入っていたというから、その注目度の高ったことで証明してるでつ。
ポイントは…
まずコンパクトカーの定番であるフィットをベースとしていること、ハイブリッドで160万円を切るという価格、30km/Lという燃費性能。
特にトヨタがHVは全チャンネル展開してるから価格と燃費は重要なポイント。
3代目フィットは、.3Lエンジンと薄型電気モーターを小さなボンネット内にすっぽり収め、駆動用ニッケル水素バッテリーも薄型にして
ラゲッジルームのフロア下にコンパクトに収納。
まるでなにごともなかったかのようにハイブリッド化に成功しているでつ。
とはいっても簡単ではなかったでつ。
バッテリーの搭載などによる重量増は約100kgほどガソリン車より重い。
重量配分変化については、ボディ、足まわり、ブッシュなどを基本から見直したでつ。
ガソリン車よりも多くの部分でコストがかかっているでつ。
10・15モード燃費30km/Lを実現するにも苦労があったでつ。
そりは、テレビの特集でもやってたでつなぁ~
とにかく燃費№1譲れないとこだったでつ。
インサイトよりボディが小さいので車重は60kgほど軽いでつが、空気抵抗が大きく、さらに全長が短いため空力的に不利となるでつ。
そのため、ライトまわりのデザイン変更、ドアミラーの形状変更、リアのディフューザーまわりの変更、エンジンのフリクション低減、
低転がり抵抗タイヤ採用、CVTフルードウオーマーの追加など…
ただ心配な点もいくつかあるでつ。
インサイトのようなハイブリッド専用車ではないので、ハイブリッドらしい演出に乏しく、ユーザーに強くアピールできるのかということ。
1.3Lエンジン+電気モーターによる走りは、出足の良さがとくに印象的。
モーターアシストによってトルクがぐいっと押し上げられ、アクセルペダルを軽く踏んだだけで前に押し出されるように加速していくでつ。
1.3Lモデルとは明らかに異なるでつ。
深く踏み込む必要がないのでエンジン回転が抑えられ、とても静かなのも特徴。
ホンダのIMAはエンジンを動力源とし、モーターは補助動力のためハイブリッドであることを強く意識させることはなく、
静かでトルクフルなエンジン。
回生ブレーキもそれほど強くはなく、ごく自然な感じで、通常のブレーキの感覚で運転することができるでつ。
このあたりになるとハイブリッドであることを強調する時代ではなくなってきてるとこでつなぁ~
ハイブリッドらしい演出よりも実性能が重要。
そう考えると、コンパクトカーとしての資質に加え、ハイブリッドという付加性能を加えられた、このモデルの実力は相当に高いでつ。
ハイブリッドで、この性能が159万円から手に入るのはやはり凄い。
このトルクフルで快適な走りが、この価格で手に入るのならば、ハイブリッドになるでつ。
居住性や使い勝手、実用性など、むしろインサイトより優っているのが、フィットハイブリッド。
ということを考えると2代目のインサイトの立ち位置がなくなってきたでつなぁ~
ここらへんは、同じタイプではなく、もう少し差を漬けてもよかった気がするでつ。
スポーツハイブリット的な感じでね。