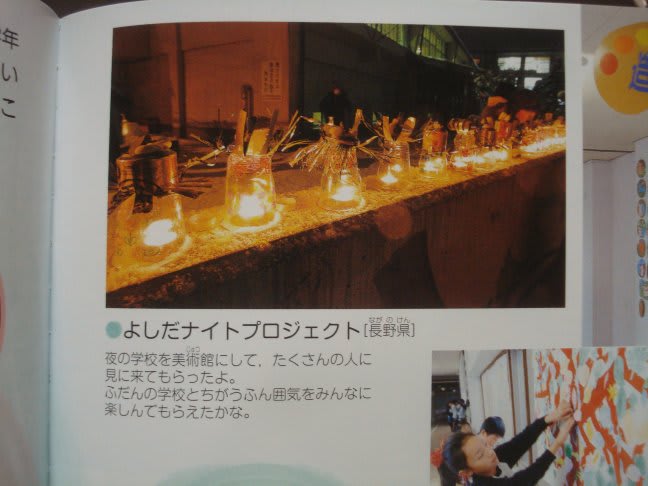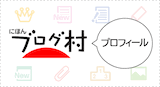裾花中学校,長崎です。
本校は,あさって8月21日が始業式です。
明日は,職員会があったり,授業の準備をしたり…ということで学校に出勤します。
美術部も文化祭に向けてステージバック制作のために朝から活動します。
全国の方々は,「え!?もう始業式?と驚かれるでしょうが,長野県ではだいたいこんな感じで,お盆が終わるとすぐに2学期が始まります。
ちなみに本校は,というと,7月29日から休みに入りましたので…夏休みは23日間ですね。
長野県教育委員会のホームページには,こんなページがありますが…
・長野県の学校はどうして夏休みが短いのですか
その質問の,納得できる答えになっているかというと,少々疑問です。
もちろん各学校ごとに休業日を決めているのはそのとおりなのですが,夏休みが短い分,他の日に休みを回しています…みたいに読めます。
実は大事なのは,年間の登校日数なのです。
本校の今年度の年間登校日数は210です。たぶん近隣の小中学校もだいたい同じだと思います。
全国でいうと,登校日数は200日より下という学校がほとんどでしょう。
長野県のホームページで,こんなページを見つけました。
・長野県の公立学校の休業日について
こちらの回答は,長野県の学校の実情や願いを正直に表していて,たぶん読まれた方々の多くは(子どもも保護者も)納得していただけるのではないでしょうか。
このブログは,小中学生の皆さんも見てくれているようなので,私からも少しだけ解説させてもらうと…
当たり前のことですが,公立学校は1年間で国語は○時間,図工は○時間…○年生では全部で○時間学習しなさい,と国で決まっています。そうした年間の教科に割り当てられた時間数は全国どこの学校だろうと同じなのです。
長野県が他の県と比べて多いのは,行事や児童会活動,学校裁量の時間といって,教科の学習以外の部分。
それは,長野県が昔から大事にしてきた運動会や音楽会(音楽会のない県も多いですよね?),遠足や文化祭,クラスマッチなど…。
他の県では,大変だからと削られてしまったり,規模が小さくなってしまったりした昔から続いてきた多くの行事が今もしっかり残っています。
長野県の先生たちは子どもたちが本当の意味で成長するためには,教科の学習だけではないそれ以外のところも大切だと思っているからなのです。
その結果,年間の登校日数が平均すると全国よりも10日ほど多くなってしまいました。
というわけです。
こんな理由で,長野県の夏休みは短いのですが…。
どうでしょう。
それでも納得してもらえない方々は多いかもしれませんね…。
でも,長野県の夏は他県に比べてやっぱり涼しいと思いますよ!
長野県の小中学生の皆さん,あさってからまたがんばろう~!
記事に興味を持っていただけましたら,クリックしてください。
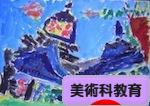 にほんブログ村
にほんブログ村
本校は,あさって8月21日が始業式です。
明日は,職員会があったり,授業の準備をしたり…ということで学校に出勤します。
美術部も文化祭に向けてステージバック制作のために朝から活動します。
全国の方々は,「え!?もう始業式?と驚かれるでしょうが,長野県ではだいたいこんな感じで,お盆が終わるとすぐに2学期が始まります。
ちなみに本校は,というと,7月29日から休みに入りましたので…夏休みは23日間ですね。
長野県教育委員会のホームページには,こんなページがありますが…
・長野県の学校はどうして夏休みが短いのですか
その質問の,納得できる答えになっているかというと,少々疑問です。
もちろん各学校ごとに休業日を決めているのはそのとおりなのですが,夏休みが短い分,他の日に休みを回しています…みたいに読めます。
実は大事なのは,年間の登校日数なのです。
本校の今年度の年間登校日数は210です。たぶん近隣の小中学校もだいたい同じだと思います。
全国でいうと,登校日数は200日より下という学校がほとんどでしょう。
長野県のホームページで,こんなページを見つけました。
・長野県の公立学校の休業日について
こちらの回答は,長野県の学校の実情や願いを正直に表していて,たぶん読まれた方々の多くは(子どもも保護者も)納得していただけるのではないでしょうか。
このブログは,小中学生の皆さんも見てくれているようなので,私からも少しだけ解説させてもらうと…
当たり前のことですが,公立学校は1年間で国語は○時間,図工は○時間…○年生では全部で○時間学習しなさい,と国で決まっています。そうした年間の教科に割り当てられた時間数は全国どこの学校だろうと同じなのです。
長野県が他の県と比べて多いのは,行事や児童会活動,学校裁量の時間といって,教科の学習以外の部分。
それは,長野県が昔から大事にしてきた運動会や音楽会(音楽会のない県も多いですよね?),遠足や文化祭,クラスマッチなど…。
他の県では,大変だからと削られてしまったり,規模が小さくなってしまったりした昔から続いてきた多くの行事が今もしっかり残っています。
長野県の先生たちは子どもたちが本当の意味で成長するためには,教科の学習だけではないそれ以外のところも大切だと思っているからなのです。
その結果,年間の登校日数が平均すると全国よりも10日ほど多くなってしまいました。
というわけです。
こんな理由で,長野県の夏休みは短いのですが…。
どうでしょう。
それでも納得してもらえない方々は多いかもしれませんね…。
でも,長野県の夏は他県に比べてやっぱり涼しいと思いますよ!
長野県の小中学生の皆さん,あさってからまたがんばろう~!
記事に興味を持っていただけましたら,クリックしてください。
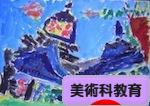 にほんブログ村
にほんブログ村