


お正月は、神人共食、神様と人間が一緒に食事をするという考えだと云われています。
神道の行事では、神様と家族が揃って食事をするのが大事なことと考えられているようです。
神様(ご先祖様)と一緒にいただくので、お正月に使うお箸(祝い箸)は両側が細く丸い柳箸を使います。
これは一方で神様(ご先祖様)が食べられるからです。
祝い箸もう少し詳しく
年初に雑煮やお節料理を食べる際に使うのが
両端を細く削った白木の祝い箸、新年を迎え感謝の気持ちを
天に向かって表す神聖なものだという。
木材は、ヤナギ、スギ、ヒノキ 中でもヤナギは
 最高級
最高級

両端を細く削って中央部が丸く膨らんでおり、
「中太両細箸」と呼ばれている。

白いもみ紙に水引をつけた箸袋に「寿]「祝い」などと書き、
家族の名前を書く。
その祝い箸を家族それぞれが清め、自分の名入りの水引がついた箸袋におさめ、お正月の三が日、
または七草がゆの七日まで使うたびに洗い、箸袋に戻して使うのが「しきたり」らしい。

毎日食事のたびに口に運ぶ箸には自身の魂がこもると考え、一年間
使った箸は大晦日で役目を終え、新年に新調してきたといわれている。

「祝い箸」は、毎年お正月には必ず使用しているが、
ここまで「しきたり」があったとは・・・・ね。

普通は、捨てちゃいますよね。
ここもね

お雑煮レシピ
 全国のお雑煮関東・関西・北海道・東北・九州 全国地方のお雑煮参加して下さいね
全国のお雑煮関東・関西・北海道・東北・九州 全国地方のお雑煮参加して下さいね
御供えも作りました この両サイドのちっちゃい花瓶の花masarinが生けました
(蛇のようなミリオンバンブー)
年賀状の書き方
 間違っていませんか年賀状2013
間違っていませんか年賀状2013 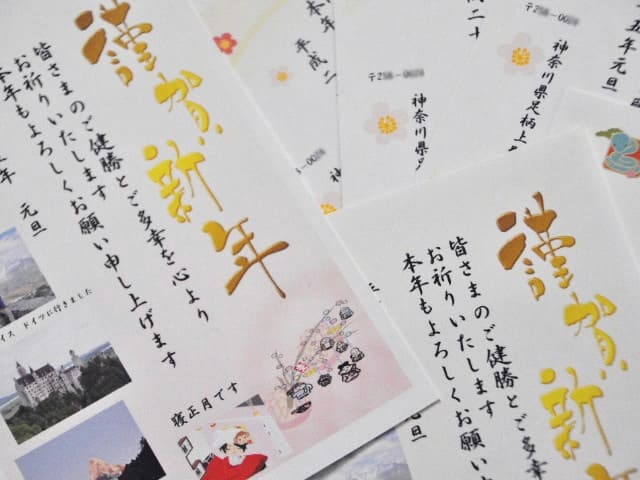
第89回東京箱根間往復大学駅伝競走大会予想
 往路優勝は駒澤大 東洋大 早稲田 山登りの5区が勝負
往路優勝は駒澤大 東洋大 早稲田 山登りの5区が勝負 関東学生陸上競技連盟 読売新聞社より
関東学生陸上競技連盟 読売新聞社より 地方自治法施行60周年記念500円記念貨幣
 25年1月16日栃木県 兵庫県 大分県
25年1月16日栃木県 兵庫県 大分県


1000円銀貨貨幣は、栃木県は国宝・日光東照宮陽明門をデザイン 大分県は、宇佐神宮の南中楼門と大分県出身の横綱・双葉山をデザイン 特別天然記念物・コウノトリと国宝・姫路城をデザインしています
初夢っていつ見た夢
 元旦それとも2日 空を飛ぶ夢をみますよ
元旦それとも2日 空を飛ぶ夢をみますよ















