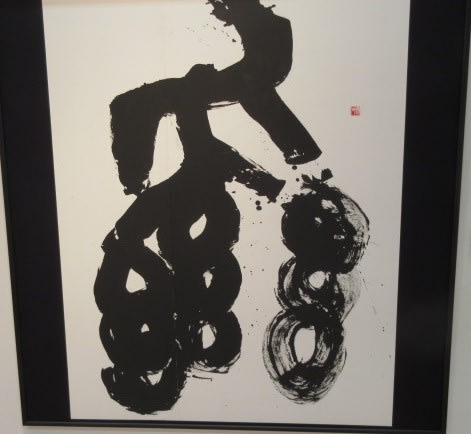桜が終わったかナと思ったら、あっというまに若葉の季節です。
見て下さい。先日までの桜が、ご覧のように目に染みるような緑になりました。

一面が桜色に染まった桜の季節から一面が緑色に変わる若葉の季節までの一か月余り、
この時期のこの辺りの自然を、本当に美しいと思います。
花咲き 鳥歌い 緑かおる、ちょっと大げさですが、街の中心部にぼつんとある谷津山という
100メートル程の丘のような山が、この豊かな自然を演出してくれる原点です。

木々に負けじ劣らじと華やぎをみせるのは、小さなキンポウゲの花。
知人が信州の田舎から運んできたのを頂いたものですが、
懸命に咲いている様は、健気で可憐、切り取って花入れに活けても丈夫です。

何処にでもあってよく見かける十二単ですが、これも生命力の強い花。
去年咲いていた場所から地下茎をのばして移動して、
思いがけないところで大群となって地面を飾ります。

一人でも可憐な白雪ケシ。木下闇を、ポッと明るく見せます。

「あれ」と思いがけないところに咲いて、目を驚かせるテッセンの紫。

いつものところに、いつものように咲くスズランのような白い花、 アマドコロ。
同じ頃、同じように ホウチャク草も 咲いています。
つくづくと ここが好きだよ 若葉色
あらとふと 青葉若葉の 日の光 ( 芭蕉 )
。