バンクーバーオリンピックで活躍した織田信成選手の先祖・織田信雄に着せられた安土城放火犯の冤罪を晴らすことにしました。冤罪の元を作ったイエズス会宣教師フロイスの記述は前回ご紹介したとおりです。
★ 本能寺の変:安土城放火・織田信雄冤罪を晴らす!
念のため以下に再掲いたします。
「附近にいた信長の一子がいかなる理由によるか明らかでなく、智力の足らざるためであろうか、城の最高の主要な室に火をつけさせ、ついで市にもまた火をつけることを命じた」
それでは、この文章の信憑性を確認しておきましょう。
安土城の発掘調査が1989年から始まっています。その調査で明らかになったひとつの事実があります。それは天主は燃えているが、城下町は燃えていない、ということです。これは明らかにフロイスの記述と矛盾しており、記述の信憑性に疑問があります。
そして大事なことはフロイスが報告書を書く基本的なスタンスの問題です。フロイスはキリスト教布教という一念を基準として報告書を書いているということです。このことはフロイスの著述を実際に読んでみればたちどころに分ります。キリスト教に寛容な人物は褒め上げ、そうでない人物には大変厳しい人物評を書いています。
明智光秀は仏教を尊んだため散々な書き方がされています。
では、織田信雄はどうかというと、やはり「味方ではない」という書き方です。一方、信長の三男・信孝はキリスト教徒になるのではないかと言われるほどでしたので、信雄とは好対照の好意的な書き方になっています。
フロイスの報告書は本能寺の変から4ヶ月の間に書かれています。この時期は織田家の家督相続や実権掌握をめぐって信雄と信孝が競い合っていました。こういった背景の中で書かれた文章ですので、イエズス会やキリスト教徒の意向が強く反映されたとみるべきでしょう。応援する方に有利に、その反対方には不利に書くという極めて「フロイス的」記述と考えられるのです。信雄はこうした背景から放火犯にでっち上げられた可能性が高いといえます。
これで、フロイスの記述を根拠とした信雄放火犯の冤罪は晴れたと考えます。
そして、何よりも安土城放火犯として相応しい別の人物がいるということが、信雄の冤罪を完全に晴らしてくれるでしょう。
拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』をお読みの方はそれが誰なのか、また何故そうなのかをもちろんご存知です。お読みでない方のために簡単に説明しておきますが、疑問があれば是非拙著をお読みください。
安土城天主の放火犯は徳川家康です。
家康は本能寺の変の直後は織田家と敵対し、甲斐・信濃の織田領を攻めていました。織田家と敵対している家康にとって安土城は「敵の本拠」でした。敵の本拠を破壊することは家康にとって余りに当然の戦術だったのです。
もう少し詳しいことを解説した以下のページもありますのでご覧ください。
★ 家康の神君伊賀越えの秘密を暴く
★ 穴山梅雪は一揆に殺されていません!
★ 安土城放火犯は徳川家康です!
安土城放火犯は迷宮入りの歴史の謎とされてきました。しかし、謎でもなんでもないのです。歴史の事実をきちんと確認すれば犯人は自ずから明らかだったのです。
それでも、私の上記の主張に納得できない方もいらっしゃると思います。何しろ四百年以上に渡って全く違うことが事実かの如くに広められてきたからです。徳川家が政権を握った江戸時代だけでなく、現代でも広められ続けているのです。私にはこういった事実の方が何故だろうかと疑問に思わざるを得ません。歴史が意図的に作られているように思えるのです。
四百年もたってしまった現代の常識で考えるのではなく、四百年前の当時の常識が何だったのかを知らねばなりません。そうでなければ歴史の事実は見えてこないと思います。
★ 本能寺の変:安土城放火・織田信雄冤罪を晴らす!
念のため以下に再掲いたします。
「附近にいた信長の一子がいかなる理由によるか明らかでなく、智力の足らざるためであろうか、城の最高の主要な室に火をつけさせ、ついで市にもまた火をつけることを命じた」
それでは、この文章の信憑性を確認しておきましょう。
安土城の発掘調査が1989年から始まっています。その調査で明らかになったひとつの事実があります。それは天主は燃えているが、城下町は燃えていない、ということです。これは明らかにフロイスの記述と矛盾しており、記述の信憑性に疑問があります。
そして大事なことはフロイスが報告書を書く基本的なスタンスの問題です。フロイスはキリスト教布教という一念を基準として報告書を書いているということです。このことはフロイスの著述を実際に読んでみればたちどころに分ります。キリスト教に寛容な人物は褒め上げ、そうでない人物には大変厳しい人物評を書いています。
明智光秀は仏教を尊んだため散々な書き方がされています。
では、織田信雄はどうかというと、やはり「味方ではない」という書き方です。一方、信長の三男・信孝はキリスト教徒になるのではないかと言われるほどでしたので、信雄とは好対照の好意的な書き方になっています。
フロイスの報告書は本能寺の変から4ヶ月の間に書かれています。この時期は織田家の家督相続や実権掌握をめぐって信雄と信孝が競い合っていました。こういった背景の中で書かれた文章ですので、イエズス会やキリスト教徒の意向が強く反映されたとみるべきでしょう。応援する方に有利に、その反対方には不利に書くという極めて「フロイス的」記述と考えられるのです。信雄はこうした背景から放火犯にでっち上げられた可能性が高いといえます。
これで、フロイスの記述を根拠とした信雄放火犯の冤罪は晴れたと考えます。
そして、何よりも安土城放火犯として相応しい別の人物がいるということが、信雄の冤罪を完全に晴らしてくれるでしょう。
拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』をお読みの方はそれが誰なのか、また何故そうなのかをもちろんご存知です。お読みでない方のために簡単に説明しておきますが、疑問があれば是非拙著をお読みください。
安土城天主の放火犯は徳川家康です。
家康は本能寺の変の直後は織田家と敵対し、甲斐・信濃の織田領を攻めていました。織田家と敵対している家康にとって安土城は「敵の本拠」でした。敵の本拠を破壊することは家康にとって余りに当然の戦術だったのです。
もう少し詳しいことを解説した以下のページもありますのでご覧ください。
★ 家康の神君伊賀越えの秘密を暴く
★ 穴山梅雪は一揆に殺されていません!
★ 安土城放火犯は徳川家康です!
安土城放火犯は迷宮入りの歴史の謎とされてきました。しかし、謎でもなんでもないのです。歴史の事実をきちんと確認すれば犯人は自ずから明らかだったのです。
それでも、私の上記の主張に納得できない方もいらっしゃると思います。何しろ四百年以上に渡って全く違うことが事実かの如くに広められてきたからです。徳川家が政権を握った江戸時代だけでなく、現代でも広められ続けているのです。私にはこういった事実の方が何故だろうかと疑問に思わざるを得ません。歴史が意図的に作られているように思えるのです。
四百年もたってしまった現代の常識で考えるのではなく、四百年前の当時の常識が何だったのかを知らねばなりません。そうでなければ歴史の事実は見えてこないと思います。










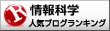














史料の評価にあたっては、史料の書かれた時期・内容だけでなく、書いた人物の意図の解釈が必要です。従来、軍記物についても、面白おかしく書かれた物語であることを忘れて、書かれていることをそのまま正しいことのように引用されてきています。
そして、軍記物が書いた怨恨説や野望説のストーリーの元ネタが、秀吉が家臣に書かせた『惟任退治記』にあることも気付かれていません。本能寺の変のわずか4か月後に秀吉が書かせた本が秀吉に都合のよい宣伝書であることをどなたも指摘していません。怨恨説も野望説も秀吉が意図的に広めたものであることを権威ある歴史学者にご指摘いただいていれば、これほど通説として広まることはなかったと思います。権力闘争の歴史を研究する方々が「政治的意図」に疎くてよいはずがありません。
そのような状況であればこそ、私は史料を書いた人物の意図を必ず検証することにしています。
この観点で14日付の家康書状の内容を評価すれば、その書状が周辺の武将を味方に引き入れる/敵に回さないことにある以上、彼らの主君である織田家に味方する内容を書く以外にありえない(光秀を支援するとは書けない)とわかります。
梅雪切腹についても同様であり、家康が梅雪の消息を尋ねられたら、梅雪を殺したとは答えられず、一揆に殺されたのだろうとしか答えられないとわかります。
したがって、14日付家康書状をもってして「家康は光秀を攻めるつもりだった」の証明とはなりません。もちろん、この書状をもってして「家康は光秀を支援するつもりだった」ともいえません。もし、そう言い張るのでしたら、それは「冷静で素直な史料解釈(特に一次史料に対して)ができなくなっている」とのそしりを受けるでしょう。
そうではなく、この史料では右とも左とも決められない、右か左かは別の証拠によって判断しなければならないと私は申し上げております。これが歴史捜査の姿勢であり、拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』を虚心坦懐にお読みいただければご理解いただけるものと期待しております。
秀吉が中川清秀に宛てた書状を類例とされていますが、軍事行動を味方の振りをして秘匿するのとはわけがちがいます。秀吉の場合は、光秀との戦闘にあたって、何が何でも清秀を味方に付けたかった。たとえそれがあからさまな嘘の情報であっても。秀吉の調略の傾向として、このような明らかな嘘や誇張はよく見えます。なお、偽装工作の類例を私は寡聞にして知りません。
また常識的に考えて、隣国ですらない美濃の諸将に変直後から偽装工作をするのかが分かりません。当初から、美濃を通って光秀救援に向かうつもりだったと言うのでしょうか。光秀救援を急ぐのであれば、なぜわざわざ津島に進軍(美濃入りが想定される)するのでしょうか?なぜ東海道(少なくとも伊勢を経由した方が近い)を進軍しなかったのでしょうか。出陣の延期や鳴海滞陣など史料による限り、家康が上洛を何よりも急いでいた様子はありません。これはおそらく14日書状に見えるように、三法師を擁立して美濃衆の軍勢を加えて、できるだけ軍勢を増やした上で明智方攻撃に出向こうとしたからだと考えるのが自然です(東近江で情勢を伺い柴田勝家らと合流するつもりだったかもしれません)。
この部分に関して、明智さんの説明は光秀・家康共謀説を前提にして強引に史料を解釈しているように思えます。史料を読まない一般の方はご説明で納得するかも知れませんが、史料を先入観なく読む限りご説明で納得できません。
結局こちらについても、仰るように共謀説の根拠をご高著で確認すべきと思いますので、またの機会としたいと思います。
藤本氏・鈴木氏のように共謀説がありえないと思っての疑問ではありません。個々の史料の積み重ねによって復元される家康の動向から見る限り、明確な反織田の動きは確認できないのに、家康は光秀救援のために尾張に進軍したと断定するのは無理がないかと思ってコメントしました。繰り返しになりますが、光秀・家康共謀説にとらわれる余り、つじつまが合うように恣意的に解釈され、冷静で素直な史料解釈(特に一次史料に対して)ができなくなっていると感じます。この点だけは是非ご理解いただきたいと思います。
前回書きましたように、光秀救援を急ぐ家康が「光秀への加担」を表明して周辺の織田勢と戦闘に及ぶような愚策をとるわけがないということです。14日に家康が光秀の敗北を知っていようが知っていまいが、この点は変わりません。家康の西陣の出陣目的は光秀救済であって、一刻も早く山崎の光秀軍との合流を急いでいたと解釈しています。(14日に家康が光秀の敗北を知っていた可能性もあることを書いたために、誤解を招いたとしたら申し訳ありません。その可能性がないとは思いませんが、本筋ではないので云々はやめます)
「家康の鳴海入りが織田領国への敵対行動ならば、それ以前の美濃の武将とのやりとりはどういう目的でなされたと解釈すべきでしょうか?」とお書きですが、これも東陣の「敵対」行動と同じであって、織田家であれば何でも構わず戦争を仕掛けることが「敵対」ということではありません。前述したとおり光秀救済のためには通路を妨害するような織田家との戦闘は避けることが当然の作戦です。そのためにはいかようにでも相手をいいくるめる、あまりにも当然の武将の戦術にすぎません。武将は勝ち残るためにあらゆる知恵を使い、工夫をしていたことは容易に想像できると思います。(秀吉が中国大返しの際に、「信長父子は無事で生きている」という書状を送って味方を増やそうとしたのも一例です)
「後世の我々は光秀の死によって明智方がまもなく滅亡したことを知っているので、山崎の敗戦で雌雄が決したと考えがちですが、光秀が生きていれば坂本なり丹波なりに退いて籠城し、短期間での決着はついていなかったと思われます。光秀と家康の密約は、光秀が緒戦に敗れただけで崩れるものだったということでしょうか?」とお書きですが、私の見方も完全に同じです。この件については解釈が一致しています。
拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』177頁にも書きましたが、家康は光秀敗北の報を受けると十六日には「津嶋へ陣替」の命令を出しています。鳴海から京都へ向かって、さらに進撃するという命令です。この命令がなぜ出されたのか?正にaki氏のご明察の通りの理由です。
「10日で先陣が出陣との推測ですが、そのような推測がありならばなんでもありになってしまいます」とお書きですが、これも拙著172頁あたりに書きましたが、九日にそれまでの「西陣待機」の方針転換となった重大な出来事があり、家康の主眼が西陣に急展開したことからの推論であって、思い付きの「なんでもあり」ではありません。
さて、ブログのコメント欄での討議からは話の進展に伴って次々に疑問が生じると思います。一度、拙著を通してお読みいただいて、全体の論理展開をご理解いただく方が有効に検討を進められると思いますが、いかがでしょうか。
『兼見卿記』は14日段階で光秀の死亡を確認していません(逃亡先は不明とする)。『多門院日記』は15日に山崎合戦で自害したとの情報を得ています(光秀が一揆に殺害されたことを知ったのは17日)。家康が光秀を救援しようとして進軍していたのならば、光秀が敗北しただけで方針を改めるでしょうか?後世の我々は光秀の死によって明智方がまもなく滅亡したことを知っているので、山崎の敗戦で雌雄が決したと考えがちですが、光秀が生きていれば坂本なり丹波なりに退いて籠城し、短期間での決着はついていなかったと思われます。光秀と家康の密約は、光秀が緒戦に敗れただけで崩れるものだったということでしょうか?
そして、『家忠日記』の記事ですが「旗本に出た。明智を京都にて信孝・秀吉・長秀・恒興らが討ち取ったとの、伊勢かんへからの注進があった」とあります。記事を素直に読めば、(軍議か何かで)旗本に集まっていたところに伊勢かんへから注進があった、と読み取れます。「伊勢かんへ」は「伊勢神戸」のことでしょう。つまり、信孝の本拠から連絡があったわけです。おそらく信孝が本拠の神戸に山崎合戦の勝利を伝え、神戸の信孝家臣は、鳴海に進軍中であった家康に情報を伝えたと考えるのが自然でしょう(大浜への渡海前に神戸付近を経由した縁か)。一度伊勢を経由しているので、15日に家康らに伝わったと考えたほうが無理がありません。
次に、14日の書状については、書状を出す前に家康が光秀敗北を知り、反織田姿勢を改め、織田方の武将に「光秀を討つために鳴海まできた」と自身の軍事行動の理由を説明をしたという解釈になろうかと思います。しかし、14日の書状を読む限りそのような解釈は不可能です。
まず6/14家康書状(吉村又太郎宛)
「今回の京都の状況は是非ないことです。そのため上様のお弔いとして我々は上洛します。それで今日14日に鳴海に出馬しました。そこで、ご馳走くださるとの旨を水野藤助が口上しました。喜ばしいことです。成就すれば本望です。」
6/14本多忠勝・石川数正連署書状(吉村又太郎宛)
「先日ご連絡いただきました。仰るように今回の不慮の事態は是非ない次第です。そのため京都に打ち上ろうと存じます。あなたがあれこれとご馳走くださるとのこと、家康は祝着と申されています。申し合わされて、今こそ、是非明智を討ち果たそうと思い、今日14日に鳴海に着陣しました。さらなるご馳走を頼みます。お考えもあるでしょうから、精一杯ご調整くださいとのことです。こちらについては任せ置かれてください。お人質は早々に出してもらえれば祝着と申されました。」
6/14本多忠勝書状(高木貞利宛)
「先日水野藤助を使者として様子について伝えましたところ、一々ご合点くださり、家康は喜ばれています。そこで、今日14日に鳴海に着陣なされました。そのため京都に打ち上られることを急がれていますので、人質を早々にお命じになるのがよいでしょう。今こそご才覚を廻らされ、ご馳走ください。また連絡します。」
6/14日家康書状写(佐藤六左衛門宛)
「手紙を拝見しました。仰るように今回の京都の仕合は是非ない次第です。しかしながら、若君様がございますので、供奉致し上洛し、彼の逆心の明智を討果たす覚悟で今日14日鳴海に出馬しました。とくにその地の日根野・金森とともに相談なさったとのこと、専一なことです。ご馳走は祝着です。なお、追って連絡します。」
以上の一次史料から、家康が14日以前から美濃の武将と連絡を取り合い、美濃の武将からは家康に協力する回答をしていたことが判明します。家康の鳴海入りが織田領国への敵対行動ならば、それ以前の美濃の武将とのやりとりはどういう目的でなされたと解釈すべきでしょうか?侵攻の下工作であったのならば、14日の返信で突然方針が変わったことを伝えなければなりませんが、そのような記述はありません。また、光秀の敗北を知ってから出した書状であれば、その記載がないのは不自然です。つまり、この書状の段階で、家康は光秀の敗北を知らなかったと読み取るべきで、家康の鳴海着陣は家康らが記すように光秀攻撃のためと解釈すべきではないでしょうか。
加えて、14日に反織田姿勢を転換したならば、17日に津島まで進軍した意味がわかりません。
また、10日で先陣が出陣との推測ですが、そのような推測がありならばなんでもありになってしまいます。『家忠日記』の記事を「家忠らへの12日出陣命令」と厳密に捉えるなら、そもそも史料に見えない先陣への出陣命令は10日に限る必要はなく、何日にでも推測できます。
また、家康一行の移動速度と軍勢の行軍速度を一緒にして比較するのはいかがなものかと思います。ましてや敵の領国であるとするならばなおさらです。
『家忠日記』での本能寺の変の勃発の報は翌日(三日)の酉の刻(夕方六時頃)。岡崎に近い深溝まで京都から届いています。13日の光秀敗戦が14日に鳴海まで届き、14日付の書状が書かれた可能性はあります。
加えて、この微妙な時期に鳴海周辺の地侍と戦闘に及ぶような「光秀への加担」を表明するような愚策を行うとも思えません。
したがって、14日付の明智討ちの書状が存在してもおかしくはありません。
また、鳴海から安土までの距離の問題ですが、拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』に書きましたが、家忠たちの東陣へ「12日出陣」の命令が出されたのが10日なので、この10日の時点で別働隊が安土へ向かえば十分な時間があります。
ラフな計算で恐縮ですが、直線距離にして160キロある堺・岡崎間を家康一行は2日早朝に出発して難儀しながらも4日に到着しています。鳴海・安土間は直線距離で65キロ程度ですので、1日で着いてもおかしくないと思われます。
なお、「敵対」の意味ですが、甲斐・信濃の織田軍に全面戦争をしかけて殲滅することではなく、家康のミッションとして軍事的な脅威を取り除けばよいわけなので、武田家旧臣を離反させて軍事力を削ぐだけで目的は達せられます。現実にそのようになったわけで、6日7日11日に書かれたような甲斐における家康方の行動は織田家への「敵対」行動です、という意味です。
ちょっと分からないのですが、本能寺の変直後の家康の西進行動は織田への敵対であっても全面戦争を意味しないということでしょうか?
家康の三法師擁立云々の典拠は、件の年表には書かれていませんので、調べてみました。おそらく『大日本史料』第11編之1の6月14日条の6月14日家康書状写(佐藤六左衛門宛)(600頁記載)かと思われます。
「京都之仕合無是非次第候、乍去若君様御座候間、致供奉令上洛、彼逆心明智可討果覚悟にて、今日十四日至鳴海出馬候」と書かれています。三法師を供奉しての上洛と明智攻撃のための鳴海出陣が明記されています。調べてみるまで全く知らない一次史料でしたが、明智さんのお考えと真っ向からぶつかる内容かと思います。明智攻めの意志については前後にも徳川方発給の史料が収録されていますので、あわせてご確認ください。
距離についてですが、100km近くは地図サイトからの目測でしたので、ルート検索で計測しました。鳴海から安土城まで最短距離と思われる421号線経由で90kmあります。
また、「鳴海にいて安土まで直線距離で100km近くあります」は本当でしょうか。日本地図で再確認していただければと思います。
なお、「敵対」を「全面戦争」と単純に見るべきでないでしょう。彼我の戦力や現実的な状況を見ながら最適な戦略・戦術をめぐらすのが当時の武将(しかも巧みに最終勝利者となった家康)の当然の姿勢と思います。光秀謀反失敗のリスクも織り込んで動くに決まっています。現代の企業経営者も同様に考えるでしょうが、戦国武将は一族の生死がかかっていたわけなので、現代の企業経営者が及びもつかないシビアな考え方をしていたと思います。
こういった戦略・戦術について、現代人の我々は彼らをしのぐ洞察はできないと私は考えています。ある歴史学者は「あの時点で信長がそんなことを考えるわけがない!」と言い切っていますが、随分と信長にも歴史にも不遜な態度だと思います。現代人には誰一人として、信長に先んじて比叡山焼き討ちも譜代の筆頭家老佐久間信盛の高野山追放も考え付かないでしょう。
ただ、依田信蕃が滝川一益に協力したことは6/21の小諸到着を示したつもりでした。光秀敗死に加えて清洲会議によって最終的に反織田姿勢を転換したとのお考えかと読み取りましたので、方針転換前のことと判断して問題にしました。
つまり、お考えでは清洲会議ではなく、15日の光秀敗死情報を知った段階で、家康は反織田姿勢を転換し、配下の勢力に反織田姿勢を中止するよう伝達したという理解でよろしいでしょうか?
徳川軍は東軍と西軍の二面作戦を遂行しており、松平家忠は西軍の部将ですから西軍の行動だけが『家唯日記』には書かれています。西軍の行動を見て甲斐侵攻が清州会議以降と判断するのは妥当ではありません。「13日徳川勢岡崎集結」という記述からして誤解を催す記述であり、家忠日記によれば「西陣に東陣からの援軍が到着」です。
また「反織田の一揆を扇動したわけでもない」という判断は6日7日11日の徳川方の行動や14日に河尻が信俊を暗殺した行為を見ると、そう言い切れないと思います。むしろ、河尻は徳川方の策謀を察知したからこそ信俊を暗殺するという非常手段をとったと考えられます。
安土城放火についても拙著をお読みください。その可能性について書いております。
信蕃が滝川一益に協力したのは六月二十七日のことであり、前回にも書きましたが、光秀の死を知った時点(十五日)で家康の織田家敵対の姿勢は転換せざるを得なかったので論点から外れています。岡崎帰着後から15日までの東陣の初動を問題としてください。
津島まで織田方と戦闘がなかったのは、その時点では敵対する織田勢力がその地域に存在していなかったにすぎないと考えます。
3日 酒井忠次より三河に家康帰国次第の西国出陣予定の沙汰がある。
4日 家康ら、岡崎に帰城。
5日 家康、陣触の下知。
6日 家康、岡部正綱に穴山領下山での築城を命じる。
7日 家康、本田信俊を河尻秀隆のもとに派遣。
9日 家康、西国出陣を延期。
10日 家康、12日出陣を通達。
11日 岡部正綱・曽根昌世、甲斐衆原多門に知行安堵。徳川勢の出陣14日に延期。
12日 小笠原貞慶、家康の支援で信濃帰国の準備が整う。
13日 徳川勢、岡崎集結。
14日 家康、美濃衆に三法師を供奉し上洛することを伝える。河尻秀隆、本田信俊を暗殺。徳川勢、鳴海に着陣。
15日 北条氏、甲斐郡内の調略を開始。
家康、本田信俊暗殺・明智光秀敗死の知らせを受ける。伊那国衆下條氏、家康の支援で帰城。
17日 徳川勢、津島に陣替。
18日 甲斐で一揆発生。河尻秀隆殺害。森長可、信濃海津城を退去。
19日 秀吉より家康に帰国要請。家康、鳴海に引き返す。森長可、美濃に帰国。
21日頃 家康、依田信蕃に甲斐衆の調略を依頼。信蕃、武田旧臣と共に信濃小諸に帰城。家康、岡崎に帰陣。滝川一益、小諸城に到着。
22日 家康、一揆を鎮圧した穴山衆を賞す。
24日 上杉勢、信濃長沼に着陣。
25日 北条氏、諏訪衆を調略。
26日 徳川勢、浜松へ移動。
27日 清洲会議。家康、酒井忠次の信濃派遣を決定。
28日 徳川勢、甲斐に侵攻し、北条方についた一揆を撃破。家康、恵林寺の修復・勝頼の菩提寺建立を布告。
7月2日 家康、甲斐に向けて出陣。掛川着陣。
家康が織田氏に敵対していたとすると、尾張の津島まで進軍過程で、織田方と戦闘に及んだ形跡がないことがまず不審です。
次に、安土城が燃えたのは15日とされますが、その頃徳川勢は鳴海にいて安土まで直線距離で100km近くあります。安土放火は不可能ではないでしょうか?
また、徳川勢の甲斐・信濃への侵攻は清洲会議以後のことで、それ以前は調略に留まっています。火事場泥棒的な行動ですが、反織田の一揆を扇動したわけでもなく、明確に織田氏への敵対とまでいえるものか疑問です。家康の支援を受けていた依田信蕃が、帰国中の滝川一益に協力している事実もありますし。
以上のような疑問から、変直後に家康が織田家と敵対したとする明確な根拠が見えてきません。
六月十八日に河尻秀隆が一揆に殺されて織田勢力が甲斐信濃から消滅した後、甲斐信濃は徳川・北条による簒奪合戦の状況となり、六月二十七日の清州会議で織田家は家康の簒奪を追認する決定をしています。
九月五日に三河刈谷の水野忠重が甲斐の徳川軍に合流しており、平山優氏はこれを清州会議の決定を受けての織田家の家康支援策と書いています。
この経緯での織田家との連携は私の認識と齟齬はありません。本能寺の変直後の初動で織田勢力が甲斐信濃から消滅したこと、さらに光秀が滅びたこと、織田家から甲斐信濃簒奪の承認を得たことによって、家康の織田家敵対の理由も消滅しているからです。
状況に応じて最善の策を選択して生き残りを図る戦国武将の政治の世界です。
なお、平山優氏は水野忠重援軍を織田信雄の家臣としての行動と判断していますが、私には若干の疑問が残ります。それは拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』に書いたように、水野忠重が本能寺の変の際に二条御所から脱出してきた「あの水野忠重」だからです。
河尻秀隆の誤解で本多が殺害される。河尻死後に甲斐の一部について穴山衆とともに一揆を鎮圧するが、織田領国であるため本格的な甲斐・信濃制圧は織田家の指示を待ってから行った。北条氏との対陣中には織田家からの家康に加勢派遣が伝えられている。
といった記述がされていたと記憶していますが、内容・頁について、週末にまた書き込みたいと思います。
「天正壬午の乱」という命名は極めて新しいもののようです。私も関心をもって調べています。平山優氏の同名の本(2011年3月学研)を読んでも、拙著『本能寺の変 四二年目の真実』に書いた事実認識は変わらないどころか、ますます確信を深めています。
その本には次のように書かれています。
「徳川方の曾根・岡部が甲斐の武士に知行安堵状を出したことを知った河尻秀隆は、家康の甲斐横領の意図は確実と判断し、六月十四日に家康家臣本多信俊を岩窪館で暗殺したのである」
ご存知のように河尻秀隆は甲斐を治めていた織田家の武将。本多信俊は家康に同行して「神君伊賀越え」をして三河に帰り着き、その後、家康の命令で甲斐へ派遣された武将。六月十四日は本能寺の変の12日後です。
この後、河尻秀隆は本多信俊殺害に怒った一揆に殺されますが、一揆の正体は家康と連携した武田家(穴山家)旧臣と考えられます。この後、武田家旧臣を抱え込んだ家康が甲斐を席巻します。織田家が甲斐で家康と連携して活動した史実は確認できていません。
「家康が織田家と連携した」という史実が全く確認できませんので、よろしくお願いいたします。
素朴な疑問なのですが、
>家康は本能寺の変の直後は織田家と敵対し、甲斐・信濃の織田領を攻めていました。織田家と敵対している家康にとって安土城は「敵の本拠」でした。
と、書かれていますが、近年研究の進んでいる「天正壬午の乱」に関する著書・論文を読んでいますと、一次史料上本能寺の変後の家康は明らかに織田家と連携して動いています。この点はいかがお考えなのでしょうか?