
本日はブリティッシュ・カウンシル主催、BBC交響楽団の奏者たちによる音楽ワークショップ「ファミリー・オーケストラ」@東京国際フォーラムに参加してきました! BBC響の人たちがトレーナーとなって、様々な楽器を持ち込んだ参加者100人と、2時間で一つの作品を作り上げるというイベント。
「あらゆる方が対象。まったく音楽に触れたことがない方でも、楽譜が読めない方でも、心配はいりません。どのような楽器を持ち込んでも大丈夫。子どもからお年寄りまで、さまざまな人が一緒になって音楽を作り上げるのが、このオーケストラの目的」
誘っていただき「面白そう!いきます!」とお返事したものの、気がつきゃ私、持ち運び可能な楽器なんてなんもできないじゃないか! ピアノしか弾けないもん・・・む?ピアノ? そういえば、持ち運べるピアノ、持ってたんでした。トイピアノ♪ 以前、フランスからやってきたアンティークピアノ君を連れていくことにしました~
会場は100人の大人と子どもたち。ヴァイオリンやクラリネットやフルートのほか、リコーダーやピアニカを持って来た人も多かったです。中には三味線や尺八も! あ、そうか、私三味線の師範だった、そのテもあったか!とは思いましたが、三味線は西洋音階で理解していないので、即座になにもできません。というわけで、トイピアノの私。どこに座るべきかわからなかったんですが、鍵盤ってことでピアニカの人たちに付いて行ったら、そこは管楽器セクションだった(爆)
で、2時間で「これから皆さんで一つの作品を作ります」っていうワークショップ・ディレクターのアポッツさん。これがまぁ、よく出来ておりました!面白かったので、 創作曲の構成を書いてみます。
まず参加者は弦、打、管、声の4つのセクションに分けられる。
1、どんな音でもいい。指揮者の合図で何音かを一斉にスタッカートで鳴らす。
↓
2、指揮者の指1本=レ、2本=ファ、3本=ソ、4本=ラ、5本=ド
の合図が、セクションごとにキューを出され、強弱や長さも指揮者に従う。
↓
3、弦=レ、管=ファ、声=ラ のロングトーンを指揮者の合図で。あいだにチューブラーベルが鳴らされる。
↓
4、セクションごとの曲の演奏(多分ここが山場。20分ほど、セクションに分かれた練習もありました)
弦=ドビュッシーの「海」的なフレーズの積み重ね
打=ストラヴィンスキーの「春祭」にインスパイアされたリズムアンサンブル
管=ガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」にインスパイアされた短いフレーズの合奏
声=ヴィラ=ロボスの・・・なんだったかな?・・・にインスパイアされた部族的な声とボディーパーカッション
↓
5、セクションごとに与えられたd mollの短いモチーフを、指揮者のキューに従い繰り返し、合図でフィニッシュ!
これを全部つなげて、見事、さいごに通して演奏したのです。何分くらいだったんだろう?たぶん10~15分くらい?の現代風な一つの曲になってました!本当に見事でした!
こんな風に言葉で書いたって、まったく状況が伝わらないかもしれませんが、良かったですよ。このワークショップの成功の鍵はどうやら・・・
●音楽的に限られた素材(モチーフ)を使うこと
●パートリーダーたちがしっかりと曲の骨組みを支えてくれること
●指揮者(ワークショップ全体のディレクター)が全身のアクションと話術で、巧みに参加者の集中力を惹き付けること
・・・あたりにあったのではないかと思います。もとより、参加者たちは何かしらオーケストラに関心のある人たちなので、経験値はバランバランだとしても、上記の条件がそろうと、創作曲の合奏としてきちんとまとまるのだと思います。
プロオーケストラによるこうしたワークショップの意味って、とくに子どもたちに「君も楽団員を目指そう!」とかいうよりも、音楽するという行為の根源的な歓びを味わい、オーケストラ団員の気分を体感することで、オーケストラを愛する「良き聴衆」を作ろうとしているのかなぁと感じました。
いいですよね、こういうアウトリーチの活動。
こうした活動が日本のオーケストラにも求められていくのでしょうか。面白いです。

「あらゆる方が対象。まったく音楽に触れたことがない方でも、楽譜が読めない方でも、心配はいりません。どのような楽器を持ち込んでも大丈夫。子どもからお年寄りまで、さまざまな人が一緒になって音楽を作り上げるのが、このオーケストラの目的」
誘っていただき「面白そう!いきます!」とお返事したものの、気がつきゃ私、持ち運び可能な楽器なんてなんもできないじゃないか! ピアノしか弾けないもん・・・む?ピアノ? そういえば、持ち運べるピアノ、持ってたんでした。トイピアノ♪ 以前、フランスからやってきたアンティークピアノ君を連れていくことにしました~
会場は100人の大人と子どもたち。ヴァイオリンやクラリネットやフルートのほか、リコーダーやピアニカを持って来た人も多かったです。中には三味線や尺八も! あ、そうか、私三味線の師範だった、そのテもあったか!とは思いましたが、三味線は西洋音階で理解していないので、即座になにもできません。というわけで、トイピアノの私。どこに座るべきかわからなかったんですが、鍵盤ってことでピアニカの人たちに付いて行ったら、そこは管楽器セクションだった(爆)
で、2時間で「これから皆さんで一つの作品を作ります」っていうワークショップ・ディレクターのアポッツさん。これがまぁ、よく出来ておりました!面白かったので、 創作曲の構成を書いてみます。
まず参加者は弦、打、管、声の4つのセクションに分けられる。
1、どんな音でもいい。指揮者の合図で何音かを一斉にスタッカートで鳴らす。
↓
2、指揮者の指1本=レ、2本=ファ、3本=ソ、4本=ラ、5本=ド
の合図が、セクションごとにキューを出され、強弱や長さも指揮者に従う。
↓
3、弦=レ、管=ファ、声=ラ のロングトーンを指揮者の合図で。あいだにチューブラーベルが鳴らされる。
↓
4、セクションごとの曲の演奏(多分ここが山場。20分ほど、セクションに分かれた練習もありました)
弦=ドビュッシーの「海」的なフレーズの積み重ね
打=ストラヴィンスキーの「春祭」にインスパイアされたリズムアンサンブル
管=ガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」にインスパイアされた短いフレーズの合奏
声=ヴィラ=ロボスの・・・なんだったかな?・・・にインスパイアされた部族的な声とボディーパーカッション
↓
5、セクションごとに与えられたd mollの短いモチーフを、指揮者のキューに従い繰り返し、合図でフィニッシュ!
これを全部つなげて、見事、さいごに通して演奏したのです。何分くらいだったんだろう?たぶん10~15分くらい?の現代風な一つの曲になってました!本当に見事でした!
こんな風に言葉で書いたって、まったく状況が伝わらないかもしれませんが、良かったですよ。このワークショップの成功の鍵はどうやら・・・
●音楽的に限られた素材(モチーフ)を使うこと
●パートリーダーたちがしっかりと曲の骨組みを支えてくれること
●指揮者(ワークショップ全体のディレクター)が全身のアクションと話術で、巧みに参加者の集中力を惹き付けること
・・・あたりにあったのではないかと思います。もとより、参加者たちは何かしらオーケストラに関心のある人たちなので、経験値はバランバランだとしても、上記の条件がそろうと、創作曲の合奏としてきちんとまとまるのだと思います。
プロオーケストラによるこうしたワークショップの意味って、とくに子どもたちに「君も楽団員を目指そう!」とかいうよりも、音楽するという行為の根源的な歓びを味わい、オーケストラ団員の気分を体感することで、オーケストラを愛する「良き聴衆」を作ろうとしているのかなぁと感じました。
いいですよね、こういうアウトリーチの活動。
こうした活動が日本のオーケストラにも求められていくのでしょうか。面白いです。












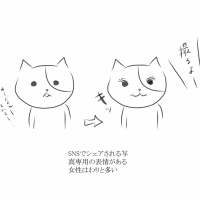


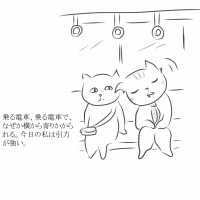
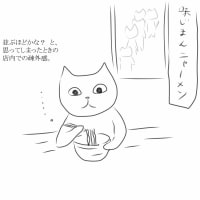


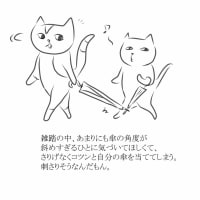
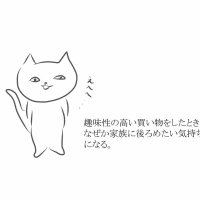
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます