第6回市民講座の報告(講演録)
【MOTOKOさんのお話】
■看護と尊厳 ―その人らしく生きることを支える―
Ⅰ.「脳死」と説明された方の看取りに関わって
はじめまして。看護師のMOTOKOと申します。今日は、『看護と尊厳―その人らしく生きることを支える―』というテーマでお話しさせていただきます。前半は、私が脳死臓器移植のドナーとなる患者さんとかかわった経験をお話させていただきます。後半は、その経験から患者さんに尊厳をもって関わるということはどういうことなのか、ということについてお話したいと思います。
1.ドナーとなる患者さんの看取りにかかわって受けた衝撃
まず臓器摘出に至った患者さんの経過を、簡単にお話します。臨床的な脳死であると医師の説明を聞いたご家族は、ドナーカードを持参され、話し合いのすえ、患者さんの臓器摘出に同意されました。一回目の脳死判定が開始されてから、臓器摘出のために手術室に向かうまでの時間は、わずか40時間にも満たない「あわただしい時間」でした。
ドナーとなる患者さんの看取りにかかわって、私はこれまでにない衝撃を感じました。臓器摘出から病室に戻ってこられた患者さんの遺体と対面して、「死なはった」、「死んではらへんかった」、そして結果的には「この人を殺してしまったんちゃうやろか」、と感じたのです。なぜそう感じたのか。自分は看護したといえるのか。落ち度が無ければそれでよしとしていいのか。そういったことをずっと問われていると感じています。
 2.臓器提供によって患者の死に意味を見出すことと、その死を悲しむこととは、同時に可能か?
2.臓器提供によって患者の死に意味を見出すことと、その死を悲しむこととは、同時に可能か?
2013年、5月25日の朝日新聞によりますと、『脳死での臓器提供を家族が承諾する理由最多は、「誰かの役に立ちたい」などの「社会貢献」』とありました。一方、本人の提供意思が書面で残っていた事例では、すべての家族が「本人の意思だから」と答えたそうです。(今年6月末、法改正後の脳死臓器摘出189例中、家族が判断したケースは142例)
ここで一つの疑問が生じます。まず、大切な家族の死を前にして、残された時間は患者と家族の為にあります。それは、亡くなっていかれる悲しみを悲しむ時間でもあります。家族の承諾によってドナーとなる患者さんとそのご家族にとっても、残された時間は共に生きる最後の時間です。「看取り」とは、「残された生を共に生きること、やがて鼓動を止めて冷たくなっていくいのちの傍で、見守り悲しむいとなみ」でもあります。しかし、報道が示すように社会貢献のために臓器提供をし、そのことによって患者の死に意味を見出すことと、その死を悲しむこととは、本当に同時に可能なのでしょうか。
私がかかえている「しんどさ」は、「いのち」の看取りと脳死臓器移植のはざまで生じた葛藤だと考えています。看護師が「いのちと向き合う」、とか「いのちに寄り添う」と言うときの「いのち」とは、どういう意味で使っているのでしょうか。
3.関わりの中で生き続ける存在:「いのち」の看取り
看護師は、病をもちながら生き、生活する人と関わります。そこにはその方の人生の歩みも見つめる目があります。ですから、看護師は病気の人とその人を取り巻く人々や環境にも眼差しを向けています。さらに、看護師でなくとも、亡くなられた方に想いを馳せるとき、私たちは死者とも会話出来るときがあると思うのです。このように、「世界の中で人々と共にさまざまな関わりをもちながら生活し、他者の記憶の中にも生き続け会話することもできる存在」を、私は「いのち」と呼びたいと思います。
さて、「いのち」がこのような意味なのだとすると、人がこの世で生き切ろうとするのを看取ることと、その方に臓器摘出に向けた様々な処置やバイタルサインの調整を行うことは、異なった次元にあることになります。およそ操作できるとかできないとかいう次元にはない「いのち」の看取りと、操作そのものである臓器摘出術前の処置の対象としての身体。両者のはざまには、絶対的な断絶があります。私のかかえた「しんどさ」とは、この絶対的な断絶がある二つのことを、一人の人間に対して同時に行わなくてはならなかったことと関係していると考えています。
誰かを「看取る」ということは、共に生きることだと言いました。そこでは、看護師も看取りの当事者の一人として関わります。私は看取ることは、「看取りの医療」を提供することと同義ではない と考えています。看護師は、患者と家族の傍らで、彼らの思い、語りを聴き取り、自らできることを考え家族と共に患者のケアを実践します。
私は、臨床的な脳死状態と説明された方の看取りにも関わってきました。そのなかの印象的な患者さんの看取りについて、いくつかお話したいと思います。
ある方のご家族は本人も希望していたので人工呼吸器をはずして欲しいと希望されました。医師、看護師、ご家族とで話し合いをし、必要最小限の呼吸と循環を確保しながら看取ろうということになりました。ご家族や恋人とできる限り自由に一緒に過ごしながらゆっくりと、静かで濃密な時間を過ごされてその方は逝かれました。
また、出産後間もない女性の実のおかあさんは、一週間ほど面会に来ることが出来ませんでした。しかし、お母さんが娘さんのところに来ることが出来たのは、「娘は私に会いたがっているにちがいない」と思えるようになったからだったのではないかと思います。それからはずっと娘の傍で過ごされました。お母さんが娘さんと過ごしておられるのを、看護師は見守り、顔を拭くなどのケアに一緒に参加していただきました。
青年のご家族は、微かでもいいから奇跡が起きて欲しいと、ずっと身体をさすり、声をかけておられました。医学的には「聞こえていない」「意識がない」「脳死状態である」といわれる人に、家族も看護師も声をかけます。それは人として当たり前の態度です。そして、声かけに何か返事を返してくれているような反応や変化を聴き取ろうとする行為でもあります。
ある小学生のお子さんは、医師の手で人工呼吸をしながら、機械音の無い病室で母親の腕に抱かれて亡くなりました。また乳児の患者さんは、二ヶ月以上をICUで過ごし、1歳のお誕生会をしました。
彼らに共通していたのは、様々な処置や検査、説明や自己決定をすることなどの、死に逝くことの外にある事柄に急かされることのない、家族だけの濃密な時間の過ごし方があったということです。こうした看取りにおいて、その人が最後の時間において社会貢献の行為をしたかどうかで、その生に価値のあるなしを見いだすような視線を向けることは、あたかも「いのちの値踏み」とさえ呼びうるものに陥りかねないのではないでしょうか。やはり、社会貢献とか死に意味を見出すことは、「いのち」を看取ることとは別の次元にあるのではないでしょうか。
4.「死へのカウントダウン」と悲しみの忘却
人が死を迎えるとき、「予定時間が決まっている」死はありません。ドナーとなる患者さんと関わるなかで、この「予定時間が決まっている」ことを「死へのカウントダウン」と表現した看護師がいました。人が亡くなる場に居合わせ、「いのち」を看取るとき、そこには「あと何分で」とか、「何時頃には」とか、あらかじめ決まっている時間に向かって待つことができるような時間は流れていません。たとえその死を待っている人がいたとしても、その時間がどれだけあるのかは誰にも待てないもの、待つことがその人の生をないがしろにするように感じるものではないでしょうか。
ところが脳死臓器移植のドナーとなる方の看取りは、幾重にも宣告がなされる過程が重ねられていきます。まず、法的脳死判定が終了し死亡時間が確定するとき、次に温かい身体で人工呼吸器の助けで息をしながら手術室に臓器摘出に向かうとき、そして摘出手術を終えて冷たく軽いご遺体となってご家族に再会されるとき、その都度、ご家族は患者さんの死に立ち会うことになるのです。そして、三回ともその予定時刻があらかじめ立てられているのです。
看護師は身体ケアを通じて患者と語らいます。声をかけ、手を動かしながら、身体の向きを変え、家族や患者と語らいながら、家族のケアへの参加を促します。そのときに、家族は患者との思い出を聞かせてくださったり、心情を打ち明けてくださったりします。看護師は、患者と家族だけの静かな時間と空間を出来るだけ見守り、その時空に満ちている空気を共有します。看護師も彼らの「いのち」と共鳴し、悲しみ、泣き、つらいと感じます。それは、人が「生きてあること、死んでいくこと」への学びを深め、「いのち」のかけがえのなさを学ばせてもらう経験でもあります。
臓器摘出を待つ患者とその家族の看護は、脳死状態に陥った人たちの看取りとは異なる決定的な困難をかかえます。一方では臓器摘出に向けての指示されたバイタルサインの維持管理、他方では家族と患者の時間を大切にし、家族と共に身体ケアを考え実践する。そこには「死体body」のバイタルサインの管理と、「いのち」に寄り添うこととの両方が求められます。
私が臓器移植のドナーとなった患者の看取りに関わってショックを受けたときの、同僚看護師たちの言葉です。ある看護師は自らが抱く「思いや疑問なんて、患者やその家族から見たら関係ない」と否認し、「患者と家族が望むことを一生懸命やるだけ。それは他の患者家族と何ら変わりはないと結論を出し、私の想いは封じ込めることにした」と述べています。
あるいは別の看護師は、「患者の意思を尊重する思いと、命を決めてしまうことに対する抵抗感」の間で「辛さ」を感じつつも、レシピエントが移植を待っていることに目をむけそれをのり越えようとします。ここでは、看護師自身が自らの辛さ、思い、疑問を棚上げにし、ドナーとなる患者と家族の意思や、レシピエントが待っていることに思いを向けて、「微妙な薬剤の調整」や「他の患者と何ら変わらない」看取りのケアを同時にやり遂げようとする姿が浮かんできます。
私は管理者として、臓器摘出に向けての諸々の処置から退院されるまでのタイムテーブルを作って担当看護師たちに示す一方で、家族が患者との残された時間を悔いなく過ごせるように看取りのケアも出来る限りしていこうと、スタッフと共に自分もケアに参加しました。
そのタイムテーブルを作り指示した私自身が、「予定時間の決まっている死」を迎えて病室に戻ってこられた患者さんを見て、大きな衝撃を受けました。「悲しみを悲しむこと」を棚上げし、いわば本来の看取りの重要な意味をあえて忘却したのです。そうすることなしに、死へのタイムテーブルは実行できなかったのです。
バイタルサインを示す脳死の患者を、看護師は「死体」とみることは出来ません。ドナーとなる患者は、今、ここで、病をかかえながら家族と病院で生活している人です。操作の一対象ではなく、一ドナーでもなく、一人の生活者、ある人の子や父母や妻や夫です。その一人の人を、人工呼吸器を作動させながら臓器摘出に送り出さなくてはならない時、それまでにいくら「看取りの看護」を実践しても、「いのち」を操作しているという「疑問」や「抵抗感」はなくなりません。しかしこうした「疑問」や「抵抗感」を押し殺し、いわば意図的に忘却することなしには、手術に送り出すことはできません。
手術室に向かう時間となったとき、看護師は家族にどのように声かけしていいかわからずにいました。ご家族の、「もういいです」に促され臓器摘出に向かいました。それがたとえば頭蓋内圧を下げるための手術であったなら、「さあ、行きましょう。がんばってね」と声をかけて送り出すこともできたでしょう。 しかし、この時担当した看護師はその言葉をかけられなかったのです。ある看護師は、「ごめんね」と「心の中で」患者に語りかけてケアしたと述べていました。
5.「問いかけ」に応えるために
あのときから年数がたちました。今私は、患者さんは私に「問いかけていた」のだと受け取っています。 私が尊重したその方の「意志」は本当に「あの時の患者の意志」だったのか。それはもうこの世では確認できないことです。私は「いのち」に向き合ったつもりで「いのちの操作」を指示し、またそうしていただけなのではないか。あるいは、私が行ってきたこれまでの各種看護実践は単なるメニューの適用にすぎなかったのではないのか。看護とは何か、看護ではないものは何か。今も、そしてこれからも問い続けなくてはならない と思っています。それがあの「問いかけに応えること」だと思うのです。
Ⅱ.看護師の仕事
それでは、後半はこうした経験を元に看護師にとって「尊厳」とはどういうことかについて私が考えていることをお話したいと思います。患者さんの尊厳を傷つけるようなことに、看護師は黙っていてはならないし、そういったことに無頓着に看護しているというのでは、それは看護とはいえないからです。
最近新聞でも「尊厳死」が取り上げられていたのですが、この「尊厳」ということについて看護の立場から考えてみたいと思います。看護の現場では「尊厳」という言葉をほとんど使いません。看護師が患者さんの「尊厳」を意味することを語るときには、「尊厳が傷つけられる」危惧や、その状況が生じたときに、その危惧や状況を生じさせるものにたいして、危惧を回避したり状況を変化させたりするために何ができるかを考えるときではないかと思います。こうした場合に、よく用いる言葉は、「人間らしく」や、「その人らしさ」という言葉です。「尊厳」という言葉は抽象的で、これを発言する人、また受け取る人によって意味が異なるものではないでしょうか。今日は、「尊厳」に代わる言葉として「その人らしさ」について考えてみたいと思います。
「その人らしさ」を大切にしてケアすることについて話し合うとき、その方が何を必要とされているのか、「その人らしく」生きる上でどのようなケアがふさわしいのか、病を抱えたその方がその病をどのように乗り越えて下さることを期待するのか等を、参加者が考えます。「その人らしさ」という言葉を使うことによって、より具体的に患者さん個々人をめぐって何をどのようにしたら良いかを、考えることができるように思います。そして、「その人らしさ」と他人が呼ぶものは、その人本人にとっては「自分らしさ」と同じではありませんが、「その人らしさ」を巡って話し合うときには、本人が「自分らしい」と感じて下さることをめざします。こうして話し合われたケアがされるとき、本人さんが、「自分が自分であっていいのだ」という自己肯定感へとつながることを期待します。
日本看護協会の看護業務基準には「看護とは、対象の生涯を通してその最後まで、その人らしく生を全うできるように支援を行うこと」
と、かかれています。
1.初めて患者さんと接したときのこと
私は看護教育を受けるまで、「看護師は注射したり、脈拍を測ったり、薬を飲ませたりする人」だと思っていました。看護学校に入学して1年目、前期の学科試験が終わると見学実習がありました。ナースキャップももらっていない高校卒業したてで、当時は見学とはいえいきなり臨床実習がありました。
私が初めて患者さんに援助に行かせてもらったのは、忘れもしない高齢女性のベッド上排尿援助でした。ナースコールがあって、臨床実習指導者に「あなた行って来なさい」といわれ、病室に行くと「あんただれ?あっちいって」とおっしゃいました。患者さんにしてみれば、援助が必要だからコールしたのに、来たのはナースキャップもかぶっていない見ず知らずの女の子、しかも自己紹介もせずに、「あの・・何ですか?」と聞かれても、役に立たない見知らぬ子がきたと思われたことでしょう。私は患者さんという方に初めて接し、しかもその方から「あっちいって」といわれて、打ちひしがれて指導者の下へ帰り報告しました。そして指導者の方から、「なぜそういわれたのかわかる?あなたが患者さんの立場だったら、今のあなたの態度や言葉かけをされたらどう感じる?」と聞かれました。実は患者さんは排尿したくて、しかもそれをベッド上でしなくてはならなかったのでナースコールを押されたのでした。
このことをきっかけに、同じ実習グループのメンバーで排尿にいたる動作と心理状況について夜を徹して話し合い考えました。
たとえば、排尿についてです。尿意を感じる⇒排尿はトイレですることがわかる⇒トイレの場所を知っている⇒トイレでの作法を知っている⇒音を立てない・聞かれたくない(当時は音姫などありません)⇒臭いを消したい(当時は便座に消臭機能はありません)⇒拭く(当時はウォシュレットなどありません)⇒流す(さすがに水洗はありました)
そして、トイレで排尿するという健康な人にはごく当たり前の行動が、実は社会的で心理的で、肉体的で、何より自尊心に関わる行動なのだということがわかったのです。このことは現代の高度で多機能な便器を思い起こせばなるほどと思われます。排尿という基本的な生理的欲求も、他者との関係で音や臭いが気になり、その行為を丸ごと他人に委ねなくてはならないとき、そこで生じる屈辱感や羞恥心、申し訳なさがおきます。そうした思いを抱いている方を共感的に受けとめられるような配慮が、看護には求められているのだということを、私たち看護学生は最初の実習で患者さんから学ばせていただいたのでした。
私がこの経験を忘れないのは、初めてでしかも拒絶された経験ということもありますが、看護師が生活の援助をすることの核になる意味を教えていただいたからだと思います。
2.病とともに生きる人への援助
看護師の業務を定めた保健師助産師看護師法、通称「保助看法」には看護師の仕事がさだめられています。レジュメをご参照ください。
「療養上の世話」と「診療の補助」が看護師の業務、仕事であると定められています。「療養上の世話」は、たとえば、食事や排泄、身体の清潔、環境の調整など日常生活行動の援助や、患者や家族の悩みを聞き、相談に乗ること、他職種との連携調整などがあります。「診療の補助」は、注射や採血、診察や手術、処置の介助などがあります。しかし、この療養上の世話と診療の補助は、実は明確に切り分けることはできません。それは、同じ一人の人に関わることだからです。人は、あるときは療養上の世話を必要としているが、別の時には診療の補助を必要としているというように区切りをつけて生きているわけではありません。
たとえば、食事療法。あるいは理学療法、作業療法。また、モーニングケアからイブニングケアまで。排泄の援助、清潔の援助。体位変換。安眠への援助。すべては、患者さんの生活そのものであり、またそれらが整えられるからこそ、治療の効果も高まるものです。
療養上の世話と診療の補助は、実際一人の人において容易に分けられないところがあります。
また、意識のない人にとって、すべては他者の支えがなくては生活できないのですが、そういったコミュニケーションのとれない人の代弁をすることが看護師に求められています。たった一筋のシーツのシワが痛みや違和感を自分で訴えることのできない人にとっては、褥瘡の元となったりします。
一人の、生きて生活する人が病を抱えて治療を受けておられ、したくてもできない、できるけれどもしてはいけない、自分の苦痛や希望を他者に訴えることができない、という状況におかれてしまうのですから、看護師は病に対する知識だけでなくその方がこれまで生きてこられた歴史的背景や大切にしてこられたものを知って、その方にとって必要な援助がその人にとって適切な仕方で受けられるように援助しなくてはなりません。
看護の主役はこうした病という状況に投げ込まれ、家族をはじめ他者とともに人生を紡いでこられたたった一人の「生活する人」なのです。
3.看護・世話・ケアcare
「看護」を辞書で引くと、「世話すること」という意味が出てきます。
次に「世話」を引いてみると、面倒をみること、取り持つこと、厄介であることなどあまりいい意味ではありません。同じ行為でも、「お世話になりました」と感謝されることもあれば、「大きなお世話や」と叱られることもあります。看護師の行為が看護であるかそうでないかは、看護師と患者さん(家族や周囲の環境)との相互関係に依存しているといえます。看護師だけが「私は看護している」と言っていても、患者さんや家族がそれを認めて下さらない限りは看護とは言えません。看護とは看護するものとその対象となる人との相互関係によって成り立ちます。
ケアcareという言葉には、看護が相互関係によって成り立つことを、日本語よりもうまく表現しているように思います。careを辞書で引くと「気づかう」「心配する」「関心がある」という意味がのっています。他者のことを気づかうこと、先ほどの実習の話のように、排尿するというプライベートで基本的な生理的行為を他人に委ねなければならない人への配慮こそケアであり、それこそ看護における倫理そのものといえます。
そして、看護の「看」という字。字義は、「手をかざして見る」とあります。看護の看は「手」と「目」でできているのです。看護は病気ではなくその患者さんをよく見ること、つまり観察と、そして援助の必要を満たすために手をさしのべること、つまり生活援助とでできているのだといえます。
Ⅲ.看護と尊厳
1.職業倫理に規定されている「尊厳」
日本看護協会の『看護師の倫理綱領』には看護師の職業倫理が規定されています。レジュメをご参照ください。
前文では、人々の「人間としての尊厳の維持と、健康、幸福」へのニーズは普遍的であること。看護師の使命はそれに応えて健康な生活の実現に貢献すること。さらに、看護の目的は「その人らしく生を全うできるように援助を行うこと」であること。最後に看護に求められるのは人権の尊重であると謳われています。
条文では、「看護者の行動の基本は生命、尊厳、権利の尊重」と謳われています。つまり、人は看護師から生命、尊厳、権利を尊重されて援助されなくてはならない、ということです。「あなたのおむつを替えてあげる」ではなく、「私におむつを替えさせてください」という態度です。
2.受動態、完了形としての尊厳:「傷つけられ」「奪われた」ものとしての尊厳
この文章には尊厳について二つの解釈ができるように見えます。一つは、人には尊厳があってそれが保障されなくてはならない、という意味。もう一つは、人には尊厳があるが、そのことを保障するのは他者(看護師)の尊厳を尊重した態度である、という意味です。前者の解釈の場合、どの人も尊厳を持っていることが前提です。
ところで、私たちは日々「私には尊厳が備わっている」と自覚しながら生活しているでしょうか。「保障されなくてはならない」尊厳とは、保障する他人がいて初めて成立つことではないでしょうか。この尊厳が保障されなかったときには、尊厳は存在していないというよりもむしろ「尊厳が踏みにじられた」という思いを抱くのではないでしょうか。したがって、看護師の倫理綱領の言おうとしているところは、後者の意味での尊厳であるといえるでしょう。すなわち、尊厳とは「私は尊厳を持っている」というよりもむしろ、「私は尊厳を尊重されている」というように、受動態・完了形として備わっているのではないでしょうか。
私たちは、普段自分の尊厳がどうであるか、守られているか、今日も尊厳をもって生活した、などと思って日々を生きていません。尊厳とは、今あると確認できるものではなく、むしろ他者によって「踏みにじられた」「辱められた」と感じるときに、尊厳が「傷つけられた」「奪われた」、と感じられるもの、常に他者によって尊重されてあるものなのではないでしょうか。
3.未来形としての尊厳:「尊厳」の反転
では、このような場合はどうでしょう。「尊厳は現に備わっており、それが奪われる前に尊厳を確保しようとする」場合です。これは、現在「誰々の尊厳は傷つけられ、奪われている」と感じる状況にあって、「その状況で生き続けるくらいなら死んだほうがマシ」という本人以外の者の判断により、死に至らせるという場合が当てはまるのではないでしょうか。
私が30年ほど前に看護師になったばかりの頃には、まだ従軍看護の経験のある方々が現役で働いておられました。その方の話によると、「満州から引き上げるときには、重症患者に青酸カリを飲ませておいてきたらしい」ということでした。当時は半信半疑だったのですが、最近ネット検索してみると同じような証言がありました。レジュメに参照例をのせていますが、
・重症患者に青酸カリを飲ませてソ連侵攻からのがれた看護師。
・婦長の指示で毒入りミルクを配られた患者たち、の証言をしたひめゆり隊の生き残り。
・ハリケーン・カトリーナのときのメモリアル病院での安楽死事件では、「もしも置き去りにするのなら、死なせてやるのが人間的」という判断のもとで死ぬまでモルヒネを投与した看護師。
戦争や災害時には、見捨てるに忍びなく、人間的処置と称して、「死なせる」ことが尊厳を守る方法として選択されてきました。そこには、「傷つけられる前に殺す」ことによって守られる「尊厳」なるものが考えられているのではないでしょうか。殺人によって守られる「尊厳」などないと思いますが、歴史を振り返ると、「尊厳」という言葉は、周りの状況によっては生かせて守る「尊厳」から、死なせて守る「尊厳」という意味へと、容易に反転してしまうことがわかります。安藤泰至さんは現代医療に混在する「二つの方向性」、「不死のベクトル」と「死なせるベクトル」と述べておられますが、尊厳の意味が反転してしまうのは、この二つのベクトルのどちらにも、「尊厳」を対象化して、人為による「操作」が可能であるという視線が注がれているのではないでしょうか。しかし、「尊厳」とは、そのように扱うものの見方によっていかようにも操れるものではないはずです。そこには、かけがえのない現在を「生きていることの尊厳」はありません。
Ⅳ.現在としての尊厳:今ここで生きている人の「その人らしさ」を大切にする
では、「尊厳」がそのように人為によって操れるようなものではないとしたら、私の尊厳が自分も含めて誰によっても損なわれてはならないものとしてみるなら、どのようにとらえたらいいのでしょう。看護師が患者さんの尊厳を守る、尊重するということはどういうことなのでしょう。
1. その人の「もてる力」への信頼
ナイチンゲールは、一般的に「病気とは、毒されたり衰えたりする過程を癒そうとする自然の努力のあらわれであり」、「回復過程」であると考えました。それゆえ、「看護とは(…)患者の生命力の消耗を最小にするように」内的あるいは外的な環境を整えることであると述べています。彼女は、看護することを不可能にしているものに対して調整を図ることは、看護の技術であると述べています。
ナイチンゲールが病気は「回復過程」であると述べていたことは、今日いわれる「自然治癒力」や「免疫力」という生命に備わる力すなわち、患者さんの「もてる力」への信頼があったということです。
患者さんの「もてる力」を信頼し、その消耗を最小にし、それが最大限に発揮されるように働きかける。このことが看護の目的であり、その結果、患者さんが「その人らしく」生活できる力を取り戻されたとき、看護師はそのような活動に関わり、変化の過程に寄り添わせてもらえたことに幸福を感じることができるのです。
2.「生きること」の「かけがえのなさ」=QOL
次に一般的には「生活の質」とか「生命の質」とも訳されるQOLについて看護の立場から考えてみたいと思います。
まず看護師の大事な仕事である「生活援助」という言葉の「生活」にもかかわるlifeの意味です。辞書で調べるとlifeには主として三つの意味が書かれています。
一つ目は「生活」、二つ目は「人生」、三つ目は「生命」という意味でのlifeです。
ここで、医療者が大切にしている「その人らしさ」の内容について調査した研究をみてみますと、その人らしさとは、レジュメにありますような6つの意味で捉えられているのだという分析がなされていました。
この研究で捉えられている「その人らしさ」も、その方が生きてこられた「人生」において築いてこられた「生活」のスタイル、嗜好、行動パターン、人生観や周囲の人との関係、役割、そしてその「生活」「人生」の土台となる「生命」の意味を含んでいるといえます。そして言い換えるなら、「その人らしさ」とは、その方の「もてる力」ということになるのではないでしょうか。「その人らしさ」がその人固有の「歴史を背負って病を生きている人」のそれである以上、一般的な言葉で言いつくせない「固有性」いいかえるなら「かけがえのなさ」としてとらえられなくてはなりません。このことが、「その人らしく生を全うすることを支援する」看護の使命だと考えます。
「歴史を背負って病を生きている人」のlifeという意味で「life」を捉えるなら、lifeを「生きること」と訳してはどうかと考えます。そして、QOLのQ、すなわちQualityは「質」ではなく、その人の今を生きていることの固有性を表わす「かけがえのなさ」と訳したいと思います。QOLとは「生きることの」「かけがえのなさ」のことで、決して生活の質の「ものさし」ではないと思います。
QOLを「ものさし」としての「生活の質」ととらえてしまうと、尊厳のように反転が起こってしまいます。たとえば、人工的な栄養補給を行えば体力が回復し、最終的には口から食事を摂ることができるかもしれないのに、そのような姿はみじめだ、尊厳がそこなわれるのではないかという声が聞かれます。「アンナンなってまで生きていたくないわ」とおっしゃる方もおられます。このようにおっしゃる方は、他人の姿をみて、そこに自分を重ねておられるのですが、実際に「胃瘻」や鼻腔栄養をされておられる方にとっては、周りの人が「かわいそうに」というほどには自分のことを「かわいそうだ」とは感じておられないのではないかと思います。それよりも、消化管を使うことによって、免疫力が保たれ、必要な栄養が摂取できることによって体力が増し、嚥下訓練に取り組めるようになり、生きる意欲につながっていく方々がたくさんおられます。
一方では救命医療、移植医療といった高度な医療処置によって、「死なせない」医療がすすめられ、また一方では、回復期、慢性期における侵襲の少ない生命維持に欠かせない処置は「尊厳を損なう」「単なる延命処置」とみなし、尊厳を守るためにはそれらを拒否・中止して「死なせる」医療がすすめられようとしています。まさに「死」さえも「操作」の対象にされるのです。
「その人らしく生きることのかけがえのなさ」を大切にしようという視点で考えたとき、そこには、これまでの生き方や周囲の人々の思いを大切にして、その方が生きていくためには何をどのように整えていくのが良いかを考える視点が生まれるのではないでしょうか。その方が、ただ生きていてくれただけで、私は励まされたという方のお話を聞きます。言語的に会話が成り立たなくても、ただ顔をみて話しかけるだけで、聞いてもらっていると感じることのできる家族の間柄があります。そのときその方たちの間には、互いにその方たちにとってのかけがえのない場が共有されているのだと思います。
私は、「尊厳」を保つこと、QOLを高めることは大切なことであると思います。でも、「今生きているその人」を飛び越えて、何か一般的な価値や真理としての「尊厳」や「QOL」があるとは思いません。尊厳とは今を生きる人に固有に見出されるべきものであり、QOLとは、「生きること」の「かけがえのなさ」という見方でとらえられるべきものだと思います。
Ⅴ.看護師が尊厳をもって看護するということ
1.「生きることのかけがえのなさ」を大事にする
人にはその人固有の身体状況があります。「病や障害をもって生きる」人にとって、時に人工呼吸器はその方の鼻であり気管であり肺そのものです。胃ろうから食事を摂っておられる方にとって、胃瘻は食道であり、心臓ペースメーカーはその方の心臓の刺激伝道系です。人工呼吸器や胃瘻や心臓ペースメーカーは、その方の生きるための機能を担っている身体の一部、というより身体そのものです。ところが、身体を様々な機能の集合体ととらえると、その人が病や障害を持ちながら一人の人として生きていることが見えなくなり、いつのまにか喪失された機能にだけ目が行き、そこに、「生活の質」「生命の質」という「ものさし」をあてがうような、偏狭な見方に陥ってしまいます。尊厳死をめぐる議論はそういったことだと思います。
2.「尊厳ある死」への疑問
私は、「尊厳」とは、「その人らしく生きることのかけがえのなさ」を自分からも他人からも大切にされることによって尊厳が尊厳として守られていくものだと思っています。自分が今あるままに生きていていいのだという自己肯定と、そうして生きるありのままのその人の生のかけがえのなさを周囲の人だけではなく社会の在り方として大切にされること、このいわば内と外からの肯定によって、たった一人のその人のかけがえのなさ、尊厳が尊重されていくものなのだと思います。
安楽死・尊厳死についてホスピス医の山崎医師が述べておられることです。彼は、「間接的安楽死(消極的安楽死と同義)という用語や概念は不要」としたうえで、レジュメにあるように述べておられます。
ここで述べておられるように、今ここで病とともに生きている人の苦痛を緩和し、よりその人らしい生を支援する適切な医療がなされるのであれば、尊厳ある生への努力はあっても、尊厳ある死を意図的にもたらすことなど、考えなくてもよいことなのです。尊厳ある生はあっても、尊厳ある死などありません。
3.「きいてください」の声に、声なき人の声に応えること
最後に次の詩を、ご紹介します。
「きいてください看護婦さん」 ルース・ジョンストン
ひもじくても、わたしは、自分で食事ができません。
あなたは、手の届かぬ床頭台の上に、わたしのお盆を置いたまま、去りました。
その上、看護のカンファレンスで、わたしの栄養不足を、議論したのです。
のどがカラカラで、困っていました。
でも、あなたは忘れていました。
付き添いさんに頼んで、水差しをみたしておくことを。
あとで、あなたは記録につけました。わたしが流動物を拒んでいます、と。
わたしは、さびしくて、こわいのです。
でも、あなたは、わたしをひとりぼっちにして、去りました。
わたしが、とても協力的で、まったくなにも尋ねないものだから。
わたしは、お金に困っていました。
あなたの心のなかで、わたしは、厄介ものになりました。
わたしは、1件の看護的問題だったのです。
あなたが議論したのは、わたしの病気の理論的根拠です。
そして、わたしをみようとさえなさらずに。
わたしは死にそうだと思われていました。
わたしの耳が聞こえないと思って、あなたはしゃべりました。
今晩のデートの前に美容院を予約したので、 勤務のあいだに、死んでほしくはない、と。
あなたは、教育があり、りっぱに話し、純白のぴんとした白衣をまとって、ほんとにきちんとしています。わたしが話すと、聞いてくださるようですが、耳を傾けてはいないのです。
助けてください。
わたしにおきていることを、心配してください。
わたしは、疲れきって、さびしくて、ほんとうにこわいのです。
話しかけてください。
手をさしのべて、わたしの手をとってください。
わたしにおきていることを、あなたにも、大事な問題にしてください。
どうか、聞いてください。看護婦さん。
この声、声なき声にも耳を傾け、聞き取る努力、応える努力を、私はこれからも続けようと思います。










 はじめに
はじめに



 血圧の変動は、皮膚切開から大動脈遮断までに6回の上昇がみられます。このうち最も急激に上昇したのは手術開始後80分頃にあり、収縮期血圧が110mmHg程度から160mmHg程度にまで急上昇した。 その後、約5分のうちに再び110mmHg程度に急下降した。この血圧が最大に上昇した時に、鎮痛剤の投与量は臓器摘出術中で2番目の大量投与となる0.2マイクログラムが投与された模様です。同様の血圧の急上昇・ 急下降が、この後にも2回記録されている。開腹操作時や胸骨切開時には、鎮痛効果が少なかった模様です。
血圧の変動は、皮膚切開から大動脈遮断までに6回の上昇がみられます。このうち最も急激に上昇したのは手術開始後80分頃にあり、収縮期血圧が110mmHg程度から160mmHg程度にまで急上昇した。 その後、約5分のうちに再び110mmHg程度に急下降した。この血圧が最大に上昇した時に、鎮痛剤の投与量は臓器摘出術中で2番目の大量投与となる0.2マイクログラムが投与された模様です。同様の血圧の急上昇・ 急下降が、この後にも2回記録されている。開腹操作時や胸骨切開時には、鎮痛効果が少なかった模様です。



 心停止が先に発生した場合、臓器摘出準備が整うまでに心臓マッサージあるいは人工心肺を使って血液循環の維持が行われることがあります。このような状態に維持される患者は、死体でしょうか?
心停止が先に発生した場合、臓器摘出準備が整うまでに心臓マッサージあるいは人工心肺を使って血液循環の維持が行われることがあります。このような状態に維持される患者は、死体でしょうか?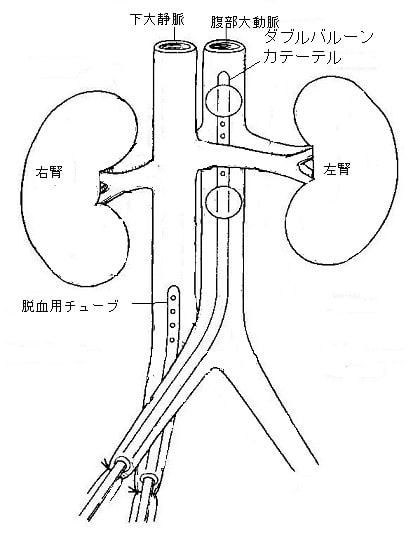 その著名人家族ドナーの例が、1993年8月、柳田洋二郎氏(当時25歳)から東京医科大学八王子医療センターの移植チームが行なったケースです(
その著名人家族ドナーの例が、1993年8月、柳田洋二郎氏(当時25歳)から東京医科大学八王子医療センターの移植チームが行なったケースです( 一言お断りしますが、私は、染色体やDNAの並び方の変化は生物や人間の多様性を示すもので、決して「異常」ではないと思います。しかしながら、医学分野では歴史的にこれらを、「染色体異常」「遺伝子異常」と言い慣わしてきました。話の中で、医学的な事柄を分かりやすく説明するためにこの言葉が出てくることがありますが、その時は、括弧つきの「異常」と思って聞いて下さるとありがたいです。
一言お断りしますが、私は、染色体やDNAの並び方の変化は生物や人間の多様性を示すもので、決して「異常」ではないと思います。しかしながら、医学分野では歴史的にこれらを、「染色体異常」「遺伝子異常」と言い慣わしてきました。話の中で、医学的な事柄を分かりやすく説明するためにこの言葉が出てくることがありますが、その時は、括弧つきの「異常」と思って聞いて下さるとありがたいです。 はじめに
はじめに まとめ
まとめ


