*安倍首相は、明治維新政変、倒幕運動の中心勢力であった2つの部族,山口の田布施町、朝鮮人、鹿児島の加治屋町、、の内、前者の出身である、朝鮮人もも全国の先進地域に拠点的に存在し、差別の対象とされてきた、だが、実際はむしろ、差別によって獲得できる全国的な差別拠点の団結と統合のためのactiveな差別であり、それはまた出身のインペイの体制を作るためであった、と考えられる、
*今回の第2次安倍内閣は、その明治維新の再現に近い、系統人脈で構成されている感じであり、ボクはこの運動を新田布施朝廷の再現と呼んでいる、集団的自衛権の解釈の変更とは、自衛隊を戦争に動員できる憲法解釈を採用、平和憲法を戦争憲法に変えようということである、
*集団的自衛権の推進責任者が自民党副総裁の高村正彦氏であることは、安倍首相とは同族系統であり、当然の人事である、
熊毛郡(くまげぐん)は、山口県東部の郡である。
人口31,487人、面積119.63km²、人口密度263人/km²。(2014年5月1日、推計人口)以下の3町を含む。
上関町(かみのせきちょう)
田布施町(たぶせちょう)
平生町(ひらおちょう)
山口県徳山市(現周南市)出身。父・高村坂彦の衆議院議員初当選を機に東京都へ移る。東京都立立川高等学校、中央大学法学部法律学科卒業。23歳で司法試験に合格。司法修習第20期を修了し、弁護士登録。同期に江田五月(元参議院議長)がいる。
山口県熊毛郡三井村(現光市三井)の農家に生まれる[1]。農業・高村宇佐吉、キチの四男[2]。父・宇佐吉は大工の棟梁でもあり、村会議員もしていた[2]。
1917年(大正6年)、三井尋常高等小学校高等科卒業[3]。「おまえは商人になれ」という父親の言いつけに従って厚狭郡船木町にある酒、醤油の醸造と呉服店を営む蔵重商店の別家に見習い奉公人として住み込む[3]。1920年(大正9年)、見習い奉公から独立、厚狭町で叔父との共同事業の形で醤油醸造業を経営、「山高醤油」の名で売り出す[3]。順調に伸びていた「山高醤油」の経営を一年半ほどで叔父に譲り、父や兄たちの反対を押し切ってやめた[4]。
上京して東京商工学校の二年に編入[5]。商工学校三年になったところで退学すると、正則英語学校と正則予備校に入学、午前中は英語を、午後は物理、化学、数学、国語を、そして高文受験資格の取得をめざし、夜間の中央大学専門部法科の別科にも入学する[6]。1925年(大正14年)9月には専門学校入学者検定試験にパス、中大の別科生から本科生となった[6]。1926年(大正15年)7月高文予備試験合格[7]。1926年(昭和元年)9月高文本試験合格[7]。1927年(昭和2年)中央大学専門部法科卒業[8]。
内務省に入り、鳥取、香川、新潟各特高課長、内務事務官、警察講習所教授、近衛内閣総理大臣秘書官、愛媛県警察部長、内務省国土局総務課長、大阪府警察局長、内務省調査局長等を歴任し、1947年(昭和22年)退官[9]。
政治家として1955年(昭和30年)衆院議員、1961年(昭和36年)から徳山市長を4期、1976年(昭和51年)から衆院議員を2期[9]。1971年(昭和46年)私立徳山大学を設立し、理事長に就任[9]。1989年(平成元年)10月7日死去。
明治天皇となった大室寅之助の生家の近くに、岸信介一族の生家もある。この地から代議士の国光五郎、難波作之助が出ている。また、元外相松岡洋右も岸信介の一族である。あの終戦内閣の最後内務大臣安倍源基も大室寅之助の生家の近くである。日産財閥の創業者、鮎川義介は大内村出身だが岸の縁戚である、












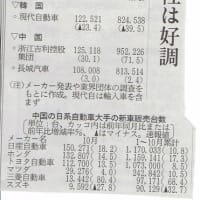


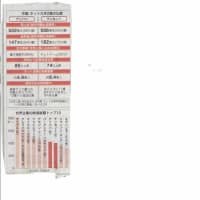
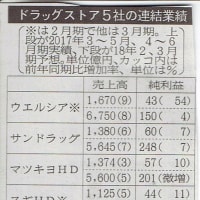

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます