
それでは今回は、多くの人々が高く評価している「和風は河谷いっぱいに吹く」について見てみたい。
今の「和風は河谷いっぱいに吹く」
それは次のようなものである。
さて、この「和風」についてはその語感からすれば「おだやかな風」(『広辞苑』にもそうある)のことだと以前の私は思っていたが、「気象庁 風力 階級表」より抜粋すれば、
十に一つも起きれまいと思ってゐたものが
わづかの苗のつくり方のちがひや
燐酸のやり方のために
今日はそろってみな起きてゐる
ということだから、『流石!、賢治』とかつてはこの詩にとても感動したものだった。これ程の強い風の中で、しかも一度倒れた稲が再び立ち上がっているというのだから奇跡だと、そして賢治の稲作指導や肥料設計は神業だとしか思えなかったからだ。
かつての「和風は河谷いっぱいに吹く」
ところが、「和風は河谷いっぱいに吹く」を調べていてあることに気付いた。それは、かつての『宮澤賢治全集 四』(筑摩書房、昭和31年発行)等に載っている〈和風は河谷いっぱいに吹く(作品第一〇八三番)〉の詩(以後、こちらの形態のものを〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟と表す)は、『校本全集』等に載っているものとは違っていることにである。実際に、『校本宮澤賢治全集第四巻』(昭和51年発行)の〈一〇二一 和風は河谷いっぱいに吹く〉と、『宮澤賢治全集 四』(筑摩書房)のそれこそ〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟とをそれぞれ左右に並べ比べてみると以下のようになる。

青い文字の部分は両者に共通であるが、その他の部分は異なっている。
そこで、この〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟をそのまま賢治の実生活に還元して鑑賞するとどうなるだろうか。それを教えてくれる一つの例が『近代文学鑑賞講座 高村光太郎宮澤賢治』にある。
かつての私であれば、この鑑賞の仕方を素直に肯んじていたと思うし、もちろん『流石、賢治!』とばかりに褒めそやしたはずだ。まして、その稲作指導の成果が実ってなんとあろうことか反当4石もの収穫を上げそうなんだと、賢治の稲作指導は神業だったんだと感激していた。そしてそのことは私一人だけにとどまらず、この「和風は河谷いっぱいに吹く」の詩を、ましてや〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟を読んだ人はなおさらに皆なそう思ったのではなかろうか<*2>。
しかし、当時の
【岩手県水稲反当収量推移】

<素データは『都道府県農業基礎統計』(加用信文監修、農林統計協会)より>
を知って、どうやら私は誤解をしていたということを知った。当時豊作であったという大正14年でも2.14石、昭和8年でも2.22石であり共に反収で2.5石さえも超えていない。となれば、少なくとも昭和初期の1927年に「村ごとの反当に/四石の稲はかならずとれる」は100%不可能であったと言い切れるだろう。まあ、これは下書稿の中のもので推敲の一過程だし、もちろん詩に虚構があることは何も悪いことではなくそれどころか当然のことではある。そして、この〝反当4石〟とはそこに賢治の強い想いと願いが込められているのだろうと理解したい気持ちも私にはもあるものの、「羅須地人協会時代」の賢治の詩に客観的な数値の変更があったということを知ってしまうと、私は以前のような感動はもうそこからは味わえなくなってしまう。また一方では、かつて〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟でこの詩を読んでいた人達の殆どはそれこそ、「宮沢賢治は肥料設計が合理的で適正であれば、つまり稲作栽培が科学的であれば、稲は「まったくの精巧な機械」にひとしく育つことをいっている。この科学的考え方を押しつめてゆくところに農耕指導の意味がある」と満々と思わせられていたということになるのであろう。実は現実には到底そんな収穫高はあり得ないというのに、である。
〔南からまた西南から〕と比べてみれば
ところでこの〈「和風は河谷いっぱいに吹く」一九二七、八、二〇〉は、〈〔南からまた西南から〕一九二七、七、一四〉を推敲したものであるという。ちなみにその詩とは、
というものであった。
ここで、この両者を比べてみると、

のようになる。そこで次に、この詩に関する気象データを確認しようと思って盛岡地方気象台を訪ねたところ、
7月14日の花巻の降水量=18.0㎜
であることを知ることが出来た。なおかつ、当時の幾つか気象データも併せて教えてもらえのでそれらを表にしてみる下表のようになる。

先に私は、「〔南からまた西南から〕の詩には虚構はあまりなさそうである」と推断できたのだが、このことに関してこの表を基にして改めて次の連を分析してみたい。
それは、7月14日付である〔南からまた西南から〕の中の次の連、
七日に亘る強い雨から ……⑤
徒長に過ぎた稲を波立て
葉ごとの暗い霧を落して
和風は河谷いっぱいに吹く
この七月のなかばのうちに
十二の赤い朝焼けと ……⑥
湿度九〇の六日を数へ ……⑦
異常な気温の高さと霧と ……⑧
のことであり、この連の中の〝⑤~⑧〟についてはそれぞれ次のようになる。
もはや感動することはないだろう
となればどうやら、「和風は河谷いっぱいに吹く」の方には少なくとも虚構があるということになりそうだ。なぜならば、〔南からまた西南から〕と「和風は河谷いっぱいに吹く」は共に〝①~④〟が詠み込まれいるのに、前者は「この七月のなかばのうちに」だというのに後者ではその当該個所が「この八月のなかばのうちに」となっているという決定的な違いがあるからだ。しかも、先に確認できたように〔南からまた西南から〕には虚構がほぼないと判断できたから、必然的に残った方の「和風は河谷いっぱいに吹く」に虚構があるとならざるを得ないからだ。したがって、単純にはこの詩「和風は河谷いっぱいに吹く」を安易には還元できない。それはまさに、天沢退二郎氏が
と指摘する通りである。
そこで天沢氏のこの表現と見方を借りれば、
端的に言えば、
・たうたう稲は起きた
とか、
・わづかの苗のつくり方のちがひや
燐酸のやり方のために
今日はそろってみな起きてゐる
とかが事実であったかどうかの保証はないし、またおのずから、そのような田圃を目の前にして
・あゝわれわれは曠野のなかに
芦とも見えるまで逞ましくさやぐ稲田のなかに
素朴なむかしの神々のやうに
べんぶしてもべんぶしても足りない
というような心理状態に実際あっとは言えなさそうで、単にこれは虚構であったということのようだ。約一ヶ月前に詠んだ詩、〔南からまた西南から〕を基にして、そこに賢治の想いを改めて込めながら推敲し、改稿したのが昭和2年8月10日付の「和風は河谷いっぱいに吹く」であり、この詩はあくまでも「心象スケッチ」だったのだろう。
そしてそれは、同日付の3つの他の詩篇
〔もうはたらくな〕〔二時がこんなに暗いのは〕〔何をやっても間に合はない〕<*3>
を読んでみればなおさらにそう思わざるを得ない。これらの投げやりなあるいは陰鬱なそしてはたまた失意のどん底にあるような詩篇と「べんぶしてもべんぶしても足りない」と喜々として高らかに詠っている「和風は河谷いっぱいに吹く」とでは両極端とも言えるほどのあまりにも大きすぎる違いがあるからだ。そして至極残念なことになってしまったが、ここは、「和風は河谷いっぱいに吹く」には虚構ありと判断せざるを得ない。
つまるところ、「和風は河谷いっぱいに吹く」は天沢氏の前掲の評〝①〟の通りだということを改めて確信したし、同時に今後「和風は河谷いっぱいに吹く」を上手い詩だと思うことはあったとしても、もはや私は感動することはないだろうということを覚悟した。それは、これらにかつて感動したのは、そこでは事実が詠まれていると思っていたからこそであったからだ。だから、「和風は河谷いっぱいに吹く」についてもやはり、いわば非可逆性が強い詩であということにならざるを得ない。
これで、先の「稲作挿話」における反収の数値の変更に留まらず、今回は「和風は河谷いっぱいに吹く」において「村ごとの反当に/四石の稲はかならずとれる」と詠もうと思っていたこともあったと知り、その挙げ句て、どうやら
そしてだからであろう、賢治が「この篇みな/疲労時及病中の/心こゝになき手記なり/発表すべからず」と封印したのは、そしてそれらの中に〔あすこの田はねえ〕や「和風は河谷いっぱいに吹く」が入っているのは、などと想像してしまった。そして変に納得してしまった。
<*1:投稿者註> 『鑑賞日本現代文学⑬宮沢賢治』(原 子朗編著、角川書店)の216pによれば、この「河谷」とは、北上川流域の田園をさす、とある。
<*2:投稿者註> この件に関しては、「和風は河谷いっぱいに吹く」の〝下書稿(四)〟の中に次のような〝連〟があるということも知った。
あゝわれわれはこどものやうに
踊っても踊っても尚足りない
もうこの次に倒れても
稲は断じてまた起きる
今年のかういふ湿潤さでも
なほもかうだとするならば
もう村ごとの反当に
四石の稲はかならずとれる
<『校本宮澤賢治全集第四巻』(筑摩書房)511pより>
という。おそらく〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟はこの〝下書稿(四)〟によるものだったのだろう。
<*3:投稿者註> 一〇九〇 〔何をやっても間に合はない〕 一九二七、八、二〇、
<*4:投稿者註> かつて私は、「野の師父」の中の次の連、
昭和2年の6月末までに賢治の肥料設計2,000枚を超えた。
と云われているその根拠(かなり心許ないそれではあったが)かなとひとまず安堵したことがある。実は、その〝2,000枚〟の客観的な根拠を与える資料や証言を私はそれまでに見つけ出せずにいたからである。そして、よくぞこれだけの短期間に〝2,000枚〟もの肥料設計をしたものだと、さぞかし賢治は献身的に取り組んだのだろうと、私は自分を納得させたつもりであった。
ところがその後、「校本年譜」の責任者である堀尾青史自身が、この「昭和2年の6月末までに賢治の肥料設計2,000枚を超えた」については、
と境忠一のインタビューに答えていたことを知り、この〝2,000枚〟が真実かはどうかは定かでない思っていた矢先だったからなおさらにであった。
 続きへ。
続きへ。
前へ 。
。
 “賢治作品についてちょっと』の目次”へ。
“賢治作品についてちょっと』の目次”へ。
”みちのくの山野草”のトップに戻る。
《鈴木 守著作案内》
◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。
本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。
あるいは、次の方法でもご購入いただけます。
☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。
☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』
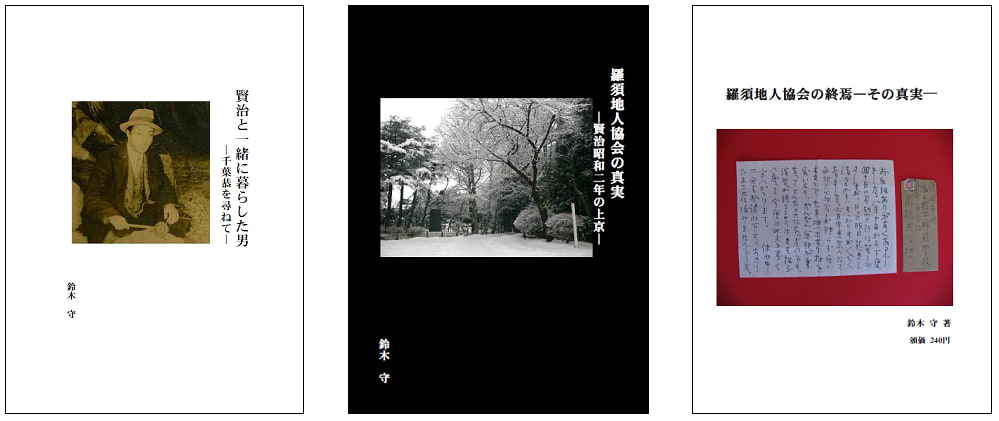
今の「和風は河谷いっぱいに吹く」
それは次のようなものである。
一〇二一 和風は河谷いっぱいに吹く 一九二七、八、二〇、
たうたう稲は起きた
まったくのいきもの
まったくの精巧な機械
稲がそろって起きてゐる
雨のあひだまってゐた穎は
いま小さな白い花をひらめかし
しづかな飴いろの日だまりの上を
赤いとんぼもすうすう飛ぶ
あゝ
南からまた西南から
和風は河谷いっぱいに吹いて
汗にまみれたシャツも乾けば
熱した額やまぶたも冷える
あらゆる辛苦の結果から
七月稲はよく分蘖し
豊かな秋を示してゐたが
この八月のなかばのうちに
十二の赤い朝焼けと
湿度九〇の六日を数へ
茎稈弱く徒長して
穂も出し花もつけながら、
ついに昨日のはげしい雨に
次から次と倒れてしまひ
うへには雨のしぶきのなかに
とむらふやうなつめたい霧が
倒れた稲を被ってゐた
あゝ自然はあんまり意外で
そしてあんまり正直だ
百に一つなからうと思った
あんな恐ろしい開花期の雨は
もうまっかうからやって来て
力を入れたほどのものを
みんなばたばた倒してしまった
その代りには
十に一つも起きれまいと思ってゐたものが
わづかの苗のつくり方のちがひや
燐酸のやり方のために
今日はそろってみな起きてゐる
森で埋めた地平線から
青くかゞやく死火山列から
風はいちめん稲田をわたり
また栗の葉をかゞやかし
いまさわやかな蒸散と
透明な汁液の移転
あゝわれわれは曠野のなかに
芦とも見えるまで逞ましくさやぐ稲田のなかに
素朴なむかしの神々のやうに
べんぶしてもべんぶしても足りない
<『校本宮澤賢治全集第四巻』(筑摩書房)>たうたう稲は起きた
まったくのいきもの
まったくの精巧な機械
稲がそろって起きてゐる
雨のあひだまってゐた穎は
いま小さな白い花をひらめかし
しづかな飴いろの日だまりの上を
赤いとんぼもすうすう飛ぶ
あゝ
南からまた西南から
和風は河谷いっぱいに吹いて
汗にまみれたシャツも乾けば
熱した額やまぶたも冷える
あらゆる辛苦の結果から
七月稲はよく分蘖し
豊かな秋を示してゐたが
この八月のなかばのうちに
十二の赤い朝焼けと
湿度九〇の六日を数へ
茎稈弱く徒長して
穂も出し花もつけながら、
ついに昨日のはげしい雨に
次から次と倒れてしまひ
うへには雨のしぶきのなかに
とむらふやうなつめたい霧が
倒れた稲を被ってゐた
あゝ自然はあんまり意外で
そしてあんまり正直だ
百に一つなからうと思った
あんな恐ろしい開花期の雨は
もうまっかうからやって来て
力を入れたほどのものを
みんなばたばた倒してしまった
その代りには
十に一つも起きれまいと思ってゐたものが
わづかの苗のつくり方のちがひや
燐酸のやり方のために
今日はそろってみな起きてゐる
森で埋めた地平線から
青くかゞやく死火山列から
風はいちめん稲田をわたり
また栗の葉をかゞやかし
いまさわやかな蒸散と
透明な汁液の移転
あゝわれわれは曠野のなかに
芦とも見えるまで逞ましくさやぐ稲田のなかに
素朴なむかしの神々のやうに
べんぶしてもべんぶしても足りない
さて、この「和風」についてはその語感からすれば「おだやかな風」(『広辞苑』にもそうある)のことだと以前の私は思っていたが、「気象庁 風力 階級表」より抜粋すれば、
風力 日本名 地上10mの風速m/s 陸上の状態
3 軟風(なんぷう) 3.4~5.4 木の葉や小枝が絶えず動く
4 和風(わ ふ う) 5.5~7.9 砂埃が立ち、紙片が舞い上がる
5 疾風(しっぷう) 8.0~10.7 樹木が揺れ始める
ということだし、自然科学者である賢治のことだからこの「和風」とはテクニカルタームとして使っていたことは間違いなかろうから、そうであったとしたならば結構強い風だ。そのような風が「河谷いっぱいに」<*1>吹く中、一度倒伏してしまった稲が立ち直ったので賢治は「べんぶしてもべんぶしても足りない」ほどに心は欣喜雀躍していたのだろう。そのように解釈した私は、賢治の稲作指導(特に肥料設計)が上手くいって、3 軟風(なんぷう) 3.4~5.4 木の葉や小枝が絶えず動く
4 和風(わ ふ う) 5.5~7.9 砂埃が立ち、紙片が舞い上がる
5 疾風(しっぷう) 8.0~10.7 樹木が揺れ始める
十に一つも起きれまいと思ってゐたものが
わづかの苗のつくり方のちがひや
燐酸のやり方のために
今日はそろってみな起きてゐる
ということだから、『流石!、賢治』とかつてはこの詩にとても感動したものだった。これ程の強い風の中で、しかも一度倒れた稲が再び立ち上がっているというのだから奇跡だと、そして賢治の稲作指導や肥料設計は神業だとしか思えなかったからだ。
かつての「和風は河谷いっぱいに吹く」
ところが、「和風は河谷いっぱいに吹く」を調べていてあることに気付いた。それは、かつての『宮澤賢治全集 四』(筑摩書房、昭和31年発行)等に載っている〈和風は河谷いっぱいに吹く(作品第一〇八三番)〉の詩(以後、こちらの形態のものを〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟と表す)は、『校本全集』等に載っているものとは違っていることにである。実際に、『校本宮澤賢治全集第四巻』(昭和51年発行)の〈一〇二一 和風は河谷いっぱいに吹く〉と、『宮澤賢治全集 四』(筑摩書房)のそれこそ〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟とをそれぞれ左右に並べ比べてみると以下のようになる。

青い文字の部分は両者に共通であるが、その他の部分は異なっている。
そこで、この〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟をそのまま賢治の実生活に還元して鑑賞するとどうなるだろうか。それを教えてくれる一つの例が『近代文学鑑賞講座 高村光太郎宮澤賢治』にある。
…その朝焼けと雨降りがつづき、つめたい霧がながれ、雨が降りつのり、稲は水につかってしまった。いまこの天候に対抗できるのは、自分が設計した肥料の効果だけである。それはたしかに適正な設計だったはずだ。そしてその効果によって、稲は自然の過酷さをくぐりぬけ、「蘆とも見えるまで逞しくさやぐ」ようになった。和風は河谷いっぱいに吹いている!
稲作指導の数篇中でこれはめずらしくあかるい詩だが、私はこの詩から賢治のものの考え方に、やはり二つの側面のあったことをおもう。その一つは「たうとう稲は起きた まったくのいきもの まったくの精巧な機械」という部分である。ここで宮沢賢治は肥料設計が合理的で適正であれば、つまり稲作栽培が科学的であれば、稲は「まったくの精巧な機械」にひとしく育つことをいっている。この科学的考え方を押しつめてゆくところに農耕指導の意味があるわけだが…
<『近代文学鑑賞講座 高村光太郎宮澤賢治』(角川書店)290p~より>稲作指導の数篇中でこれはめずらしくあかるい詩だが、私はこの詩から賢治のものの考え方に、やはり二つの側面のあったことをおもう。その一つは「たうとう稲は起きた まったくのいきもの まったくの精巧な機械」という部分である。ここで宮沢賢治は肥料設計が合理的で適正であれば、つまり稲作栽培が科学的であれば、稲は「まったくの精巧な機械」にひとしく育つことをいっている。この科学的考え方を押しつめてゆくところに農耕指導の意味があるわけだが…
かつての私であれば、この鑑賞の仕方を素直に肯んじていたと思うし、もちろん『流石、賢治!』とばかりに褒めそやしたはずだ。まして、その稲作指導の成果が実ってなんとあろうことか反当4石もの収穫を上げそうなんだと、賢治の稲作指導は神業だったんだと感激していた。そしてそのことは私一人だけにとどまらず、この「和風は河谷いっぱいに吹く」の詩を、ましてや〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟を読んだ人はなおさらに皆なそう思ったのではなかろうか<*2>。
しかし、当時の
【岩手県水稲反当収量推移】

<素データは『都道府県農業基礎統計』(加用信文監修、農林統計協会)より>
を知って、どうやら私は誤解をしていたということを知った。当時豊作であったという大正14年でも2.14石、昭和8年でも2.22石であり共に反収で2.5石さえも超えていない。となれば、少なくとも昭和初期の1927年に「村ごとの反当に/四石の稲はかならずとれる」は100%不可能であったと言い切れるだろう。まあ、これは下書稿の中のもので推敲の一過程だし、もちろん詩に虚構があることは何も悪いことではなくそれどころか当然のことではある。そして、この〝反当4石〟とはそこに賢治の強い想いと願いが込められているのだろうと理解したい気持ちも私にはもあるものの、「羅須地人協会時代」の賢治の詩に客観的な数値の変更があったということを知ってしまうと、私は以前のような感動はもうそこからは味わえなくなってしまう。また一方では、かつて〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟でこの詩を読んでいた人達の殆どはそれこそ、「宮沢賢治は肥料設計が合理的で適正であれば、つまり稲作栽培が科学的であれば、稲は「まったくの精巧な機械」にひとしく育つことをいっている。この科学的考え方を押しつめてゆくところに農耕指導の意味がある」と満々と思わせられていたということになるのであろう。実は現実には到底そんな収穫高はあり得ないというのに、である。
〔南からまた西南から〕と比べてみれば
ところでこの〈「和風は河谷いっぱいに吹く」一九二七、八、二〇〉は、〈〔南からまた西南から〕一九二七、七、一四〉を推敲したものであるという。ちなみにその詩とは、
一〇八三 〔南からまた西南から〕 一九二七、七、一四、
南からまた西南から
和風は河谷いっぱいに吹く
七日に亘る強い雨から
徒長に過ぎた稲を波立て
葉ごとの暗い霧を落して
和風は河谷いっぱいに吹く
この七月のなかばのうちに
十二の赤い朝焼けと
湿度九〇の六日を数へ
異常な気温の高さと霧と
多くの稲は秋近いまで伸び過ぎた
その茎はみな弱く軟らかく
小暑のなかに枝垂れ葉を出し
明けぞらの赤い破片は雨に運ばれ
あちこちに稲熱の斑点もつくり
ずゐ虫は葉を黄いろに枯らす
今朝黄金の薔薇東もひらけ
雲は騰って青ぞらもでき
澱んだ霧もはるかに翔ける
森で埋め地平線から
青くかゞやく死火山の列から
風はいちめん稲田をゆすり
汗にまみれたシャツも乾けば
熱した額やまぶたを冷える
あゝさわやかな蒸散と
透明な汁液の転移
吸収される燐酸と硅酸
つくられる強靱な維管
鋼にも克てそのセルロース
乾かされ堅められた葉と茎は
秋のはじめの風や雨まで
ならされよならされよoryza sativa
oryza sativaよ
こゝをキルギス曠原と見せるまでなびいて
和風は河谷いっぱいに吹く
<『校本宮澤賢治全集第四巻』(筑摩書房)の「下書稿(三)」、507p~より>南からまた西南から
和風は河谷いっぱいに吹く
七日に亘る強い雨から
徒長に過ぎた稲を波立て
葉ごとの暗い霧を落して
和風は河谷いっぱいに吹く
この七月のなかばのうちに
十二の赤い朝焼けと
湿度九〇の六日を数へ
異常な気温の高さと霧と
多くの稲は秋近いまで伸び過ぎた
その茎はみな弱く軟らかく
小暑のなかに枝垂れ葉を出し
明けぞらの赤い破片は雨に運ばれ
あちこちに稲熱の斑点もつくり
ずゐ虫は葉を黄いろに枯らす
今朝黄金の薔薇東もひらけ
雲は騰って青ぞらもでき
澱んだ霧もはるかに翔ける
森で埋め地平線から
青くかゞやく死火山の列から
風はいちめん稲田をゆすり
汗にまみれたシャツも乾けば
熱した額やまぶたを冷える
あゝさわやかな蒸散と
透明な汁液の転移
吸収される燐酸と硅酸
つくられる強靱な維管
鋼にも克てそのセルロース
乾かされ堅められた葉と茎は
秋のはじめの風や雨まで
ならされよならされよoryza sativa
oryza sativaよ
こゝをキルギス曠原と見せるまでなびいて
和風は河谷いっぱいに吹く
というものであった。
ここで、この両者を比べてみると、

のようになる。そこで次に、この詩に関する気象データを確認しようと思って盛岡地方気象台を訪ねたところ、
7月14日の花巻の降水量=18.0㎜
であることを知ることが出来た。なおかつ、当時の幾つか気象データも併せて教えてもらえのでそれらを表にしてみる下表のようになる。

先に私は、「〔南からまた西南から〕の詩には虚構はあまりなさそうである」と推断できたのだが、このことに関してこの表を基にして改めて次の連を分析してみたい。
それは、7月14日付である〔南からまた西南から〕の中の次の連、
七日に亘る強い雨から ……⑤
徒長に過ぎた稲を波立て
葉ごとの暗い霧を落して
和風は河谷いっぱいに吹く
この七月のなかばのうちに
十二の赤い朝焼けと ……⑥
湿度九〇の六日を数へ ……⑦
異常な気温の高さと霧と ……⑧
のことであり、この連の中の〝⑤~⑧〟についてはそれぞれ次のようになる。
⑤→ 直前の7/14、7/13、7/11、7/10、7/8、7/7、7/1の7日に亘ってたしかにかなり強い雨が降っている。
⑥→7月14日以前は連日のように雨が降っており、このような気象であれば「やがて雨が降るであろう兆し」である「赤い朝焼け」が「この七月のなかばのうちに/十二」日も続いていると詠んでいることは理に適っている。
⑦→これは、「宮沢賢治研究Annual」3号(1993)に佐藤泰平氏の論考「『春と修羅』(第1集・第二集・第三集)の<気象スケッチ>と気象記録」が載っていて、そこに掲げたてある表の、「水沢の湿度(90%以上)」の数と符合している(ただし水沢のデータではあるが。なお、盛岡地方気象台には当時の花巻の湿度のデータの記録は存在していない)。
⑧→この「異常な気温の高さ」については、前掲の同表の中の「昭和2年7月1日~14日」の気温(赤文字部分)の高さが前年及び次年のそれと比べてみればたしかに高いことが言えるから符合する。
したがって、〔南からまた西南から〕に詠まれている気象に関する事柄〝⑤~⑧〟がこれだけ当時の気象データと符合しているから、こちらの詩には気象上の虚構はないと判断できる。またそのことを敷衍すれば、その他の内容についてもそこには虚構がなさそうだ。やはり、先の「この詩には虚構はあまりなさそうである」という推断はほぼ妥当であったようだ。⑥→7月14日以前は連日のように雨が降っており、このような気象であれば「やがて雨が降るであろう兆し」である「赤い朝焼け」が「この七月のなかばのうちに/十二」日も続いていると詠んでいることは理に適っている。
⑦→これは、「宮沢賢治研究Annual」3号(1993)に佐藤泰平氏の論考「『春と修羅』(第1集・第二集・第三集)の<気象スケッチ>と気象記録」が載っていて、そこに掲げたてある表の、「水沢の湿度(90%以上)」の数と符合している(ただし水沢のデータではあるが。なお、盛岡地方気象台には当時の花巻の湿度のデータの記録は存在していない)。
⑧→この「異常な気温の高さ」については、前掲の同表の中の「昭和2年7月1日~14日」の気温(赤文字部分)の高さが前年及び次年のそれと比べてみればたしかに高いことが言えるから符合する。
もはや感動することはないだろう
となればどうやら、「和風は河谷いっぱいに吹く」の方には少なくとも虚構があるということになりそうだ。なぜならば、〔南からまた西南から〕と「和風は河谷いっぱいに吹く」は共に〝①~④〟が詠み込まれいるのに、前者は「この七月のなかばのうちに」だというのに後者ではその当該個所が「この八月のなかばのうちに」となっているという決定的な違いがあるからだ。しかも、先に確認できたように〔南からまた西南から〕には虚構がほぼないと判断できたから、必然的に残った方の「和風は河谷いっぱいに吹く」に虚構があるとならざるを得ないからだ。したがって、単純にはこの詩「和風は河谷いっぱいに吹く」を安易には還元できない。それはまさに、天沢退二郎氏が
「和風は……」の下書稿はまだ七月の、台風襲来以前の段階で発想されており、最終形と同日付の「〔もはたらくな〕」は、ごらんの通り、失意の暗い怒りの詩である。これら、一見リアルな、生活体験に発想したと見られる詩篇もまた、単純な実生活還元をゆるさない、屹立した〝心象スケッチ〟であることがわかる。………①
<『新編宮沢賢治詩集』(天沢退二郎編、新潮文庫)414pより>と指摘する通りである。
そこで天沢氏のこの表現と見方を借りれば、
「和風は河谷いっぱいに吹く」は、一見リアルな、生活体験に発想したと見られる詩篇だが、単純な実生活還元をゆるさない、屹立した〝心象スケッチ〟である。
ということを私もそろそろ受け容れる覚悟をせねばならないということだろう。端的に言えば、
・たうたう稲は起きた
とか、
・わづかの苗のつくり方のちがひや
燐酸のやり方のために
今日はそろってみな起きてゐる
とかが事実であったかどうかの保証はないし、またおのずから、そのような田圃を目の前にして
・あゝわれわれは曠野のなかに
芦とも見えるまで逞ましくさやぐ稲田のなかに
素朴なむかしの神々のやうに
べんぶしてもべんぶしても足りない
というような心理状態に実際あっとは言えなさそうで、単にこれは虚構であったということのようだ。約一ヶ月前に詠んだ詩、〔南からまた西南から〕を基にして、そこに賢治の想いを改めて込めながら推敲し、改稿したのが昭和2年8月10日付の「和風は河谷いっぱいに吹く」であり、この詩はあくまでも「心象スケッチ」だったのだろう。
そしてそれは、同日付の3つの他の詩篇
〔もうはたらくな〕〔二時がこんなに暗いのは〕〔何をやっても間に合はない〕<*3>
を読んでみればなおさらにそう思わざるを得ない。これらの投げやりなあるいは陰鬱なそしてはたまた失意のどん底にあるような詩篇と「べんぶしてもべんぶしても足りない」と喜々として高らかに詠っている「和風は河谷いっぱいに吹く」とでは両極端とも言えるほどのあまりにも大きすぎる違いがあるからだ。そして至極残念なことになってしまったが、ここは、「和風は河谷いっぱいに吹く」には虚構ありと判断せざるを得ない。
つまるところ、「和風は河谷いっぱいに吹く」は天沢氏の前掲の評〝①〟の通りだということを改めて確信したし、同時に今後「和風は河谷いっぱいに吹く」を上手い詩だと思うことはあったとしても、もはや私は感動することはないだろうということを覚悟した。それは、これらにかつて感動したのは、そこでは事実が詠まれていると思っていたからこそであったからだ。だから、「和風は河谷いっぱいに吹く」についてもやはり、いわば非可逆性が強い詩であということにならざるを得ない。
これで、先の「稲作挿話」における反収の数値の変更に留まらず、今回は「和風は河谷いっぱいに吹く」において「村ごとの反当に/四石の稲はかならずとれる」と詠もうと思っていたこともあったと知り、その挙げ句て、どうやら
たうたう稲は起きた
まったくのいきもの
まったくの精巧な機械
稲がそろって起きてゐる
と詠んではいるものの、実態はどうやら稲は倒伏したままだったということを知ってしまったならば、今まではいたく感動していた「稲作挿話」も「和風は河谷いっぱいに吹く」にももはや魅力は薄れ、それに伴って正直「野の師父」ももはや空々しさを拭えなくなってしまった<*4>。まったくのいきもの
まったくの精巧な機械
稲がそろって起きてゐる
そしてだからであろう、賢治が「この篇みな/疲労時及病中の/心こゝになき手記なり/発表すべからず」と封印したのは、そしてそれらの中に〔あすこの田はねえ〕や「和風は河谷いっぱいに吹く」が入っているのは、などと想像してしまった。そして変に納得してしまった。
<*1:投稿者註> 『鑑賞日本現代文学⑬宮沢賢治』(原 子朗編著、角川書店)の216pによれば、この「河谷」とは、北上川流域の田園をさす、とある。
<*2:投稿者註> この件に関しては、「和風は河谷いっぱいに吹く」の〝下書稿(四)〟の中に次のような〝連〟があるということも知った。
あゝわれわれはこどものやうに
踊っても踊っても尚足りない
もうこの次に倒れても
稲は断じてまた起きる
今年のかういふ湿潤さでも
なほもかうだとするならば
もう村ごとの反当に
四石の稲はかならずとれる
<『校本宮澤賢治全集第四巻』(筑摩書房)511pより>
という。おそらく〝旧〈和風は河谷いっぱいに吹く〉〟はこの〝下書稿(四)〟によるものだったのだろう。
<*3:投稿者註> 一〇九〇 〔何をやっても間に合はない〕 一九二七、八、二〇、
何をやっても間に合はない
そのありふれた仲間のひとり
雑誌を読んで兎を飼って
巣箱もみんなじぶんでこさえ
木小屋ののきに二十ちかくもならべれば
その眼がみんなうるんで赤く
こっちの手からさゝげも喰へば
めじろみたいに啼きもする
さうしてそれも間に合はない
何をやっても間に合はない
その〔約五字空白〕仲間のひとり
カタログを見てしるしをつけて
グラヂオラスを郵便でとり
めうがばたけと椿のまへに
名札をつけて植え込めば
大きな花がぎらぎら咲いて
年寄りたちは勿体ながり
通りかゝりのみんなもほめる
さうしてそれも間に合はない
何をやっても間に合はない
その(約五字空白)仲間のひとり
マッシュルームの胞子を買って
納屋をすっかり片付けて
小麦の藁で堆肥もつくり
寒暖計もぶらさげて
毎日水をそゝいでゐれば
まもなく白いシャムピニオンは
次から次と顔を出す
さうしてそれも間に合はない
何をやっても間に合はない
その〔約五字空白〕仲間のひとり
べっかうゴムの長靴もはき
オリーヴいろの縮みのシャツも買って着る
頬もあかるく髪もちゞれてうつくしく
そのかはりには
何をやっても間に合はない
何をやっても間に合はない
その〔約五字空白〕仲間のひとり
その〔約五字空白〕仲間のひとり
<『校本宮澤賢治全集第四巻』(筑摩書房)より>そのありふれた仲間のひとり
雑誌を読んで兎を飼って
巣箱もみんなじぶんでこさえ
木小屋ののきに二十ちかくもならべれば
その眼がみんなうるんで赤く
こっちの手からさゝげも喰へば
めじろみたいに啼きもする
さうしてそれも間に合はない
何をやっても間に合はない
その〔約五字空白〕仲間のひとり
カタログを見てしるしをつけて
グラヂオラスを郵便でとり
めうがばたけと椿のまへに
名札をつけて植え込めば
大きな花がぎらぎら咲いて
年寄りたちは勿体ながり
通りかゝりのみんなもほめる
さうしてそれも間に合はない
何をやっても間に合はない
その(約五字空白)仲間のひとり
マッシュルームの胞子を買って
納屋をすっかり片付けて
小麦の藁で堆肥もつくり
寒暖計もぶらさげて
毎日水をそゝいでゐれば
まもなく白いシャムピニオンは
次から次と顔を出す
さうしてそれも間に合はない
何をやっても間に合はない
その〔約五字空白〕仲間のひとり
べっかうゴムの長靴もはき
オリーヴいろの縮みのシャツも買って着る
頬もあかるく髪もちゞれてうつくしく
そのかはりには
何をやっても間に合はない
何をやっても間に合はない
その〔約五字空白〕仲間のひとり
その〔約五字空白〕仲間のひとり
<*4:投稿者註> かつて私は、「野の師父」の中の次の連、
しかもあなたのおももちの
今日は何たる明るさでせう
豊かな稔りを願へるままに
二千の施肥の設計を終へ
その稲いまやみな穂を抽いて
花をも開くこの日ごろ
に「二千の施肥の設計を終へ」を見つけ出し、しかも、『旧校本年譜』に「八月中旬〔推定〕<一〇二〇 野の師父>」とあったから、この詩が巷間今日は何たる明るさでせう
豊かな稔りを願へるままに
二千の施肥の設計を終へ
その稲いまやみな穂を抽いて
花をも開くこの日ごろ
昭和2年の6月末までに賢治の肥料設計2,000枚を超えた。
と云われているその根拠(かなり心許ないそれではあったが)かなとひとまず安堵したことがある。実は、その〝2,000枚〟の客観的な根拠を与える資料や証言を私はそれまでに見つけ出せずにいたからである。そして、よくぞこれだけの短期間に〝2,000枚〟もの肥料設計をしたものだと、さぞかし賢治は献身的に取り組んだのだろうと、私は自分を納得させたつもりであった。
ところがその後、「校本年譜」の責任者である堀尾青史自身が、この「昭和2年の6月末までに賢治の肥料設計2,000枚を超えた」については、
二千枚を超えたかもしれませんが、よくわかりません。田圃一枚ずつ作っていくのだったらそうなるかもしれません。これも正確にしにくいので迷った末、やめました。
<『國文学 宮沢賢治』(昭和53年2月号、學灯社)より>と境忠一のインタビューに答えていたことを知り、この〝2,000枚〟が真実かはどうかは定かでない思っていた矢先だったからなおさらにであった。
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “賢治作品についてちょっと』の目次”へ。
“賢治作品についてちょっと』の目次”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》
◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。
本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。
あるいは、次の方法でもご購入いただけます。
まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。
☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』
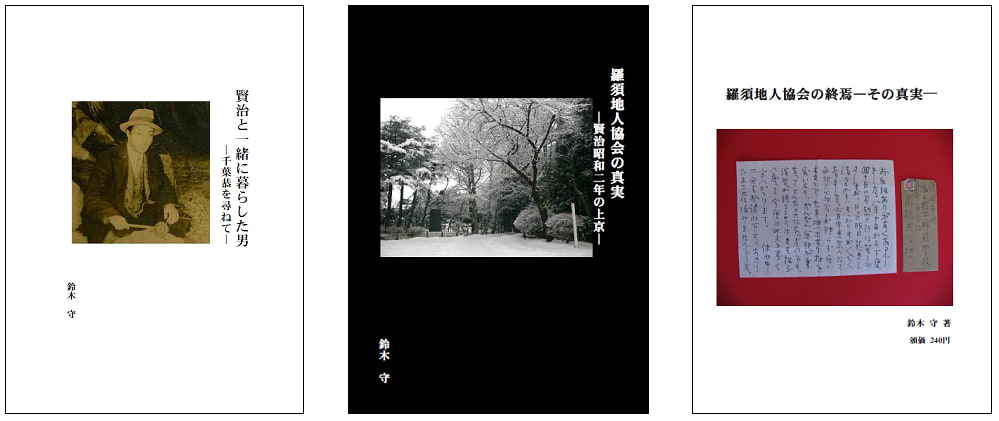



























稲体に雨水が付着してその重みで稲がわん曲するタイプの倒伏の場合、茎が折れる挫折型倒伏や、株ごと転ぶ転び型倒伏と違って、雨水が乾くか払い落とされれば稲は起き上がります。
シャツが乾くような風が吹いて、稲に起き上がってほしい、リン酸肥料(ようりん)の効果で挫折型倒伏でなくわん曲型倒伏であってほしい、という願いは、農業技術者としてよくわかります。腑に落ちました。ありがとうございました。
お早うございます。
そうなんですか、倒伏にもいろいろなタイプがあるのですね。
そして、「わん曲型倒伏であってほしい、という願いは、農業技術者としてよくわかります」という心情を教わり、目から鱗が落ちました。
これからもいろいろとご教示お願いいたします。
鈴木 守
一部の優良農家だけでなく村ごとに4石とりたいという願い。もし倒伏した稲が起きるなら4石とれる、という「なほもかうだとするならば」との表現に惹かれます。
賢治の時代から約30年後に品種の短稈化と追肥時期の明確化により倒伏が抑えられ、普通の農家でも4石近くとれる時代になります。できるなら賢治に見せてあげたいと思います。
稲作改良増収法(大正9年)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/964503
お早うございます。
この度もご親切にご教示ありがとうございます。
お陰様で、『稲作改良増収法(大正9年)』も閲覧できました。
そしてそうなんだ、反当6石8斗4升もの玄米を実際に穫っていたのかということで、凄いものだと感心いたしました。
おそらく賢治もこの本などを読んでいたことでしょう。
そこで私が思ったことは、確かにこのような増収法であれば賢治が村ごとに4石は穫れると詠むのも分かりますが、しかし現実には当時の反当収量はずっと2石前後であり、3倍以上もの違いがあるというのになぜこの増収法が広まって定着しなかったのだろうか、ということです。
鈴木 守
しかし、追肥のタイミングがまだよく明確化されておらず、倒伏の危険がまだまだ多くありました。
現在では、出穂30日前に追肥すると稲が伸びすぎて倒伏の危険が高まること、出穂25日前ではそれほど伸びすぎずに穂の籾数が増えることがわかっています。一般農家にも出穂前日数がわかりやすい診断法も開発されていますし、農協や行政が稲の生育予測を発表しています。
当時はそうした追肥のタイミングや、出穂前日数の診断法がなく、篤農家は鋭い観察力と勘で対応できたのに対して、一般農家は対応できずに肥料を少なくしすぎたり、追肥時期が悪くて倒伏したりして増収できなかったということもあったと思います。
お早うございます。ご丁寧にまたご教示いただきありがとうございます。
そういうことだったんですね。
これからもまたよろしくご助言のほどお願いいたします。
鈴木 守