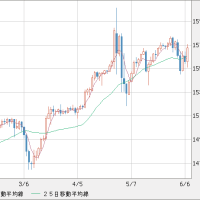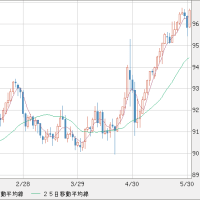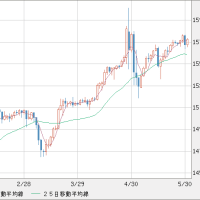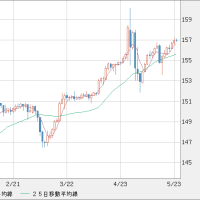今週、愛知県でメタンハイドレートの試験掘削が開始され話題になっている。
当ウェブログでは2008年にこの「燃える氷」を取り上げた。
そのエントリーへのアクセスが今週に入って急増し、
多くの人々が強い関心を抱いていることが示された。
昨年来、エネルギー問題・電力不足問題への関心が強まったためでもあろう。
しかし4年前とは状況が大きく違う。
メタンハイドレート利用技術の開発は重要だが、過度な期待はできない。
寧ろ優先順位で言えば、後回しにすべきである。
今はメタンハイドレートに期待できない3つの明白な理由がある。
1)深海油田以上の技術的困難があり実用化まで時間がかかり過ぎる
2)膨大な資源量のあるシェールガスに対しコストで惨敗する
3)日本国内で別のガス資源開発に成功する可能性が高い
かつての問題は、1)だけだった。今はそうではない。
新たに2つの問題が追加され、「燃える氷」は一段と不利になったのだ。
最後の国内ガス開発の話に首を捻る者が多いかもしれないが
これは確度の高い話であり技術的にも難しくない。
(断っておくが首都圏地下のガス層などではない)
来週の別エントリーで取り上げるので期待して欲しい。
いずれにせよこの3つの壁は余りに高く強固である。
従って日本は一次エネルギー効率(特に天然ガス)を高めて
海外からのエネルギー輸入の無駄を削減することを急がねばならない。
原子力の劣悪な経済性と過大なリスクが明らかになり
眼前に無視できない電力需要逼迫が控えている今、
当ウェブログで何度も主張しているように、
資源をガスコージェネ・ヒートポンプ・太陽電池に傾斜配分し
ピーク電力を需要側で削減することが最優先である。
それでこそ日本経済の逞しい自律的成長が可能になろう。
不透明で非効率的な原子力にロックインされていた
予算や人材が解放され新しい地平を拓くからだ。
↓ 参考
製造業で進む省エネ投資は電力不足対策の王道である - ガスコージェネでの廃熱利用・地中熱利用など
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/e604eec607c6f43f21080d7b390cb9d2
▽ シェールガスなどの非在来型ガスは膨大な資源量を誇る
※ 高価な燃料電池がすぐコストダウンできるとの主張があり要検証。
メタンハイドレート掘削開始 夢の資源、技術確立手探り(産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/life/news/120215/trd12021523140015-n1.htm
産経新聞が実に素晴らしい報道を出している。
夢の資源を追うのも結構だが、川重の高効率ガスコージェネシステム、
ホンダの家庭用ガスコージェネのような日本の優れたガス利用技術が
実質的にはガス田と同様の効果を持つ点に是非とも言及して欲しいものだ。
何しろ最新鋭のガスコンバインド火力発電所より数段も効率が高いのだから。
当ウェブログでは2008年にこの「燃える氷」を取り上げた。
そのエントリーへのアクセスが今週に入って急増し、
多くの人々が強い関心を抱いていることが示された。
昨年来、エネルギー問題・電力不足問題への関心が強まったためでもあろう。
しかし4年前とは状況が大きく違う。
メタンハイドレート利用技術の開発は重要だが、過度な期待はできない。
寧ろ優先順位で言えば、後回しにすべきである。
今はメタンハイドレートに期待できない3つの明白な理由がある。
1)深海油田以上の技術的困難があり実用化まで時間がかかり過ぎる
2)膨大な資源量のあるシェールガスに対しコストで惨敗する
3)日本国内で別のガス資源開発に成功する可能性が高い
かつての問題は、1)だけだった。今はそうではない。
新たに2つの問題が追加され、「燃える氷」は一段と不利になったのだ。
最後の国内ガス開発の話に首を捻る者が多いかもしれないが
これは確度の高い話であり技術的にも難しくない。
(断っておくが首都圏地下のガス層などではない)
来週の別エントリーで取り上げるので期待して欲しい。
いずれにせよこの3つの壁は余りに高く強固である。
従って日本は一次エネルギー効率(特に天然ガス)を高めて
海外からのエネルギー輸入の無駄を削減することを急がねばならない。
原子力の劣悪な経済性と過大なリスクが明らかになり
眼前に無視できない電力需要逼迫が控えている今、
当ウェブログで何度も主張しているように、
資源をガスコージェネ・ヒートポンプ・太陽電池に傾斜配分し
ピーク電力を需要側で削減することが最優先である。
それでこそ日本経済の逞しい自律的成長が可能になろう。
不透明で非効率的な原子力にロックインされていた
予算や人材が解放され新しい地平を拓くからだ。
↓ 参考
製造業で進む省エネ投資は電力不足対策の王道である - ガスコージェネでの廃熱利用・地中熱利用など
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/e604eec607c6f43f21080d7b390cb9d2
▽ シェールガスなどの非在来型ガスは膨大な資源量を誇る
 | 『大転換する日本のエネルギー源 脱原発。天然ガス発電へ』(石井彰,アスキー・メディアワークス) |
※ 高価な燃料電池がすぐコストダウンできるとの主張があり要検証。
メタンハイドレート掘削開始 夢の資源、技術確立手探り(産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/life/news/120215/trd12021523140015-n1.htm
” ■コスト削減、環境への負荷課題
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が15日に愛知県渥美半島沖で世界初となる海底掘削を始めた「メタンハイドレート」は、日本を囲む近海に豊富に埋蔵されている。安定的な供給が実現すれば、資源小国ニッポンにとっては、“夢のエネルギー”となる。ただ、採掘技術が確立されていないうえ、大幅なコスト削減による採算性向上も不可欠だ。環境への影響も未知数で、乗り越えるべき課題は多い。
メタンハイドレートは、都市ガスなどに使われるメタンが低温高圧状態で水分と結び付き、結晶化した氷のような物質。火を付けると結晶内のメタンが燃焼することから「燃える氷」とも呼ばれる。永久凍土の地下深くや深海に埋蔵が確認されており、採掘して結晶からメタンガスを取り出せば、都市ガスのほか、火力発電向け燃料として使用することができる。
日本では平成13年から本格的な採掘計画に着手。JOGMECなどが20年にカナダで凍土からの採掘に成功した。今回は愛知県沖から和歌山県沖にかけての東部南海海域で海底採掘の試験を開始。政府は30年度の商業生産を目指している。
経済産業省によると、東部南海海域のメタンハイドレートの埋蔵量は、国内の天然ガス使用量の十数年分にあたる約1兆立方メートル。北海道周辺や新潟沖も合わせると、日本近海の総埋蔵量はガス使用量の約100年分に相当する計7.4兆立方メートルに上ると推計されており、日本の新たなエネルギー源として「大きな可能性を持つ」(枝野幸男経済産業相)と期待されている。
ただ、深海に眠るメタンハイドレートを効率的に掘削する技術の確立は手探り状態だ。採掘コストは同量の天然ガスを輸入する場合の「5倍近くに達する」(経産省関係者)との見方もある。開発事業者の利益や輸送費を含めれば、他のエネルギーに比べさらに割高となる。
〔中略〕
石油や天然ガスなどエネルギー資源のほとんどを海外に頼る日本にとって、メタンハイドレートへの期待は大きいが、確実に商業生産が見通せる段階にはなっていないのが実情だ。”
産経新聞が実に素晴らしい報道を出している。
夢の資源を追うのも結構だが、川重の高効率ガスコージェネシステム、
ホンダの家庭用ガスコージェネのような日本の優れたガス利用技術が
実質的にはガス田と同様の効果を持つ点に是非とも言及して欲しいものだ。
何しろ最新鋭のガスコンバインド火力発電所より数段も効率が高いのだから。