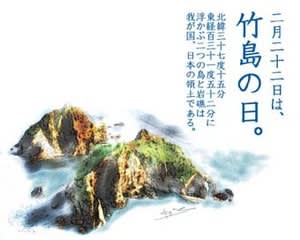中華思想のこの国は、清朝時代には世界一の経済大国だったのだそうです。今、膨れ上がったあり余る外貨で資源を買いあさり、軍備を増強し、内需に向けた大規模な財政出動をして経済成長を維持し、その世界一の座の復活を目指しているのです。
そんななかで、日本はどうあるべきかを書いた記事がありました。悲観する必要はなく、聖徳太子が遣隋使に持たせた手紙の文の様な精神を見習い、プラス思考で考えようと。
<前略>
「世界一」は悲願であり、国力の復興を意味する
中華思想と言われる「天動説」ならぬ「夷狄動説<注1>」に立ち異民族が朝貢に来るのは当たり前と考えていた中国人が、100年前までは「化外<注2>」の地および民と考えて来た日本および日本人にその主客を逆転されたことに対する「苛立ち」は想像以上のものがあったに違いない。
<注1>夷狄(いてき):野蛮な異民族、「夷狄動説」は筆者の造語
<注2>化外(けがい):国家の統治の及ばない所
それが今やGDPで日本を抜いて「世界第2の経済大国」となる時を目前にとらえたのである。
江沢民時代を基点として愛国心教育を充実させ、ナショナリズムを高揚させて来た中国にとって、日本を抜いて「世界第2の経済大国」となることでアジアの主導権を握ることは、中国および中国人としての誇りを掻き立てるものにほかならない。
さらにその先には、GDPで米国を抜いて「世界一の経済大国」となる目標が設定されている。ある資料によれば、中国の清朝後期の1820年に中国が世界経済に占めるGDPの割合は32.9%で、「世界一の経済大国」だったという。
当時のGDP割合は、欧州23.6%、インド16%、ロシア5.4%、アフリカ4.5%で、日本は3%、米国に至ってはわずか1.8%に過ぎなかった。従い、中国にとって「世界一の経済大国」という称号の奪還は悲願であり、国力の復興を意味するものなのである。
ところが中国は、COP15でも主張していましたが、まだ途上国だという見方もできるのです。
中国と日本の差は、国土面積も耕地面積でも26倍、人口は10倍、GDPは2008年がほぼ同額といった状況ですので、一人当たりGDPは、未だ日本が10倍多いのです。
つまり、合計の数値ではなく内容の濃さを言っているのです。
日本の最大の悩みは人口減による国力(労働力と消費力)の衰えです。記事が日本の人口と近い広東省と河南省の人口推移と日本を比較していますが、出生数はわずかに日本が少ないのですが、死亡者の数が圧倒的に異なるのですね。その差が中国の人口増、日本の人口減につながっています。
しかし、中国も一人っ子政策(見直し撤廃の声も聞かれます)のせいで、出生率は抑えられており少子高齢化の流れの中にあり、日本のように死亡数が増えてきて、2030年には老齢化のピーク(=国内消費の頭打ち。福祉厚生費用も?)を迎えると言われています。日本のように掛け声だけで無策で時を重ねることなく、フランスなど欧州各国の様に対策を打つのでしょうが、共産主義のいまでも大きな格差があるのですから、今後の悩ましい課題ではあります。
で、日本はどうすればよいのか。
<中略>
臆することなき姿勢で中国に対応を
この点(一人当たりGDPの差)については、中国の知識人も注意を喚起しており、1月4日付の「第一財経日報」に馬俊という人が「展望2010年:GDP世界2位に驕るなかれ」という記事を書いている。
馬俊氏は、GDPの順位よりも重要なのは、今後何年間、中国が富を蓄積し、経済体質を強め、国民の生活水準を向上させ続けることができるかという問題であると警鐘を鳴らしている。
これは正に至言である。早ければ2015年から国民の老齢化が表面化し、2030年には老齢化のピークを迎えると予測されている中国にとっては、「世界第2の経済大国」などという称号は大きな意味を持たないはずである。
周囲を海に囲まれた島国である日本は、中国に比べて国土も狭く、人口も少なく、エネルギー資源も鉱物資源も持っていない。しかし、国民の高い教育水準と勤勉性の故に1968年以来40年間も「世界第2の経済大国」の座を守ってきたのである。
たとえ2010年中にその座を中国に奪われたとしても、それは表面的なものに過ぎない。対等な土俵に立てば、日本は中国に依然として大きな差をつけており、中国が本当の意味で日本を追い越すには相当の年数が必要である。
我々日本人はこうした前提に立って、今まで以上に国力の増強に努め、中国の追撃を許さぬようにしなければならない。
607年の第2回遣隋使の時に聖徳太子が小野妹子に託した隋の煬帝宛の手紙には、有名な「日出処の天子、書を日が没する処の天子に致す。つつがなきや…」で始まる文章が書かれていた。
今こそ我々はこの1400年前の聖徳太子の精神を見習い、臆することなき姿勢で中国と対応して行かねばならない。それには何事もプラス思考で進むことが肝要だが、この点、貴方は大丈夫ですか。
(北村豊=住友商事総合研究所 中国専任シニアアナリスト)
小沢氏が率いた、国会議員140人の朝貢外交姿勢の時にも引き合いに出された聖徳太子の外交姿勢。覇を争うのではなく、外交の立場を唱えたものですが、鳩山氏の浅薄であまい対等論でもありません。中国の経済成長も、日米をはじめとする輸出があってこそ成り立っているのであって、胡錦濤主席は歴代の主席のなかでは十分理解していて、反日姿勢は比較的押さえられていますね。
ただ、経済成長する中国と、少子高齢化・人口減で内需の縮小化の日本のトレンドの交差は、今のまま(内向きの財源無視のバラ巻き政策だけで、政局優先の政権)では、交差後の格差が拡大するばかりで、10倍の差は容易に詰まることが予測されます。
プラス思考の気持ちは大切で、いい話ではあります。が現実には、鉄道技術、太陽光発電他の環境関連技術などのグローバルな競争への官民一体での体制作りなど、数人の国会議員とその取り巻き民間人のパフォーマンス優先で取捨することなく、叡智を集約した長期ビジョンのもとに進めていただける政権の誕生が必要で、その出現を願っています。

↓ よろしかったら、お願いします。