国立新美術館 2012年4月25日(水)-2012年7月16日(月・祝)
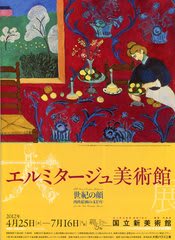
公式サイトはこちら
今年は大型の西洋美術展が目白押しで大変ですね~。大方の皆さんの関心はすでに、フェルメールの≪真珠の耳飾りの少女≫@東京都美術館や、≪真珠の首飾りの少女≫@国立西洋美術館などに向いておられるかと思いますが、もしまだこちらの美術展をご覧になっていないようであれば、もうあまり日数はないながらおすすめしたいと思います。
本展は彫刻や資料系の展示品などが皆無の、ひたすら西欧絵画の400年の歴史を追っていく内容となっています。16世紀から20世紀までを世紀ごとに5章に区切り、しかも各章の作品は国と地域を限定しています。例えば1章はヴェネツィア派、2章はオランダ/フランドルというような具合に。このようなスパッと潔い構成を可能にし、私たちにより深い鑑賞の場を提供してくれるのも、所蔵作品の質・量が並はずれた美術館ならでは。
ちなみに、今回の出品作のほとんどはエルミタージュ美術館の常設展示作品だそうで、83作家、89点の作品が並びます。第1章の1作品目、ティツィアーノの≪祝福するキリスト≫は、あたかも展覧会の幕開けを祝福しているようでもあります。
展覧会の構成は以下の通りです:
Ⅰ 16世紀 ルネサンス:人間の世紀
Ⅱ 17世紀 バロック:黄金の世紀
Ⅲ 18世紀 ロココと新古典主義:革命の世紀
Ⅳ 19世紀 ロマン派からポスト印象派まで:進化する世紀
Ⅴ 20世紀 マティスとその周辺:アヴァンギャルドの世紀
では、印象に残った作品をいくつかご紹介したいと思います。
≪裸婦≫ レオナルド・ダ・ヴィンチ派 (16世紀末)

微笑んではいるのですが、離れ気味の薄い色の瞳、まっすぐ伸びるやや太めの鼻筋が、私にはどことなくネコ科の動物を思わせます。しかも、画面を観つつ立ち去ろうとしても、彼女の目がどこまでも追ってきます。。。
≪聖カタリナ≫ ベルナルディーノ・ルイーニ (1527-1531年)

こちらの作品の方が普通にレオナルド色が濃いですよね。本に目を落とす聖カタリナの穏やかな表情や仕草、それをあどけない微笑みを浮かべて両脇から見守る二人の天使。観ているこちらも落ち着いた心持になります。
≪聖家族と洗礼者ヨハネ≫ バルトロメオ・スケドーニ (16世紀末-17世紀初め)

スケドーニを初めて知ったのは2007年の「パルマ展」。その展覧会の図録の表紙にもなっていたこの画家の、≪キリストの墓の前のマリアたち≫を観た時の鮮烈な印象は忘れがたいものがありました。主題も異なるその作品と比べてもあまり意味はありませんが、本作は登場人物たちの動きも明暗の対比も穏やかで、一般家庭の情景を見ているような温かさを感じます。ただし、マリアの指がちょっと気持ち悪かったです。
≪若い女性の肖像(横顔)≫ ソフォニスバ・アングィソーラ (16世紀末)

まだまだ知らない素晴らしい女性画家が結構いるもんだなぁ、としみじみ。スペイン王フェリペ2世の宮廷画家だったそうです。この時代の肖像画で真横顔というのも新鮮ですが、服の質感描写が見事。
≪エリザベスとフィラデルフィア・ウォートン姉妹の肖像≫ アンソニー・ヴァン・ダイク (1640年)
クリクリの巻き毛が愛らしい二人の幼い姉妹が立っています。まっすぐ正面を見ているお姉さんの目は本当に活き活きとしていて、さすがヴァン・ダイクだなぁ、と思いつつ(ちなみに、腰に手をあててすかしたポーズで立つ画家本人の自画像も並んでいます)、姉妹の後方に見える木がほとんど倒れそうに傾いているのが気になりました。いくらなんでもこれはないだろうと思い、あとで図録の解説を読んだら「助手の関与をうかがわせる」とのこと。
≪花飾りに囲まれた幼子キリストと洗礼者ヨハネ≫ ダニエル・セーヘルス (1650年代前半)
オランダ・フランドル絵画には花の静物画がよく登場しますが、この作品ではそんな花飾りに囲まれた幼子キリストと洗礼者ヨハネが描かれています。一瞬、宗教画にしてはやや違和感を感じるほど装飾的な絵だと思いましたが(後半にもっと驚く作品がありましたが)、よく見ると美しい花に紛れてアザミやヒイラギなどトゲトゲしい植物が。
≪農婦と猫≫ ダーフィト・ライカールト(3世) (1640年代)

ミイラのようにぐるぐる巻きにされた猫がちょっとコミカルですが、その猫におかゆを食べさせているこの老婆は、画家の「五感」連作のうちの、「味覚」の擬人像だそうです。フム。他の4作はどんな具合なんでしょう?
≪老婦人の肖像≫ レンブラント・ファン・レイン (1654年)
暗闇から浮き上がる老婦人の顔。浮き上がっているのは、造形ではなく表情なのだとふと思いました。年齢を重ねるごとに筆触も大胆になっていくレンブラントですが、この婦人の手はほとんどゴッホのようです。
≪幼少期のキリスト≫ ヘリット・ファン・ホントホルスト (1620年頃)
17世紀にオランダのユトレヒトからイタリアへ赴き、カラヴァッジョの作風をオランダに伝えた画家たちがいました。そんなユトレヒト・カラヴァッジョ派の一人がこのホントホルスト。初老のヨセフのおでこに浮き出るたくさんのシワは、蝋燭の灯りによる明暗を表現するのにうってつけのパーツですね。隣にあったマティアス・ストーマーの≪ヤコブに長子の権利を売るエサウ≫(1640年代)という作品も、当初ホントホルストの作品とみなされていたこともあったそうですが、この2作品を比べる限り、ホントホルストの方が上手です。
≪蟹のある食卓≫ ウィレム・クラースゾーン・ヘダ (1648年)
オランダの17世紀絵画といえば1作品は拝見したい超絶的写実の静物画。この作品も素晴らしいです。光沢のある白いテーブルクロスが乱雑に敷かれた卓上には、金属、ガラス、陶器と様々な素材の食器類が並び、ところどころに蟹、レモン、オリーブの実、パンなどが配されています。それぞれの質感描写、とりわけ部屋の窓と思しき光を反映させた銀製のポットとワイングラス(?)は見事だと思いました。
≪死の天使≫ オラース・ヴェルネ (1851年)

実は個人的に一番観たかった作品。何年も前に初めて本で見た時は、耽美的ながら何て怖い絵なんだろうと思いました。その画像が小さくて細部がよくわからなかったこともありますが、少女を連れ去ろうとしている死の天使がちょっと獣っぽくて、何度観てもぞっとしたものです。まさか実作品を日本で観られる日がくるとは。
ということで、じっくり鑑賞しました。想像していたよりも大き目の作品(146x113cm)であったのみならず、やはり実作品は画像のイメージとはずいぶん違うことを実感。なんだかダースベーダーっぽく見えた天使の頭部のベールや、少女を抱え込む手にかかる衣の襞などが確認でき、画像のみで抱いていた見当違いな気味悪さが払しょくされました。イコンの前に下がる蝋燭のか細い灯(画像だと潰れて分かりづらいかと思いますが)は、少女の昇天とともにふっと消えてしまうのでしょう。
≪洞窟のマグラダのマリア≫ ジュール・リフェーヴル (1876年頃)

これはまた艶っぽい裸婦像だなぁ、と近寄り、タイトルを見て「え~っ」と思ってしまいました。神話ならともかく、こんな蠱惑的な流し目のマグダラのマリアも許容されるんですね。
≪赤い部屋(赤のハーモニー)≫ アンリ・マティス (1908年)
チラシの作品です。マティスが注文主のシチューキンに宛てて、「私には作品の装飾性が不十分に思えて、どうしても作品をやり直さざるをえなくなったのです」と書き、最初の完成時は背景が緑色の「緑のハーモニー」だったものが「赤のハーモニー」に生まれ変わりました。緑の上に赤を塗り重ねているためか、想像していたよりも深みのある赤に感じました。観れば観るほどマティスの秩序なき秩序に巻き込まれていく、不思議な絵。
以上、自分の趣味でご紹介しましたが、この他にもロココ、印象派、イギリスの肖像画、20世紀のフランス絵画などまだまだ盛りだくさんの内容です。と言いつつ振り返ったら、女性の画像ばかりですね。最後は美少年に登場してもらいましょうか。
≪ゴリアテの首を持つダヴィデ≫ ヤコプ・ファン・オースト(1世) (1643年)

7月16日(月・祝)までです。
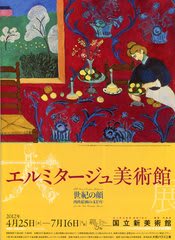
公式サイトはこちら
今年は大型の西洋美術展が目白押しで大変ですね~。大方の皆さんの関心はすでに、フェルメールの≪真珠の耳飾りの少女≫@東京都美術館や、≪真珠の首飾りの少女≫@国立西洋美術館などに向いておられるかと思いますが、もしまだこちらの美術展をご覧になっていないようであれば、もうあまり日数はないながらおすすめしたいと思います。
本展は彫刻や資料系の展示品などが皆無の、ひたすら西欧絵画の400年の歴史を追っていく内容となっています。16世紀から20世紀までを世紀ごとに5章に区切り、しかも各章の作品は国と地域を限定しています。例えば1章はヴェネツィア派、2章はオランダ/フランドルというような具合に。このようなスパッと潔い構成を可能にし、私たちにより深い鑑賞の場を提供してくれるのも、所蔵作品の質・量が並はずれた美術館ならでは。
ちなみに、今回の出品作のほとんどはエルミタージュ美術館の常設展示作品だそうで、83作家、89点の作品が並びます。第1章の1作品目、ティツィアーノの≪祝福するキリスト≫は、あたかも展覧会の幕開けを祝福しているようでもあります。
展覧会の構成は以下の通りです:
Ⅰ 16世紀 ルネサンス:人間の世紀
Ⅱ 17世紀 バロック:黄金の世紀
Ⅲ 18世紀 ロココと新古典主義:革命の世紀
Ⅳ 19世紀 ロマン派からポスト印象派まで:進化する世紀
Ⅴ 20世紀 マティスとその周辺:アヴァンギャルドの世紀
では、印象に残った作品をいくつかご紹介したいと思います。
≪裸婦≫ レオナルド・ダ・ヴィンチ派 (16世紀末)

微笑んではいるのですが、離れ気味の薄い色の瞳、まっすぐ伸びるやや太めの鼻筋が、私にはどことなくネコ科の動物を思わせます。しかも、画面を観つつ立ち去ろうとしても、彼女の目がどこまでも追ってきます。。。
≪聖カタリナ≫ ベルナルディーノ・ルイーニ (1527-1531年)

こちらの作品の方が普通にレオナルド色が濃いですよね。本に目を落とす聖カタリナの穏やかな表情や仕草、それをあどけない微笑みを浮かべて両脇から見守る二人の天使。観ているこちらも落ち着いた心持になります。
≪聖家族と洗礼者ヨハネ≫ バルトロメオ・スケドーニ (16世紀末-17世紀初め)

スケドーニを初めて知ったのは2007年の「パルマ展」。その展覧会の図録の表紙にもなっていたこの画家の、≪キリストの墓の前のマリアたち≫を観た時の鮮烈な印象は忘れがたいものがありました。主題も異なるその作品と比べてもあまり意味はありませんが、本作は登場人物たちの動きも明暗の対比も穏やかで、一般家庭の情景を見ているような温かさを感じます。ただし、マリアの指がちょっと気持ち悪かったです。
≪若い女性の肖像(横顔)≫ ソフォニスバ・アングィソーラ (16世紀末)

まだまだ知らない素晴らしい女性画家が結構いるもんだなぁ、としみじみ。スペイン王フェリペ2世の宮廷画家だったそうです。この時代の肖像画で真横顔というのも新鮮ですが、服の質感描写が見事。
≪エリザベスとフィラデルフィア・ウォートン姉妹の肖像≫ アンソニー・ヴァン・ダイク (1640年)
クリクリの巻き毛が愛らしい二人の幼い姉妹が立っています。まっすぐ正面を見ているお姉さんの目は本当に活き活きとしていて、さすがヴァン・ダイクだなぁ、と思いつつ(ちなみに、腰に手をあててすかしたポーズで立つ画家本人の自画像も並んでいます)、姉妹の後方に見える木がほとんど倒れそうに傾いているのが気になりました。いくらなんでもこれはないだろうと思い、あとで図録の解説を読んだら「助手の関与をうかがわせる」とのこと。
≪花飾りに囲まれた幼子キリストと洗礼者ヨハネ≫ ダニエル・セーヘルス (1650年代前半)
オランダ・フランドル絵画には花の静物画がよく登場しますが、この作品ではそんな花飾りに囲まれた幼子キリストと洗礼者ヨハネが描かれています。一瞬、宗教画にしてはやや違和感を感じるほど装飾的な絵だと思いましたが(後半にもっと驚く作品がありましたが)、よく見ると美しい花に紛れてアザミやヒイラギなどトゲトゲしい植物が。
≪農婦と猫≫ ダーフィト・ライカールト(3世) (1640年代)

ミイラのようにぐるぐる巻きにされた猫がちょっとコミカルですが、その猫におかゆを食べさせているこの老婆は、画家の「五感」連作のうちの、「味覚」の擬人像だそうです。フム。他の4作はどんな具合なんでしょう?
≪老婦人の肖像≫ レンブラント・ファン・レイン (1654年)
暗闇から浮き上がる老婦人の顔。浮き上がっているのは、造形ではなく表情なのだとふと思いました。年齢を重ねるごとに筆触も大胆になっていくレンブラントですが、この婦人の手はほとんどゴッホのようです。
≪幼少期のキリスト≫ ヘリット・ファン・ホントホルスト (1620年頃)
17世紀にオランダのユトレヒトからイタリアへ赴き、カラヴァッジョの作風をオランダに伝えた画家たちがいました。そんなユトレヒト・カラヴァッジョ派の一人がこのホントホルスト。初老のヨセフのおでこに浮き出るたくさんのシワは、蝋燭の灯りによる明暗を表現するのにうってつけのパーツですね。隣にあったマティアス・ストーマーの≪ヤコブに長子の権利を売るエサウ≫(1640年代)という作品も、当初ホントホルストの作品とみなされていたこともあったそうですが、この2作品を比べる限り、ホントホルストの方が上手です。
≪蟹のある食卓≫ ウィレム・クラースゾーン・ヘダ (1648年)
オランダの17世紀絵画といえば1作品は拝見したい超絶的写実の静物画。この作品も素晴らしいです。光沢のある白いテーブルクロスが乱雑に敷かれた卓上には、金属、ガラス、陶器と様々な素材の食器類が並び、ところどころに蟹、レモン、オリーブの実、パンなどが配されています。それぞれの質感描写、とりわけ部屋の窓と思しき光を反映させた銀製のポットとワイングラス(?)は見事だと思いました。
≪死の天使≫ オラース・ヴェルネ (1851年)

実は個人的に一番観たかった作品。何年も前に初めて本で見た時は、耽美的ながら何て怖い絵なんだろうと思いました。その画像が小さくて細部がよくわからなかったこともありますが、少女を連れ去ろうとしている死の天使がちょっと獣っぽくて、何度観てもぞっとしたものです。まさか実作品を日本で観られる日がくるとは。
ということで、じっくり鑑賞しました。想像していたよりも大き目の作品(146x113cm)であったのみならず、やはり実作品は画像のイメージとはずいぶん違うことを実感。なんだかダースベーダーっぽく見えた天使の頭部のベールや、少女を抱え込む手にかかる衣の襞などが確認でき、画像のみで抱いていた見当違いな気味悪さが払しょくされました。イコンの前に下がる蝋燭のか細い灯(画像だと潰れて分かりづらいかと思いますが)は、少女の昇天とともにふっと消えてしまうのでしょう。
≪洞窟のマグラダのマリア≫ ジュール・リフェーヴル (1876年頃)

これはまた艶っぽい裸婦像だなぁ、と近寄り、タイトルを見て「え~っ」と思ってしまいました。神話ならともかく、こんな蠱惑的な流し目のマグダラのマリアも許容されるんですね。
≪赤い部屋(赤のハーモニー)≫ アンリ・マティス (1908年)
チラシの作品です。マティスが注文主のシチューキンに宛てて、「私には作品の装飾性が不十分に思えて、どうしても作品をやり直さざるをえなくなったのです」と書き、最初の完成時は背景が緑色の「緑のハーモニー」だったものが「赤のハーモニー」に生まれ変わりました。緑の上に赤を塗り重ねているためか、想像していたよりも深みのある赤に感じました。観れば観るほどマティスの秩序なき秩序に巻き込まれていく、不思議な絵。
以上、自分の趣味でご紹介しましたが、この他にもロココ、印象派、イギリスの肖像画、20世紀のフランス絵画などまだまだ盛りだくさんの内容です。と言いつつ振り返ったら、女性の画像ばかりですね。最後は美少年に登場してもらいましょうか。
≪ゴリアテの首を持つダヴィデ≫ ヤコプ・ファン・オースト(1世) (1643年)

7月16日(月・祝)までです。
















































 *光背のみ展示
*光背のみ展示





 部分
部分

 部分
部分 部分
部分



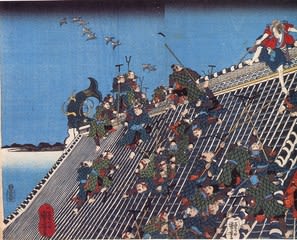













 部分
部分 部分
部分

 右隻部分
右隻部分 部分
部分

 部分
部分 部分
部分
