国立新美術館 2010年4月28日(水)-6月21日(月)
*会期終了

公式サイトはこちら
美術雑誌で名前と少しばかりの作品を知っていた陶芸家、ルーシー・リー。1995年に93歳でこの世を去った彼女の、没後初の本格的な回顧展だという本展覧会で、私は初めてその実作品に対面した。
というわけで、まずは図録を参照しながら彼女についてざっと触れておきたいと思う。
ルーシー・リー(1902-1995)は、父が医者、母が名家出身というウィーンの裕福なユダヤ人家庭に生まれた。1921年にウィーン工業美術学校の聴講生となり、翌年正規に入学。たまたま通りかかった陶芸科の教室で見かけた轆轤に魅了され、すぐさま陶芸家になることを決心。ブリュッセル万博(1935)やパリ万博(1937)など7つの国際展に出品して銀賞等を受賞するなど活躍するも、1938年のナチス・ドイツによるオーストリア侵攻により、夫と共にイギリスへの逃亡を余儀なくされる。イギリスではバーナード・リーチの知遇を得たりしながら、以降半世紀に渡り制作を続けた。
では、印象に残った作品を挙げながら章ごとに見ていきたいと思います:
Ⅰ. 初期―ウィーン時代 1921-38年
#4 『鉢』 (1926年)

解説によると、ルーシーがウィーン工業美術学校で指導を受けたウィーン工房のヨーゼフ・ホフマンのスタイルを踏襲した作品とのこと。ちょっとゴテゴテした印象ではあるが、この鮮やかなターコイズ・ブルーは後の作品にも多用され、彼女が初期からこの色が好きだったことを伺わせる。
この章には資料として彼女の「釉薬ノート」が5冊展示されていた。小さ目のノートに鉛筆でびっしり書かれた、アルファベットや数字を羅列した釉薬の調合法は私が見てもさっぱりわからないが、科学者や数学者による神経症的に細かいメモなどに比べたら大らかな覚書。柔和な字体やところどころにちゃちゃっと描かれている作品のラフなスケッチなどを見ると、几帳面さと良い意味での雑把さとのバランスがとれた人という印象を受けた。
#16 植木鉢 (1936-37年頃)

ルーシーのウィーン時代の作品は①ウィーン工房タイプ、②前熔岩釉タイプ、③バウハウス・タイプの3種類に分けられるそうだ。これは②。後に本格的に「熔岩釉タイプ」と言われる作品群に取り組む彼女の、言わば予兆的作品となったことから「前」がつく。素地の土色が見えているが、ほんのり発色する明るい緑色のせいかあまり土臭さが感じられず、軽やかに思える。
Ⅱ. 形成期―ロンドン時代
本当はロンドン経由で夫と共にアメリカに渡るはずが結局別離の道を選んだルーシーは、ハイド・パークの北に小さな家を見つけ、そこを工房兼住居とした。これがアルビオン・ミューズ。ちなみにミューズとはMews、馬小屋のことで、昔の貴族が馬小屋にしていた建物を住居に改築したもの。私もロンドンで何軒か見たことがあるが、正面は間口が狭く、こじんまりした印象ながら、貴族の馬小屋であるからして高級住宅街に立地していることが多く、プロパティとしての価値は非常に高い。このような瀟洒な建物の中でルーシーは以降50年間制作を続けたのですね。
#19 『黄色文鉢』 (1947年頃)

弥生土器のような素地の薄さと、たわんだ縁がルーシーの器の特徴の一つ。
#27 『線文花器』 (1950年頃)

友人に連れられて訪れたイングランド西部のエイヴベリー(ストーン・サークルで有名なところ)の博物館で、表面に鳥の骨で引っ掻いて描かれた模様を持つ新石器時代の土器がルーシーに新たなインスピレーションを与えた。彼女は細い金属棒を使ってフリーハンドで模様をつける手法を発展させていく。この、ちょっとギリシャの古代土器を思わせる花器は、恐らくその初期の作風例ではないでしょうか。
#49 『線文薬味入れ』 (1956年頃)

薬味入れ3点セットは、これの他にもう一つ、線文の入らない#32 『薬味入れ』(1950-55)も出ていた。上にちょんちょんと開けられた穴がいじらしく、目玉焼きとかにしゃかしゃかこれでお塩を振りかけてみたくなる。他にも蓋の部分が可愛い#44 『線文ドレッシング瓶(オイルとビネガー)』 (1955年頃)や、ピノキオの鼻のような取っ手のついた#45 『茶釉手付注器』(1955年頃)、#46 『手付注器』(1955年頃)などのテーブルウエアーも。彼女の手から生まれる小物類はしっくりと手に馴染みそうなものばかりで、見た目も可愛い。そそっかしい私はピノキオの細い鼻は折ってしまいそうでちょっと怖いけど。
#53 『黄釉線文鉢』 (1957年)

先述の引っ掻いて紋様をつける「掻き落とし」(スグラッフィート)技法は、垂直、斜め、格子、それらのコンビネーションと様々な表情を見せる。この作品ではとろみのある黄色の胴の上の縁にこげ茶の格子が引かれ、作品を引きしめている。
#54 『青釉小鉢』 (1957年頃)

薄い青色が好み。
#79 『白釉花器』 (1960年頃)

縁の広がった帽子を被った貴婦人が立っているような気品を感じる。首が長く伸び、朝顔のように口が開くフォルムはルーシーの作品によく観られる。
#108 『熔岩釉鉢』 (1968年頃)

ルーシーが生み出した釉薬の一つ、「溶岩釉」。表面の気泡のような穴が溶岩の肌を思わせるために彼女がそう呼んだ。カプチーノの泡のようにも見え、苔のような色から抹茶を思わせもする。
【ルーシー・リーのボタン】

ルーシーはウィーン時代からガラス製のボタンを作っていたが、ロンドンに亡命後戦争が激しくなり、器の制作がままならなくなると、ロンドンの高級衣料店の注文で陶製ボタンを制作し、生計を立てた。誠にお気の毒な状況ではあるが、暗い展示室に宝飾店のように置かれたケースの中にたなびくそれらのボタンは、ルーシーの手からまき散らされた天の川のように美しかった。
#R14 『水差しとカップ』 (1950-55年頃)

ボタン制作に忙しいルーシーの工房へ仕事を求めてやってきた、彫刻家志望のハンス・コパー。彼女のアシスタントとなったこの18歳年下の青年は、その後長きに渡ってルーシーが最も信頼を寄せる友人となり、共作のパートナーとなった。これはそんな二人の共同制作品。
そう言えば、「ハンス・コパー展-20世紀陶芸の革新」がパナソニック電工 汐留ミュージアムで開催中です。9月5日(日)まで。
Ⅲ. 円熟期
#150 『線文円筒花器(青)』 (1974年頃)

基本的にこの形で数色のヴァリエーションがあったが、私はこの濃い青とこげ茶の落ち着いたコンビネーションが一番好みだった。
#170 『白釉線文鉢』 (1970年代)

何かを静かに語りかけてくるような器。
#175 『ピンク線文鉢』 (1980年頃)

歪んだ口縁、すぼみながら下に収斂していきつつ、高さのある高台を持つ器はルーシー独特のフォルム。ピンク色を主体に、縁にはブロンズ色、その間に青緑の筋が入れられ、なんて美しい色のコンビネーションだろうと見入ってしまう。
㊧ #174 『ピンク線文鉢』 (1980年頃) ㊨ #171 『ピンク線文鉢』 (1970年代後半)


ルーシーの器の色彩は、白いものには清廉さと穏やかさが漂い、色彩のついたものにはマカロンやウィーン菓子を想起させる西洋的な甘い香りがする。それも、田舎の素朴なお菓子ではなくて、都会の洗練されたケーキ類。そういえば、彼女は工房を訪ねてきたお客さんにお手製のチョコレート・ケーキをふるまったそうだ。きっと美味しかったことでしょう。
ここに紹介したのは、約200点の出展作品のほんの一部。次々にケースの中に現れる器たちは観ていてとても楽しく、会場にいる間ほんわりと幸せな気持ちに包まれた。
工房で制作中のルーシーの写真が飾ってあったが、鼻筋の通った気品ある美しい彼女の横顔には、生真面目さや、穏やかな中にも芯の強そうな人柄が想像された。1939年7月にバーナード・リーチ宛に送ったルーシーの手紙には“「陶芸」はいつも私の心のなかにあります”とあって、本当にその通りの制作活動を全うしたのだと思う。
東京展は終わってしまったが、以下の通り巡回するそうなので、お近くの方は是非!
【栃木展】
益子陶芸美術館
2010年8月7日(土)-9月26日(日)
【静岡展】
MOA美術館
2010年10月9日(土)-12月1日(水)
【大阪展】
大阪市立東洋陶磁美術館
2010年12月11日(土)-2011年2月13日(日)
【三重展】
パラミタミュージアム
2011年2月26日(土)-4月17日(日)
【山口展】
山口県立萩美術館・浦上記念館
2011年4月29日(金・祝)-6月26日(日)
*会期終了

公式サイトはこちら
美術雑誌で名前と少しばかりの作品を知っていた陶芸家、ルーシー・リー。1995年に93歳でこの世を去った彼女の、没後初の本格的な回顧展だという本展覧会で、私は初めてその実作品に対面した。
というわけで、まずは図録を参照しながら彼女についてざっと触れておきたいと思う。
ルーシー・リー(1902-1995)は、父が医者、母が名家出身というウィーンの裕福なユダヤ人家庭に生まれた。1921年にウィーン工業美術学校の聴講生となり、翌年正規に入学。たまたま通りかかった陶芸科の教室で見かけた轆轤に魅了され、すぐさま陶芸家になることを決心。ブリュッセル万博(1935)やパリ万博(1937)など7つの国際展に出品して銀賞等を受賞するなど活躍するも、1938年のナチス・ドイツによるオーストリア侵攻により、夫と共にイギリスへの逃亡を余儀なくされる。イギリスではバーナード・リーチの知遇を得たりしながら、以降半世紀に渡り制作を続けた。
では、印象に残った作品を挙げながら章ごとに見ていきたいと思います:
Ⅰ. 初期―ウィーン時代 1921-38年
#4 『鉢』 (1926年)

解説によると、ルーシーがウィーン工業美術学校で指導を受けたウィーン工房のヨーゼフ・ホフマンのスタイルを踏襲した作品とのこと。ちょっとゴテゴテした印象ではあるが、この鮮やかなターコイズ・ブルーは後の作品にも多用され、彼女が初期からこの色が好きだったことを伺わせる。
この章には資料として彼女の「釉薬ノート」が5冊展示されていた。小さ目のノートに鉛筆でびっしり書かれた、アルファベットや数字を羅列した釉薬の調合法は私が見てもさっぱりわからないが、科学者や数学者による神経症的に細かいメモなどに比べたら大らかな覚書。柔和な字体やところどころにちゃちゃっと描かれている作品のラフなスケッチなどを見ると、几帳面さと良い意味での雑把さとのバランスがとれた人という印象を受けた。
#16 植木鉢 (1936-37年頃)

ルーシーのウィーン時代の作品は①ウィーン工房タイプ、②前熔岩釉タイプ、③バウハウス・タイプの3種類に分けられるそうだ。これは②。後に本格的に「熔岩釉タイプ」と言われる作品群に取り組む彼女の、言わば予兆的作品となったことから「前」がつく。素地の土色が見えているが、ほんのり発色する明るい緑色のせいかあまり土臭さが感じられず、軽やかに思える。
Ⅱ. 形成期―ロンドン時代
本当はロンドン経由で夫と共にアメリカに渡るはずが結局別離の道を選んだルーシーは、ハイド・パークの北に小さな家を見つけ、そこを工房兼住居とした。これがアルビオン・ミューズ。ちなみにミューズとはMews、馬小屋のことで、昔の貴族が馬小屋にしていた建物を住居に改築したもの。私もロンドンで何軒か見たことがあるが、正面は間口が狭く、こじんまりした印象ながら、貴族の馬小屋であるからして高級住宅街に立地していることが多く、プロパティとしての価値は非常に高い。このような瀟洒な建物の中でルーシーは以降50年間制作を続けたのですね。
#19 『黄色文鉢』 (1947年頃)

弥生土器のような素地の薄さと、たわんだ縁がルーシーの器の特徴の一つ。
#27 『線文花器』 (1950年頃)

友人に連れられて訪れたイングランド西部のエイヴベリー(ストーン・サークルで有名なところ)の博物館で、表面に鳥の骨で引っ掻いて描かれた模様を持つ新石器時代の土器がルーシーに新たなインスピレーションを与えた。彼女は細い金属棒を使ってフリーハンドで模様をつける手法を発展させていく。この、ちょっとギリシャの古代土器を思わせる花器は、恐らくその初期の作風例ではないでしょうか。
#49 『線文薬味入れ』 (1956年頃)

薬味入れ3点セットは、これの他にもう一つ、線文の入らない#32 『薬味入れ』(1950-55)も出ていた。上にちょんちょんと開けられた穴がいじらしく、目玉焼きとかにしゃかしゃかこれでお塩を振りかけてみたくなる。他にも蓋の部分が可愛い#44 『線文ドレッシング瓶(オイルとビネガー)』 (1955年頃)や、ピノキオの鼻のような取っ手のついた#45 『茶釉手付注器』(1955年頃)、#46 『手付注器』(1955年頃)などのテーブルウエアーも。彼女の手から生まれる小物類はしっくりと手に馴染みそうなものばかりで、見た目も可愛い。そそっかしい私はピノキオの細い鼻は折ってしまいそうでちょっと怖いけど。
#53 『黄釉線文鉢』 (1957年)

先述の引っ掻いて紋様をつける「掻き落とし」(スグラッフィート)技法は、垂直、斜め、格子、それらのコンビネーションと様々な表情を見せる。この作品ではとろみのある黄色の胴の上の縁にこげ茶の格子が引かれ、作品を引きしめている。
#54 『青釉小鉢』 (1957年頃)

薄い青色が好み。
#79 『白釉花器』 (1960年頃)

縁の広がった帽子を被った貴婦人が立っているような気品を感じる。首が長く伸び、朝顔のように口が開くフォルムはルーシーの作品によく観られる。
#108 『熔岩釉鉢』 (1968年頃)

ルーシーが生み出した釉薬の一つ、「溶岩釉」。表面の気泡のような穴が溶岩の肌を思わせるために彼女がそう呼んだ。カプチーノの泡のようにも見え、苔のような色から抹茶を思わせもする。
【ルーシー・リーのボタン】

ルーシーはウィーン時代からガラス製のボタンを作っていたが、ロンドンに亡命後戦争が激しくなり、器の制作がままならなくなると、ロンドンの高級衣料店の注文で陶製ボタンを制作し、生計を立てた。誠にお気の毒な状況ではあるが、暗い展示室に宝飾店のように置かれたケースの中にたなびくそれらのボタンは、ルーシーの手からまき散らされた天の川のように美しかった。
#R14 『水差しとカップ』 (1950-55年頃)

ボタン制作に忙しいルーシーの工房へ仕事を求めてやってきた、彫刻家志望のハンス・コパー。彼女のアシスタントとなったこの18歳年下の青年は、その後長きに渡ってルーシーが最も信頼を寄せる友人となり、共作のパートナーとなった。これはそんな二人の共同制作品。
そう言えば、「ハンス・コパー展-20世紀陶芸の革新」がパナソニック電工 汐留ミュージアムで開催中です。9月5日(日)まで。
Ⅲ. 円熟期
#150 『線文円筒花器(青)』 (1974年頃)

基本的にこの形で数色のヴァリエーションがあったが、私はこの濃い青とこげ茶の落ち着いたコンビネーションが一番好みだった。
#170 『白釉線文鉢』 (1970年代)

何かを静かに語りかけてくるような器。
#175 『ピンク線文鉢』 (1980年頃)

歪んだ口縁、すぼみながら下に収斂していきつつ、高さのある高台を持つ器はルーシー独特のフォルム。ピンク色を主体に、縁にはブロンズ色、その間に青緑の筋が入れられ、なんて美しい色のコンビネーションだろうと見入ってしまう。
㊧ #174 『ピンク線文鉢』 (1980年頃) ㊨ #171 『ピンク線文鉢』 (1970年代後半)


ルーシーの器の色彩は、白いものには清廉さと穏やかさが漂い、色彩のついたものにはマカロンやウィーン菓子を想起させる西洋的な甘い香りがする。それも、田舎の素朴なお菓子ではなくて、都会の洗練されたケーキ類。そういえば、彼女は工房を訪ねてきたお客さんにお手製のチョコレート・ケーキをふるまったそうだ。きっと美味しかったことでしょう。
ここに紹介したのは、約200点の出展作品のほんの一部。次々にケースの中に現れる器たちは観ていてとても楽しく、会場にいる間ほんわりと幸せな気持ちに包まれた。
工房で制作中のルーシーの写真が飾ってあったが、鼻筋の通った気品ある美しい彼女の横顔には、生真面目さや、穏やかな中にも芯の強そうな人柄が想像された。1939年7月にバーナード・リーチ宛に送ったルーシーの手紙には“「陶芸」はいつも私の心のなかにあります”とあって、本当にその通りの制作活動を全うしたのだと思う。
東京展は終わってしまったが、以下の通り巡回するそうなので、お近くの方は是非!
【栃木展】
益子陶芸美術館
2010年8月7日(土)-9月26日(日)
【静岡展】
MOA美術館
2010年10月9日(土)-12月1日(水)
【大阪展】
大阪市立東洋陶磁美術館
2010年12月11日(土)-2011年2月13日(日)
【三重展】
パラミタミュージアム
2011年2月26日(土)-4月17日(日)
【山口展】
山口県立萩美術館・浦上記念館
2011年4月29日(金・祝)-6月26日(日)










 『闘牛士姿のアンブロワーズ・ヴォラール』 ルノワール(1917)
『闘牛士姿のアンブロワーズ・ヴォラール』 ルノワール(1917) 




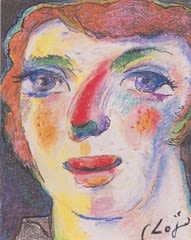


 ベルギー製レース
ベルギー製レース
 カード・セット
カード・セット



