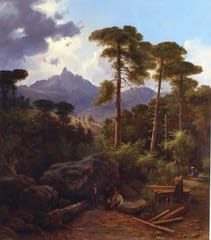東京国立近代美術館 2009年7月3日-9月23日
冒頭から何ですが、個人的にあまり得意ではない画家、ポール・ゴーギャン。観る機会も少なくなく、かくも目につく彼の作品が目の前に現れる度に、ああ、ゴーギャン、と思う。なのにその前にあまり長く留まった記憶がない。
彼の作品に私の関心が向かないのは、私がタヒチのような南国の自然やプリミティヴな文化にさほど興味がないことも一因かもしれないが、思えば個展という形でこの画家の作品をまとめて観たことがない。というより、私はこの画家の何を知っているのだろう?この展覧会を観れば、私が見落としているゴーギャン作品の何かが見えてくるだろうか?そんなことをぐだぐだと考えながら、私は近美に向かった。
個展と言っても、全出展数53点、うち油彩画は24点のみ。とはいえ、彼の最高傑作とされる
『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこに行くのか』(ボストン美術館からアメリカの外に出るのは今回がたった3例目だそうである)というクライマックスを含め、彼の画業の変遷を追いながら展観できるようになっている。勿論これだけで彼を云々できるわけはないが(実際さまざまな疑問も浮かんだ)、それでも私なりに、今までよりはゴーギャンという画家への理解が深まる、有意義な展覧会だった。
公式サイトは
こちら。
本展の構成は、シンプルに以下の3章から成っていた:
第1章 野性の解放
第2章 タヒチへ
第3章 漂泊のさだめ
結局カタログは買わなかったので、メモを元に順を追って感想を残しておこうと思う。
第1章 野性の解放
ゴーギャンは17歳で船乗りとなり、その後株式仲買人に転じて成功。そう聞くと芸術にあまり縁のある人物に思えないが(ロンドンのシティでトレーダーの仕事をしていた友人の言葉、「この手の職業で成功するには教養は邪魔」という言葉が浮かぶ)、この人はもともと絵を描くのが好きだったらしく、印象派絵画のコレクターとなり、カミーユ・ピサロに絵の手ほどきを受け、ついには34歳で脱サラ、画家の道を歩み始める。これにより、結婚して四男一女までもうけて幸せに暮らしていた生活にもピリオド。
そんなゴーギャンの初期の作品がこの章には並ぶ。当然最初は印象派の影響が大きいが、そこからの脱却を図って移住したフランス北西部のブルターニュにて描かれた作品では画風ががらりと転換。
『オスニー村の入口』 (1882-83)
ピサロの教えを忠実に守って描かれたような、細かい筆触が印象派風の風景画。少量であるが、中景に固まって建つ家屋の屋根や木のハイライトなどに使われた朱色に目が行く。ただし、その屋根の集まり具合がぎこちない感じ。
『愛の森の水車小屋の水浴』 (1886)
芸術新潮7月号はゴーギャン特集だが、その中の記事にゴーギャンが同性愛の趣味も持っていたらしいことが書かれてあったので、裸の少年たちが並ぶこの作品もちょっとそんな目で観てしまう。特に左端の、体をしならせて座る少年のポーズは少女のようだ。
『アリスカンの並木道、アルル』 (1888)
損保ジャパン美術館で観るときと、こうしてゴーギャン展での一作品として展示されているのとではこうも観え方が違うものかと思った。前者ではいつもスルー状態だったが、今回は木からはらはらと落ちる紅葉した葉の繊細さに気づく。
『洗濯する女たち、アルル』 (1888)

川に向かって前かがみの姿勢で洗濯をする女たち。彼女らが身につけるスカートやスカーフなどは、くっきりとした輪郭線に縁取られてフラットに色塗りされている。印象派からの脱却とナビ派へ与えた影響を思う。左下に二つの中途半端な顔が唐突に描かれていて、いったい画家がどこからこの情景を観ているのかわからず、あやふやな画面にしている。しかも右側の人物の顔の上にはサインと年号が乗ってしまっている。
『家畜番の少女』 (1889)
この絵に左下から右上に伸びる対角線を引くと、右下側はいいとして左上側の、まるでほうれん草のお浸しみたいな木が好きじゃない。よく観ると細かく塗っているのだが。中央の木の左側に観える白いピラミッドのようなものは何?
『ブルターニュの少年と鵞鳥』 (1889)
少年が寄りかかる岩が不安定(底部が浮いているように観える)が気になる。右で羽を広げる鵞鳥は何か意味があるのだろうか?一瞬ブルターニュはフォアグラの産地で鵞鳥が一杯いるのかと思ったが、そうでもないらしい。
『海辺に立つブルターニュの少女たち』 (1889)

少女たちの顔や手、不釣り合いに大きな足の描き方を観て、タヒチに行く前からこんな画風で人物を描いていたのかと初めて知った。右側の少女の左肩から右上に伸びる木には、もはや初期の細やかな筆触はない。
『二人のブルターニュ女のいる風景』 (1889)

対角線状に右上に伸びる木の枝の下に、俯いて座る二人の女性。ブルターニュ特有の白い頭巾をかぶっている。構図、柔らかい色彩はとてもいいと思うのだが、左上の木がどうも好きじゃない。今後ゴーギャンはこんな風に木を描いていくことになるのだが。。。
『純潔の喪失』 (1890-91)
異質な作品。私にはあまりゴーギャンっぽく感じられない彩度の低い色の帯がやや単調に横にたなびき、これまたゴーギャンが描く裸体にしては異様に白い全裸の女性が横たわる。開いているのか閉じているのかよくわからない女の目元。彼女の胸に手を置き、意味ありげに目を吊り上げてこちらに視線を送る狡猾そうなキツネ、体に沿って置かれた女の右手が握る1輪の花、重ね合わされた女のつま先、丘の向こうからやってくる人の行列。ゴーギャンが孕ませた20歳のお針子がモデルで、しかも彼は身重の彼女を残してタヒチに行ってしまったという。タイトルといい、ゴーギャンはどんなつもりでこの作品を描いたのだろう?
ところで結局私は、ゴーギャンの作品としてはブルターニュ時代の絵が一番好きらしい。絵は線と色彩でできているという原初的なこと、そのことで観る者の心を豊かにしてくれるのが絵なのだ、と語りかけてくるような気がする。
第2章 タヒチへ
タヒチの原始や野性が自分の芸術の探求に新たな活力を吹き込むと信じたゴーギャンは、1891年にタヒチへ旅立つ。1歳から7歳までペルーのリマで育ち、「私の出生の背景はインディアンでありインカである」と自ら語るゴーギャンは、自分の中にある「野蛮人」の感性がタヒチで解放されることを願った。実際すでにこの地も西洋文明の洗礼を受けていたが、タヒチの風土の中にキリスト教的なモティーフが描かれたりと、独特な絵画世界が広がる。
『かぐわしき大地』 (1892)

「楽園追放」タヒチ・バージョン。タヒチにはリンゴと蛇が存在しないので(蛇がいないというのは意外)、真っ赤な翼を広げるトカゲが女性に何やらそそのかし、女性は花に手を伸ばす。大地を踏みしめる女性の大きな足が印象的だが、頭も画面に入りきらないほど女性が大きく描かれている。彼の作品には、人物が画面からはみ出している構図の絵が目につく。画面のプロポーションが何だというのだ、といわんばかりに。
『オヴィリ』 (1894-95)
彩色された、高さ75cmほどの石膏像。その手前、像の横には、この像と同じようなポーズをとる女性が描かれた油彩画、『
エ・ハレ・オエ・イ・ヒア(どこへ行くの?)』 (1892)が置かれている。画中、その上半身裸の女が腰から下に両手で抱えているのは、はじめ黒い袋か何かと思ったら、ダックスフントのような犬だった。犬の腰から下が画面から切れてしまっていて、どんな抱え方をしているのか不自然な感じがするが、全身像であるこの石膏像
『オヴィリ』では、同じように抱えられた動物の後ろ脚が女のふくらはぎに載っていて安定感がある。とはいえ、この像は「野性」の女神で、抱える動物は彼女の野性のパワーを表わしているという。足元にも女神に踏みつけられる獣がいて、解説にゴーギャンはこの像を自分の墓碑にすることを考えていたとあった。一瞬お墓を護る神様の像かと思ったが、ゴーギャンはこの像を「殺人者」とも呼んでいて、足元に踏みつけられる獣はゴーギャン自身という説もあるらしいので、実際の作品意図はわからない。
『パレットを持つ自画像』 (1984)
筆を握る右手が青白すぎるとか、パレットの上の絵の具が不自然とか、左目の下のシェイドが傷口みたいなどと思ったら、ゴーギャンに鼻で笑われそう。不敵な面構えにもまして私は背景の鮮やかなバーミリオンにゴーギャンの主張を感じる。やはり自画像、しかも画家であることを自負しているような作品の背景には、自分の勝負色を使いたかったのだと思う。
『ノアノア』連作版画
1回目のタヒチ滞在からフランスに帰国後の1893年、パリのデュラン・リュエル画廊にてタヒチで制作した作品のお披露目をするが、反応は芳しくない。まずは鑑賞者にタヒチの自然や文化について知ってもらう必要があると思ったゴーギャンは「タヒチ滞在記」を執筆することに。これが
『ノアノア(かぐわしき香り)』で、その挿絵として制作されたのがこの連作版画。①自摺り版(数が少ない1点もの)、②ロワ版(友人ルイ・ロワに依頼して制作された30部のセット。朱色が特徴的)、③ポーラ版(ゴーギャンの4男ポーラによる1921年の後摺りで、限定100部。モノクローム)の3種類があり、作品によりこれらから2種類もしくは3種類が展示され、比較しながら鑑賞できるのは大変興味深い。モノクロームと朱が入るのとでは、同じ作品でも雰囲気ががらりと変わる。全般的には、ロワ版は朱が強すぎるだけでなく黒インクもつけ過ぎの感が否めないものがあったが、マリオの神話からインスピレーションを得たという
#29 『テ・アトゥア(神々)』などは、逆光に浮かぶ神々の輪郭に朱がいい効果を出していた。ポーラ版は彫りがよく観て取れる。
第3章 漂泊のさだめ
1893年にパリに戻るも、タヒチで描いた作品は理解されず。幻滅したゴーギャンは二度とヨーロッパに戻らない覚悟で1895年に再びタヒチへ。健康状態も悪化、経済状態も逼迫した中で制作活動もままならない孤独の生活に、追い打ちをかけるように最愛の娘アリーヌの死の知らせが届く。ゴーギャンは絶望の淵へ投げ出され、生涯の集大成、
『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこに行くのか』 を描いたのち、1901年にマルキーズ諸島に移住、1903年にこの地で波乱の人生の幕を下ろした。
『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこに行くのか』 (1897-98)

この絵が展示されている展示室の手前の部屋で、5分くらいの解説映像が流れている。解説と言っても小難しいものではなく、画面に描きこまれた図像のポイント各所をクローズ・アップしながら、鑑賞者の注意を喚起するもの。
これを観終えて隣の部屋に歩を進めると、展示されているのはこの作品1点のみ。縦139.1×横374.6cmの大作であり、ゴーギャンの画業の集大成と言われる通り、これまでの作品に登場した様々なモティーフが多数描きこまれている。「死ぬ前に、たえず念頭にあった大作を描こうと思い、まる一月の間、昼も夜もこの作品に取り組んだ」というゴーギャンは、実際この作品を仕上げたあとに大量の砒素を飲み込み、自殺を図る。文字通りゴーギャンが生命をかけて描き上げた渾身の一作に、どう対峙すればいいのだろう?
作品タイトルになっている問いと呼応させながら、画面を右から左へ追っていく。右端の赤ん坊、中央の若い青年、そして左端の老婆と平たく鑑賞していけば、これは人生の春夏秋冬を謳ったものにも観える。でも左の老婆のポーズがパリの博物館にあったペルーのミイラを源泉としていると聞くと、自分の出生の背景はインカであると自負するゴーギャンが自身の源泉と重ねているようにも思え、また右の赤ん坊へ輪廻していくようにも思える。
タヒチの神像、様々な姿態で描かれる画中の人物(像も入れれば13人)や動物たちを観ていく中、私が一番惹かれるのは神像の横に立つ少女である。その死により、画家に最後の力を振り絞らせ、この大作を描かた画家最愛の娘アリーヌと言われている。ゴーギャンがフランスからタヒチに去るとき、他の家族が皆冷淡だった中、彼女だけは父を気遣い、笑顔を見せたという。その笑みは、ほとんど死と隣り合わせにあるゴーギャンにますます幻想のごとく蘇ったのではないだろうか。そう思うと、この鬱蒼たる南国の風景は、すでに現世とも思えない雰囲気が漂ってくる。
『ファア・イヘイヘ(タヒチ牧歌)』 (1898)
右から左へ流れていく暖色のグラデーションが美しい。描き込みのバランスも良いせいか、それほど大きな画面ではないのに巻物のようなスケール感がある。特に青ざめた色彩の『我々はどこから来たのか~』の後に観ると、温かみが戻ってきたような心もちがする。
その他、朱色が復活する
『テ・パペ・ナヴェ・ナヴェ(おいしい水)』 (1898)、両性具有の人物が描かれた
『赤いマントをまとったマルキーズ島の男』 (1902)、自らが葬られることになる、丘の上の墓所の白い十字架が印象的な
『女性と白馬』(1903)などが並ぶが、薄塗りの画面にはもはや豪胆な色彩も筆触もない。
こうして見ると、波乱に満ちているとは言え、55歳で幕を閉じたゴーギャンの人生は決して長くないし、何より絵を描いていた期間がたった20年強しかないのには改めて驚く。先に挙げた芸術新潮7月号のゴーギャン特集で彼の「下半身事情」を読むと、沢山の女性に(しかも特にタヒチではローティーンの少女にも)手を出し、身を孕ませながら責任を取らない態度は「野蛮性」云々の前にただの「野獣」じゃないかと辟易もした。でも最初にタヒチに行くときは画家として成功して家族を迎えに行く心づもりであったし、タヒチで絵画用の画布ではなく、穀物を入れる粗い麻袋に絵の具を節約しながら塗りこんで格闘していたのも、そして娘の死に打ちのめされ、あの大作を仕上げたのもゴーギャンなのである。いろいろな意味で稀有な画家であったのだとしみじみ思った。
 ほら、ね?
ほら、ね?
 ほら、ね?
ほら、ね?














 部分
部分