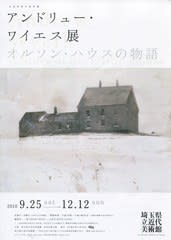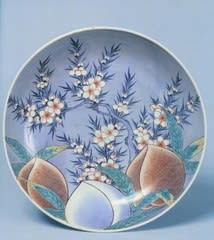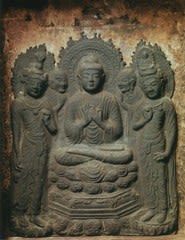三井記念美術館 2010年10月9日(土)-11月28日(日)

展覧会の詳細はこちら
「三井記念美術館 開館五周年記念 特別展」ということで、円山応挙(1733-1795)を「空間の画家」として捉え、その奥行きのある立体的画面をこの画家がどのように構築していったのか、様々な作品で「視覚体験」するもの。
眼鏡絵、応挙の絵画論が垣間見られる『萬紙』、実験的な絵画、といろいろな仕掛け花火を楽しみながら、最後には水墨で松を描いた国宝、重文の「二大最高傑作」の揃い踏みという大輪の打ち上げ花火が用意されています。
構成は以下の通り:
[展示室1] 遠近法の習得
[展示室2] 応挙の絵画空間理論 「遠見の絵」
[展示室3] 応挙の茶掛け
[展示室4] 応挙様式の確立―絵画の向うに広がる世界
[展示室5] 淀川両岸図巻と小画面の中の空間
[展示室6] (タイトルなし)
[展示室7] 応挙二大最高傑作―松の競演
今回は画像がほとんどなく、私の拙い文章ではあまり参考にならないと思いますが、感想だけ留めておきたいと思います。
[展示室1]
応挙が若かりし頃に描いた眼鏡絵の数々。眼鏡絵は18世紀初めにヨーロッパで誕生し、中国から日本に伝わったもので、鏡に映してレンズでのぞく「反射式」と、直接レンズでのぞく「直視式」があるそうだ。
ここには応挙によるその両方の作例が並び、どれも建物や景色が極端な線遠近法で描かれているものの、立体的に見えるという「のぞき眼鏡」がないので実際どのように見えるのかわからない。
いずれにせよ、小さいながらどれも緻密に描き込まれ、細部も手抜きのない画面で(中には部分的に青いガラスがはめ込まれていて、背後から光を当てると夜景のようになって月が青い光を放つという『石山寺図』も)、それまで東洋の画法になかった概念への応挙のチャレンジャー精神、そして創るからには観る者を喜ばそうというエンターテイナー精神のようなものを感じます。
蛇足ながら、『京洛・中国風景図巻』の中で目に止まったものが。スーパーって、建物の上にそのスーパーのロゴの入った、目印的立方体のものが載っているでしょう?あれの先祖みたいなのが、この絵の中に。。。
[展示室2]
応挙と深い信仰があったという三井寺(みいでら)円満院門主の祐常(1723-73)が残した『萬誌』が展示。この中には、応挙の絵画制作における考えが述べられていてとても興味深い。
その一つは、掛け軸、屏風、襖絵などの大画面の作品には、“近くで見ると筆ばなれなどがあるが、間をおいて見ると真の如く見える「遠見(とおみ)」の絵”にすること。もう一つは、モティーフを三次元的に把握する「三遠の法」(すなわち「平遠」「深遠」「高遠」を捉えること)の重要性。「うまくできなければ鏡に写して描くとよい」とも。
応挙は西洋の解剖学なども学んでいたと聞くし、やはり西洋画のテクニックの研究も相当のレベルだったのでしょうね。
[展示室4]
『雲龍図屏風』 安永2年(1773年) *重文
六曲一双の紙本墨画淡彩で、2匹の龍が天の雲と地の波を逆巻きながら画面を駆け巡る。左隻の龍は天から下り、右隻の龍は地から昇っていく。下で荒れ狂う波はまるで龍の分身か鉤爪のごとくいきり立ち、龍たちの躍動感を盛り立てる。ほとんど墨の濃淡で描かれているが、龍の鱗には薄く金彩が入れられ、顔の表情も豊か。特に右の龍の、昇りながら後ろを見やる眼光にやられました。
『竹雀図屏風』 天明5年(1785年)
こちらも六曲一双の紙本墨画淡彩だが、竹林の中に可愛い雀たちを捉えた平穏な作品。3羽が竹から飛び立つシーンがあるのだが、3羽いるのではなく、枝から飛び立ち、羽ばたいてから滑空に移る1羽の雀の連続した姿を捉えたのかもしれないという解説を読んだら本当にそう観えてきて、なるほど~と思った。別の個所でも地上に3羽いて、こちらも1羽の歩く動作を連続して描写しているようにも観える。
[展示室5]
『淀川両岸図巻』 明和2年(1765年)
応挙の「視覚実験」の作品。中央に流れる淀川を挟んで、右岸(画面上部)と左岸(同下部)の川辺の景色を眺めながら右から左へ目を移していくと、急に左岸の景色だけ上下逆さまになってしまう。つまり、例えば川辺に生える木々は最初、右岸も左岸も上を向いて立っているのに、途中から左岸(下部)の木々だけがぱたっとこちらに倒れたような生え方(木のてっぺんが下を向いている)になってしまうのです。と言葉で言ってもわかりにくいと思うので、どうぞ現物を。作品の良し悪しはともかく、応挙って本当にいろいろ試したんだなぁ、と思わずにいられません。
[展示室7]
『雪松図屏風』 *国宝
 左隻
左隻
 右隻
右隻
初めてお目にかかった応挙の名作(国宝だったのですね)。解説によると、画面両端から中心へ向かい、中央部に空白を残す構図を「迫央構図」と呼ぶそうで、これにより奥行き感、立体感を強く意識した空間の広がりが実現される。ブログの画面の都合上横並びに載せられなくて残念だが、確かに左隻の右上と右隻の左上が白く抜かれていて、二つを合体させると中央上部が空白となる。
単純に左と右の松のフォルムに変化を持たせ、リズムを作っているのかと思っていたが、それ以上の深い計算がされているのですね。塗り残しによって、この松の枝や幹にふんわりと積もる純白の雪を表現したテクニックにもひたすらため息。
『松に孔雀図襖』 寛政7年(1795年) *重文
チラシの下の方に一部が載っている、金箔地に松の木と孔雀が墨で描かれた襖絵。彩色はされていないというのに、金箔マジックなのか線描が真っ黒に見えず、墨の濃淡、線の強弱で色を感じるから不思議。
金箔は大気や地面を表わしていると解説にあり、よく観るとなるほど地面にはうっすら墨が引いてあるし、今まで画面をゴージャスに見せる装飾だとばかり浅はかに思っていた背景の金箔も、透明な大気に色がつけられることによって奥行きが増しているのだと理解された。
下降していく松の枝と、枝の下にいる孔雀の長い尾が呼応して流れるようなリズムを感じる。
以上です。
途中展示替えがあり、後半も別の重文作品が登場しますので、気になる方はサイトの出品目録をご確認下さい。11月28日(日)までです。

展覧会の詳細はこちら
「三井記念美術館 開館五周年記念 特別展」ということで、円山応挙(1733-1795)を「空間の画家」として捉え、その奥行きのある立体的画面をこの画家がどのように構築していったのか、様々な作品で「視覚体験」するもの。
眼鏡絵、応挙の絵画論が垣間見られる『萬紙』、実験的な絵画、といろいろな仕掛け花火を楽しみながら、最後には水墨で松を描いた国宝、重文の「二大最高傑作」の揃い踏みという大輪の打ち上げ花火が用意されています。
構成は以下の通り:
[展示室1] 遠近法の習得
[展示室2] 応挙の絵画空間理論 「遠見の絵」
[展示室3] 応挙の茶掛け
[展示室4] 応挙様式の確立―絵画の向うに広がる世界
[展示室5] 淀川両岸図巻と小画面の中の空間
[展示室6] (タイトルなし)
[展示室7] 応挙二大最高傑作―松の競演
今回は画像がほとんどなく、私の拙い文章ではあまり参考にならないと思いますが、感想だけ留めておきたいと思います。
[展示室1]
応挙が若かりし頃に描いた眼鏡絵の数々。眼鏡絵は18世紀初めにヨーロッパで誕生し、中国から日本に伝わったもので、鏡に映してレンズでのぞく「反射式」と、直接レンズでのぞく「直視式」があるそうだ。
ここには応挙によるその両方の作例が並び、どれも建物や景色が極端な線遠近法で描かれているものの、立体的に見えるという「のぞき眼鏡」がないので実際どのように見えるのかわからない。
いずれにせよ、小さいながらどれも緻密に描き込まれ、細部も手抜きのない画面で(中には部分的に青いガラスがはめ込まれていて、背後から光を当てると夜景のようになって月が青い光を放つという『石山寺図』も)、それまで東洋の画法になかった概念への応挙のチャレンジャー精神、そして創るからには観る者を喜ばそうというエンターテイナー精神のようなものを感じます。
蛇足ながら、『京洛・中国風景図巻』の中で目に止まったものが。スーパーって、建物の上にそのスーパーのロゴの入った、目印的立方体のものが載っているでしょう?あれの先祖みたいなのが、この絵の中に。。。
[展示室2]
応挙と深い信仰があったという三井寺(みいでら)円満院門主の祐常(1723-73)が残した『萬誌』が展示。この中には、応挙の絵画制作における考えが述べられていてとても興味深い。
その一つは、掛け軸、屏風、襖絵などの大画面の作品には、“近くで見ると筆ばなれなどがあるが、間をおいて見ると真の如く見える「遠見(とおみ)」の絵”にすること。もう一つは、モティーフを三次元的に把握する「三遠の法」(すなわち「平遠」「深遠」「高遠」を捉えること)の重要性。「うまくできなければ鏡に写して描くとよい」とも。
応挙は西洋の解剖学なども学んでいたと聞くし、やはり西洋画のテクニックの研究も相当のレベルだったのでしょうね。
[展示室4]
『雲龍図屏風』 安永2年(1773年) *重文
六曲一双の紙本墨画淡彩で、2匹の龍が天の雲と地の波を逆巻きながら画面を駆け巡る。左隻の龍は天から下り、右隻の龍は地から昇っていく。下で荒れ狂う波はまるで龍の分身か鉤爪のごとくいきり立ち、龍たちの躍動感を盛り立てる。ほとんど墨の濃淡で描かれているが、龍の鱗には薄く金彩が入れられ、顔の表情も豊か。特に右の龍の、昇りながら後ろを見やる眼光にやられました。
『竹雀図屏風』 天明5年(1785年)
こちらも六曲一双の紙本墨画淡彩だが、竹林の中に可愛い雀たちを捉えた平穏な作品。3羽が竹から飛び立つシーンがあるのだが、3羽いるのではなく、枝から飛び立ち、羽ばたいてから滑空に移る1羽の雀の連続した姿を捉えたのかもしれないという解説を読んだら本当にそう観えてきて、なるほど~と思った。別の個所でも地上に3羽いて、こちらも1羽の歩く動作を連続して描写しているようにも観える。
[展示室5]
『淀川両岸図巻』 明和2年(1765年)
応挙の「視覚実験」の作品。中央に流れる淀川を挟んで、右岸(画面上部)と左岸(同下部)の川辺の景色を眺めながら右から左へ目を移していくと、急に左岸の景色だけ上下逆さまになってしまう。つまり、例えば川辺に生える木々は最初、右岸も左岸も上を向いて立っているのに、途中から左岸(下部)の木々だけがぱたっとこちらに倒れたような生え方(木のてっぺんが下を向いている)になってしまうのです。と言葉で言ってもわかりにくいと思うので、どうぞ現物を。作品の良し悪しはともかく、応挙って本当にいろいろ試したんだなぁ、と思わずにいられません。
[展示室7]
『雪松図屏風』 *国宝
 左隻
左隻 右隻
右隻初めてお目にかかった応挙の名作(国宝だったのですね)。解説によると、画面両端から中心へ向かい、中央部に空白を残す構図を「迫央構図」と呼ぶそうで、これにより奥行き感、立体感を強く意識した空間の広がりが実現される。ブログの画面の都合上横並びに載せられなくて残念だが、確かに左隻の右上と右隻の左上が白く抜かれていて、二つを合体させると中央上部が空白となる。
単純に左と右の松のフォルムに変化を持たせ、リズムを作っているのかと思っていたが、それ以上の深い計算がされているのですね。塗り残しによって、この松の枝や幹にふんわりと積もる純白の雪を表現したテクニックにもひたすらため息。
『松に孔雀図襖』 寛政7年(1795年) *重文
チラシの下の方に一部が載っている、金箔地に松の木と孔雀が墨で描かれた襖絵。彩色はされていないというのに、金箔マジックなのか線描が真っ黒に見えず、墨の濃淡、線の強弱で色を感じるから不思議。
金箔は大気や地面を表わしていると解説にあり、よく観るとなるほど地面にはうっすら墨が引いてあるし、今まで画面をゴージャスに見せる装飾だとばかり浅はかに思っていた背景の金箔も、透明な大気に色がつけられることによって奥行きが増しているのだと理解された。
下降していく松の枝と、枝の下にいる孔雀の長い尾が呼応して流れるようなリズムを感じる。
以上です。
途中展示替えがあり、後半も別の重文作品が登場しますので、気になる方はサイトの出品目録をご確認下さい。11月28日(日)までです。


















































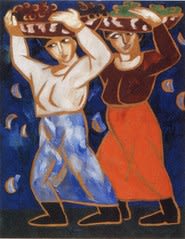









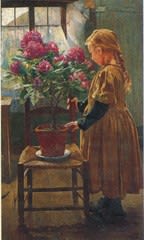






 これが広げたチラシ
これが広げたチラシ