ギャルリーためなが 2009年10月1日-11月1日

注)チラシでは10月31日までとなっていますが、11月1日(日)は中央区が主催する「中央区まるごとミュージアム2009」という催しの一環で12:00~17:00の間開廊しており(『アフタヌーン・ギャラリーズ by画廊の夜会』というイベント名で、銀座の22のギャラリーが参加)、自由に入れるそうです。
私はそれほど銀座の画廊巡りはしないのだが、先日たまたま一目で惹かれたアメリカ人の画家に行き当たった。場所は「ギャルリー ためなが」。
通りに面したガラス越しにかかる色鮮やかな作品が目に入ったとき、日本人の絵ではないと瞬時に思った。上手く説明できないが、一言でいえば”センス”。覗き込むと、作者の名はTom Christopherとあった。私が知らないだけで、恐らく有名な人なのだろうな、と思いつつ、画廊の中に足を踏み入れた。
そこに広がるのは、ニューヨークのマンハッタンの街中の光景。幅1mくらいの作品を中心に、横幅が数メートルある大きなものから小ぶりなものまで40点余が並ぶ。
回遊魚のように流れ続ける黄色いタクシーの群れ。その隊列を縫って自転車で颯爽と走り抜けていくメッセンジャー・ボーイ。信号に煽られるように、早足に道を渡っていく人々。道に並ぶ紅白の三角コーン。何やら相談している、蛍光色の作業服を着た工事人夫たち。クラクション、ヒールの靴音、話し声。慌ただしい人間たちの出す雑多な音が混ざった都会の喧騒が、どの画面からも聞こえてきそう。
若い頃にほんの数日滞在しただけで私の肌には合わないと断じてしまったNYなのに、それらの絵に囲まれていると不思議と高揚感に包まれ、煽られる。
これらの絵を描いたトム・クリストファーはカリフォルニアのハリウッド生まれ(1952年)。プロフィールを斜め読みしてみたが、新聞社の記事のためにスケッチ画を描いていたこともあるようで、あの鉛筆の下描きの線もそのままの疾走感ある画面はそんな背景も反映しているのだろう。そういえば、絵の中でアスファルトは眩しいくらいに真っ白だ。氏の出身地、カリフォルニアの陽光を思わせるような。
モノクロームの作品を観て思ったが、建物も、人々も、何もかもが大雑把に捉えられているのにリアリティがあるのは、やはりその即効的な描写力が秀でているからなのだろう。大きく手前に信号が描かれていたりと構図も筆致同様大胆でおもしろく、本来原色が飛び交う絵が余り得意でない私が惹かれる要素がいろいろ隠れていそうだ。
彼の作品のコレクション先の一つにNY市長のオフィスの名が挙がっていた。こんな絵が執務室にあったら、市長の仕事に対するモチベーションも上がることだろう。
トム・クリストファー氏の(恐らく)公式サイトはこちら

注)チラシでは10月31日までとなっていますが、11月1日(日)は中央区が主催する「中央区まるごとミュージアム2009」という催しの一環で12:00~17:00の間開廊しており(『アフタヌーン・ギャラリーズ by画廊の夜会』というイベント名で、銀座の22のギャラリーが参加)、自由に入れるそうです。
私はそれほど銀座の画廊巡りはしないのだが、先日たまたま一目で惹かれたアメリカ人の画家に行き当たった。場所は「ギャルリー ためなが」。
通りに面したガラス越しにかかる色鮮やかな作品が目に入ったとき、日本人の絵ではないと瞬時に思った。上手く説明できないが、一言でいえば”センス”。覗き込むと、作者の名はTom Christopherとあった。私が知らないだけで、恐らく有名な人なのだろうな、と思いつつ、画廊の中に足を踏み入れた。
そこに広がるのは、ニューヨークのマンハッタンの街中の光景。幅1mくらいの作品を中心に、横幅が数メートルある大きなものから小ぶりなものまで40点余が並ぶ。
回遊魚のように流れ続ける黄色いタクシーの群れ。その隊列を縫って自転車で颯爽と走り抜けていくメッセンジャー・ボーイ。信号に煽られるように、早足に道を渡っていく人々。道に並ぶ紅白の三角コーン。何やら相談している、蛍光色の作業服を着た工事人夫たち。クラクション、ヒールの靴音、話し声。慌ただしい人間たちの出す雑多な音が混ざった都会の喧騒が、どの画面からも聞こえてきそう。
若い頃にほんの数日滞在しただけで私の肌には合わないと断じてしまったNYなのに、それらの絵に囲まれていると不思議と高揚感に包まれ、煽られる。
これらの絵を描いたトム・クリストファーはカリフォルニアのハリウッド生まれ(1952年)。プロフィールを斜め読みしてみたが、新聞社の記事のためにスケッチ画を描いていたこともあるようで、あの鉛筆の下描きの線もそのままの疾走感ある画面はそんな背景も反映しているのだろう。そういえば、絵の中でアスファルトは眩しいくらいに真っ白だ。氏の出身地、カリフォルニアの陽光を思わせるような。
モノクロームの作品を観て思ったが、建物も、人々も、何もかもが大雑把に捉えられているのにリアリティがあるのは、やはりその即効的な描写力が秀でているからなのだろう。大きく手前に信号が描かれていたりと構図も筆致同様大胆でおもしろく、本来原色が飛び交う絵が余り得意でない私が惹かれる要素がいろいろ隠れていそうだ。
彼の作品のコレクション先の一つにNY市長のオフィスの名が挙がっていた。こんな絵が執務室にあったら、市長の仕事に対するモチベーションも上がることだろう。
トム・クリストファー氏の(恐らく)公式サイトはこちら















 右隻の永徳作品
右隻の永徳作品




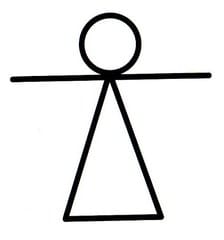 ちょっとクレーを思い浮かべる
ちょっとクレーを思い浮かべる





















 斜め前から撮ったら、ケースの枠が入ってしまった。
斜め前から撮ったら、ケースの枠が入ってしまった。






 仮面の後ろにはこちらを向く顔が(映像でも顔は見えないが)。
仮面の後ろにはこちらを向く顔が(映像でも顔は見えないが)。