出光美術館 2009年4月25日-5月31日
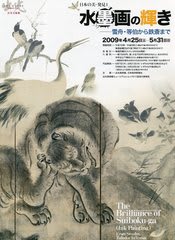
今回は水墨画の歴史を勉強しに出光美術館に行ってきた。水墨画のみの展覧会は今回が初めてかもしれない。日本における水墨画の歴史を追いつつ、ほどよい出展作品数で構成されたこの展覧会は、各パネルの説明も丁寧で、私のような初心者にもとりあえずわかりやすく理解できるものだった。
まず、墨のみで表現する水墨画は、「自然界に溢れる色彩の再現を放棄するという立脚点」から出発しているとある。志がはなからとてもチャレンジングだ。また、「墨は五彩を兼ねる」とあるが、黒一色の濃淡を駆使して、対象物の有形・無形を問わず、質感描写までこなして"多彩"に表現しなくてはならない。しかも「描き直しのきかない、一発勝負の世界」。以前油絵の先生と「本当に画力が問われるのは日本画だ」と話をしたことがあるが、色を使わない水墨画は描き手の感性・技量が徹底的に試される高度な世界だとしみじみ思った。
展覧会の構成は以下の通り:
第一章 水墨山水画の幕開け
第二章 阿弥派の作画と東山御物
第三章 初期狩野派と長谷川等伯
第四章 新しい個性の開花―近世から近代へ
では、各章ごとに印象に残った作品を挙げていく:
第一章 水墨山水画の幕開け
水墨画は8世紀後半、唐時代の中国に山水画を描く技法として生まれた。時代と共に人物画や花鳥画なども描かれるようになり、10~13世紀頃の宋の時代になると一般的な絵画技法として普及。12世紀末に禅宗とともに日本へ伝わった。
『待花軒図』 画・伝 周文 賛・大岳周崇他八僧 (室町時代)
詩画軸(詩、書、画が一体となった作品)。屋根、戸、塀などに細かく直線がたくさん引かれているが、まさかフリーハンドなのだろうか?手に汗をかきそうだ。
『破墨山水図』 雪舟 (室町時代)
破墨という技法(ネットでちょこっと調べた限りでは、墨の濃淡、筆触で立体感を出す技法のようだ)で描かれた山水画。遠景や陰影に薄墨が使われ、山肌や崖には濃い墨が踊る。小さな作品だったが、筆の躍動感が印象に残った。

『赤衣達磨図』 伝 雪舟 (室町時代)
肉感的な赤い唇、眉や髭の柔らかい感じ、立体感のある目鼻立ちと、とても写実的。このところ白隠慧鶴のデフォルメされた達磨像ばかり観ていたから、妙に新鮮な感じがした。
第二章 阿弥派の作画と東山御物
14世紀には道釈人物画(神仏等)が描かれるようになり、応永年間の1394年-1428年を境に日本における水墨山水画の制作が始まる。室町幕府に仕えた能阿弥、芸阿弥、相阿弥の三阿弥は、水墨画家であると同時に足利将軍家の美術コレクション管理を任された、芸術顧問のような人々。日本の水墨画に大きな影響をおよぼした牧谿、玉澗らの作品も合わせて展示。
『四季鳥花図屏風』 能阿弥 (1469)
四曲一双の作品。おしどり、山じゃく、鳩など様々な野鳥が描かれているが、大きく開けた空に飛翔する鷺のフォルムが何と言ってもかっこいい。大きく広げた白い羽、下を見下ろす首の角度、風に乗ってしなやかに伸びる足の重なり具合。惚れ惚れする。
『腹さすり布袋図』 相阿弥 (室町時代)
はだけた着物から突き出すお腹を左手でさすりながら、独特の笑顔を見せる布袋。大きく開けた口元には細かい歯が並んでいる。目つきが鋭くて、何だかワルそうな顔だが。。。 頭の曲線を描くとき、よく手が震えないものだ。右から左に引いているように見えるけど、この人左利き?息を止めて一気に描くんだろうか、と不器用な私はついつい感嘆してしまう。

第三章 初期狩野派と長谷川等伯
日本の水墨表現が大きく飛躍するのは桃山時代。16世紀になると狩野正信・元信父子の登場により室町水墨画の幕開け。狩野永徳による桃山の金地濃彩画なども誕生するが、長谷川等伯により日本独特の水墨画が確立する。
『鳥花図屏風』 元信印 (室町~桃山時代)
急に画面がまろやかな感じになった印象を受けた。筆の荒々しい動き、簡素性が消え、一言でいえばとても丁寧な画風になっている。鳥の体など面的に均一的な彩色がされ、はみ出し感がない。滝や波紋も形式的だし、絵全体が造形的。
『竹虎図屏風』 長谷川等伯 (桃山時代)
長谷川等伯といえば私でも幽玄な竹林が浮かぶが、今回は虎の作品。チラシに使われている屏風画である。右隻にいる雄の虎が、左隻にいる雌の虎に求愛をしているところ、と説明を読むまで、そんな場面とは思いも寄らなかった。そう言われて屏風を観ると、身を伏せ気味にして雌の虎を見つめる右の雄虎は思いつめているようにも観えるし、そんな必死な相手に、この、口を半開きにして後ろ足で頭をかきむしっている雌の虎は、「しょうがないわね~、そんなにまで言うならつき合ってあげましょうか?」とでも言わんばかりである。もしくは全く相手にしていないのか。虎の体に走る線が闊達。尚、同じ長谷川等伯による『竹鶴図屏風』も並んで展示されていた。
第四章 新しい個性の開花―近世から近代へ
戦国時代に入ると、それまで禅僧、幕府の御用絵師のみが描いていた墨絵に地方武士、在野の画家が出てきて、水墨画の需要も広がる。江戸時代には狩野探幽が現れ、個性的な画家、様々な表現が生まれて、琳派、文人画へと広がっていく。近代に入ると、富岡鉄斎らが出てくる。
『鍾離権図』 俵屋宗達 (江戸時代)
柔らかい線で表現された、風にたなびく髪、ふさふさの顎鬚、芭蕉扇の装飾毛や、淡く繊細な色彩。観ていると心が穏やかになる作品。
『龍虎図』 伝 俵屋宗達 (江戸時代)
通常この画題では龍が虎を見下ろすのが定番だが、この作品では虎が龍を見下ろしている。龍は垂らしこみという技法で描かれており、私はそのにじみ具合を観ているうちに思わずお茶か何かの染みがついた書類を思い出す(宗達に失礼な、誠に貧相な発想だ)。隣の親子が虎を観て「虎には観えないな」と言っている。あれ、私と同じ意見か?と耳をそばだてていると、「猫だよね」と少年。いやー、私にはどうしても人間のオヤジさまに観えてしまう。虎を擬人化しているのかとさえ思った。
この章では他に、浦上玉堂、富岡鉄斎などの作品が並んでいたが、個人的には宮本武蔵『竹雀図』、尾形光琳『蹴鞠布袋図』、仙『狗子画賛』などが印象に残った。
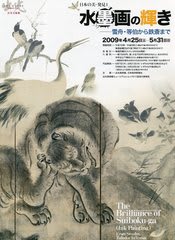
今回は水墨画の歴史を勉強しに出光美術館に行ってきた。水墨画のみの展覧会は今回が初めてかもしれない。日本における水墨画の歴史を追いつつ、ほどよい出展作品数で構成されたこの展覧会は、各パネルの説明も丁寧で、私のような初心者にもとりあえずわかりやすく理解できるものだった。
まず、墨のみで表現する水墨画は、「自然界に溢れる色彩の再現を放棄するという立脚点」から出発しているとある。志がはなからとてもチャレンジングだ。また、「墨は五彩を兼ねる」とあるが、黒一色の濃淡を駆使して、対象物の有形・無形を問わず、質感描写までこなして"多彩"に表現しなくてはならない。しかも「描き直しのきかない、一発勝負の世界」。以前油絵の先生と「本当に画力が問われるのは日本画だ」と話をしたことがあるが、色を使わない水墨画は描き手の感性・技量が徹底的に試される高度な世界だとしみじみ思った。
展覧会の構成は以下の通り:
第一章 水墨山水画の幕開け
第二章 阿弥派の作画と東山御物
第三章 初期狩野派と長谷川等伯
第四章 新しい個性の開花―近世から近代へ
では、各章ごとに印象に残った作品を挙げていく:
第一章 水墨山水画の幕開け
水墨画は8世紀後半、唐時代の中国に山水画を描く技法として生まれた。時代と共に人物画や花鳥画なども描かれるようになり、10~13世紀頃の宋の時代になると一般的な絵画技法として普及。12世紀末に禅宗とともに日本へ伝わった。
『待花軒図』 画・伝 周文 賛・大岳周崇他八僧 (室町時代)
詩画軸(詩、書、画が一体となった作品)。屋根、戸、塀などに細かく直線がたくさん引かれているが、まさかフリーハンドなのだろうか?手に汗をかきそうだ。
『破墨山水図』 雪舟 (室町時代)
破墨という技法(ネットでちょこっと調べた限りでは、墨の濃淡、筆触で立体感を出す技法のようだ)で描かれた山水画。遠景や陰影に薄墨が使われ、山肌や崖には濃い墨が踊る。小さな作品だったが、筆の躍動感が印象に残った。

『赤衣達磨図』 伝 雪舟 (室町時代)
肉感的な赤い唇、眉や髭の柔らかい感じ、立体感のある目鼻立ちと、とても写実的。このところ白隠慧鶴のデフォルメされた達磨像ばかり観ていたから、妙に新鮮な感じがした。
第二章 阿弥派の作画と東山御物
14世紀には道釈人物画(神仏等)が描かれるようになり、応永年間の1394年-1428年を境に日本における水墨山水画の制作が始まる。室町幕府に仕えた能阿弥、芸阿弥、相阿弥の三阿弥は、水墨画家であると同時に足利将軍家の美術コレクション管理を任された、芸術顧問のような人々。日本の水墨画に大きな影響をおよぼした牧谿、玉澗らの作品も合わせて展示。
『四季鳥花図屏風』 能阿弥 (1469)
四曲一双の作品。おしどり、山じゃく、鳩など様々な野鳥が描かれているが、大きく開けた空に飛翔する鷺のフォルムが何と言ってもかっこいい。大きく広げた白い羽、下を見下ろす首の角度、風に乗ってしなやかに伸びる足の重なり具合。惚れ惚れする。
『腹さすり布袋図』 相阿弥 (室町時代)
はだけた着物から突き出すお腹を左手でさすりながら、独特の笑顔を見せる布袋。大きく開けた口元には細かい歯が並んでいる。目つきが鋭くて、何だかワルそうな顔だが。。。 頭の曲線を描くとき、よく手が震えないものだ。右から左に引いているように見えるけど、この人左利き?息を止めて一気に描くんだろうか、と不器用な私はついつい感嘆してしまう。

第三章 初期狩野派と長谷川等伯
日本の水墨表現が大きく飛躍するのは桃山時代。16世紀になると狩野正信・元信父子の登場により室町水墨画の幕開け。狩野永徳による桃山の金地濃彩画なども誕生するが、長谷川等伯により日本独特の水墨画が確立する。
『鳥花図屏風』 元信印 (室町~桃山時代)
急に画面がまろやかな感じになった印象を受けた。筆の荒々しい動き、簡素性が消え、一言でいえばとても丁寧な画風になっている。鳥の体など面的に均一的な彩色がされ、はみ出し感がない。滝や波紋も形式的だし、絵全体が造形的。
『竹虎図屏風』 長谷川等伯 (桃山時代)
長谷川等伯といえば私でも幽玄な竹林が浮かぶが、今回は虎の作品。チラシに使われている屏風画である。右隻にいる雄の虎が、左隻にいる雌の虎に求愛をしているところ、と説明を読むまで、そんな場面とは思いも寄らなかった。そう言われて屏風を観ると、身を伏せ気味にして雌の虎を見つめる右の雄虎は思いつめているようにも観えるし、そんな必死な相手に、この、口を半開きにして後ろ足で頭をかきむしっている雌の虎は、「しょうがないわね~、そんなにまで言うならつき合ってあげましょうか?」とでも言わんばかりである。もしくは全く相手にしていないのか。虎の体に走る線が闊達。尚、同じ長谷川等伯による『竹鶴図屏風』も並んで展示されていた。
第四章 新しい個性の開花―近世から近代へ
戦国時代に入ると、それまで禅僧、幕府の御用絵師のみが描いていた墨絵に地方武士、在野の画家が出てきて、水墨画の需要も広がる。江戸時代には狩野探幽が現れ、個性的な画家、様々な表現が生まれて、琳派、文人画へと広がっていく。近代に入ると、富岡鉄斎らが出てくる。
『鍾離権図』 俵屋宗達 (江戸時代)
柔らかい線で表現された、風にたなびく髪、ふさふさの顎鬚、芭蕉扇の装飾毛や、淡く繊細な色彩。観ていると心が穏やかになる作品。
『龍虎図』 伝 俵屋宗達 (江戸時代)
通常この画題では龍が虎を見下ろすのが定番だが、この作品では虎が龍を見下ろしている。龍は垂らしこみという技法で描かれており、私はそのにじみ具合を観ているうちに思わずお茶か何かの染みがついた書類を思い出す(宗達に失礼な、誠に貧相な発想だ)。隣の親子が虎を観て「虎には観えないな」と言っている。あれ、私と同じ意見か?と耳をそばだてていると、「猫だよね」と少年。いやー、私にはどうしても人間のオヤジさまに観えてしまう。虎を擬人化しているのかとさえ思った。
この章では他に、浦上玉堂、富岡鉄斎などの作品が並んでいたが、個人的には宮本武蔵『竹雀図』、尾形光琳『蹴鞠布袋図』、仙『狗子画賛』などが印象に残った。







































