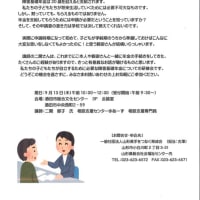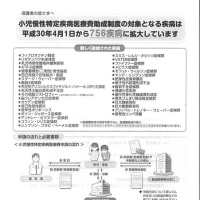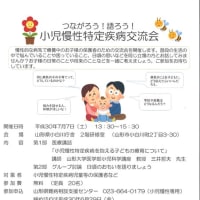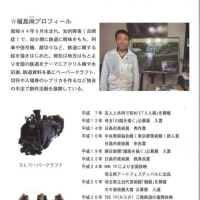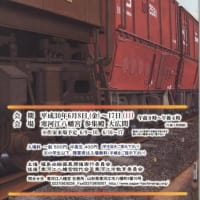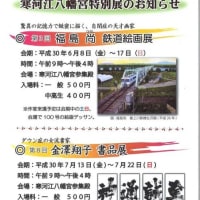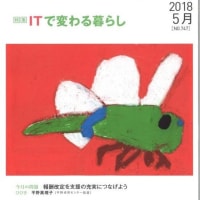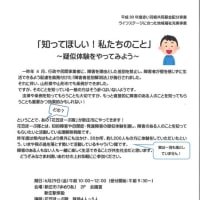◎ 「親のための成年後見ハンドブック シリーズ1」だれにもわかるすぐに役立つ
2008年5月1日増刷版
発行者 NPO法人 Panda-J(代表 野沢和弘)
発行所 PandaA-J編集部
〒187-0032 東京都小平市小川町1-830 白梅学園大学 堀江まゆみ研究室気付
FAX 042-344-1889 Mail info-panda-j@shiraume.ac.jp
定価 100円
---------------------------------------------
上記、ハンドブックの内容(p.24)を紹介する。
その第23回目。
【9 第三者の後見人はどうなのか?(3)=p.24】
〈社会福祉士は身上監護が得意〉
1 社会福祉士は、法的な事案には強くはないかもしれませんが、福祉の現場をよく知っているだけに、「身上監護」については弁護士や司法書士よりも得意な人が多いと言えるかもしれません。
2 障害者施設の職員として働いていた経験のある社会福祉士も多く、彼らは施設の実情をよく知っているだけに、なかなか言いたいことを言えない障害者の気持ちをよく汲み取れる可能性はあります。
3 ある社会福祉士は「施設で働いていたときには、障害者が虐待されたり権利侵害されたりしているのを見ても、職員同士のしがらみがあってなかなか言えなかった。そういう経験があるので、今は後見人としてよく実情がわかるし、何もしがらみがなく障害者本人のためだけに主張することができる」と話しています。
4 もちろん、その人の感性や能力によって異なりますし、障害者の気持ちを汲み取れたとしても、それをどうやって代弁して改善につなげていけるのかは、また別の能力が求められるのかもしれません。
-------------------------------------------
【感想】
社会福祉士の多くは障害者施設の現場をよく知っている。
知的障がいのある人たちについて、行動特性を理解して、基本的な問題を把握している。
社会福祉士は後見人として「身上監護」を行うにはうってつけである。
被後見人(障がい者)の最善の利益を実現するために、課題解決に努力してくれることだろう。
ただ、社会福祉士といえども、被後見人と長年付き合うのだから、それぞれの相性といったものを考慮して後見人選定を行うのはもちろんである。
〈ケー〉
《次は、「成年後見初歩の初歩(23)」に続く》
2008年5月1日増刷版
発行者 NPO法人 Panda-J(代表 野沢和弘)
発行所 PandaA-J編集部
〒187-0032 東京都小平市小川町1-830 白梅学園大学 堀江まゆみ研究室気付
FAX 042-344-1889 Mail info-panda-j@shiraume.ac.jp
定価 100円
---------------------------------------------
上記、ハンドブックの内容(p.24)を紹介する。
その第23回目。
【9 第三者の後見人はどうなのか?(3)=p.24】
〈社会福祉士は身上監護が得意〉
1 社会福祉士は、法的な事案には強くはないかもしれませんが、福祉の現場をよく知っているだけに、「身上監護」については弁護士や司法書士よりも得意な人が多いと言えるかもしれません。
2 障害者施設の職員として働いていた経験のある社会福祉士も多く、彼らは施設の実情をよく知っているだけに、なかなか言いたいことを言えない障害者の気持ちをよく汲み取れる可能性はあります。
3 ある社会福祉士は「施設で働いていたときには、障害者が虐待されたり権利侵害されたりしているのを見ても、職員同士のしがらみがあってなかなか言えなかった。そういう経験があるので、今は後見人としてよく実情がわかるし、何もしがらみがなく障害者本人のためだけに主張することができる」と話しています。
4 もちろん、その人の感性や能力によって異なりますし、障害者の気持ちを汲み取れたとしても、それをどうやって代弁して改善につなげていけるのかは、また別の能力が求められるのかもしれません。
-------------------------------------------
【感想】
社会福祉士の多くは障害者施設の現場をよく知っている。
知的障がいのある人たちについて、行動特性を理解して、基本的な問題を把握している。
社会福祉士は後見人として「身上監護」を行うにはうってつけである。
被後見人(障がい者)の最善の利益を実現するために、課題解決に努力してくれることだろう。
ただ、社会福祉士といえども、被後見人と長年付き合うのだから、それぞれの相性といったものを考慮して後見人選定を行うのはもちろんである。
〈ケー〉
《次は、「成年後見初歩の初歩(23)」に続く》