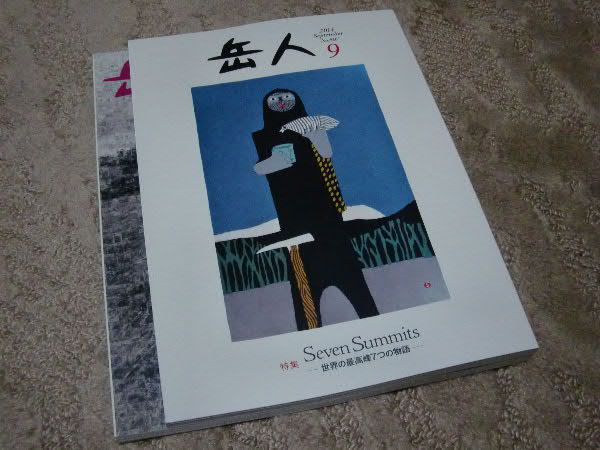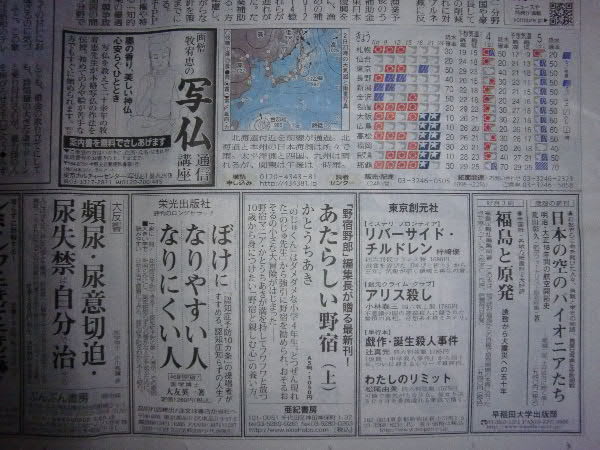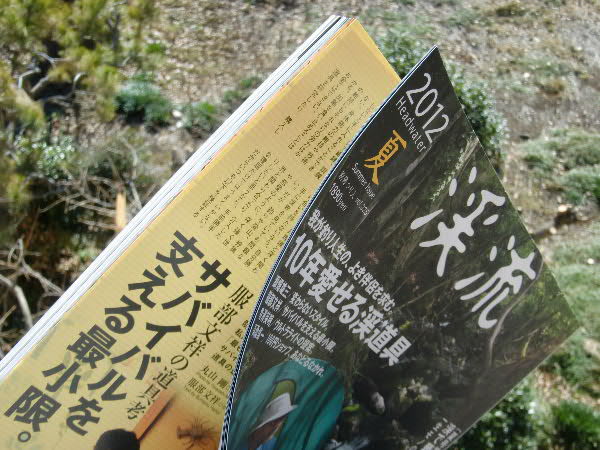今春から触れている、『岳人』の出版元が東京新聞からモンベルの関連会社の株式会社ネイチュアエンタープライズに移行し、今月に発行の14年9月号から新装刊、の件に関する続き。
12日(火)の発売日から、校正のいち作業の「素読み」ばりに時間をかけて本気で精読してみると、たしかに写真のように判型は小さくなって、ページ数も(写真の9月号の下に敷いた)東京新聞版の8月号の7割ほどと減ったものの、読み物が主体で写真も案外きれいで本自体は結構良い。ただ、予想通りに? ツッコミどころは版元が変わっても相変わらず多かった。
以下に特に目立ったものを。「×→○」は明らかにおかしい誤植で、「疑→改」は疑問点とその改善案を。
●P8、本文下段
× 山男たちに出迎えらた
○ 山男たちに出迎えられた
※単なる脱字。
●P15、マッキンリー(デナリ)の写真
× 1970年に植村直己が~遭難した山として知られる
○ 1984年に植村直己が~遭難した山として知られる
※この山で植村直己が冬季単独登頂後に遭難したのは1984年2月。植村直己の略年譜を要参照。
●P17、本文中段
疑 冒検を行うには
改 冒険を行うには
※この場合は一般的には「冒険」だが、類語の「探検」と意図的に混ぜた、両方の意味を含めた表記も野外系雑誌では稀に見られる。「冒検」や「探険」のように。しかし本文のエヴェレスト登頂については登山業界ではよくあることなので(海抜0mから8848mへ人力移動で到達という記録は珍しいが、前例はある)、ふつうに「冒険」でよいと思う。
●P23、本文上段
× 内蔵の調子を整え
○ 内臓の調子を整え
※人間を含む動物の体(身体)に関する記述で分野を問わず、よくある誤変換。最近は人体および健康に関する媒体・記事のほかに、釣り(釣った魚を捌くくだり)や狩猟(熊・猪・鹿・兎・鳥類などの獣の解体)に関するものでも増えてきたような気がする。
●P29、筆者紹介
× 『空へ』(文芸春秋)
○ 『空へ』(文藝春秋)
※単に文藝春秋の社名で略字か正字か、の判別。ただ文春の場合は社名が「文藝春秋」なので、やはりこのとおりに書くべきで。また、P39の座談会記事の本文3段目にも雑誌名の『文藝春秋』があり、これと字面を統一させる意味でも正しく書きたいものだ。
ちなみに、『空へ』は文藝春秋の単行本・文庫本版よりも現在はヤマケイ文庫版のほうが新しいが、まあそこはあまり気にしなくてもよいかも。
●P30、本文上段
× 『石器時代のへの旅』
○ 『石器時代への旅』
※単なる衍字(えんじ。不必要な字)。絶版状態の50年前の本なので、amazon.co.jpの古書の書影を参照した。
もちろん国会図書館にはあるようなので、行く機会があれば確認してみたい本ではある。
ちなみに、同ページ下段の「現在カルステンツ・ピラミッドへの~」からの改行は、改行字下げが1字(全角)ではなく2字分になっているのも誤り。
●P32、下段(天地の「地」)の表
疑 7~400万円
改 70~400万円
※マッキンリーの登山費用に関する表記で、日本から最安で7万円で行けるものなのか? という疑問。おそらく金額の桁が1桁少ないと思われるが、ひょっとしたら日本からこの登山で最寄りのアメリカ・アンカレジまで格安で渡航できる方法があるのかもしれない。この山に登頂した知人もいるのでなんとなく聞きかじった話では、たしか入山料だけでも200ドルほど必要だと思うが、となるとそれ以外の航空券代など諸費用を5万円前後で、というのは至難の業か……。
●P32、33
疑 所用日数
改 所要日数
※この号の特集のセブンサミッツ(世界七大陸最高峰)の登頂を目指すさいの難易度や費用や時間の紹介で、「所用」か「所要」の違い。多くの一般登山者にとっては趣味的な登山という行為を用事・用件という事務的な意味合いの「所用」と扱うよりも、この場合は純粋に登頂するためにはこのくらいの時間が必要であるという「所要」のほうが適していると思う。
ただ、この見開きページを監修している(エヴェレストに6回登頂など高所登山の経験豊富な)倉岡祐之氏のような山岳ガイドにとっては、主に仕事として登りに行っているということで「所用」のほうの感覚なのかもしれない。
●P68、本文4段中2段目
× 登攀そして、そして滑り手にとって
○ 登攀、そして滑り手にとって
※これも「そして」が重複で、衍字のはず。
●P78、「前号までのお話」
疑 ツンドラをサバイバル登山スタイルで隕石湖まで徒歩旅行させて、新種のイワナを釣りあげさせる(食べさせる)という番組企画を
改 ツンドラをサバイバル登山スタイルで隕石湖まで徒歩旅行して、新種のイワナを釣りあげる(そして食べる)という番組企画を
※服部文祥氏の連載で、14年1月にNHKBSで放送された『地球アドベンチャー ~冒険者たち~』の極東シベリア行の顛末を書いているが、この取材のあらすじとして「~させる」という使役の表現が目立つ。が、この番組ディレクターの山田和也氏の話も聞いたことはあるが、(山田氏から番組企画を申し出た)服部氏とは使役のような主従(上下)関係にはなかった気がする。この「前号までのお話」のような書き方では、山田氏が服部氏に指示して演出としてやらせている、という純粋なドキュメンタリー番組とは言い難い意味にも取れてしまう。
取材とはいえ旅なので、そのような主従関係ではなく、服部氏がこの連載で詳述しているように現地入り後は(というか日本を出国する前から許可の件も含めて)トラブル続きではあったようだが運命共同体として対等な人間関係で苦楽をともにしたと見受けられるのだが。よって、不適切と思われる「~させる」表記には疑問出ししたい。
●P103、本文中段
× 三陸リアス式海岸は
○ 三陸リアス海岸は
※7、8年前からだと思うが、世代を問わず地理教育上の専門用語では「リアス式海岸」の「式」を取った「リアス海岸」のほうが一般化している。この畠山重篤氏の連載では漁場の宮城県・気仙沼について触れているが、リアス海岸については地域は問わないと思う。
・「リアス式海岸」から「リアス海岸」への変更について (帝国書院編集部)
・岩手県にはなぜリアス式海岸があるの? (NHK盛岡放送局)
・Q3「リアス海岸」について (教育出版)
3つ挙げたリンクのなかで、教育出版の根拠が最もわかりやすいかも。帝国書院の地図帳を凝視すると、スペイン北西部に「リアスバハス海岸」があるし。
僕も仕事で高校地理の教材をかれこれ7年ほど扱っているが、たしかにその頃からすでに「リアス海岸」に切り替わっているため、僕は「リアス式海岸」という表記は古い、という認識である。ただ、用語の大枠としては「式」があっても間違いではないので、実務では赤字(要修正)扱いではなく疑問出しに留めておいたほうがよさそう。
「リアス海岸」を各地で当てはめる場合の大雑把な意味合いとしては、「(スペインの)リアス(地方)のような沈水海岸」ということかなあ。だからこの本文の表記もホントは、「三陸にある、リアスのような沈水海岸」が正しいのかもしれない。ただそれでは長すぎるから、便宜的に「三陸リアス海岸」に縮めざるを得ない、みたいな。
●P125、「Profile」
× カイトボーデイングに親しむ
○ カイトボーディングに親しむ
※鈴木英貴氏の連載で、筆者プロフィール内の「ボーディング」の「ィ」が小文字か大文字かという、単に字面の問題で内容にはまったく抵触しない程度の傍目にはどうでもよい? ことだが、国内の代表的な団体である「日本カイトボード協会」のウェブサイトでは「カイトボーディング」と小文字の表記なので、これに沿った表記にしたいものだ。
●P126、筆者略歴
× 1954年生まれ。登攀暦半世紀。
○ 1945年生まれ。登攀歴半世紀。
※海津正彦氏の連載の筆者略歴で、生年の4と5が入れ替わっている(入れ替わると9歳違いになってしまう)。東京新聞版の8月号以前は合っていたのだが……。
また、「暦」と「歴」という「れき」の使い分けでは、半世紀(50年間)の「登攀」という経験年数を言い表す場合は「歴」だろう。
「暦」で「こよみ」の読み方の意味も厳密に考えると、(年・月・週・日などの)言わばカレンダーの1年間の範囲内の話なので、やはり不適切だと思う。
という感じ。内容・意味に抵触するほどでもない字面の問題だけという点も気になるのは、もはや職業病なので致し方ない。
まあそれはそれとして(しかし改善はもちろん所望するが)、このカタチの新しい『岳人』を末永く発行し続けてほしい、と期待する。
※14年9月末の追記
9月発売の10月号の巻末に、「9月号のお詫びと訂正」として「1970年」の件が出ており、「1984年」に改めている。
また、10月号で「1954年」は「1945年」に修正された。しかし、「登攀暦」は変わらず……。
※15年3月上旬の追記
15年3月号から、「登攀暦」は「登攀歴」に修正されている。