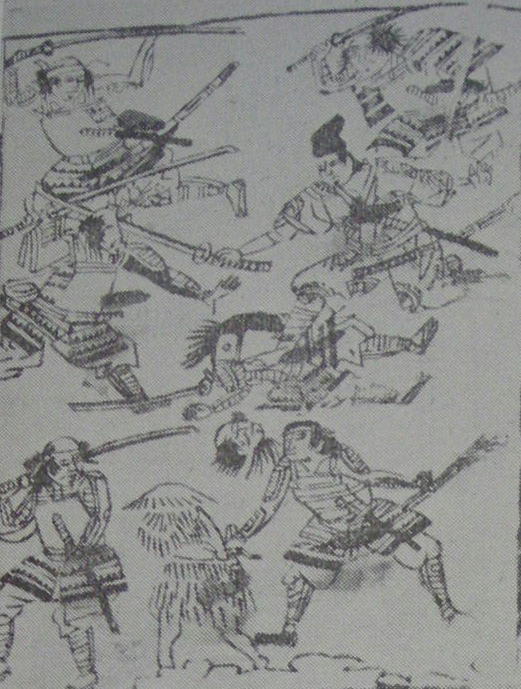はらだ ⑤
間もなく、若君の事は、鎌倉殿にも聞こえました。鎌倉殿は、
「この国に、不思議な稚児がやって来たと聞いた。連れて参れ。」
と、命じました。直ぐに使者が立ち、若君は、鎌倉殿の御前においでになりました。鎌倉殿は、若君にいろいろな事を尋ねました。
「御稚児は、まだ若いのに、どうして修行に出る事になったのか。」
若君は、
「人の為、又、自分の為、諸国修行の旅に出ました。世間を知らず、憂い事も、辛い事も知らない儘では、立派な人間にはなれないからです。」
と答えました。鎌倉殿は、重ねて、
「おお、それは大変、尤もなことだが、白骨を集めて、千体の地蔵を作ったのは、どういうわけか。」
と尋ねました。若君は、
「白骨を集めて地蔵を作ったのは、外でもありません。『将軍菩薩』こそが、修羅道に落ちた者達を救ってくれるからです。十三年前に、筑前の者達が、由比ヶ浜で討ち死にしましたが、無縁仏となり、弔う者もありません。彼らの修羅の苦患を救う為に、千体の地蔵を作ったのです。」
と答えました。次に、鎌倉殿は、
「御稚児は、毎日、法華経を読誦すると聞くが、その功徳は、どのようなものか。」
と尋ねました。若君は、
「釈迦一代の説法の中でも、法華経は、『一切衆生、即身成仏』にて『草木国土、悉皆成仏』と、説かれました。つまり、草木や土くれですら、仏性を具有し、成仏するということです。殊に、五逆罪の龍女ですら、ついには仏となるのです。このような尊いお経ですから、毎日読めば、成仏は間違いありません。」
と、すらすらと答えます。今度は、
「さて、それでは、夜念仏(よねぶつ)をしているのは何故か。」
と尋ねました。若君が、
「はい、夜念仏とは、『一念弥陀仏、即滅無量罪』と申しまして、一度でも弥陀仏を念ずれば、弘誓(ぐぜい)の舟に救い上げて、浄土の台(うてな)に運び上げようという誓いなのです。殊に、このように危うい世の中で、何に縋って生きて行けば良いのでしょうか。人の心こそが一番、恐ろしい。世の為、人の為、自分の為に、毎日、夜念仏をするのです。」
と答えたので、鎌倉殿は、感心して、
「実に有り難き次第。」
と、お手を合わせて、若君を拝むのでした。周りの人々も、有り難い、有り難いと、拝まない者はありませんでした。それから、鎌倉殿は、
「御稚児殿。寺が欲しければ造らせよう。所領が欲しければ、与えよう。望みは何か。」
と言いましたが、若君は、
「私は、修行の身の上ですから、寺も所領もいりませんが、ひとつだけ望みがあります。叶えて頂けるのなら、申しましょう。」
と答えたのでした。鎌倉殿は、気軽に、
「さあ、申してみよ。」
と言いましたので、若君は、改めて、
「大変に、畏れ多い事ですので、簡単ではありません。ご誓文をなされるのなら、申しましょう。」
と念を押しました。鎌倉殿が、
「それ程に言うのであれば、若宮八幡に誓って、お前の望みを叶えよう。」
と答えたので、若君は、
「分かりました。それならば、申します。鎌倉、谷七郷の牢屋に繋がれて人々を、全ていただきたい。」
と、願い出たのでした。鎌倉殿は、予期せぬ望みに驚いて、しばらく答えることができませんでした。ようやく、鎌倉殿は、
「牢に下した者共には、咎人で有るから、それはできぬ。」
と答えましたが、若君は、立ち上がって、
「だから、言った事ではありませんか。ご誓文というものは、綸言(りんげん)汗の如し、出たら再び帰らぬものです。慈悲の心をもって御世を治めると言われる最明寺殿は、この様な愚人でありましたか。そいうのを『嚙み済んだ後は、舌にも残らぬ』と言うのです。やれやれ、あなたの政(まつりごと)も思いやられますね。」
と、吐き捨てました。これには、鎌倉殿も、ぐうの音もでませんでした。すごすごと、
『三十六人の牢下し者を御稚児に参らす。』という自筆の御判を下されたのでした。
喜んだ若君は、牢の奉行を呼ぶと、
「鎌倉殿のご命令によって、牢下しの者の身柄を預かった。皆、釈放するので、その由、触れを出せ。」
と命じたのでした。早速に、谷七郷に触れが回り、近国他国より、咎人を引き取ろうと、縁者が駆けつけて来ました。若君は、牢奉行に、
「牢の戸口に、鼠木戸(ねずみきど)を設えて、一人一人呼び出し、その名前をすべて記録いたせ。もしかしたら、父の種直と、名乗る者がいるかもしれないので、ようく気をつけるように。」
と、命じましたので、一人一人の名前を記録しながら、咎人を釈放して行きます。釈放された人々は、次々に親類、眷属の者達が受け取って、我が家へと帰って行きますが、父の種直を名乗る者はいません。若君は、
「いつの日にかは、父に巡り会えると思って、ここまで来たのに、とうとう父には会えなかったか。」
と、悲嘆に暮れて泣くより外はありません。若君の心の内は、何にも例え様がありません。
つづく

間もなく、若君の事は、鎌倉殿にも聞こえました。鎌倉殿は、
「この国に、不思議な稚児がやって来たと聞いた。連れて参れ。」
と、命じました。直ぐに使者が立ち、若君は、鎌倉殿の御前においでになりました。鎌倉殿は、若君にいろいろな事を尋ねました。
「御稚児は、まだ若いのに、どうして修行に出る事になったのか。」
若君は、
「人の為、又、自分の為、諸国修行の旅に出ました。世間を知らず、憂い事も、辛い事も知らない儘では、立派な人間にはなれないからです。」
と答えました。鎌倉殿は、重ねて、
「おお、それは大変、尤もなことだが、白骨を集めて、千体の地蔵を作ったのは、どういうわけか。」
と尋ねました。若君は、
「白骨を集めて地蔵を作ったのは、外でもありません。『将軍菩薩』こそが、修羅道に落ちた者達を救ってくれるからです。十三年前に、筑前の者達が、由比ヶ浜で討ち死にしましたが、無縁仏となり、弔う者もありません。彼らの修羅の苦患を救う為に、千体の地蔵を作ったのです。」
と答えました。次に、鎌倉殿は、
「御稚児は、毎日、法華経を読誦すると聞くが、その功徳は、どのようなものか。」
と尋ねました。若君は、
「釈迦一代の説法の中でも、法華経は、『一切衆生、即身成仏』にて『草木国土、悉皆成仏』と、説かれました。つまり、草木や土くれですら、仏性を具有し、成仏するということです。殊に、五逆罪の龍女ですら、ついには仏となるのです。このような尊いお経ですから、毎日読めば、成仏は間違いありません。」
と、すらすらと答えます。今度は、
「さて、それでは、夜念仏(よねぶつ)をしているのは何故か。」
と尋ねました。若君が、
「はい、夜念仏とは、『一念弥陀仏、即滅無量罪』と申しまして、一度でも弥陀仏を念ずれば、弘誓(ぐぜい)の舟に救い上げて、浄土の台(うてな)に運び上げようという誓いなのです。殊に、このように危うい世の中で、何に縋って生きて行けば良いのでしょうか。人の心こそが一番、恐ろしい。世の為、人の為、自分の為に、毎日、夜念仏をするのです。」
と答えたので、鎌倉殿は、感心して、
「実に有り難き次第。」
と、お手を合わせて、若君を拝むのでした。周りの人々も、有り難い、有り難いと、拝まない者はありませんでした。それから、鎌倉殿は、
「御稚児殿。寺が欲しければ造らせよう。所領が欲しければ、与えよう。望みは何か。」
と言いましたが、若君は、
「私は、修行の身の上ですから、寺も所領もいりませんが、ひとつだけ望みがあります。叶えて頂けるのなら、申しましょう。」
と答えたのでした。鎌倉殿は、気軽に、
「さあ、申してみよ。」
と言いましたので、若君は、改めて、
「大変に、畏れ多い事ですので、簡単ではありません。ご誓文をなされるのなら、申しましょう。」
と念を押しました。鎌倉殿が、
「それ程に言うのであれば、若宮八幡に誓って、お前の望みを叶えよう。」
と答えたので、若君は、
「分かりました。それならば、申します。鎌倉、谷七郷の牢屋に繋がれて人々を、全ていただきたい。」
と、願い出たのでした。鎌倉殿は、予期せぬ望みに驚いて、しばらく答えることができませんでした。ようやく、鎌倉殿は、
「牢に下した者共には、咎人で有るから、それはできぬ。」
と答えましたが、若君は、立ち上がって、
「だから、言った事ではありませんか。ご誓文というものは、綸言(りんげん)汗の如し、出たら再び帰らぬものです。慈悲の心をもって御世を治めると言われる最明寺殿は、この様な愚人でありましたか。そいうのを『嚙み済んだ後は、舌にも残らぬ』と言うのです。やれやれ、あなたの政(まつりごと)も思いやられますね。」
と、吐き捨てました。これには、鎌倉殿も、ぐうの音もでませんでした。すごすごと、
『三十六人の牢下し者を御稚児に参らす。』という自筆の御判を下されたのでした。
喜んだ若君は、牢の奉行を呼ぶと、
「鎌倉殿のご命令によって、牢下しの者の身柄を預かった。皆、釈放するので、その由、触れを出せ。」
と命じたのでした。早速に、谷七郷に触れが回り、近国他国より、咎人を引き取ろうと、縁者が駆けつけて来ました。若君は、牢奉行に、
「牢の戸口に、鼠木戸(ねずみきど)を設えて、一人一人呼び出し、その名前をすべて記録いたせ。もしかしたら、父の種直と、名乗る者がいるかもしれないので、ようく気をつけるように。」
と、命じましたので、一人一人の名前を記録しながら、咎人を釈放して行きます。釈放された人々は、次々に親類、眷属の者達が受け取って、我が家へと帰って行きますが、父の種直を名乗る者はいません。若君は、
「いつの日にかは、父に巡り会えると思って、ここまで来たのに、とうとう父には会えなかったか。」
と、悲嘆に暮れて泣くより外はありません。若君の心の内は、何にも例え様がありません。
つづく