
ここで在庫に関する取引とは、在庫の変動を伴う取引を総称して呼んでいます。
商品を出荷したり、発注した商品が納入されることにより、商品の在庫が増減します。実際に商品が動くことのみを在庫管理の対象とすることもありますが、ここでは、もう少し範囲を拡げて論理的な在庫数の増減を含めて考えていきます。
例えば、受注しただけでは商品の移動は発生しません。受注商品を出荷した場合に実際の在庫が減少することになります。しかし、商品の在庫が100個あるからといって90個の受注を受けていいかというと、必ずしもそうではありません。
前日に別の得意先から30個分の注文を受けているかもしれないからです。(受注可能な在庫かどうかを把握する必要があります。)
通常、在庫数として在庫引当数(在庫未引当数)というものを管理し、今現在、何個までの商品の受注が可能かということを管理しています。
実際に商品が何個存在するかということだけではなく、何個の在庫が有効なのか(有効在庫数)や、あと何個の商品が入ってくる予定なのか(発注未入荷数)といった情報も在庫情報として管理することが必要となる場合もります。
これらの在庫と関係する取引としては、以下のような取引が存在します。
1.受注
2.出庫(受注品出荷)
3.出庫(購買品返品)
4.出庫(倉庫間移動)
5.出庫(雑出庫)
6.売上
7.発注
8.入庫(購買品入荷)
9.入庫(未発注入荷)
10.入庫(良品返品)
11.入庫(不良品返品)
12.入庫(倉庫間移動)
13.入庫(雑入庫)
14.仕入
15.在庫処分
16.評価替え
17.棚卸差異
等です。(これら以外にも在庫に関する取引が存在するかもしれませんし、企業によってはこの全てを管理する必要はないかもしれません。)
これらの取引の説明については、別途行いたいと思います。
在庫取引では、在庫数量が変化する取引の内容を管理するようにします。 
(図1)在庫に関連する取引
上記のように取引と在庫の関連を整理することにより、在庫の変遷を管理することができます。
在庫と在庫に関連する取引の関係ですが、ある在庫に関する受注や出荷や入荷といった取引はそれぞれ複数存在する可能性があります。
また、在庫に関連する取引は上記のようにさまざまな取引が存在しますので、”在庫取引”のサブタイプとしてそれぞれの取引に対する在庫取引を追加します。
そして、それぞれの在庫取引(のサブタイプ)には、関連する取引そのものから関連を定義しておきます。
こうすることにより、ある商品の在庫の変遷を各種の取引と関連付けて管理することが可能となります。(在庫受払表に該当する情報と考えてもらうと分かりやすいかもしれません。)
(図2)在庫取引のパターン












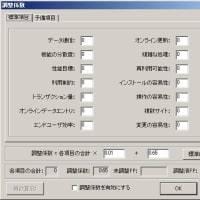

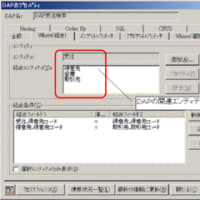


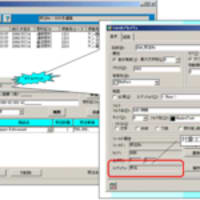
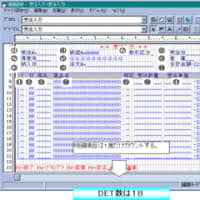








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます