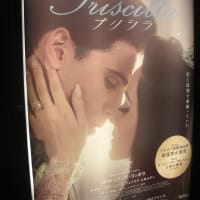ようやく蓮實重彦の『ショットとは何か』(講談社 2022.4.29)を読み終えて、ところでamazonのレビューではどのような評価をされているのか調べてみたところ、驚いたことに事実誤認があるとして批判されていたので、そのことを改めて検証してみようと思う。
まず最初の批判として、蓮實の、アメリカの映画研究者デヴィッド・ボードウェルに対する批判が見当違いだとされている。
「著者はアメリカの映画研究者デヴィッド・ボードウェルの所説をきびしく批判していますが、そのすべてが、彼の主著 Classical Hollywood Cinema(1985年) や Narration in the Fiction Film(1985年) などをきちんと参照していれば絶対に出てこない批判ばかりです。ボードウェルらは、「180度ルール」のような古典的ハリウッド映画の映像技法が、アメリカ映画産業全体に結果として強くあらわれていると言っているにすぎなくて、著者が思い込んでいるように美学的規則が成立しているとは一言も述べていません。」
本書で蓮實はボードウェルの『小津安二郎 : 映画の詩学(Ozu and the Poetics of Cinema)』(原著 1988 / 邦訳 1993)を引用している。
「古典的ハリウッド映画は、『一八〇度のライン』や『アクション軸』(中略)の規則を神聖視した。これは、人物を向き合うように配置し、彼らの相互の関わり合いを示す様々なショットを、アクション軸の一方の側から撮ることを前提とした。」(p.209)
その上で蓮實は自身の解釈を披露している。
「ちなみに、そこで『規則』と呼ばれているのは、原文では≪the rule≫の一語にあたっているのですから、一応『規則』という訳語は正しいといえるでしょう。しかし、著者はそれとは異なる場所では≪system≫(一八〇度のシステム)と書いており、そこでは若干のニュアンスの違いが見られます。『規則』なら、それに従わない場合はすべてが違反と見なされることになりますが、『システム』であるなら、それとは異なる『システム』を代置すればそれでよいということになるからです。」(p.210)と述べており、蓮實は「著者が思い込んでいるように美学的規則が成立している」とは一言も述べおらず、「しいていうなら、それはいわゆる『一八〇度の慣行』とでもいうにとどめておくべき語彙なのです。」(p.210)と断っているのだから、『「180度ルール」のような古典的ハリウッド映画の映像技法が、アメリカ映画産業全体に結果として強くあらわれている』と言っているらしいボードウェルと同意見なのである。
蓮實が問題にしているのは「古典的ハリウッド映画は、『一八〇度のライン』や『アクション軸』(中略)の規則を神聖視した。」と書いているボードウェルがどれほどの自信を持って書いているのかという点にある。本当に「神聖視していたの?」という話である。
「ハリウッド映画の撮影・編集技術のほとんどをD・W・グリフィスが発明した」と蓮實が本書のどこで述べているのか確認できなかったのだが、「ショットという概念を映画に導入したのがグリフィスだと考えていいのでしょうか?」と問われた蓮實は以下のように述べている。
「それはいかにも微妙な問題です。確かに、グリフィスがショットを演出の基本概念として極度に洗練化したのは間違いありません。しかし、それ以前に、リュミエール兄弟の『シネマトグラフ』にもショットはまぎれもなく存在していたからです。」(p.133-p.134)
「グリフィスがクローズアップを巧みに画面にとりこんでいたのは確かな事実だとしても、『撮る』監督としての彼の真の偉大さは、ごく普通のショットをごく普通に撮って見せることにあったのだとわたくしは思っています。」(p.195)
蓮實は決してグリフィスを「神聖視」してはいない。
せっかくなので「ショットとは何か」という問いに対する蓮實の回答めいたものを引用しておきたい。
「例えば、『雨に唄えば』の驟雨の中のジーン・ケリーのソロなども、スキルの顕示といった側面が強く、それを映像的に表象しているだけといった印象が強い。それはパフォーマンスとして優れたものでありますが、それに対して映画の表象能力がかろうじて対抗しているといった気がしてならない。ところが、『バンド・ワゴン』のこのシーンには、その種のスキルの顕示といった曲芸性はまったく希薄で、しかも、往年のハリウッドのスターとこれから名声を得ようとしている若いバレリーナとが、初めて二人だけで歩調を合わせて踊るという、いわば身振りの一回性だけが持ちうる緊張感があたりにはりつめているのです。」(p.245)
ジル・ドゥルーズの『シネマ1・2』を批判できる映画批評家も蓮實くらいであろう。評者は別に蓮實重彦の崇拝者ではなく、むしろボコボコに論破されている蓮實をいつかは見てみたいと心から願っているのだが、早くしないともうそんなに時間がないよ!
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/nikkangendai/entertainment/nikkangendai-932864