
freefan74号が届いた。
今回の目玉は、柏木特集。
再開に向けて、私の元にも、問合せメールが何度か来た。
当時の開拓者の多くは、引退したりで、連絡がつかないようだ。
私も分かっている限り、仲介の労をとった。
また、私の知っている情報も提供した。
さて、今回のJFA表紙は「神がかり」。
クライマーは「親方」。
この「神がかり」の初登者が分からなかったようで、空白となっている。
問合せが来たので、nakano君にメールを送って、さらに「神頼み」初登者hiranoさんに連絡を取ってもらった。 (nakano君とhiranoさんは、同じ社会人山岳会の後輩・先輩の関係…現在、その山岳会は解散している。ちなみに、nakano君は、「パラレル」「アーリーバード」の設定/初登者)
ルート名「神頼み」の由来は、hiranoさんが、行き詰まった時、バナナをお供えしてRPしたことから付けたと聞いている。(RPしてすぐ、そのバナナを食べたそうだ)
「神がかり」は、その途中から右に派生するルートであるが、こちらはhiranoさんの初登ではない。
これはメールで本人に確認してもらったし、当時、私も聞いていない。
私は(たぶん)マルちゃんではないか、と思う。
「神がかりにならなくても、登れる」と、当時、コメントしていたから。
でも、今回のトポには間に合わず、本人に確認できなかったようだ。(実際どうなんだろう?)
もっと早くに言ってくれたら、連絡の取りようが有ったのだが、結局「空白」となったようだ。
さて、P10-P11に、ルート名と設定/初登者が掲載されている。
この中で、女性の名前が2人ある。
#3「マリノライン」と、#23「日本ちゃちゃちゃ」。
私は80年代から90年代前半に柏木に通った。(90年代後半は、鳳来にシフトした)
当時、柏木に来る女性クライマーは少なかった。(現在でも少ないだろうけど)
「マリノライン」は、マリちゃんが作ったから、「マリノライン」である。
ちなみに、『再開にあたって』の文章を書いているのが、まりこさんだけど、全く別人である。
マリちゃんは、現在、iseki君の奥さんだから。
「日本ちゃちゃちゃ」は、みっちゃんが作った。
こちらは、現在、マルちゃんの奥さんである。
つまり、このトポにある2人の女性名は、旧姓という事だ。
ついでに言うと、開拓当時、柏木に来ていた女性クライマーは…
Hさん、Rちゃんを覚えている。(現在、音信不通)
Mちゃんも当然来ていたと思うけど、あまり記憶にないから、前夜の宴会には参加してなかったのだろう。(現在、年賀状のやり取りのみ)
ホッシーは、開拓時代最後の頃に来ていた。(現在、ナカガイ君の奥さん)
こんなところかな…。
私も、歳と共に、記憶力も薄れてきた。
「私も通っていた」、と言われそう。
忘れていたら、ご指摘下さい。
最後に、おまけ情報として書いておくと、「トパッピー」12+の2ピッチ目に、
私も、(森脇さんの了解を得て)「トタッキー」というルートを作った。(命名・森脇氏)
あまりの不人気ルートゆえ、リボルトから外れ、ルート図にも載らなかった。
鳳来にも、私の不人気ルートがあるが、どうも、私はルートを作る才能がないようだ。
マルちゃんや親方と大違い、だ。
(関係ないけど、親方とyuzuki君には、私の家の手すりも作ってもらった…感謝!)
たわいもない思い出ばかり語った。
今回の柏木再開は、多くの方の尽力のたまものである。
この文章に、名前が出なくても、リボルトやアプローチの整備など、多くのクライマーの助力がある。
地元との交渉など、大変だったと聞いている。
ご苦労様と申しあげたい。
今後、二度と事故の無いよう、願っている。(祈るような気持ちだ)
私は、個人的事情で、あまり自宅を留守にできず、おそらく柏木訪問は無理。
代わりに、どなたか行かれたら、私に話を聞かせてください。
柏木記事ばかり書いたが、P24-31『信頼されるビレイヤーになろう』も良かった。
ぜひ、一読をお勧めする。
P431
もうひとつ大切なことは、ビレイを引き受けたら、決してクライマーから目を離さない、ということです。(中略)
さらには、ビレイ中は他の人とおしゃべりしたりせず、ビレイに集中してください。ビレイヤーが会話していいのは、ビレイしているクライマーだけです。
(中略)
高度なクライミングは高度なビレイから生まれます。「勝負の時はビレイはあいつに頼みたい」と思われるような、信頼されるビレイヤーになってください。
(「こんな事、当たり前やん」と思われるかもしれないが、出来ていないクライマーが多い、ということだろう)

「アローンオンザウォール 単独登攀者、アレックス・オノルドの軌跡」アレックス・オノルド/デイヴィッド・ロバーツ/堀内瑛司/訳
フリーソロで有名なアレックス・オノルド。
読んでいて、指先から汗が出る。
文字通り、手に汗握る内容だ。
ヨセミテの歴史も語られていて、知識の確認にもなる。
お薦めです。(図書館には入荷しなかったので購入した)
クライマーなら、読んで良かった、と感じるはず。
P18
「ぼくはいつもリスクのことを”実際に墜落する可能性”と呼んでいる。結果とは、実際に落ちたときに起こることだ。つまり、ぼくはソロで登るときのリスクを低く抑えようとしている。もし落ちたら本当に重大な結果になるとしても、落ちる可能性が低くなるようにしているんだ」
P25
ぼくはヨセミテに行った。狙っていたのは二つの名ルート――240メートルの美しい花崗岩の壁、ロストラムのノース・フェース(5.11c)と、ワシントン・コラムにある試金石というべき330メートルのアストロマン(5.11c)だ。
1987年にピーター・クロフトが両ルートを1日でフリーソロし、クライミング界を震撼させた。それから20年、同じことを成し遂げた者はいない。
(アレックス・オノルドは2007年9月19日、両ルートフリーソロに成功…う~ん、ロープを使ってもRPは困難と思う。なお、ディーン・ポッターも2000年、アストロマンをフリーソロしている、2015年5月16日ベースジャンプに失敗して死亡。合掌…)
P37
「しばらくクライミングをしないこともあるんですか」「もちろん」とぼくは答えた。
「では、例えば1カ月ほどまったく登らずに過ごすことは?」
「それはありえない。1カ月なんて想像もつかないよ。”しばらく”っていうのは3日くらいのことかと思ったんだ」
P46
ぼくはドラッグには生まれてから一度も手を出したことがない。アルコールについては、味見をしてみたことはあるけれど、グラスを飲み干したことはない。コーヒーも飲まない。
P261
ある場所でトミー(コールドウェル)が石を拾ったかと思うと、10センチほどのクラックに嵌め込んでアンカーにした。「前にもこうやって下りたことがあるのか」と訊くと、トミーはぼくを安心させるように言った。「大丈夫、絶対に抜けやしないさ」
【参考リンク】
【PR・動画特集】『ALONE ON THE WALL アローン・オン・ザ・ウォール
アレックス・オノルドのこれまでを綴った自叙伝『ALONE
【おまけ】
しかし、よくこの本を出版したものだ。確かにすごい内容だけど、一般ウケするとは思えない。ただ、何パーセントかの読者には、興奮して唖然とする中身になっている。こいつは、ただ者ではない、と。
訳も自然な感じで良かった。それなりの経験のあるクライマーでないと、この翻訳はできない。
【ネット上の紹介】
ロープなし。落ちたら最後。男はなぜ、極限のフリーソロに挑むのか―クライミング界で今、最も気になる男の「魂」の書。これまでのクライミングの常識を覆し、驚異的なフリーソロの記録を出し続けてきたアレックス・オノルドが半生を振り返り、自らのクライミング哲学を語る。自身も登山家で山岳ノンフィクション作家として知られるデイヴィッド・ロバーツが共著に加わり、極限スポーツのさらなる極限に挑み続ける男の人物像を描き出す。
[目次]
第1章 ムーンライト・バットレス
第2章 独りきりの地獄
第3章 恐怖と愛
第4章 世界を旅する
第5章 ヨセミテ・トリプル
第6章 スピード記録
第7章 アラスカとセンデロ・ルミノソ
第8章 フィッツ・ロイ
第9章 さらなる高みへ
オノルド,アレックス (オノルド,アレックス) Honnold,Alex
1985年カリフォルニア州生まれのアメリカ人ロッククライマー。10歳のときにクライミングを始める。カリフォルニア大学バークレー校に入学するも19歳で中退し、車上で暮らしながらクライミングに専念する。ハーネスやロープなど安全確保のための道具を一切使わずに登るフリーソロクライミングで数々の記録を打ち立て世界の注目を集める。2010年に、世界で最も優れたクライマーに贈られるゴールデン・ピトン賞を受賞。2015年には、その年の最も優れたアルパイン・クライミングを顕彰するピオレドール(黄金のピッケル)賞も受賞した
ロバーツ,デイヴィッド (ロバーツ,デイヴィッド) Roberts,David
1943年生まれ、マサチューセッツ州在住。クライミング関係の著作物が多く、クライマーとしても名高い。特にアラスカではマッキンリー山のウィッカーシャム壁の初登攀を含め、数々の記録を残している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

「天空の犬」樋口明雄
3年ほど前に読んだ作品。→「「天空の犬」樋口明雄
読みながら、思い出してきた。
南アルプス・北岳が舞台。
山岳救助隊・星野夏実と、救助犬・メイの活躍が描かれる。
2回目だけど、楽しめた。
【ネット上の紹介】
南アルプス山岳救助隊の新人隊員・星野夏実は、相棒の救助犬、ボーダーコリー=メイとともに、北岳にある現地警備派出所に着任した。過酷な訓練と、相次ぐ山岳事故、そして仕事への情熱と誇り。そんな日々の苦楽をともにする仲間にも打ち明けられない秘密が、彼女にはあった。東日本大震災の被災地で目の当たりにした凄惨な光景―“共感覚”という能力を持つがゆえに受けてしまった深い心の疵が、今もなお越えられぬ岩壁のように夏実の前に立ちはだかっていた。やがて立て続けに起こり始める不審な出来事。招かれざるひとりの登山者に迫る陰謀と危難を察知した夏実は、猛り狂う暴風雨の中、メイとともに命をかえりみず救助に向かった…。

「外道クライマー」宮城公博
沢をやる人は無謀な方が多い。
そういう印象を持っている。
沢の方が岩よりも、不確定要素が多いからかもしれない。
「無謀」という表現が悪ければ、冒険心に富んだ、と言い換えてもいい。
無謀と冒険は紙一重だから。
何%の確率で生還できたら冒険なのだろう?
その方の体力、技術力、精神力で変わってくる。
同じことをしても、個々人によって差がでる。
運も左右する。
パソコン、衛星電話、GPSの利用。
外部の気象専門家とのやりとり。
これらをどれだけ利用し、あるいは排除するのか?
現代において、冒険は条件をつけないと成立しにくい。
ある程度、こだわりが必要ということだ。
いくつか文章を紹介する。
私が笑った箇所、那智の滝を登って捕まって取り調べを受ける…P21
取り調べが終わると、指紋を採取される。大西はクライミングのしすぎで指がまっすぐに伸びないので、指紋採取で警官に無理やり手を押さえれて指を伸ばされると、
「いてっ、痛い、痛いって」
と、悶絶していた。
(う~ん…これは痛い、当局による拷問だ!byたきやん)
P80-81
意外に思うかもしれないが、沢登りでは脱水症状に陥りやすい。水に濡れて身体が冷えるので、水分摂取がおろそかになりがちなのだ。脱水症になると身体は水分を蓄える方向に働き、むくみはじめる。むくむと身体のキレが悪くなるし、その状態が続くと身体の不調に繋がることは明白だ。だから水分を意識的に多く取るのだが、どうしても夜に集中するので、夜中に起きて小便に行きたくなる。夜中に起きると寝不足に繋がってまたむくむという、なかなか断ち切れない悪循環に陥るのだ。私たちはこれを「小便地獄」と名付けた。
著者の感情が素直に表現されている。
自分の負の感情も、かっこ悪いところもさらけ出している。
なかなか出来ない事だ。
臨場感が伝わってくる文章だ。
さて、タイトルで「外道」と称している。
でも、私が本作を読んで感じた限りでは、
著者はクライミングの本質を突いた行動をしている、と思う。
世間がズレてしまっているのかもしれない。
【おまけ】
誤解を避けるために明記しておくが、私は神域を侵したり、法を守らなくてよい、と言ってる訳じゃない、心の持ちようの話である。
【誤植】
校正ミスを見つけた。
P131
(誤)いや、仕事を止める覚悟だと?
↓
(正)いや、仕事を辞める覚悟だと?
【目次】
逮捕!日本一の直瀑・那智の滝
タイのジャングル四六日間の沢登り
日本最後の地理的空白部と現代の冒険
台湾最強の渓谷チャーカンシー
二つの日本一への挑戦
沢ヤの祭典ゴルジュ感謝祭
【ネット上の紹介】
「最も野蛮で原始的な登山」と呼ばれる沢登り。那智の滝登攀による逮捕をきっかけに、日本や台湾、タイの未知の渓谷に挑む筆者と沢ヤたち。地球上に残された最後の秘境、ゴルジュに挑む壮絶なる冒険記。
【著者略歴】
1983年愛知県春日井市生まれ。凸版印刷、福祉施設職員を経て、現在はライター、登山ガイド、NPO富士山測候所職員。ヒマラヤ、カラコルムでのアルパインクライミングから南国のジャングルでの沢登りにいたるまで初挑戦にこだわり続け、国内外で数々の初登攀記録をもっている。2009年、ヒマラヤ・キャジョリ峰北西壁への単独初挑戦。12年、那智の滝での逮捕によって七年間勤めた福祉施設を辞める。13年、立山称名滝冬期初登攀、台湾チャーカンシー初遡行、カラコルムK6西峰北西壁挑戦(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
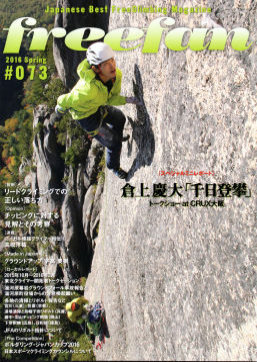
freefan72号
だいぶ前に郵送されてきたが、紹介とコメントが遅くなった。
今回、私が注目した記事は、篠崎喜信さんによる「リードクライミングでの正しい落ち方」。
P12
「今墜ちたらどうなる?どうする?」ということを意識しながら登るべきである
クライミング中の墜落で起きた事故・怪我の相当数はビレイヤーの技量、注意不足が原因となることが多い。よって、信頼出来るビレイヤーに確保してもらうことが必要。
P13
高度なクライミングは、高度なビレイから生まれる。登れるより、頼られる、信頼されるビレイヤーを目指す事も安全にクライミングを続けるうえで大切なことである。
クライミングは、クライマーとビレイヤーの共同作業。
落ち方もテクニック、落とし方もテクニック。
クライマーの動きを見ていないビレイヤーもいる。
これは論外、クライミング以前の問題。
クライマーから目を離さず、動きを察知し、的確にロープを繰り出す。
これだけで相当数の事故を回避できる。
この上に「技術」を積み上げていく。
これは逆、と思う。
ビレイが上手いと、次回も誘ってもらえる。
結果として、岩登りが上手くなる、って寸法だ。
登りたい時は、とりあえずビレイしてくれたら誰でもOK、って感じで岩場に行く。
特に、若い時は、そうであろう。
でも、信頼できるビレイヤーがいなかったら岩場に行かない、って判断も重要。
【参考リンク】
このところ、鳳来でも事故が続いている。
【内容】
[スペシャルミニレポート]
倉上慶大 「千日登攀」トークショー at CRUX大阪
[文:尾崎基文 ミニインタビュー:井上大助
写真:萩原悟、木織隆生]
- [技術]
リードクライミングでの正しい落ち方
[文:篠﨑喜信 写真:山本浩明] - [Opinion]
チッピングに対するJFAの見解とその考察
[文:北岡和義] - [連載] ローカル強強クライマー列伝
高橋洋祐
[文:若林伸一郎 写真提供:高橋洋祐] - [ローカルレポート] 2015年10月~2016年3月
[構成:宮脇岳雄、北岡和義、井上大助、小川郁代]
- 東北クライマー開拓者トークセッション
- 湯河原幕岩グラウンドフォール事故報告と湯河原町役場からの注意喚起願い
- 各地の清掃とリボルト報告など
宮川(三重)、笠置(京都)、道場清掃と烏帽子岩リボルト(兵庫)、備中羽山チッピング問題(岡山)、下帝釈峡(広島)、日和佐(徳島) - JFAのリボルト指針について[文:枝村康弘]
- [The Competition]
ボルダリングジャパンカップ [文:伊東秀和 写真:窪田美和子]
日本スポーツクライミングカウンシルについて [文:藤枝隆介] - [連載 MADE IN JAPAN (株)グラウンドアップ 宇高要樹 [文と写真:榎戸雄一]

「現代ヒマラヤ登攀史8000メートル峰の歴史と未来」池田常道
新書で285ページ、コンパクトな割に読むのに時間が掛かった。
それもそのはず。
8000m峰のデータがびっしり詰まっている。
資料だけでない、そこからドラマが見えてくる。
生と死のドラマである。
P284
本書は、隔月刊誌「岩と雪」の98号(1983年3月)から112号(1985年10月)まで、112回にわたる連載記事に大幅な加筆訂正を施したものである。
(中略)
改めて『現代ヒマラヤ登攀史』を書く気にさせたのは、ネット時代のヒマラヤ情報が数字ばかりで語られる傾向が強いからである。それぞれの山には尊重されるべき歴史があり、現代の8千メートル峰登山者もその土台の上に自分たちの登山があることをもっと意識してもらいたい。昨今続出している頂上の取り違えなど、無知をさらけ出す以外の何物でもない。ガイドやシェルパが設置した固定ロープの終点を「頂上」と解して、誇らしげにブログに発表するなど、ほとんど想像を絶する。
新しい情報も盛り込まれている。
P196
2013年6月の夜半、ディアミール側ベース・キャンプがパキスタン・タリバン運動(TTP)の武装集団に襲われ、登山者10人と現地スタッフ1人が銃撃されて死亡するという事件が起こった。TTPの声明では、米軍の無人攻撃機による同派幹部殺害に対する報復だと言うが、犠牲になった外国人の国籍はウクライナ、中国、スロヴァキア、リトアニア、ネパールで米国人はいなかった。襲撃者はいちいち登山者のパスポートを確認して国籍を確かめ「ビン・ラーディンの仇」と呼号していたという。
なお、この事件については「ロクスノ」#061,P94,ON THE SCENEに詳しい。
…・こちらも単行本化されることを希望する。
海外に行く限り、現地の政情、日本との関係をきちんと把握する必要がある。
「登りたい」って思いだけで登れる訳ではない。
登山界にもグローバル化の波が押し寄せている。
【感想】
仮に登山がスポーツであるとするなら、これほど致死率の高い行為があるだろうか?
それも練習と経験を積んで熟達者となっても死亡率は高い。
生と死の境目を見極め、ぎりぎりの線を見切ろうとするからであろう。
普通に登っても、満足感が得られないから。
成功すれば、さらに危険度が増したルートを選択していく。
練習を積み、技を磨いて死に近づいていく。
なんと理不尽なことか。
普段は臆病すぎるほど慎重に、いざという時は、大胆に。
このタイミングを極め、尚且つ運の良いものが生き残るのだろう。
【ネット上の紹介】
1950年のアンナプルナ初登頂から60年を経た今日に至るまで、ヒマラヤ登山はどのように変遷し、どこに向かっていこうとするのか。『岩と雪』元編集長による8000メートル峰登攀史の集大成。
[目次]
マウント・エヴェレスト
K2
カンチェンジュンガ
ローツェ
マカルー
チョー・オユー
ダウラギリ1峰
マナスル
ナンガ・パルバット
アンナプルナ1峰
ガッシャブルム1峰
ブロード・ピーク
ガッシャブルム2峰
シシャ・パンマ
昨日紹介した「私には山がある」は、インタビューを原稿に起こしたものだが、
本作は、 田部井淳子さん自身による作品。
第1章と第2章に、分かれている。
第1章は、危機状況に陥ったときの対処。
第2章は、癌と診断され、その後の手術と闘病生活、それでも山に登った話。
P3
山で切羽詰まった状態になった時、つまり土壇場に立たされた時、どう行動したかについて本にしたいという話を編集部からいただいた。
P83
不満を持っている人というのは、言葉よりも態度でわかる。自分の不調を口に出して言えないとますます不満が溜まり、不満が溜まると、仲間からも遠ざかることになる。そして、孤立して人とのふれあいがなくなると、ますます不満が溜まっていく、というような悪循環に陥ることになる。
こういう人が一人いるだけで、グループ全体の雰囲気は悪くなってしまうものだ。だからこそ、わたしはできるだけ、早目に、不満を溜めていそうな人の傍に行き、まめに声をかけるように心がけている。
P147
一番の苦労は人との付き合いである。義理を欠いて多少悪人にされても、ストレスのない付き合い方に変えていかないといけない。まずは自分の健康、体治しが最優先である。
【おまけ】
一番良かったのが、第一章(P43)の「声が大きい人に気をつけろ」。
極限状況での、この対処・・・「ベースキャンプまで来て、登山の仕方そのものをひっくり返すような発言」に対して、冷静かつ波風を立てず、相手の立場を尊重した対応に感心した。
【参考リンク】
「私には山がある 大きな愛に包まれて」田部井淳子
【ネット上の紹介】
余命三カ月!?抗がん剤の副作用で足がしびれ、自宅の階段を上ることさえままならない。だが、点滴の合間を縫って登山家は山へ向かった。
[目次]
第1章 山から学んだこと(大切なものを守るために
墜落と平常心
偏らずに見る
声が大きい人には気をつけろ
疲れている時はまちがえやすい ほか)
第2章 それでもわたしは山に登る(がんのはじまり
乳がんのこと
そうだ、騒ぐな、オタオタするな
山とシャンソンと抗がん剤
こんな山に登った ほか)

「私には山がある 大きな愛に包まれて」田部井淳子
NHK・BSプレミアムで放送された内容をもとに、原稿を構成して単行本化してある。
読みやすく、実際すぐ読了した。
昔、「エベレスト・ママさん 山登り半生記」を読んだが、「その後」も書かれている。
田部井淳子さんの波乱に富む、濃い人生が語られる。
P24
頂上に着いた時の「やった!」という喜び。自分の足で一歩一歩登っていかない限り、頂上には辿り着けない。どんなにつらくても、登り始めたら誰も選手交代はできない。そんなことも私にとっては何かすごく心地よかったんですね。
P39
登っている時はつらい坂だなと思っても、歩くことで風景が変わっていくのは、たまらない魅力でしたね。
P73
親は子どもを常に守れるかといえば、そうではないと私は思っていました。三歳までは一緒でなければいけませんけれども、私に何かあっても、子どもは子どもの人格で育っていくと思っていました。
【参考リンク】
公式HP
NHKアーカイブス 日本女子登山隊エベレスト登頂(1975年) - 日本放送協会(NHK)
青春の挫折を救ってくれた山。雪崩に遭い、病気にもなり、子どもの反抗もあり、それでも一歩一歩登り続けた。夏には東北の高校生と富士山へ。今なお世界中の頂を目指す登山家の「山と人生」。
[目次]
第1章 病弱な子ども時代
第2章 憧れの東京、苦悩の日々
第3章 山に夢中
第4章 大切な出会い
第5章 エベレストへの道
第6章 女性だけの登山
第7章 登山と子育て―両立のはざまで
第8章 “下り”も楽しむ人生
第9章 「がん」になって
第10章 “一歩一歩”未来をひらく

「日本の山究極の絶景ガイド」西田省三
読んでいると、行ってみたい、って気分になる。
そのためにも、体力は維持しておきたい。
神遊びの庭のお花畑とトムラウシ山
四国山地・剣山直下から望む次郎笈
草すべりから見るカラマツの紅葉と浅間山
八甲田樹氷原
【おまけ】
現状に鑑みて、いったい、行ける日が来るのだろうか?
ある種、目の毒、でもある。
【ネット上の紹介】
山岳写真家が厳選した一生に一度は歩いて訪れたい四季折々の「山の絶景」を収録!
[目次]
夏の絶景(神遊びの庭のお花畑とトムラウシ山―北海道大雪山
南岳から望む大キレットと穂高連峰―北アルプス ほか)
秋の絶景(双六台地から望む槍・穂高連峰―北アルプス
大汝峰から望む剣ヶ峰と御前峰―白山 ほか)
冬の絶景(姿見の池から見る冬の旭岳―北海道大雪山
八甲田樹氷原―青森県八甲田山 ほか)
春の絶景(至仏山から望む尾瀬ヶ原と燧ヶ岳―尾瀬
さくらの里から望む妙義山―群馬県 ほか)
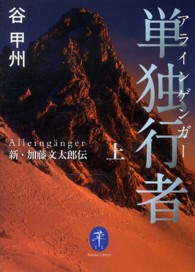
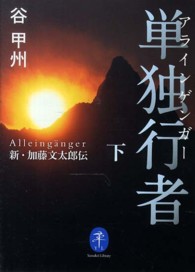
「単独行者(アラインゲンガー)新・加藤文太郎伝」(上・下)谷甲州
以前から気になっていた作品。
加藤文太郎伝と言えば、新田次郎氏の「孤高の人」。
故にサブタイトルが「新・加藤文太郎伝」と「新」と付いている。
いったい、どう違うのか?
一番大きな違いは、山岳シーン中心に書かれていること。
職場の人間関係、家族との関係は最小限に抑えられている。
人生最大の節目である結婚さえ、軽く流している。
しかし、山岳シーンになると、細かく非常にリアル。
それもそのはず、著者は山屋として文壇でもトップクラスの経験と実力を持っている。
故に、自然描写、冬山シーン、ルートの描き方も見事。
当時のデータも交えて描写される。
P365
たとえば陸軍の歩兵は通常、一日につき六合の精米が支給されることになっている。重量にして約0.9キロだから、加藤の行動食と重量の点ではそれほど差がないことになる。とはいえ米よりも多少軽量化されていて、緊急時には調理不要なのだから甘納豆の方が有利ではある。(一合の米=お茶碗3杯~4杯である。私なら六合の米で1週間過ごせる・・・昔の人は大食いなのか?おかずを食べないから、1日でこれだけ、食べることが可能なのか?昔の人は燃費が悪いのか?)
前半の山場は昭和5年の立山山行。
他のパーティと目標が重なり、一緒に行動しようとする。
しかし、徹底して疎外される。
この描写もすばらしく、読んでいて我が事のように感じられ、忸怩たるものがある。
この山行後、迷いを吹っ切り、「単独行者」としての登山を確立する。
後半の山場は、昭和11年1月、最後の山行となった北鎌尾根。
どうして遭難したのか、リアルに再現している。
こうしていたら、ああしていたら、と胸がふさがる思い。
悲劇に向かって怒濤の展開である。
先ほど、「孤高の人」との違いに触れたが、さらに2点追加しておく。
「孤高の人」では宮村健、「アラインゲンガ―」では吉田登美久の描き方が異なる。
「孤高の人」では加藤文太郎の足をひっぱって、その結果、遭難したかのような描き方。
「アラインゲンガ―」では、若き優秀な登山家として描かれている。
少なくとも、登攀技術では、加藤文太郎を凌駕している。
二人の気が合う様子も納得の描写である。
加藤文太郎は、自分にないものを感じたのであろう。
もう一つ、本書の特徴は、当時の案内人と登山者の関係を丁寧に説明している事。
当時では、通例、案内人を雇う。
社会人も大学山岳部も同様。
また、当時の登山者が、エリートであったこと。
これらが、分かりやすく説明されている。
主人公の疎外感と自負心、当時の登山界の雰囲気を感じることが出来た。
【関連図書】

【ネット上の紹介】
昭和十一年一月、厳冬の槍ヶ丘・北鎌尾根に消えた加藤文太郎。冬季登山の草創期、ガイド登山が一般的だった時代に、ただひとり、常人離れした行動力で冬季縦走を成し遂げていった「単独行者」は、なぜ苛烈な雪山に挑みつづけたのか。構想三十五年、加藤文太郎の真実の人間像に挑む本格山岳小説。
JFAの「freefan72号」つづき
もうひとつ、興味深い特集があった。
「クライマーのための岩場で使える英会話集」
海外に登りに出かける方には便利、かと思う。
P25
We're also gonna warm up with this route.
I'll clean your quickdraws.
(俺らもアップするからヌンチャクの回収はするよ)
海外に行くなら、“ヌンチャク”はquickdraw、これくらい知っておく必要がある。
回収する=clean、これは受験英語レベルでは、思いつかない。
私なら、 take them away, removeくらいしか考え付かない。
同じルートを現地の方と一緒にトライする時があれば、自分のヌンチャクだと回収してもらう必要がある。(あるいは、逆に回収してあげる時もあるかも)
でも、突然外人に“clean”とか言われたら、思わずホールドを掃除するかもね。
P26
How many bolts are there?
(ボルトは何本ですか?)
There are 12 bolts on the way, and the anchor is a ring.
(中韓ボルトが12本で、終了点は結び替えだよ)
終了点=anchor、これも覚えておきたい。
たまに、外人にボルト数を聞かれるときがあるかも。
I will belay you.
(ビレイするよ)
I'm flaking out a rope. The knot checked! Do you have me?
(ロープ良し!結び目良し!確保はいいですか?)
確保=have、この単語も(私は)出てこない
I've got you.(ビレイ準備良し!)
Climbing!(では登りまーす)
Climb on!(オーケー)
P28
Let me crip on to the next bolt. I took a self belay.Give me some slack.
(ちょっと上の支点にロープかけます。セルフビレイはとりました。ロープをください)
All right, slack.(オーライ)
Mike, I will try the whole sequence of this crux once more. Then let me down all the way. I will try for the Redpoint after taking a rest.(マイク、核心のムーブが終わるまでつなげてみます。その後いったん降りてRPトライします)
海外には日本人どうしで行くから、現地の人にビレイしてもらったり、逆に、現地の人をビレイすることは、めったにない。
でも、何かの拍子に、ありうるかもしれない。「テンション」=“take”、「ゆるめる」=slack、は基本用語。
外人ペアのトライを見ていると、核心部(crux)で“take”と言っている。
P22を見ると、次のように書かれている。
企画:JFA理事一同 挿絵:柘植求
構成:平野直子(千葉フリークライミング協会)
監修:川口優作・榎戸雄一
さらに、スペイン編、フランス編、ドイツ編、イタリア編、と続けほしい。
でも、難しいでしょうね。
海外に行って最初に覚えるのが、フォールしたときの地元の方が発する罵倒放送禁止用語。
実践で役立つのは、スーパーのレジの方が言う「数字」を聞き取る「耳」。
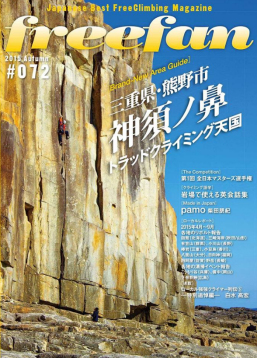
「freefan72」JFA
先週送られてきたfreefan最新号。
今回の目玉は熊野にある『神須ノ鼻』。
とても立派な岩である。
このような岩がまだ残っていたのか、と驚いた。
記事を読むと、道旗さんが見つけて、仲間達と開拓したようだ。
若者に負けず頑張っているようで、感心した。
(でも、怪我には気をつけてね)
【目次】
- JFA協賛会員のご紹介
- [特集]Brand New Area Guide
三重県・熊野市 神須ノ鼻
トラッドクライミング天国
[文と写真:大藪皓平 構成:井上大助
写真:道旗秀人、小澤高範、相川創、小峰直城] - [語学]クライマーのための岩場で使える英会話集
[企画:JFA理事会 構成:平野直子(CFA)
監修:川口優作、榎戸雄一 挿絵:柘植 求] - [連載] MADE IN JAPAN
「pamo」 柴田朋紀
[聞き手・写真:藤枝隆介] - [ローカルレポート] 2015年4月~2015年9月
[構成:宮脇岳雄、北岡和義、井上大助、小川郁代]
- 各地のリボルト報告
函館(北海道)、三崎海岸(秋田/山形)、有笠山(群馬)、小川山(長野)、椿岩(三重)
小豆島(香川)、 八面山(大分)、日向神(福岡)、四阿屋(佐賀)野岳(長崎) - 各地の清掃イベント報告
大倉ボルダー(宮城)、御手洗(奈良)、こうもり谷(兵庫)、備中(岡山)、下帝釈峡(広島) - 岩手花巻 のぞき石公開イベント
- 小川山クライムオン2015報告
- 香落渓遭難対策訓練レポート
- 各地のリボルト報告
- [連載]ローカル強強クライマー列伝5 -特別追悼編-
白水 高宏 [文:本 武史、竹内真史 写真提供:中冨珠己 ほか]
* “安全ブック4”(2015年11月発行)
様々な事故例が掲載されている。
避けられる事故もあれば、不可避な事故もある。
読んでいて、「これって事故?」、ってな例もある。
少なからずある。
普通にムーブを起こしていて、怪我をしたり、故障したり。
それでも支払われている。
日常にない動作をするからであろう。
アプローチで転んで怪我をしている。
クライミングで疲労困憊して、足下がおろそかになるのであろう。
保険が適用されるなら、ありがたいことだ。
クライミング界全体も高齢化の波が押し寄せている。
私も若くない。
気をつけて、慎重に行動したい。
【覚書】
11月12日、郵便局から来年H28年度分JFA会費¥3000円を支払った。
本日11月17日、会員証が届いた。
素早い対応である、感心した。
【目次】
- クライミングを楽しむすべての方へ
- クライミングは危険をともなうスポーツです
- オウンリスク=自己責任の原則
- 事故例(2015年版)
過去のクライミング事故例から学ぶ - ロープクライミング前の簡単なギアチェック
- 8の字結びの基本
- アプローチ困難な岩場へのアクセス方法
- 岩場での終了点の使い方
- ボルダリング
「安全」+「スポット」+「ルール、マナー」 - 全国アクセス問題エリア一覧
2015 - トイレを携帯してみよう
- アクセス問題
自分たちのフィールドを守るために - 国立公園について学ぼう
- JFA入会&更新のお願い
- JFA会員特典協力店一覧
- がんばれのぼる君/編集後記
- JFA団体保険のご案内

「日本の山に生きた人々」安川茂雄
佐々成政、播上人、上条嘉門次、立山のガイドたち、野中至夫妻、以上5章に分かれている。
上条嘉門次の熊の捕まえ方
P126
まずなかまの猟師たちをあなの出口にまたせておいて、かれはわらのみのを腰のまわりにつけて、しりから先にあなの中へ、ゆっくりはいりこんでゆく。まだ体力の弱りきっているクマは、はいってきた人間におそいかかるだけの気力もないので、やがてかれのしりがクマにふれると、クマはうす気味わるいのでからだをよける。そのとき嘉門次は、とっさにクマのうしろにまわりこんで、こんどはクマのしりをかれの背中としりでくすぐる。するとクマはしだいにあなの出口におしだされてくるというのだ。(驚異の熊捕獲法、だ!)
【誤植】
先日紹介した、同著者による「世界の屋根にいどんだ人々」でも書いたが、
間違いが気になる。→「世界の屋根にいどんだ人々」安川茂雄
P49
(前略)あの信雄でさえ・・・
ルビが「のぶお」とある、一般的には「のぶかつ」である。
織田信雄の話をしてるから。(・・・脱力)
P196
十三日午前五時に雷鳥沢から別山にたどりつくと、かれらはまず剣沢小屋を見おろした。
別山のルビが「わけやま」となっている。(・・・再び脱力)

「世界の屋根にいどんだ人々」安川茂雄
著名な登山家達の伝記。
ウィンパー・ヘックマイヤー・テンジン・ブール・コガン夫人・ウェストン。
登山史を俯瞰するにも役立つ読みやすい作品。
ウエストンに関して、略歴を作ってみた。
明治21年 ウエストン、宣教師として日本を訪れる
明治25年 富士山、槍ヶ岳に登頂
明治26年 嘉門次と前穂高に登頂(徳本峠~上高地~明神池~前穂高)
明治29年 「日本アルプスの登山と探検」をイギリスで出版
明治35年 エミリー・フランシスと結婚、2度目の来日
小島久太、岡野金治郎、槍ヶ岳に登る
小島久太、岡野金治郎、ウェストンを訪問(最初は岡野金治郎だけで訪問)
明治38年 ウエストンのアドバイスで日本山岳会発足
明治44年 3回目の来日
昭和15年 死去
【誤植】
間違いを3箇所見つけた
P248 Te Japaress Alps →The Japanese Alps(綴りの誤り・・・校正の方しっかりして!)
P266 その年の秋に、ウェストンは神戸から帰国した。そしてあくる年の1928年には、ロンドンのイギリス山岳会で、日本の山々についての講演をおこない・・・(略)
↓
1928年=昭和3年・・・あきらかにおかしい。明治28年が正しい、はず。
P269 かれが三回めに来日したのは、1911年(明治45年)12月で・・・
↓
1911年=明治44年・・・単純なミス
軽く読んだだけで、3箇所の誤り。
校正の方も、出版社の方も、しっかりしてね!

















