
「あきない世傳金と銀」(12)高田郁
シリーズ最新作、12巻目。
五鈴屋へ女中奉公に上がった時、ヒロインは9歳だった。
そして今、40歳になった。
『出帆篇』とあるとおり、将来への布石となる一歩を踏み出す。
過去、何度も節目となる変革の巻があったが、今回は江戸に出てくる巻に匹敵する内容か、と思う。
P83
「暖簾て、大事やけど厄介で、厄介やけど大事なもんだすな。この頃、とみに思うんだす」
日食
P242
「お日ぃさんをじかに見たら、目ぇを傷めてしまう。店の表に床几を出して、水を張った盥を置いて、水面に目ぃを映して、欠けていく姿を眺めたんだす。短い間なら、そうやって見ても構わへん、と教わりましたのや。予め日食があるんがわかっていたからこその、お祭り騒ぎだした」
(中略)
月の満ち欠けは毎夜のことだが、日が欠け、暫くして戻る、というのを目の当たりにするのは希だ。日食が起きるだろう日時を暦が示し、それが的中するからこそ、ひとは暦を信じ、さらには暦を作らせた幕府に信を置く。
P308
「船乗りは、その日の天候や風向き、満ち潮や引き潮など、充分に気を払い、船出を決める。それでも、出帆した船は、沖に出るまでの間に、予測も出来ぬ波に遭う。その波を作るのは風だそうです」
(中略)
「実はもっとも危ないのは、出帆して沖へ出るまでだと聞きました。五鈴屋と仲間の船は今、沖を目指して進んでいるところだ。如何なる風浪も越えて、大海へ出てください」
【ネット上の紹介】
浅草田原町に「五鈴屋江戸本店」を開いて十年。藍染め浴衣地でその名を江戸中に知られる五鈴屋ではあるが、再び呉服も扱えるようになりたい、というのが主従の願いであった。仲間の協力を得て道筋が見えてきたものの、決して容易くはない。因縁の相手、幕府、そして思いがけない現象。しかし、帆を上げて大海を目指す、という固い決心のもと、幸と奉公人、そして仲間たちは、知恵を絞って様々な困難を乗り越えて行く。源流から始まった商いの流れに乗り、いよいよ出帆の刻を迎えるシリーズ第十二弾!!

「あんの夢 お勝手のあん」⑤柴田よしき
シリーズ5作目。
今回はいつもの品川から江戸・深川へ舞台が移動。
紅屋は立て替えで2ヶ月休業。
年内いっぱい、深川の煮売り屋へ料理修業にでる。
P173
上方の料理は江戸の料理より上だ、という話は聞いたことがある。こちらでは高価なのであまり使わない昆布を上方ではよく使うらしい。そう言えば、あの棒鱈も上方ではよく食べられていると政さんが言っていた。同じ日の本に生まれても、その土地ごとに料理は違い、味の好みも変わって来る。
【ネット上の紹介】
安政の大地震から一年も経たず、颶風の高波に品川の街は呑みこまれてしまった。品川宿の宿屋「紅屋」も、かろうじて建ってはいたが、一階はすべて水に浸かり、二階は強風で屋根も壁も壊れて使い物にならなかった…。紅屋は建て替えのため二ヶ月の休業が決まり、その間、やすは政さんの親戚であるおくまさんから紹介された深川の煮売屋へ、年内いっぱい料理修業にでることに―。大好評「お勝手のあん」シリーズ、待望の第五弾!

菊池仁/編
時代小説アンソロジー。
次の6編が収録されている。
あぶなげな卵 有馬美季子
しづめる花 志川節子
色男 中島要
吉原水鏡 南原幹雄
如月は初午の化かし合い 松井今朝子
怪異投込寺 山田風太郎
P80
娘たちは、廓へきた当座こそ涙にくれているものの、いずれ別の顔をみせるようになる。じたばたしたところで苦界を抜け出せぬのだと、ある時期をしおに、頭でなく身体でもって悟るのだ。
P108
初回に続いての登楼を「裏を返す」といい、三度目の登楼で「馴染み」と呼ばれる仲になる。そうなれば吉原中が二人を公認したようなもので、客もすぐには見限れない。
【ネット上の紹介】
吉原遊郭に売られてきた娘を遊女に仕立て上げる裏稼業の上ゲ屋「しづめる花」、惚れた男が忘れられず、身請け話に迷う花魁・朝霧の矜持「色男」、廓で死人が出る数日前になると現れる墓番の鴉爺い「怪異投込寺」など。吉原の妖しい魅力と人間模様を描いた短編6作品を収録。

「くら姫 出直し神社たね銭貸し」櫻部由美子
時代小説の佳編。
働き者だが運の悪い十六歳の娘おけいは、カラスに似た閑古鳥に導かれて神社にやってくる。神社を守るのは、うしろ戸の婆と呼ばれる老女。その“出直し神社”には、人生を仕切り直したいと願う人々が訪れる。おけいは、老女を手伝うことになる。
P131-132
「お寺の本堂に入ると、正面に釈迦や阿弥陀などのご本尊がお祀りしてあるだろう。あのご本尊さまの裏側には、背中合わせに別の神仏像が置かれていることがある。宗派にもよるだろうが、西国の古刹にみられる風習だと聞いている。とにかくご本尊をお守りする神を、うしろ戸の神と呼ぶのだ」
(中略)
「うしろ戸の神というのは、本尊の仏さまと正反対のお顔を持つものなのだよ。たとえば慈愛の相を浮かべた観音菩薩の裏には、馬頭観音や摩多羅神など、憤怒の相をあらわした荒々しい像が置かれていたりする」
【感想】
以前、同著者の「シンデレラの告白」を読んだが、まさかこっちの方向に来るとは思わなかった。嬉しい驚きだ。
松田志乃ぶさんもそうだけど、日本を舞台にした時代小説を書ける方は、海外を舞台にしても書ける。逆もまた真なり、だ。
【参考リンク】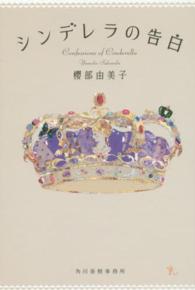
「シンデレラの告白」櫻部由美子
【ネット上の紹介】
下谷にある“出直し神社”には、人生を仕切り直したいと願う人々が訪れる。縁起の良い“たね銭”を授かりに来るのだ。神社を守るのは、うしろ戸の婆と呼ばれる老女。その手伝いをすることになった十六歳の娘おけいは、器量はよくないが気の利く働き者だ。ある日、神社にお妙と名乗る美女が現れる。蔵茶屋の商売繁盛を望む彼女が授かったのは大枚金八両。さらにうしろ戸の婆は、お妙に相談役としておけいを連れていくように言い、おけいには「蔵に閉じ込められたものをすべて解き放ってくるように」と耳打ちして―。読み応え抜群の時代小説。

「マリー・アントワネットの嘘」惣領冬実/塚田有那
誤った「伝説」が定着している。
それを正そう、って企画。
シュテファン・ツヴァイクの「マリー・アントワネット」は1932年出版。
それを元に「ベルサイユのばら」が描かれた。
その後、新たな資料が発掘され、「そこ違うんじゃないの」、ってのが出てきた。
P11
21世紀に入ってから、歴史研究者たちの間でこうしたねじ曲がって伝えられてきたパブリックイメージのどこまでが史実だったかをより緻密に調べ直す動きが出てきた。シモーヌ・ベルティエールによる伝記『マリー・アントワネット 不屈の王妃』(日本未訳)とジャン=クリスチャン・プティフィスによる伝記『ルイ十六世』の2冊がその代表作だ。そして2016年、この2冊をベースに全く新しいマリー・アントワネットとルイ十六世のマンガが生まれた。それが惣領冬実による『マリー・アントワネット』だ。史上初めてヴェルサイユ宮殿がマンガを監修し、資料提供に全面協力した。
P41
当時流行のサロン文化においては子どもさえできなければ不倫ではないとされたことだ。
マリア・テレジアとマリー・アントワネット往復書簡
P73
「この書簡をベースにしたのが、後のツヴァイクの伝記に書かれた、頭の弱いマリー・アントワネット像、ダメなルイ=オーギュストなのではないか・・・・・・・と思い始めているので、あまりこれに固執するのは危険な気がしてきました」
P79
アントワネットのスキャンダラスなイメージを積み上げていった噂の本体は、「チビでデブで頭の弱い国王を、高飛車でプライドの高い王妃は愛せなかった」という言説に由来するものだ。
P82
ルイ十六世は本当に愚鈍で気のきかない男だったのか?アントワネットは、本当にお馬鹿なお姫様だったのか?
P93
マリー・アントワネットが生涯感じていた「居心地の悪さ」は、夫が不能だったからでも、彼女が馬鹿だったからでもなく、当時の絶対王政下の宮殿の異質さ、しきたりによって決まりきった人生への抵抗だったのではないかと惣領はいう。
惣領冬実と萩尾望都の対談
P129
『チェーザレ』の時代と違って『マリー・アントワネット』の時代はレースがふんだんに使われているので、必然的に線がかなりの細かさになります。レースの風合いを出すために、0.03ミリのペンを使っています。チェーザレの時代はゴブラン織りなどカーテンのような布地なので、その質感を出すために0.1ミリくらいの太さで描いていますね。
【感想・コメント】
目から鱗の数々。勉強になった。
ちなみに、7つの嘘とは、次の通り。
第1の嘘「パンがなければ、お菓子を食べればいいじゃない」は誰のセリフ?
第2の嘘 ベッドに隠された謎 ルイ16世は不能だった?
第3の嘘 マリー・アントワネットはフランスに嫁いだ時、フランス語ができなかった?
第4の嘘 マリー・アントワネットはデュ・バリー夫人を無視し続けた?
第5の嘘 フェルセンはマリー・アントワネットの愛人だった?
第6の嘘 ルイ16世は愚鈍な男だった?
第7の嘘 プチ・トリアノン離宮は王妃の淫らな社交場だった?
実際読んで、確認してみて。
新資料によると、シュテファン・ツヴァイクも池田理代子も根本部分を誤って認識し、描かれたエピソードのいくつかも間違い、ってことになる。
【新資料・・・特に驚いた点】
皇帝ヨーゼフ二世が弟(マリー・アントワネットにとっては兄)のトスカーナ大公レオポルトに送った手紙。これが発掘されたことにより、なぜ7年間も子どもができなかったのか?、って謎の答えが得られる。シュテファン・ツヴァイクは、ルイ16世が真性包茎のように記述しているが、そこ違うんじゃないの?、となる。P22-23を読んでみて。(きわどい内容なので、ブログでの記述を控える)
これって本来夫婦間のプライベートな問題だけど、オーストリアとフランス、ハプスブルク家とブルボン家、政治と歴史の大問題だ。
【関連リンク】


「マリー・アントワネット」シュテファン・ツヴァイク
【ネット上の紹介】
夫はチビでデブの気弱な国王、不能の夫に欲求不満でフェルセンと密通、「パンがなければ、お菓子を食べればいいじゃない」発言、離宮は王妃の淫らな社交場だった…etc.その歴史、ぜんぶ嘘でした。ヴェルサイユ宮殿、そしてマリー・アントワネット協会が監修した史上初の漫画企画『マリー・アントワネット』。その作者である惣領冬実が「真実のマリー・アントワネット」に出会うまでの製作秘話のすべてがこの一冊に。
第1章 マリー・アントワネットの七つの嘘(「パンがなければ、お菓子を食べればいいじゃない」は誰のセリフ?
ベッドに隠された謎―ルイ十六世は不能だった? ほか)
第2章 マンガ家と美術館のコラボはどうやって誕生したか(ヴェルサイユ宮殿の誘い
歴史探偵・惣領冬実のプロファイリング ほか)
第3章 「歴史美術の職人」として(百科事典への欲望
「描く」ことで見えてくる真実 ほか)
第4章 対談・萩尾望都×惣領冬実「マンガ、それは異端者のための芸術」(妄想VSプロファイリング!?―史実へのアプローチ
衣装は、時代を反映する芸術 ほか)
第5章 マンガが、社会を変えていく(鼎談「マンガ」は新しい血を必要としている)

「心淋(うらさび)し川」西條奈加
2020年 第164回 直木賞受賞。
古びた長屋を舞台にした連作時代小説。
次の6編が収録されている。
心淋(うらさび)し川
閨仏
はじめましょ
冬虫夏草
明けぬ里
灰の男
P117
捨子の処遇には、お上が口を出す。あつかいが悪ければ、寺や町内の顔役が咎めを受ける。まず夫婦者であることが条件になるのだが、るいには強い後ろ盾があった。
P156
「子どものためと口にする親ほど、存外、子どものことなぞ考えてないのかもしれないな」
【感想】
西條作品にハズレなし。
今まで、けっこう読んできたが、どれも面白かった。
直木賞受賞は当然、と思う。
今回も面白かった。
もし忙しくて1編しか読めない、というなら「閨仏」を読んでみて。
六兵衛は妾を囲っているが、不美人ばかり。
一つ屋根の下に妾を全員集めてるから、確執も生まれる。
りきはその中のひとり。
あるとき、小刀で仏像を彫りだす。
・・・奥が深く、最後に泣かせる技は見事。
【ネット上の紹介】
不美人な妾ばかりを囲う六兵衛。その一人、先行きに不安を覚えていたりきは、六兵衛が持ち込んだ張形に、悪戯心から小刀で仏像を彫りだして…(「閨仏」)。飯屋を営む与吾蔵は、根津権現で小さな女の子の唄を耳にする。それは、かつて手酷く捨てた女が口にしていた珍しい唄だった。もしや己の子ではと声をかけるが―(「はじめましょ」)他、全六編。生きる喜びと哀しみが織りなす、渾身の時代小説。第164回直木賞受賞。


「あんの青春若葉の季(とき) お勝手のあん」(3)柴田よしき
「あんのまごころ お勝手のあん」(4)柴田よしき
換骨奪胎、枠組のみ頂いた「アン」シリーズ3弾と4弾。
江戸時代版「赤毛のアン」だ。
最初幼かったヒロインも、16歳になった。
少ないながら、お給金も貰えるようになった。
(見逃していて読むのが遅くなった)
P72
「それ、なんなんです?」
「これはむじなの皮です」
「ひぇっ、むじな!」
「穴熊とも言いますが、山の民はこれで着るものを作るんです。肉は食べてしまうそうです。それで余った皮を分けてくれるんです。猫の蚤取りに」
(「蚤とり侍」という作品もある→「蚤とり侍」小松重男 )
よく眠れない、と言う人への処方
P76
「まずは猫と寝る。そして十回ずつ噛んで食べる。(後略)」
P207
「薬種のお商売も、昔のように楽ではないそうよ。黒船のあといろいろな国の人たちがやって来て、この国で商売させろと迫っているんでしょ。お上はそうした人たちと条約を結ぶ気があるのかどうか、清さんは気をもんでるわ。しかもね、これってまだ瓦版にも出ていないことなんだけど」
お小夜さまが、いたずらでも相談するように顔をやすに近づけた。
「公方様がご正室をお迎えになるんですって」(2巻登場の際、気づかなかった・・・後の天璋院・篤姫)
②P170
「心も病にかかるんですね」
「そりゃかかるさ。心だってからだの一部なんだからね。(後略)」
【関連図書】

「お勝手のあん」①②柴田よしき
【ネット上の紹介】
昨年の大地震が残した爪痕も、ようやく幾らか薄れてきたように思えた頃。品川宿の宿屋「紅屋」では、おやすが見習いから、台所付きの女中として正式に雇われることとなり、わずかばかりだが給金ももらえることになった。「百足屋」のお嬢さま・お小夜が嫁ぎ、おあつから別れの手紙を受け取るなど、寂しくもなるおやすだが、心配していた勘平の消息を聞き、「むら咲」の女料理人・おみねから出された謎も考えながら、充実した日々を送っていく―。時代小説版「赤毛のアン」、大好評シリーズ第三弾。
物語が華やかになった気がする。(結やお梅さんだけでは、少しもの足りない)
幸と結が久しぶりに出会う――結のセリフ
P81
「そないな目ぇで、見んといておくれやす。同情やったら、要りませんよって」
(中略)
「私を憐れに思うてはるのなら、いずれ悔いることになりますやろ」
(この関西弁の心地よさが、高田郁作品の大きな魅力)
P122
「勧進相撲て、女子には見せまへんのやろ。それに勧進どころか、私はお相撲をまともに見たことがおまへんのや。(後略)」
幸が音羽屋に言う
P216
「商いには浮き沈みがつきもの。音羽屋さんこそ、本両替商の株をお売りになられるのなら、ご相談くださいませ。日本橋音羽屋と合わせて、買い上げを検討させて頂きますので」(冗談とは言え、幸の気概を感じる・・・なんとも豪気である)
【ネット上の紹介】
湯上りの身拭いにすぎなかった「湯帷子」を、夕涼みや寛ぎ着としての「浴衣」に──そんな思いから売り出した五鈴屋の藍染め浴衣地は、江戸中の支持を集めた。店主の幸は「一時の流行りで終らせないためにはどうすべきか」を考え続ける。折しも宝暦十年、辰の年。かねてよりの予言通り、江戸の街を災禍が襲う。困難を極める状況の中で、「買うての幸い、売っての幸せ」を貫くため、幸のくだす決断とは何か。大海に出るために、風を信じて帆を上げる五鈴屋の主従と仲間たちの奮闘を描く、シリーズ第十一弾!!

「本日も晴天なり」梶よう子
お江戸家族小説、とあるので読んでみた。
大久保鉄砲百人組、礫一家の話。
泰平の世が続いて、鉄砲同心たちは鉄砲を実践で使うことがなくなった。
代わりに、つつじ栽培の内職をして生活している。
P10
「我らだけではない。根来組は提灯、青山百人町の甲賀衆は傘張りだ。御徒組も朝顔栽培で糊口をしのいでいる」
P270
「(前略)今なら御家人株の相場は二百両だ」
P273
信介が向かおうとしている先は寺が建ち並ぶところだ。こうした寺町の門前の通りには、少々いかがわしい店が並んでいる。(聖と俗は、昔からセットのようで、神社仏閣の近くには、その手の店がある)
【ネット上の紹介】
長く泰平の世が続き、代々大久保の地を守る鉄砲同心たちは火薬の材料を転用したつつじ栽培の内職に励み、時季には美しい花々を求めて多くの人が集まる江戸名所となっていた。礫家はつつじ作りの才を持つ丈一郎、頑固者の父・徳右衛門、温和な母・広江、勝気な妻・みどり、生真面目な息子・市松、物忘れが多くなってきた祖母・登代乃の六人暮らし。銃の代わりに大ばさみを握り、火薬の材料を肥料に花を咲かせる。大久保鉄砲百人組、礫一家が繰り広げる笑いと涙の春夏秋冬。温かなお江戸家族小説!

「神様の果物 江戸菓子舗照月堂」篠綾子
シリーズ最終巻、これで完結!
P212
最初の菓子が何かはご存じどすか――と、宝山から目を据えられ、なつめは「橘の実と聞いております」と答えた。
「そうどす。田道間守命さんが海の向こうから天子さまのために持ち帰った不老不死とされる非時香菓(ときじくのかくのこのみ)。これが橘の実で、日の本初の菓子とも言われています。(田道間守命が祀られているのが吉田神社・・・お菓子の神社と言われている)
P237
少彦名命(すくなひこのみこと)は大国主命の国造りを手伝うが、その途中で常世の国へ去ってしまう。その常世の国に生えているのが非時香菓(後略)」
『あとがき』より
なつめ以外の菓子職人を目指す人々も、照月堂の子供たちも含めてまだまだおりますし、いずれその後を書くことができたらと願ってやみません。(「後日談」がある、ってことですね?・・・楽しみに待ちましょう)
【ネット上の紹介】
母代わりの了然尼が建立中の寺の庫裏になつめが越して初めて迎えた秋のある日、駿河で医者をしている兄・慶一郎が突然訪ねてきた。なつめが七歳のときに京の生家で起きた火事の夜以来、十余年ぶりの再会である。兄からは、両親が亡くなった火事の真相が明かされる。一方、京の菓子司・果林堂の御曹司で、江戸遊学中の長門からもたらされた寒天なる材料に興味津々のなつめ。世話になった照月堂を辞め、今後どのような菓子を作っていこうかと模索した後に辿り着いた道とは……。菓子職人を志した娘・なつめの物語、ついに完結。

「猫の傀儡」西條奈加
大江戸「猫」捕物帖。
時代小説+猫が主人公。
人間を傀儡として操り、猫が犯罪捜査をする・・・画期的な時代小説だ。
P8
オレはミスジ。二歳のオス猫だ。
人を遣い、人を操り、猫のために働かせる。それが傀儡師だ。
P11
「(前略)江戸の猫の尾は、総じて長いんだとよ。西へ行くほど短くなるそうだぜ。面白いと思わねえか?」
P155
「吹き矢は含み針と同じたぐいで、流派によっては武芸十八般にも入るそうです。十八般は、もとは唐から渡ったもので、今昔や流派によっては中身はさまざまなんでさ。十八を超えることも多いとききやした」
【ネット上の紹介】
猫町に暮らす野良猫のミスジは、憧れていた順松の後を継いで傀儡師となった。さっそく、履物屋の飼い猫・キジから、花盗人の疑いを晴らしてほしいと訴えられる。銅物屋の隠居が丹精していた朝顔の鉢がいくつも割られるという事件が起こり、たまたま通りがかったためにその犯人扱いをされているという。人が絡んでいるとなれば、人を絡めないと始末のしようがない。ミスジは傀儡である狂言作者の阿次郎を連れ出すことにした―。当代屈指の実力派が猫愛もたっぷりに描く、傑作時代“猫”ミステリー!!
「芝居」をテーマにした作品。
江戸の街を地震が襲う。
P74
「七夕の夜の自身と灰――あれは浅間山の噴火によるものだそうですよ」
P83
「・・・・・・実は、お才の縁談が決まりそうでね。おまえさんがけしかけている妙な遊びをいますぐやめさせたいんだよ」
今回、キャラクターの父親視点の章があって面白かった。
より立体的になるので、これからも期待したい。
【ネット上の紹介】
空から謎の灰が降り注ぐなか、七夕の夜に江戸の街を地震が襲った。翌朝、芹は今まで見たこともないどす黒い空を見上げ、不安な気持ちに駆られながらも「少女カゲキ団」の稽古所へと向かう。一方で才の父親が踊りの師匠・花円に「娘の縁談が決まりそうなので、あんたがけしかけている妙な遊びをやめさせろ」と詰め寄ってきた。このままでは飛鳥山での芝居が出来なくなってしまう。花円が取った行動とは!?夢を追いかけ、芝居をとおして羽ばたこうと懸命に生きる少女たちを描く、話題沸騰の時代小説シリーズ第四弾!!
最初、2019年に図書館で借りて読んだとき、とてもよい作品だと感じた。
(現在、全巻絶版となっており、新品での入手不可能)
その後、再読に備えて、古本をあさって全巻揃えておいた。次の7冊。
実意がありゃ、お互いに持ちつ持たれつしてこそ契も深まって、偕老の仲になるんじゃないのかえ。生身の人間が、そんなきれい事を言ってて、生きていけるかい。せっかくのえにしの糸が切れちまうよ。
P49第5巻
女の子は七歳の十一月に吉日を選んで帯解きをするものだが、今年は閏年で、暦より季節が早い。(そういえば、奈良に日本最古の安産祈願・求子祈願= 帯解寺(おびとけでら)がある・・・氷室冴子さんの「ジャパネスク」でも言及され事件の発端となっている)
P66第7巻
P124第7巻
芸者は客次第、金次第、都合次第の三拍子がそろえば転ぶこともあると言いますからな。
日々草(にちにちそう)
P162第7巻
「この花をみると、心のしおれた1日があっても、さあ、明日はしゃんとしましょうって、そう思えるんです」
時代小説の解説には時々、そのようなモラル違反が見られる。
困ったものだ。だから、時代小説の解説は、(大矢博子さんのもの以外は)読まないようにしている。

「あかね紫」篠綾子
平安朝を舞台に、紫式部の娘・藤原賢子が活躍。
同僚は、和泉式部の娘・小武部、中将の君。
彰子は皇太后になっている。
「とりかえばや」を加味したコメディタッチ作品。
(著者は児童書として、既に藤原賢子の活躍を書かれているが、その成人バージョン)
P225
紫の一本ゆゑに武蔵野の 草はみながらあわれとぞ見る
紫草の一本を愛しく思うゆえに、その紫草が生えている武蔵野の草はすべて愛しく見える――つまり、恋しい人本人ばかりでなく、その係累までもすべて大事に思えるという意味の歌だ。
この歌から、「紫のゆかり」「草のゆかり」という言葉が生まれ、『源氏物語』の中でも、光源氏が藤壺の宮へ恋心を抱き、その姪である紫の上に想いをかける一連の物語を「紫のゆかり」と呼ぶ。
【備考】
昨年2020年だけで、著者は8冊上梓されている。
今年に入って、既に2冊。
多作で、いずれもレベルが高い。
1999年デビューだけど、驚きのポテンシャルだ。
【追記】
「とりかえばや」と言えば、氷室冴子さんの「ざ・ちぇんじ!」。
(その後、「ジャパネスク」シリーズを上梓)
当時、平安朝を舞台に現代風にアレンジ、エンターテインメントにした作品はなかった。
つまり、時代を切り開いた先駆者、と言える。
【ネタバレの備考】
あとがきを読むと、中将の君は、源懿子。
と言うことは、後に後白河天皇の妃となる源懿子だ。
【ネット上の紹介】
平安京に遷都して、二百年ばかり。紫式部の娘・藤原賢子が仕える中宮彰子の息子が後一条天皇となった。そんなある日、賢子、小武部、中将の君のライバル三人娘に、憧れの藤原頼宗から妙な依頼が。訳も分からず快諾をしてしまうが、なんと男女入れ替わって振る舞う妹と弟を元に戻してほしいというのだ。しかも、時の権力者・藤原道長からの至上命令だと…。ドタバタ三人娘が活躍する時代小説。

「十日えびす」宇江佐真理/著
宇江佐真理さんお得意の人情小説。
江戸・日本橋が舞台。
夫が亡くなり、八重は先妻の長男夫婦に家を追い出される。
先妻の子だけど、仲のよかったおみちと日本橋に引っ越し、小間物屋を始める。
そこの長屋の一癖ある住人とのやりとり、追い出しておきながら、金の無心に来る義理の息子。とかくこの世は生きにくい。
毎回全ての作品が標準以上の出来栄えで面白い。
それにしても、乳がんで早世されたのが悔やまれる。
【ネット上の紹介】
錺職人の夫が急逝し、家を追い出された後添えの八重。実の親子のように仲のいいおみちと日本橋に引っ越したが、向かいには岡っ引きも手を焼く猛女お熊が住んでいたからたまらない。しかも、この鼻摘み者の息子におみちがほの字の様子。やがて、自分たちを追い出した義理の息子が金の無心に現われる。渡る世間は揉め事ばかり?健気に暮らす母娘の明日はいかに。
























