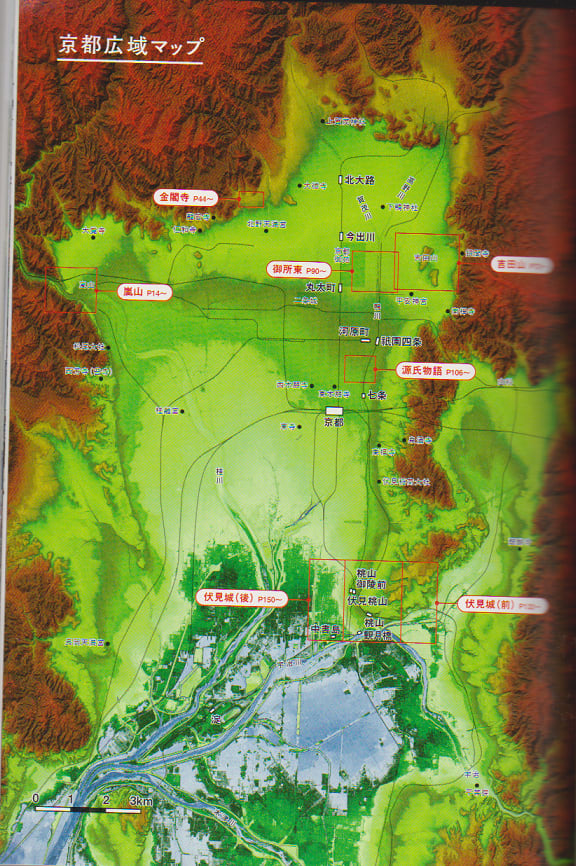「シンデレラ 中野京子特別授業 読書の学校」中野京子
灰が象徴するもの…死、再生、キリスト教での改悛や贖罪
P52
しかし古代の多くの文化圏では、灰は魔術と関連づけられました。これは火に焼かれたものの力が灰に凝縮されるとの考えからきたようです。かまどのそばで寝起きし、常に灰にまみれていたシンデレラが、いつしか異界の魔力を身につけていったとしても不思議ではありません。
P55
――昔話における「王族」は、特になんらかの説明がない限り、完璧さの象徴です。人は誰しも心の中に各々の王国を持っており、不遇から脱して上昇すること、ないし精神的成長を遂げることが、王や女王になる、ないし王子や王女と結婚する、という形で表現されているのです。
P58
「豆」は古代ギリシャで死者の魂を宿すと信じられていました。そのため食べると魂が乗り移るとして(「灰」と非常によく似ています)、当時の哲学者ピタゴラスは食べることを禁じました。(中略)豆と霊魂の結びつきは人びとの無意識に食い込み、「ジャックと豆の木」で主人公が豆の木を登ると異界へ行けたのはそのためです。シンデレラの豆の拾い出し作業にも、同じシンボル性が考えられましょう。
P67
いったいどうしてシンデレラの足はそんなに小さいのでしょう。そこで思い出されるのは、シンデレラ類話の最古版が中国だったということ。シンデレラ纏足説が有力視される由縁です。

アレクザンダー・ツィック「豆を選り分ける鳥たち」