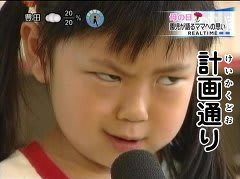こんばんは
5日間、留守にして伊勢神宮に行ってきました (正式には「神宮」)
(正式には「神宮」)
日本の神様の最高峰で、研鑽を積むというのが神職に課せられた責務
なので何度も行っているのはぐうじだけじゃなく、全国の皆様のお近くの神職さんも同じです

早朝の伊勢神宮

日中の模様は後日UPしますが、とんでもない観光の人・人・人です
インバウンド以外で、なんでこんなに人が来るのかというぐらい

日中は、この街道が人で埋め尽くされます

やっぱり朝がいいです
あ・・・
街道に飲み屋さんはないので夜は真っ暗になります

それでも「赤福」だけは早朝から営業し、早朝から行列です

バイクの駐車場は無料
朝から来てますねぇ

ここが宇治橋
伊勢神宮は20年に一度「遷宮」があり、すべての建物や調度品が新しく作り替えられますが、ここ、宇治橋が一番最初に竣工します

早朝の伊勢は寒く、なんと宇治橋に滑り止めの砂が撒かれていました
何度も伊勢に来て2月に来たこともありますが、初めての体験でした

宇治橋の正面では・・・・

桜が咲き始めていました

滞在期間中に三重県では田植えも行われており、8月に収穫だとか
まったく、日本列島は広いです

ここが五十鈴川
右に視線を移動すると・・・

国旗で最大の大きさという日の丸がはためきます
旗の大きさは縦9m×横13.6m(畳75畳分)掲揚塔の高さは47mです。旗布の重さが49㎏もあります
そしてこの場所は平安時代「西行法師」が・・
「なにごとの おはしますをば しらねども
かたじけなさに なみだこぼるる」
と、いう句を詠んだ場所だということです
当時、お坊さんは伊勢神宮に入れませんでした
それでも、伊勢神宮の神秘の杜の雰囲気に深く感動し、
かつ驚き静寂の中に凛とした目には見えないもの、耳にも聞こえない不可思議な力に深く胸を打たれた。
その時の気持ちを詠んだと言われています

そんな国旗が見える宇治橋
宇治橋あるあるもたくさんある中・・・

20年に1度作り変えられる宇治橋で、矢印のギボシだけは交換されません
1853年(嘉永6年/江戸時代後期)6月の吉日に奉納され、1853年から一度も交換されずに 現代まで伝わってます
そして擬宝珠(ぎぼし)の中には、橋の安全を祈って饗土橋姫(あえどはしひめ)神社の萬度麻(まんどぬさ)が収められています
この擬宝珠(ぎぼし)に触れて帰ると、また参拝に訪れる事ができると言われています
右側通行で帰る際には、最後から二本目となります。
色が違っていますし、文字が刻まれていますのですぐにわかります。
今はちょっとコロナ禍で考えちゃいますが、普段、このギボシを触ってご利益を頂いている人たちは「伊勢通」です
ご利益、ありますよ~

さてさて、神域に入ります

色んな方々が五十鈴川で手水

鳥居をくぐって末社巡り

境内内にはたくさんの末社さんがあります

御手洗場の近くにあり、御垣と御門のみで社殿はなく、石畳に祀られています
五十鈴川の守り神として古くから大切に祀られています

ここっすね

そして正宮
ほんの少しのお伊勢さんのお話なのでした
皆様にはステキな夜をお過ごし下さいませ