月曜の終電で広島から帰ってきて,火曜(昨日)以降は「相変わらず」の仕事をしております。今日は,2校舎めぐって仕事をして,帰宅後は【スタ論1C】民事系1・第3問(民訴)の添削・採点をしています。「基本的事項の骨太な理解ある良い答案」「そのレベルにはないが書くべきことはだいたいはずしていない普通の答案」「基本事項の理解を欠くいけない答案」の3つのレベルに分類されます。本当,かなりきれいに割れてしまいます。あるとても基本的な事柄につき,ある特定のLS,ある特定の入学年度の方が同じ間違い方をしている点が非常に気になります(さすがにここではどこのLSとは言えませんが…)。LSでそういうふうに教えてしまっているのだろうか…??
民訴の採点をしていたので,今日は民訴の話を。スタ論と関連する部分はまずいので,それとは無関係の,それでいて絶対に聞いたことのある「二段の推定」。しかし,ちゃんと理解している人は意外に少ないように思う。自問自答しながら確認してください。
まず,前提。文書の「成立の真正」ってなんですか?
文章が挙証者の主張する特定人の「意思に基づいて」作成されたこと
です。それでもって,形式的証拠能力が認められるわけですね。もちろん偽造文書は意思に基づいて作成されたものではない。また,ある者がペンを持っていたとしても,他の誰かが手を持って書いていたら(子どもに習字を教えるときのように),これまた意思に基づいて作成されたとは言えないわけです。ある者が「これを書くぞ」と思って書いた文章であることが必要なわけです。
しかし,これが立証が容易じゃないわけです。「意思に基づく」というのは内心の状態ですから。そこで,228Ⅳの推定規定です。
「本人または代理人の(署名又は)押印があるとき」
に文書の成立の真正が推定されるわけです。さて,ここでの「押印」の意義をしっかり言えますか?
ただ押印があるわけでなく,「意思に基づく押印」という意味です。これは,上の説明と同じ理屈です。
だから…
押印=本人の意思に基づく押印
↓(228Ⅳによる推定)
文書の成立の真正
となります。では,「意思に基づく押印」はどう証明すればいいのでしょう?「意思に基づくか」は内心の状態だから,さっきと同じような問題が浮上します。そこで,判例法理。
本人の印影
↓(事実上の推定)
意思に基づく押印
こういう推定を認めたわけです。印鑑は他人に貸すものではない,軽々しく押すものではない,という経験則です。銀行印なんかはまさにこの体現ですよね。で,
本人の印影
↓(事実上の推定)
本人の意思に基づく押印
↓(228Ⅳによる推定)
文書の成立の真正
となるわけです。
ちなみに,「署名」も「意思に基づくもの」であることが必要です。当たり前ですよね。意思に基づかない署名で文書の成立の真正が推定されるはずがありません。もっとも,これは押印と違ってわかりやすい。押印の場合,誰が押しても同じ印影になるから問題になるんです。署名は,筆跡鑑定をすればわかります。ちなみに,ワープロ打ちは「記名」ですので,「署名」ではないことに注意してください。ワープロ打ちではもう意思に基づくのかどうなのかさっぱりわかりません。「コレ私の印鑑」とは言えても,「コレ私のワープロの字体」とは言えない(あまりにも当たり前ですね)。だから世の中では「署名(自署)」なのです。加えて,押印も要求する。
では,文書の成立の真正を争う側は,例えばどんな争い方があるでしょうか?少し考えてみてください。こういうシュミレーションが実戦力を養います。続きは,明日以降書きます。
<参考文献>
アルマ(275頁以下),藤田・講義(243頁以下)
民訴の採点をしていたので,今日は民訴の話を。スタ論と関連する部分はまずいので,それとは無関係の,それでいて絶対に聞いたことのある「二段の推定」。しかし,ちゃんと理解している人は意外に少ないように思う。自問自答しながら確認してください。
まず,前提。文書の「成立の真正」ってなんですか?
文章が挙証者の主張する特定人の「意思に基づいて」作成されたこと
です。それでもって,形式的証拠能力が認められるわけですね。もちろん偽造文書は意思に基づいて作成されたものではない。また,ある者がペンを持っていたとしても,他の誰かが手を持って書いていたら(子どもに習字を教えるときのように),これまた意思に基づいて作成されたとは言えないわけです。ある者が「これを書くぞ」と思って書いた文章であることが必要なわけです。
しかし,これが立証が容易じゃないわけです。「意思に基づく」というのは内心の状態ですから。そこで,228Ⅳの推定規定です。
「本人または代理人の(署名又は)押印があるとき」
に文書の成立の真正が推定されるわけです。さて,ここでの「押印」の意義をしっかり言えますか?
ただ押印があるわけでなく,「意思に基づく押印」という意味です。これは,上の説明と同じ理屈です。
だから…
押印=本人の意思に基づく押印
↓(228Ⅳによる推定)
文書の成立の真正
となります。では,「意思に基づく押印」はどう証明すればいいのでしょう?「意思に基づくか」は内心の状態だから,さっきと同じような問題が浮上します。そこで,判例法理。
本人の印影
↓(事実上の推定)
意思に基づく押印
こういう推定を認めたわけです。印鑑は他人に貸すものではない,軽々しく押すものではない,という経験則です。銀行印なんかはまさにこの体現ですよね。で,
本人の印影
↓(事実上の推定)
本人の意思に基づく押印
↓(228Ⅳによる推定)
文書の成立の真正
となるわけです。
ちなみに,「署名」も「意思に基づくもの」であることが必要です。当たり前ですよね。意思に基づかない署名で文書の成立の真正が推定されるはずがありません。もっとも,これは押印と違ってわかりやすい。押印の場合,誰が押しても同じ印影になるから問題になるんです。署名は,筆跡鑑定をすればわかります。ちなみに,ワープロ打ちは「記名」ですので,「署名」ではないことに注意してください。ワープロ打ちではもう意思に基づくのかどうなのかさっぱりわかりません。「コレ私の印鑑」とは言えても,「コレ私のワープロの字体」とは言えない(あまりにも当たり前ですね)。だから世の中では「署名(自署)」なのです。加えて,押印も要求する。
では,文書の成立の真正を争う側は,例えばどんな争い方があるでしょうか?少し考えてみてください。こういうシュミレーションが実戦力を養います。続きは,明日以降書きます。
<参考文献>
アルマ(275頁以下),藤田・講義(243頁以下)











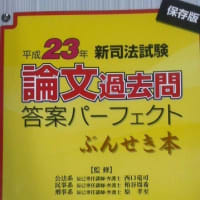
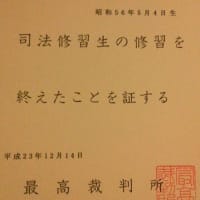
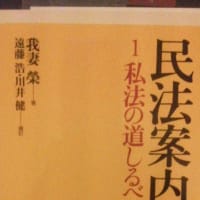






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます