今日は,この内容で少し。ややこしいところです,証拠開示。特に断らずに条文を示した場合は,刑訴法を指します。
まず,従来(注:現在においても公判前整理手続に付さない場合を含む)はどうであったか,という点から。従来は,299条での証拠開示が主でした。この条文,よく読んでください。検察官の手持ち証拠のすべての開示ができたわけではありません。取調請求をしたもののみです。しかし,取調請求がされない証拠にこそ,弁護側に有利な証拠があるものです。そういう場合の証拠開示ですが,検察官が任意に開示してくれればいいのですが,そうでなければ裁判所の訴訟指揮権の発動として,証拠開示命令を出してもらいます。これは,有名な判例があるので,ご存じでしょう。時期としては,証拠調べの段階に入った後です。弁護人が,証拠開示命令を出すことを「お願い」し,それが認められなくても,単に職権発動を促す行為が入れられなかっただけなので,異議を申し立てることはできません(訴訟法上,特段の意味を持たない事実行為が入れられなかっただけであるから)。弁護人としては,公判活動の準備がしにくかったわけです。反対尋問をしようにも,なかなかターゲットを決められない,そうした不都合がありました。
そこで,平成16年改正です。公判前整理手続の創設です(316の2以下。なお,全ての事件が公判前整理手続に付されるわけではない。ただし,裁判員裁判は必ず公判前整理手続に付される点は,裁判員法49参照)。公判前整理手続は,なかなかイメージしにくいでしょうから,流れを追って説明します。公判前整理手続の目的等は,条文を見て確認してください(そんなにびっくりすることは書かれていません)。
当該事件が,決定で公判前整理手続に付されると(316の2Ⅰ),まずは検察官が証明予定事実記載書面をを提出し,それを証明するために必要な証拠調べ請求をします(316の13)。証明予定事実とは,起訴状の公訴事実をより詳細にしたようなものです。「Aは,どんな動機で,いつ,どこで,どんな方法で,Vを殺害した」という事件のストーリーを記載したものです。そんなに数を見ていないのですが,A4判で3~5枚くらいのものでしょうか。それを立証するために必要な証拠書類(KS・PS・実況見分調書等),証拠物,証人尋問の請求をします。
で,まずはここで「検察官請求証拠の開示」があります(316の14)。基本的には,従来の299条と同じですが,第1回公判期日前とかなり早い段階での開示でること,また,弁護人は「謄写」できることなどの相違があります(299は「閲覧」のみ)。
弁護人は,被告人と接見して聞いた話,あるいは,検察官請求証拠として開示された証拠を参考に,「類型証拠の開示」を請求します(316の15)。この316の15は非常に重要ですから,一度は目を通してください。検察官請求証拠の証明力を判断するための一定類型の証拠の開示請求ができるんですね。証拠物や,検証調書,証人尋問を請求した者の供述録取書などを開示請求することができます。
で,弁護人は,この類型証拠の開示を受け,被告人の話や検察官請求証拠を参考に,検察官請求証拠に対する意見を述べます。どの証拠に同意する,あるいは,同意しない,というやつですね(316の16)。
次の段階は,以上のプロセスを経て集めた情報をもとに,「弁護人の」主張予定事実記載書面を提出をします(316の17)。「被告人には殺意がなかった,だから,傷害致死にとどまる」などのように主張を記載した書面を出します。これでもって,争点がはっきりするわけですね。弁護人も何を公判で主張するのか明らかにするのですね。そのうえで,弁護側の証拠調べ請求をします。証拠調べ請求をしたら,検察官と同じくその開示をします(316の18)。
さらに,弁護人は主張を明らかにしたら,その主張に関連する証拠(主張関連証拠)の開示請求ができます(316の20)。例えば,被告人はVととても仲が良かった旨(だから殺意がなかった,と言いたい)を供述しているKSやPSがあるなら,そうした証拠の廃寺請求ができます。
公判前整理手続は,こんな感じでながれていきます。なお,公判前整理手続の証拠氏ら目に関する決定には,即時抗告ができます(316の25Ⅲなど)。これも従前との違いです。
では,周辺事項を短答の肢形式で確認。
・公判前整理手続は,検察官,弁護人,被告人の出席がないと開くことができない。
→×。検察官と弁護人の出席は義務的ですが(316の7),被告人は任意的です(316の9)。事務的な手続ですので,被告人は出なくてもいいのですね。他方で,検察官と弁護人がいないと話が進まないのは言うまでもありません。
・公判前整理手続への被告人の出席は任意的なため,仮に被告人に陳述させる場合であっても,黙秘権の告知は不要である。
→×。書記官が立ち会って調書ができることもあって(316の12。調書ができれば321Ⅱでそれが証拠となることもある),黙秘権の告知は必要です(316の9Ⅲ)。まぁ,被告人にしゃべらせるわけですから,黙秘権の告知をすべき,ということでしょう。
公判前整理手続と証拠開示については,これくらいわかっていれば十分だろう,と思います。
ふぅ。今日はたくさん書きました(ブログだけでなく,今日は起案だったので,その意味でも:笑)。明日,私はまた横浜へ帰ります。土曜日に,LSクラス会(新年会)が品川でありまして。修身幹事に任命されているので,広島にいるけれども,私が幹事(笑)若き法曹の話が聞けたら,また紹介します。と,その前に明日の夜はもう一つお楽しみ。予備校講師が乗る新幹線(最終の「ひかり534号」)を予約し,名古屋,浜松,静岡で懐かしい(といっても,まだ2か月経たない)講師たちと順次合流しながら,新横浜まで帰ります。予備校講師たちは,冬期講習の終盤で疲れてるんだろうなぁ。
まず,従来(注:現在においても公判前整理手続に付さない場合を含む)はどうであったか,という点から。従来は,299条での証拠開示が主でした。この条文,よく読んでください。検察官の手持ち証拠のすべての開示ができたわけではありません。取調請求をしたもののみです。しかし,取調請求がされない証拠にこそ,弁護側に有利な証拠があるものです。そういう場合の証拠開示ですが,検察官が任意に開示してくれればいいのですが,そうでなければ裁判所の訴訟指揮権の発動として,証拠開示命令を出してもらいます。これは,有名な判例があるので,ご存じでしょう。時期としては,証拠調べの段階に入った後です。弁護人が,証拠開示命令を出すことを「お願い」し,それが認められなくても,単に職権発動を促す行為が入れられなかっただけなので,異議を申し立てることはできません(訴訟法上,特段の意味を持たない事実行為が入れられなかっただけであるから)。弁護人としては,公判活動の準備がしにくかったわけです。反対尋問をしようにも,なかなかターゲットを決められない,そうした不都合がありました。
そこで,平成16年改正です。公判前整理手続の創設です(316の2以下。なお,全ての事件が公判前整理手続に付されるわけではない。ただし,裁判員裁判は必ず公判前整理手続に付される点は,裁判員法49参照)。公判前整理手続は,なかなかイメージしにくいでしょうから,流れを追って説明します。公判前整理手続の目的等は,条文を見て確認してください(そんなにびっくりすることは書かれていません)。
当該事件が,決定で公判前整理手続に付されると(316の2Ⅰ),まずは検察官が証明予定事実記載書面をを提出し,それを証明するために必要な証拠調べ請求をします(316の13)。証明予定事実とは,起訴状の公訴事実をより詳細にしたようなものです。「Aは,どんな動機で,いつ,どこで,どんな方法で,Vを殺害した」という事件のストーリーを記載したものです。そんなに数を見ていないのですが,A4判で3~5枚くらいのものでしょうか。それを立証するために必要な証拠書類(KS・PS・実況見分調書等),証拠物,証人尋問の請求をします。
で,まずはここで「検察官請求証拠の開示」があります(316の14)。基本的には,従来の299条と同じですが,第1回公判期日前とかなり早い段階での開示でること,また,弁護人は「謄写」できることなどの相違があります(299は「閲覧」のみ)。
弁護人は,被告人と接見して聞いた話,あるいは,検察官請求証拠として開示された証拠を参考に,「類型証拠の開示」を請求します(316の15)。この316の15は非常に重要ですから,一度は目を通してください。検察官請求証拠の証明力を判断するための一定類型の証拠の開示請求ができるんですね。証拠物や,検証調書,証人尋問を請求した者の供述録取書などを開示請求することができます。
で,弁護人は,この類型証拠の開示を受け,被告人の話や検察官請求証拠を参考に,検察官請求証拠に対する意見を述べます。どの証拠に同意する,あるいは,同意しない,というやつですね(316の16)。
次の段階は,以上のプロセスを経て集めた情報をもとに,「弁護人の」主張予定事実記載書面を提出をします(316の17)。「被告人には殺意がなかった,だから,傷害致死にとどまる」などのように主張を記載した書面を出します。これでもって,争点がはっきりするわけですね。弁護人も何を公判で主張するのか明らかにするのですね。そのうえで,弁護側の証拠調べ請求をします。証拠調べ請求をしたら,検察官と同じくその開示をします(316の18)。
さらに,弁護人は主張を明らかにしたら,その主張に関連する証拠(主張関連証拠)の開示請求ができます(316の20)。例えば,被告人はVととても仲が良かった旨(だから殺意がなかった,と言いたい)を供述しているKSやPSがあるなら,そうした証拠の廃寺請求ができます。
公判前整理手続は,こんな感じでながれていきます。なお,公判前整理手続の証拠氏ら目に関する決定には,即時抗告ができます(316の25Ⅲなど)。これも従前との違いです。
では,周辺事項を短答の肢形式で確認。
・公判前整理手続は,検察官,弁護人,被告人の出席がないと開くことができない。
→×。検察官と弁護人の出席は義務的ですが(316の7),被告人は任意的です(316の9)。事務的な手続ですので,被告人は出なくてもいいのですね。他方で,検察官と弁護人がいないと話が進まないのは言うまでもありません。
・公判前整理手続への被告人の出席は任意的なため,仮に被告人に陳述させる場合であっても,黙秘権の告知は不要である。
→×。書記官が立ち会って調書ができることもあって(316の12。調書ができれば321Ⅱでそれが証拠となることもある),黙秘権の告知は必要です(316の9Ⅲ)。まぁ,被告人にしゃべらせるわけですから,黙秘権の告知をすべき,ということでしょう。
公判前整理手続と証拠開示については,これくらいわかっていれば十分だろう,と思います。
ふぅ。今日はたくさん書きました(ブログだけでなく,今日は起案だったので,その意味でも:笑)。明日,私はまた横浜へ帰ります。土曜日に,LSクラス会(新年会)が品川でありまして。修身幹事に任命されているので,広島にいるけれども,私が幹事(笑)若き法曹の話が聞けたら,また紹介します。と,その前に明日の夜はもう一つお楽しみ。予備校講師が乗る新幹線(最終の「ひかり534号」)を予約し,名古屋,浜松,静岡で懐かしい(といっても,まだ2か月経たない)講師たちと順次合流しながら,新横浜まで帰ります。予備校講師たちは,冬期講習の終盤で疲れてるんだろうなぁ。











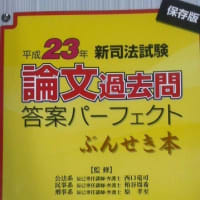
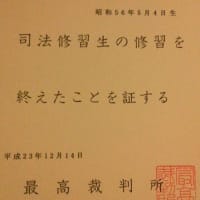
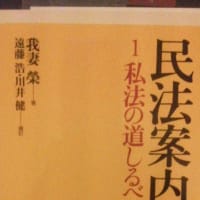






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます