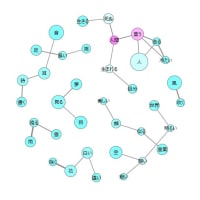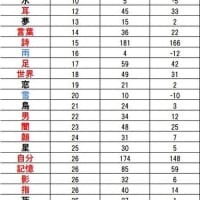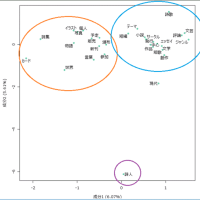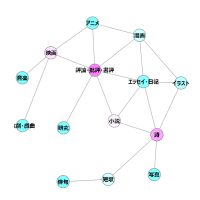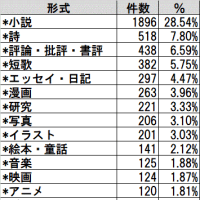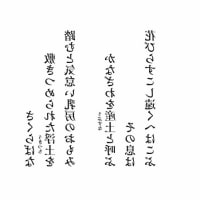あいにきて、なんて到底いえないまどろみの、座席にゆられて書をひらく。
白昼の各駅停車。うっすらと青い窓ガラスを透過して、ひろげた紙片に点々と溢 れるひかりが、しろく眩しい。わたしの隣はあいている。しらない影が時折気配を落とし、停車するたびに音もなく立ち去ってゆく。そのつかの間に息をとめ、耳を澄ませど。いつまでも、いつまでも〝不在〟を抱えるてのひらが、満たされることはない。そっと目を瞑る。このたった数秒の空白にさえ、身を置くことのできないひとを想う。電車に乗れないそのひとと、肩を並べて窓のむこうにうつりゆく空の蒼さをただ、みたかった。その日わたしは、人しれず。さめざめと泣いた。
郊外のショッピングモールでは
様々な娯楽を体験できてしまう
映画を見てごはんを食べてゲームをして
スケートリンクで滑って過ごせる
でもあなたと手を繋ぐ時間は買えない
どのコーナーに行ってもあなたはいない
あなたに会いたい (高橋克知「心の買い物」)
高橋克知著『わたしたちのおとぎ話』におさめられたこの詩は、「心の買い物」と名づけられ、〝あなたに会いたい〟という詩句が、ぽつりと繰りかえされる。「会いたい」のだから、あなたはここにはいない。不在がうたわれている。「いろんなものが買え」る「スーパーマーケット」でも「あなたの気持ちは売られていない」し、「大きな百貨店」でも「あなたの心は買うことはできない」。「どのフロアに行っても見つからない」。そして「私ときたらあなたに電話をかけて本当の気持ちを確かめる/勇気がでない」。
切ない詩と想った。素直で、一途で、それでも伝わらないこの気持ち。くちにして確かめられないもどかしさが、詩のことばでなら表すことができるかのように。しかし、時間を置いて読みかえしてみると、また別のひかりが射し込んでくる。どんなに親しくなろうとも、信じている間柄であろうとも。そもそも、ひとの気持ちを手に入れることなどできない。本当のそれを「確かめる」ことなど、誰にも叶わない。だけど、心のなかでなら? たとえ一瞬でも、語り手は「あなた」に会えただろうか。人混みをかきわけて、日常をすり抜けて、「あなた」と向き合うことができただろうか。だから、「心の買い物」という名の願いが、この詩に添えられているのかもしれない。
「前略。初めてお手紙差し上げます。」から始まる便箋を、綺麗にたたまれた誌面から抜きとってみる。几帳面に綴られた著者・高橋克知の文字が、寸分のずれもないほど律儀に整列して。膝のうえに置かれた手づくりの詩誌。表紙と裏表紙に描かれる〝親梟〟と〝子梟〟の瞳が、どこか謙虚なまなざしを湛えつつ、愛くるしい。
*
奇しくも同じ街、広島から届けられたもう一冊の詩集は、橘しのぶ『道草』。存分に魅力を語られてきた詩集であるから、わたしに言及できることなどないのかもしれないが、著者本人によって綴られたやわらかな筆跡の手紙と、同封されたエッセイ文をふくめ、いま、ひそやかに読むことをゆるされた悦びを、かみしめたいと想う。ここでは、ラストからふたつ前に置かれた詩「立春」を挙げてみる。
ゆめから降りたら
見知らぬ駅のホームにゆきが舞っていた (七八頁)
なんてうつくしい〝うたいだし〟だろう、と想う。ゆめから覚める、でもなく「降り」てみる。しずけさを感じる。舞い降りたそこにひろがる光景は「見知らぬ駅」。現実の日常から溶け出し、無色透明の世界に迷い込んだかのような空間の、その「ホーム」に音もなく「舞って」いる、「ゆき」。ともすれば自分の存在をもみうしないかねない、こころもとなさを胸に抱えつつ、淡く消えてしまう一瞬のしろい「ゆき」に恍惚とし、そっと目をとじる。するとまた、みたこともない幻想世界へと読者はつれさられてゆく。
構内にもゆきがちらつくので
見上げると天井が裂けてそこから
羽根を毟られた音符のように
ゆきのひらがこぼれおちてくるのだった (七八頁)
幽かに、けれども確かにここから、〝奏でられる前の楽音〟の気配が感じられよう。それがどんな音色であるかは、まだわからない。儚げなうつくしさは、いつ失くしてしまうかもわからぬ怖さを同時に孕んでいることがあるゆえに。筆者はそれをしっている。否応なしに視えて しまう。だから、筆をとる手を止めることができない。
無人改札機からは闇が滲み出て
改札のあちらがわの時空の澱みで
セルロイドの鬼の面をかぶった子供が
火影のようにゆらぎながら
トライアングルを鳴らしている (七八頁)
「無人改札機」「闇」「時空の澱み」「セルロイドの鬼の面」「子供」「火影」「トライアングル」――次々に一種不穏な、糸を張られたような緊迫感が、高らかな金属音を伴いながら紡がれてゆくなか、唐突に次の行で「おとうと」という名が、語り手の心のなかに想起される。
あれは、おとうとにちがいないと
咄嗟にポケットの中をまさぐったが
在るはずの乗車券が見当たらなかった
終電を告げるホタルノヒカリが流れ始め
点から線になったゆきは痛いほどふりしきる (七九頁)
悲痛なまでの、声にならない〝届かなさ〟を想う。「乗車券」さえあれば、走って追いかけてゆけるものを。「点から線」になるほどに「ふりしきる」「ゆき」を目の前に、語り手は茫然と佇ちつくすほかないのである。ここにあらわれる「おとうとにちがいない」者が、生者であるのか死者であるのか、実在するのかしないのか、あるいは何処か、異界からの使者であるのか否かも、読者にはわからない。しかし、誰の心のなかにもきっと存在するであろう、〝あいたくてもあえない者〟――それが人であろうとなかろうと、かれらの総称が仮にも、ここに描かれる「おとうと」であるならば、我々読者もまた語り手の視る世界にみずからを重ねあわせ、各々のなかに眠る〝呼びかけ〟を必死にくちにするだろう。顔が隠された「おとうと」を前にして、語り手は問う。
鬼の面をかぶったまま
おとうとが白で塗りつぶされてゆくのを
こちらで見ているだけのわたしは
やさしいねえさんですか? (七九頁)
だが「おとうと」が「白で塗りつぶされてゆく」逼迫さに、語り手も我々もなす術がない。まるで死者への接近が禁忌 であることを、あまりにもきよらかに、うつくしく歌いあげられる様を目の当たりにしたかのように。ゆめのなかでさえ、あいたいひとに近づくことがゆるされないならば、我々はそれをどう受けとめれば良いのだろう。それが詩人・橘しのぶに嘗て「私は私に詩を禁じた」と言わしめたゆえんである、とでも?
フロアには誰かがわすれたのか
水栽培のヒヤシンスが春を匂わせている (七九頁)
声にならないかなしみをよそに、詩は声音を変える。時とともに、季節もまたうつろうのだ。視界は白。「誰かがわすれたのか」真実はあかされないが、「春を匂わせている」「ヒヤシンス」の花言葉のひとつに、〝かなしみを超えた愛〟がある。ここにすべてが込められているように想う。カタルシス、と呼ぶにはあまりにも及ばない。どんなちいさな感情のしずくも取りこぼさない、著者の繊細な筆致。消え入りそうな〝一瞬の絵〟に、我々は跪くしかない。
トライアングルの透明な音色が
鼓膜を劈く (八〇頁)
この詩句を最後に、本作品はむすばれる。目に視えるものが消え、色は「透明」に解かれ、〝異界と人界の関係をあらわす象徴〟ともいわれる三角形のトライアングルの「音色」が、いつまでも心に余韻を残す。そして語り手への〝応答〟ともとれるその音は。その声は。きっと、読者一人ひとりにゆだねられている。
――どこか見えない糸で、紫衣さんと私と、つながっていたのかもしれません。紫衣さんのお幸せをいつもお祈りしています――。手書きの文字。綴られた言葉。本をとじたあとも、まだすこしふるえている頬に、なみだがつたう。ひかり。風。花びら。まばゆいほどの幼年期の記憶。外科医師だったという父の面影、「ハートの王様」。いちど踏み入れたらもう、かえりたくない。どんなに耐えがたいことに見舞われたとしても、ここに身を浸せばいきていられる、そんな詩があつめられた一冊である。傷つくことのいたみを、喪うことのかなしみを、しったものたちへの贈りものである。
肌を刺すつめたさはやわらぎ、ゆきはとけ、季節は春。ひときわうつくしい天上のため息にふれた気がして、ゆっくりと席をたつ。あいにきて、と言えないならば。わたしは何処へでもむかう。あいに、ゆける。
白昼の各駅停車。うっすらと青い窓ガラスを透過して、ひろげた紙片に点々と
郊外のショッピングモールでは
様々な娯楽を体験できてしまう
映画を見てごはんを食べてゲームをして
スケートリンクで滑って過ごせる
でもあなたと手を繋ぐ時間は買えない
どのコーナーに行ってもあなたはいない
あなたに会いたい (高橋克知「心の買い物」)
高橋克知著『わたしたちのおとぎ話』におさめられたこの詩は、「心の買い物」と名づけられ、〝あなたに会いたい〟という詩句が、ぽつりと繰りかえされる。「会いたい」のだから、あなたはここにはいない。不在がうたわれている。「いろんなものが買え」る「スーパーマーケット」でも「あなたの気持ちは売られていない」し、「大きな百貨店」でも「あなたの心は買うことはできない」。「どのフロアに行っても見つからない」。そして「私ときたらあなたに電話をかけて本当の気持ちを確かめる/勇気がでない」。
切ない詩と想った。素直で、一途で、それでも伝わらないこの気持ち。くちにして確かめられないもどかしさが、詩のことばでなら表すことができるかのように。しかし、時間を置いて読みかえしてみると、また別のひかりが射し込んでくる。どんなに親しくなろうとも、信じている間柄であろうとも。そもそも、ひとの気持ちを手に入れることなどできない。本当のそれを「確かめる」ことなど、誰にも叶わない。だけど、心のなかでなら? たとえ一瞬でも、語り手は「あなた」に会えただろうか。人混みをかきわけて、日常をすり抜けて、「あなた」と向き合うことができただろうか。だから、「心の買い物」という名の願いが、この詩に添えられているのかもしれない。
「前略。初めてお手紙差し上げます。」から始まる便箋を、綺麗にたたまれた誌面から抜きとってみる。几帳面に綴られた著者・高橋克知の文字が、寸分のずれもないほど律儀に整列して。膝のうえに置かれた手づくりの詩誌。表紙と裏表紙に描かれる〝親梟〟と〝子梟〟の瞳が、どこか謙虚なまなざしを湛えつつ、愛くるしい。
*
奇しくも同じ街、広島から届けられたもう一冊の詩集は、橘しのぶ『道草』。存分に魅力を語られてきた詩集であるから、わたしに言及できることなどないのかもしれないが、著者本人によって綴られたやわらかな筆跡の手紙と、同封されたエッセイ文をふくめ、いま、ひそやかに読むことをゆるされた悦びを、かみしめたいと想う。ここでは、ラストからふたつ前に置かれた詩「立春」を挙げてみる。
ゆめから降りたら
見知らぬ駅のホームにゆきが舞っていた (七八頁)
なんてうつくしい〝うたいだし〟だろう、と想う。ゆめから覚める、でもなく「降り」てみる。しずけさを感じる。舞い降りたそこにひろがる光景は「見知らぬ駅」。現実の日常から溶け出し、無色透明の世界に迷い込んだかのような空間の、その「ホーム」に音もなく「舞って」いる、「ゆき」。ともすれば自分の存在をもみうしないかねない、こころもとなさを胸に抱えつつ、淡く消えてしまう一瞬のしろい「ゆき」に恍惚とし、そっと目をとじる。するとまた、みたこともない幻想世界へと読者はつれさられてゆく。
構内にもゆきがちらつくので
見上げると天井が裂けてそこから
羽根を毟られた音符のように
ゆきのひらがこぼれおちてくるのだった (七八頁)
幽かに、けれども確かにここから、〝奏でられる前の楽音〟の気配が感じられよう。それがどんな音色であるかは、まだわからない。儚げなうつくしさは、いつ失くしてしまうかもわからぬ怖さを同時に孕んでいることがあるゆえに。筆者はそれをしっている。否応なしに
無人改札機からは闇が滲み出て
改札のあちらがわの時空の澱みで
セルロイドの鬼の面をかぶった子供が
火影のようにゆらぎながら
トライアングルを鳴らしている (七八頁)
「無人改札機」「闇」「時空の澱み」「セルロイドの鬼の面」「子供」「火影」「トライアングル」――次々に一種不穏な、糸を張られたような緊迫感が、高らかな金属音を伴いながら紡がれてゆくなか、唐突に次の行で「おとうと」という名が、語り手の心のなかに想起される。
あれは、おとうとにちがいないと
咄嗟にポケットの中をまさぐったが
在るはずの乗車券が見当たらなかった
終電を告げるホタルノヒカリが流れ始め
点から線になったゆきは痛いほどふりしきる (七九頁)
悲痛なまでの、声にならない〝届かなさ〟を想う。「乗車券」さえあれば、走って追いかけてゆけるものを。「点から線」になるほどに「ふりしきる」「ゆき」を目の前に、語り手は茫然と佇ちつくすほかないのである。ここにあらわれる「おとうとにちがいない」者が、生者であるのか死者であるのか、実在するのかしないのか、あるいは何処か、異界からの使者であるのか否かも、読者にはわからない。しかし、誰の心のなかにもきっと存在するであろう、〝あいたくてもあえない者〟――それが人であろうとなかろうと、かれらの総称が仮にも、ここに描かれる「おとうと」であるならば、我々読者もまた語り手の視る世界にみずからを重ねあわせ、各々のなかに眠る〝呼びかけ〟を必死にくちにするだろう。顔が隠された「おとうと」を前にして、語り手は問う。
鬼の面をかぶったまま
おとうとが白で塗りつぶされてゆくのを
こちらで見ているだけのわたしは
やさしいねえさんですか? (七九頁)
だが「おとうと」が「白で塗りつぶされてゆく」逼迫さに、語り手も我々もなす術がない。まるで死者への接近が
フロアには誰かがわすれたのか
水栽培のヒヤシンスが春を匂わせている (七九頁)
声にならないかなしみをよそに、詩は声音を変える。時とともに、季節もまたうつろうのだ。視界は白。「誰かがわすれたのか」真実はあかされないが、「春を匂わせている」「ヒヤシンス」の花言葉のひとつに、〝かなしみを超えた愛〟がある。ここにすべてが込められているように想う。カタルシス、と呼ぶにはあまりにも及ばない。どんなちいさな感情のしずくも取りこぼさない、著者の繊細な筆致。消え入りそうな〝一瞬の絵〟に、我々は跪くしかない。
トライアングルの透明な音色が
鼓膜を劈く (八〇頁)
この詩句を最後に、本作品はむすばれる。目に視えるものが消え、色は「透明」に解かれ、〝異界と人界の関係をあらわす象徴〟ともいわれる三角形のトライアングルの「音色」が、いつまでも心に余韻を残す。そして語り手への〝応答〟ともとれるその音は。その声は。きっと、読者一人ひとりにゆだねられている。
――どこか見えない糸で、紫衣さんと私と、つながっていたのかもしれません。紫衣さんのお幸せをいつもお祈りしています――。手書きの文字。綴られた言葉。本をとじたあとも、まだすこしふるえている頬に、なみだがつたう。ひかり。風。花びら。まばゆいほどの幼年期の記憶。外科医師だったという父の面影、「ハートの王様」。いちど踏み入れたらもう、かえりたくない。どんなに耐えがたいことに見舞われたとしても、ここに身を浸せばいきていられる、そんな詩があつめられた一冊である。傷つくことのいたみを、喪うことのかなしみを、しったものたちへの贈りものである。
肌を刺すつめたさはやわらぎ、ゆきはとけ、季節は春。ひときわうつくしい天上のため息にふれた気がして、ゆっくりと席をたつ。あいにきて、と言えないならば。わたしは何処へでもむかう。あいに、ゆける。