ツイッター(現X)を見ていたところ、詩人の久谷雉(@kutanikiji)のツイートに目が留まった。引用させていただくと、「SNSに「宣伝」や「告知」しか書き込まない書き手とは、本質的な部分でわかり合えないだろうという確信めいたものがある」(2024/04/07)。加えて、このツイートに紐づけてこう述べる。「でも、おそらくそういう人間のほうが「出世」はする。昔、野村沙知代の言っていた「金持ちケンカせず」の一つの実践なのだろう、このようなSNSとの距離感も」。ということは、久谷雉は、「ツイッターは自分の活動の予定を(家のPCから)投稿・記録するだけ」という批評家の大谷能生とは、本質的な部分でわかり合えないということである。
昨年(2023年)11月、フィルムアート社から『〈ツイッター〉にとって美とはなにか』という刺激的なタイトルの本が出版された。その著者が前述の大谷能生である。吉本隆明の著作『言語にとって美とはなにか』(1965年)から題を拝借したこの本は、吉本に加えて菅谷規矩雄の『詩的リズム』(1975年)、時枝誠記の『国語学言論』(1941年)の三冊を足がかりにして、副題である「SNS以後に「書く」ということ」について論じている(ということは、本題の「〈ツイッター〉にとって美とはなにか」という問いには答えていないということである)。この本の面白いところは、やはりこの三冊のラインナップだろう。自ら音楽を作り、音楽についての批評を行う大谷は決して詩人ではない。その中で、とりわけ菅谷の『詩的リズム』を取り上げたところにこの本の意義がある(もっとも、その読書の成果は大谷の前著『歌というフィクション』(月曜社)により反映されているという)。
「〈ツイッター〉にとって美とはなにか」を本当に問おうと思えば、「美しい/面白いツイートとはなにか(美学的問い)」、あるいは「〈ツイッター〉に対する望ましい態度とはなにか(倫理的問い)」を問う必要がある。久谷の「SNSの距離感」に対する問題提起は、この後者に関わるものである。大谷にしても、スマートフォンを所有せず、活動の予定について投稿・記録するだけというツイッターとの付き合い方を、決して自分が主体的に選んだ態度ではないことを殊更に記す点において、この問いに強かに答えている。
SNS以後(2011.3.11を潮目にツイッターの状況が大きく変動したとは言われるが、当時中学二年生で、ツイッターのアカウントを確かその年の夏休みに作成した私にとっては、そのリアリティは分からない)に詩を書き始めた(若い)詩人にとって、ツイッターとの距離感は抜き差しならない問題である(/あった)。ツイッター(を代表とするSNS)がもたらしたインパクトとして、1.共通感覚の数値(エビデンス)化、2.言語表現の総合格闘技化、3.「発表」概念の問い直しの三つを仮に挙げることができよう。それらは詩の内容、詩の形式、詩の媒体と言い換えることができる。
1.ツイッターが生み出した言語表現のジャンルの一つとして、「ネタツイ」がある(例えば「にんげんっていいな」の替え歌)。もともとは大喜利やお笑いのジャンルに近いものだと思われるが、ネタツイと称されるツイート群がネタツイと称されることを知った時、何でもジャンル化するのだという驚きを覚えた。ネタツイは総じて、共通感覚からの「ズレ」の塩梅が是非を決める。そしてネタツイ(的感性)が普及すると、「共通感覚からのズレ」それ自体が共通感覚を形成し、それを前提とする共通感覚からの「ズレ」が再度要請されるようになる。これらの共通感覚を押さえているかどうかが、現代のセンス、はたまた教養と名指されている状況がある。
たくさんの本当のことを言わなくちゃ はじまりまくってる山月記
2.2月に発表された、現代詩の二つの賞(中原中也賞および西脇順三郎賞)の選評は、表面的には随分と対照的なものであった。中也賞は選考委員が一新され、唯一の既存メンバーである蜂飼耳に、川上未映子、穂村弘、カニエ・ナハ、野崎有以が加わった。歌人の穂村を除く三人はみな中原中也賞の歴代受賞者であるが、いまや川上を詩人と呼ぶ人は稀少だろうし、カニエも詩に軸足を置きながら非常に多彩な活動を展開している。結果として受賞した『渡す手』(思潮社)の著者、佐藤文香は俳人である。山口市の〈ホームページ〉を介して発表された選考経過を見ると、佐藤の対抗馬になった大島静流の第二詩集『蔦の城』(思潮社)については、「現代詩としての既視感があるとの意見も出された」とある。一方の西脇賞は広瀬大志の『毒猫』(ライトバース出版)が受賞。選考委員長を務めた野村喜和夫は自身の〈ツイート〉で、「選評には書きませんでしたが、愚直なまでに「恐怖」の言語化を実践してきた広瀬氏の受賞は、散文化、ナラティブ化、平準化が進む現代詩の世界にあって、「メタファーの逆襲」と言っていいでしょう」と述べている。いかなる制度も伝統の継承と破壊の緊張関係によって成立しているが、現代詩という制度に関してその両面がよく表れた選考結果に(表面的には)思われた。
3.相次ぐ中也賞の受賞もありすっかり名が通った「インカレポエトリ」の実践にせよ、「いいね」の数を含むインプレッションに辟易した若者にとって、独立した小空間としての本に自分の作品が掲載されることが、大きな救いになったに違いない。コロナによって拍車がかかったZINEを中心とするリトルプレスの流行は、隔絶した世界を持ちながら、他者とゆるやかにつながりたいという欲望に適切な言語を与えてくれた。まずもって詩は、(それが文字によって書かれるということは)、遅効性を本懐とする。ツイッターと相性が良くないのは明らかであるが、各々の詩人は自身のポイエーシス(詩作)を活動(プラクシス)として報告することを中心にツイッターを使用している。東浩紀は以前、ハンナ・アーレントにおけるポイエーシスとアクション(プラクシス)の区別について、アクションの「目に見えず、手で触れることもできない」という性質がツイッターの台頭によって変容し、いまや計量可能なものとなっていると指摘していた。ポイエーシスとプラクシスは一体化し、詩人は自ら働いていることを示し続けなければならない。詩について語ることは、詩よりも価値があるのである。
*
田中さとみの個人誌『Hector(ヘクトー)』は、以上のような言語表現を取り巻く状況を色濃く、魅惑的に表しているように思われた。東京の小鳥書房から2022年11月に400部限定で出版された、B6変形サイズ・全100頁の小さな本だが、公式のプロモーション動画まである。私がこの本に出会ったのは昨年の暮れ、本郷は機械書房においてである。シリアルナンバー、239。
参加しているのは中尾太一(詩人)、金川晋吾(写真家)、川口好美(文芸批評家)、田中さとみ(詩人)の四人で、それぞれのテクストが順番に並び、各パートの直前には金川の写真が挿入されている。中尾太一「未刊詩集 海の家まで」は、2006年から2013年に書かれた未発表の「恋歌」が9篇、2022年に書かれた近作が1篇の計10篇。著者曰く、「小詩集の体をとっているが、俯瞰してみてこれが自分の全詩集でもよいような気持ちになっている」。
そうさ、トーチカ、星がたくさん見える東部の森で日々つけていた
唾液や日記
世界が終わった翌日に書かれたそれらの文章は間違った「し」、間違う「けれど」
金川晋吾「2021年6月の日記」は、日記の体をした散文(断章)、あるいは散文(断章)の体をした日記が配置されている。
その男やその他もろもろの人たちが感じているであろう「自分がやりたいわけでもないことをこれからもやっていかなければならないことに対する疲れ」みたいなものを、自分も共有できたような気持ちに一瞬なる。「多くの人たちが感じているのはこれか」と思う。
川口好美「テクストごっこ(遊びの練習)」は、ヴァルター・ベンヤミンの著作(久保哲司訳)の一部を引用し、その続きを川口自身が書き継いでいくという遊び(の練習)。それも、かなり書き足している。生成AIに遊ばせることも可能だろう。この本ではフォントを変えることでベンヤミンと川口の境目が分かるようにされているが、もしフォントが一方通行だったら。
《ニモカカワラズ!》の賛歌で充たされるその一瞬の気配を感じようとして、私もためしにその男を真似て横になり目を閉じてみた。
田中さとみは詩が三篇。様々なレイアウトや記法の挑戦が見られる。
とーととーとーるーるるーるーるー。音が聞こえてくる。地下からInternet Explorerが溢れ出し、ソーダ水に入ったカラフルなゼリーに似た胞子(デザインベイビー)、小さな粒子が空中にリツイートされていく。
*
この時評が詩客のサイトに掲載された際、私は一定の留保とともにその旨を〈ツイート〉することだろう。そして改めて、詩人にとって〈ツイッター〉とはなにか、と問わずにいられなくなるだろう。
昨年(2023年)11月、フィルムアート社から『〈ツイッター〉にとって美とはなにか』という刺激的なタイトルの本が出版された。その著者が前述の大谷能生である。吉本隆明の著作『言語にとって美とはなにか』(1965年)から題を拝借したこの本は、吉本に加えて菅谷規矩雄の『詩的リズム』(1975年)、時枝誠記の『国語学言論』(1941年)の三冊を足がかりにして、副題である「SNS以後に「書く」ということ」について論じている(ということは、本題の「〈ツイッター〉にとって美とはなにか」という問いには答えていないということである)。この本の面白いところは、やはりこの三冊のラインナップだろう。自ら音楽を作り、音楽についての批評を行う大谷は決して詩人ではない。その中で、とりわけ菅谷の『詩的リズム』を取り上げたところにこの本の意義がある(もっとも、その読書の成果は大谷の前著『歌というフィクション』(月曜社)により反映されているという)。
「〈ツイッター〉にとって美とはなにか」を本当に問おうと思えば、「美しい/面白いツイートとはなにか(美学的問い)」、あるいは「〈ツイッター〉に対する望ましい態度とはなにか(倫理的問い)」を問う必要がある。久谷の「SNSの距離感」に対する問題提起は、この後者に関わるものである。大谷にしても、スマートフォンを所有せず、活動の予定について投稿・記録するだけというツイッターとの付き合い方を、決して自分が主体的に選んだ態度ではないことを殊更に記す点において、この問いに強かに答えている。
SNS以後(2011.3.11を潮目にツイッターの状況が大きく変動したとは言われるが、当時中学二年生で、ツイッターのアカウントを確かその年の夏休みに作成した私にとっては、そのリアリティは分からない)に詩を書き始めた(若い)詩人にとって、ツイッターとの距離感は抜き差しならない問題である(/あった)。ツイッター(を代表とするSNS)がもたらしたインパクトとして、1.共通感覚の数値(エビデンス)化、2.言語表現の総合格闘技化、3.「発表」概念の問い直しの三つを仮に挙げることができよう。それらは詩の内容、詩の形式、詩の媒体と言い換えることができる。
1.ツイッターが生み出した言語表現のジャンルの一つとして、「ネタツイ」がある(例えば「にんげんっていいな」の替え歌)。もともとは大喜利やお笑いのジャンルに近いものだと思われるが、ネタツイと称されるツイート群がネタツイと称されることを知った時、何でもジャンル化するのだという驚きを覚えた。ネタツイは総じて、共通感覚からの「ズレ」の塩梅が是非を決める。そしてネタツイ(的感性)が普及すると、「共通感覚からのズレ」それ自体が共通感覚を形成し、それを前提とする共通感覚からの「ズレ」が再度要請されるようになる。これらの共通感覚を押さえているかどうかが、現代のセンス、はたまた教養と名指されている状況がある。
たくさんの本当のことを言わなくちゃ はじまりまくってる山月記
(瀬口真司「KILLING TIME」)
2.2月に発表された、現代詩の二つの賞(中原中也賞および西脇順三郎賞)の選評は、表面的には随分と対照的なものであった。中也賞は選考委員が一新され、唯一の既存メンバーである蜂飼耳に、川上未映子、穂村弘、カニエ・ナハ、野崎有以が加わった。歌人の穂村を除く三人はみな中原中也賞の歴代受賞者であるが、いまや川上を詩人と呼ぶ人は稀少だろうし、カニエも詩に軸足を置きながら非常に多彩な活動を展開している。結果として受賞した『渡す手』(思潮社)の著者、佐藤文香は俳人である。山口市の〈ホームページ〉を介して発表された選考経過を見ると、佐藤の対抗馬になった大島静流の第二詩集『蔦の城』(思潮社)については、「現代詩としての既視感があるとの意見も出された」とある。一方の西脇賞は広瀬大志の『毒猫』(ライトバース出版)が受賞。選考委員長を務めた野村喜和夫は自身の〈ツイート〉で、「選評には書きませんでしたが、愚直なまでに「恐怖」の言語化を実践してきた広瀬氏の受賞は、散文化、ナラティブ化、平準化が進む現代詩の世界にあって、「メタファーの逆襲」と言っていいでしょう」と述べている。いかなる制度も伝統の継承と破壊の緊張関係によって成立しているが、現代詩という制度に関してその両面がよく表れた選考結果に(表面的には)思われた。
3.相次ぐ中也賞の受賞もありすっかり名が通った「インカレポエトリ」の実践にせよ、「いいね」の数を含むインプレッションに辟易した若者にとって、独立した小空間としての本に自分の作品が掲載されることが、大きな救いになったに違いない。コロナによって拍車がかかったZINEを中心とするリトルプレスの流行は、隔絶した世界を持ちながら、他者とゆるやかにつながりたいという欲望に適切な言語を与えてくれた。まずもって詩は、(それが文字によって書かれるということは)、遅効性を本懐とする。ツイッターと相性が良くないのは明らかであるが、各々の詩人は自身のポイエーシス(詩作)を活動(プラクシス)として報告することを中心にツイッターを使用している。東浩紀は以前、ハンナ・アーレントにおけるポイエーシスとアクション(プラクシス)の区別について、アクションの「目に見えず、手で触れることもできない」という性質がツイッターの台頭によって変容し、いまや計量可能なものとなっていると指摘していた。ポイエーシスとプラクシスは一体化し、詩人は自ら働いていることを示し続けなければならない。詩について語ることは、詩よりも価値があるのである。
*
田中さとみの個人誌『Hector(ヘクトー)』は、以上のような言語表現を取り巻く状況を色濃く、魅惑的に表しているように思われた。東京の小鳥書房から2022年11月に400部限定で出版された、B6変形サイズ・全100頁の小さな本だが、公式のプロモーション動画まである。私がこの本に出会ったのは昨年の暮れ、本郷は機械書房においてである。シリアルナンバー、239。
参加しているのは中尾太一(詩人)、金川晋吾(写真家)、川口好美(文芸批評家)、田中さとみ(詩人)の四人で、それぞれのテクストが順番に並び、各パートの直前には金川の写真が挿入されている。中尾太一「未刊詩集 海の家まで」は、2006年から2013年に書かれた未発表の「恋歌」が9篇、2022年に書かれた近作が1篇の計10篇。著者曰く、「小詩集の体をとっているが、俯瞰してみてこれが自分の全詩集でもよいような気持ちになっている」。
そうさ、トーチカ、星がたくさん見える東部の森で日々つけていた
唾液や日記
世界が終わった翌日に書かれたそれらの文章は間違った「し」、間違う「けれど」
(「フォルテ、フォルテ、風の盾」)
金川晋吾「2021年6月の日記」は、日記の体をした散文(断章)、あるいは散文(断章)の体をした日記が配置されている。
その男やその他もろもろの人たちが感じているであろう「自分がやりたいわけでもないことをこれからもやっていかなければならないことに対する疲れ」みたいなものを、自分も共有できたような気持ちに一瞬なる。「多くの人たちが感じているのはこれか」と思う。
川口好美「テクストごっこ(遊びの練習)」は、ヴァルター・ベンヤミンの著作(久保哲司訳)の一部を引用し、その続きを川口自身が書き継いでいくという遊び(の練習)。それも、かなり書き足している。生成AIに遊ばせることも可能だろう。この本ではフォントを変えることでベンヤミンと川口の境目が分かるようにされているが、もしフォントが一方通行だったら。
《ニモカカワラズ!》の賛歌で充たされるその一瞬の気配を感じようとして、私もためしにその男を真似て横になり目を閉じてみた。
(『一九〇〇年頃のベルリン幼年時代』より「冬の朝」)
田中さとみは詩が三篇。様々なレイアウトや記法の挑戦が見られる。
とーととーとーるーるるーるーるー。音が聞こえてくる。地下からInternet Explorerが溢れ出し、ソーダ水に入ったカラフルなゼリーに似た胞子(デザインベイビー)、小さな粒子が空中にリツイートされていく。
(「The fuck glass patorol」)
*
この時評が詩客のサイトに掲載された際、私は一定の留保とともにその旨を〈ツイート〉することだろう。そして改めて、詩人にとって〈ツイッター〉とはなにか、と問わずにいられなくなるだろう。











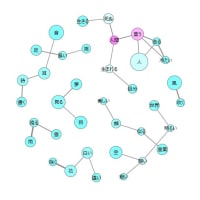


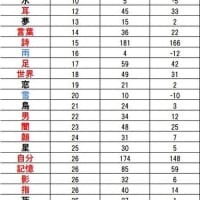
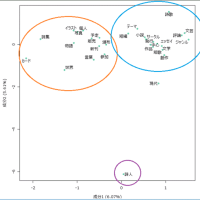
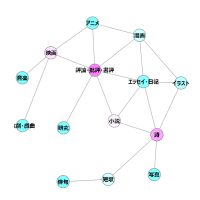
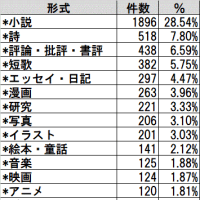
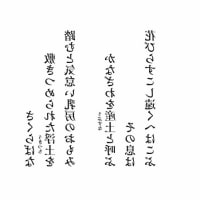
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます