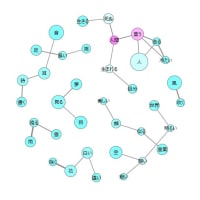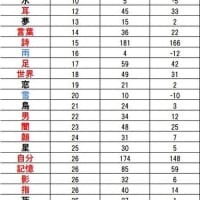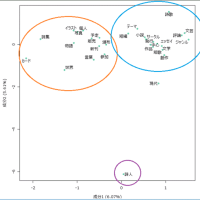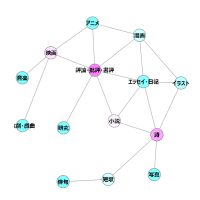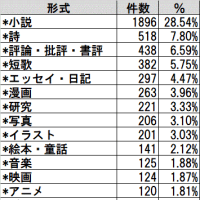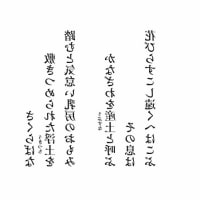森本孝徳『暮しの降霊』(思潮社)に関するメモを取る。あらゆる「問題」=技術を体に繰り入れることで(入れ込むことで)、「問題」にこたえるというやり方か。「創造」の経路を通らずに、結果的に「創造」している。
降霊とは何か。さまざまな局面で降ってわいてくるような幽霊としての「技術」を半透明にして重ね合わせる、というようなことか。そのように仮定してみると、一つのルール、方向性を持ったことばが途中で別の経路に分岐したり、それがまた違う遊びの中に入りこんだりするさまをイメージしやすくなる。
あるいは、詩を書いていると、ことばが一つの方向にしか進まないことが窮屈になってくる。どんな動きを取ろうとしても、このことばの次にこのことば、その連続の一本道から抜けられない。そのことに対して、分岐点をしかける。
このことが自由奔放、開放系、断片系として試みられているのなら、こうはならないわけだ。すべてを「技術」の重なり合いとして意識的に行なう、不意打ちさえも「技術」の一つとする勢いである。実際のところ、意識しないことはコントロールできるものではない、とするなら、まずはかぎりなく意識できる領域を増やすこと。
〇、△、□などに関して、『現代詩手帖』2020年12月号の鼎談で朝吹亮二が、発話者を示す記号としてとらえていて、ぼくもまったく同じことを考えていたので、ちょっとおどろいたが、やはり『詩篇 パパパ・ロビンソン』の直後に読んだためだろう。最初、序数詞にして順番がつくのを嫌い、アスタリスクなどただの区切りにもしたくない、かといってそれほど特殊な記号にもしたくない、ということで選ばれた記号かと思った。これを『パパパ・ロビンソン』のように、それぞれの発話者として読むと、しっくりいくような気になるのだ。あるいは、〇、△、□といえば「ひらけ! ポンキッキ」にそういう歌があった、それぞれの星、とか宇宙人とか。
というのは、空想というか恣意的というか、仮定の話だが、そういう仮定の補助線を呼び入れる作品であることには違いない。
詩集の構成としては、ゴシック体で書かれた見出しに区切られた章のようなもののなかに、「(」ではじまるタイトルがつけられた詩篇が何篇か入っている、ように見える。詩篇の中では、「〇、」「△、」「□、」などの符号が各節の冒頭に見出しのようにつけられている。「(」ではじまるタイトルらしきものは、ページの中心にそれだけ示されるものと、「〇、」とかと同様に、本文の冒頭につけられている場合とがある。ページの中心にそれだけ示されている場合はいくつかの節をまとめてのタイトルとして読め、本文の冒頭の場合は、その節のみのタイトルということなのだろうか。そうなると、ただ符号になっている場合と、節の冒頭にタイトルがついている場合は、同格と見ていいのだろうか。位置としては同格だが、符号の場合は、節の独立性が弱く、見出し語になっている場合は、節の独立性が少し高まる、そういうことなのか。しかしそうなると「(☆」という符号になっているのは、どちらの場合なのか軽く混乱する。「〇、」などの符号の一種と考えられなくはないが、わざわざ見出し語を示すときにも使っている「(」を使っていることからして、独立性を高めたいが、見出し語はつけたくないくらいの位置にあるということなのか。「〇、」などは見出しの位置ではなく、「文中」ともいえる位置に入っていることもある。「、」もなく、かぎかっこの中の文中に入りこんでいるところもある。見出しの位置にある場合でも「〇△□、」という箇所も出てきている。「〇、」などを発話者としてとらえることが再浮上してくるのだが、発話というより、朗読劇とか卒業式の「呼びかけ」のように、各パートで違う人間が声を出しているようにも思え、「〇△□、」は三人一斉に声を出したということなのかとも思った。
さて、冒頭、いきなり、「(ノース、ポール」の見出しではじまる部分は、いまいったような「法則」でいったら、ゴシック体で区切られた「章」の中に入っていない、外側の「序文」のような部分ということになるのか。ただ、そもそもゴシック体の見出しのあとが一つのまとまりの「章」だという保証もないのだが、大方そういう枠で読むのが「ある程度の自然」と思うのにすぎない。そうしたものがはっきりしなくなる、というのはP62の「写真の水質」というゴシックの見出しのあるページで、それまでゴシック体はそれだけで独立したページを占めていたのだが、ここでは前の作品の本文と同じページに印刷されている。これは、やはり前の作品と次の見出しがそれぞれ半透明に重なっている、ということかもしれないし、「ゴシックの見出し」ということがすでにレイヤーのうちの一つであって、別の何かに従属しているのではなく、その膜は膜としてただ重ねあわされる働きしか持っていないということかもしれない(よってその膜をずらせば、全然変なところに「ゴシックの見出し」全体がずれる、ということもある)。後者はわかりにくい仮定だが、「法則」についての「軽い混乱」が「仮定の調整」を狂わせてくる、ということだ。
そして、「読めない」という方向に作りこまれているにもかかわらず、細部といったようなものが保持されていると思えることにおどろかされる。
ところで。森本孝徳は、座談会での発言や評論を読んでみると、ほかの人の詩に対して、恣意的なまでに「創造的」な読み方をしばしばしているように思われる。とすると、森本孝徳が自分の詩の中で作っているしかけは、やはり「読みとき」を待っているのではなく、「創造的」な読み方を誘発するための「きっかけ」として置かれていると見たほうがいいということになる。答えに至りつくための目印ではなく、そこから線を伸ばしていけば思いもよらぬ絵をえがくことができる、えがいていい、そういうポイントだ。それは空想とは違う。あくまでも線を伸ばしていったすえに、であり、しすぎであってもあくまでも「推論」、推論に推論をつみかさねることを誘っているのだ、としたい。
「読みとく」ための経路をたくみに抹消して、「読みはじける」(?)とでもいったような経路へと目印をつけかえる。そこでは「読むという範囲内」であれば、どんな読みも「排除」されないルールがひらけている。そのための経路といっていいのだが、しかし、読者というものは、「読みとく」ための経路(目印)と「読みはじける」ための経路(目印)との間で「指示の読みまちがい」を起こしてつまずくものだ。森本孝徳の詩を読んだときに起こる「ブレ」のような感覚はそのことから来る。そしてそのつまずき、「ブレ」の感覚こそ、ここで読んだ当のものとなり、中毒性を引き起こすことになっている。
柿沼徹『某日の境』(思潮社)。
冒頭の詩「とっぴんぱらり」について何がいえるか。「あんなこと」を言って何かを憎み、ひとりきりになった存在がいる。何を言ったのか書かれていない。ひとりきりになったのは「女」であるが、その女は「私」の中にいる。「女」は庭に立っている、「死んでいる」と書かれる、そして「ま新しい過去」をつぶやきつづけている、そのことが「とっぴんぱらりの/ぷう」ということばで受けられる。そして、「私」も「ひとけない嘘の/ほぼまん中に」立っている。「女」と「私」はイメージとして重なりつつも、同じ存在を指しているともいえず、この二つの存在の仕方がどう関係してくるのか、どういう状況にあるのか、十分な記述を意識的に避けることで、個別的な状況を保ちつつ抽象化された状況にあるというような描き方になっている(いろいろ想像はできる。「あんなこと」を言った存在が、生活世界ではなく「心の底」でひとりきりになった。「あんなこと」を言った存在の性別は不明だが、その心の底でひとりきりになったのは「女」である。「あんなこと」を言うことで「心の底」にひとりきりになった「女」が出てきた。「あんなこと」とは「嘘」なのか?)。「私」の中にいるとされる「女」に対して、「私」が現実の世界で実体を持っているかというと、そう単純な構図ではない。読みすすめると、むしろ、「女」は庭(「私」の中でもある?)に立っていて、「私」は嘘のまん中に立っていて、その意味で実体と観念の関係は逆転しているようにも感じられるのだ。しかし、「女」は死んでもいるわけで、それは、「私」の中にいる観念的な存在の仕方としては「過剰」でもある。ここでは、図式的な理解、整理をはみだすことばのしぐさが絶えず起こっている。そうしたことばの決定的な中心に「とっぴんぱらりの/ぷう」が置かれている。これはものごとを「台なし」にすることばであり、人間世界の中で「ひとりきり」になった存在の、存在の仕方を、軽みと謎の方へ解放的に押しひろげる力を持つ。
降霊とは何か。さまざまな局面で降ってわいてくるような幽霊としての「技術」を半透明にして重ね合わせる、というようなことか。そのように仮定してみると、一つのルール、方向性を持ったことばが途中で別の経路に分岐したり、それがまた違う遊びの中に入りこんだりするさまをイメージしやすくなる。
あるいは、詩を書いていると、ことばが一つの方向にしか進まないことが窮屈になってくる。どんな動きを取ろうとしても、このことばの次にこのことば、その連続の一本道から抜けられない。そのことに対して、分岐点をしかける。
このことが自由奔放、開放系、断片系として試みられているのなら、こうはならないわけだ。すべてを「技術」の重なり合いとして意識的に行なう、不意打ちさえも「技術」の一つとする勢いである。実際のところ、意識しないことはコントロールできるものではない、とするなら、まずはかぎりなく意識できる領域を増やすこと。
〇、△、□などに関して、『現代詩手帖』2020年12月号の鼎談で朝吹亮二が、発話者を示す記号としてとらえていて、ぼくもまったく同じことを考えていたので、ちょっとおどろいたが、やはり『詩篇 パパパ・ロビンソン』の直後に読んだためだろう。最初、序数詞にして順番がつくのを嫌い、アスタリスクなどただの区切りにもしたくない、かといってそれほど特殊な記号にもしたくない、ということで選ばれた記号かと思った。これを『パパパ・ロビンソン』のように、それぞれの発話者として読むと、しっくりいくような気になるのだ。あるいは、〇、△、□といえば「ひらけ! ポンキッキ」にそういう歌があった、それぞれの星、とか宇宙人とか。
というのは、空想というか恣意的というか、仮定の話だが、そういう仮定の補助線を呼び入れる作品であることには違いない。
詩集の構成としては、ゴシック体で書かれた見出しに区切られた章のようなもののなかに、「(」ではじまるタイトルがつけられた詩篇が何篇か入っている、ように見える。詩篇の中では、「〇、」「△、」「□、」などの符号が各節の冒頭に見出しのようにつけられている。「(」ではじまるタイトルらしきものは、ページの中心にそれだけ示されるものと、「〇、」とかと同様に、本文の冒頭につけられている場合とがある。ページの中心にそれだけ示されている場合はいくつかの節をまとめてのタイトルとして読め、本文の冒頭の場合は、その節のみのタイトルということなのだろうか。そうなると、ただ符号になっている場合と、節の冒頭にタイトルがついている場合は、同格と見ていいのだろうか。位置としては同格だが、符号の場合は、節の独立性が弱く、見出し語になっている場合は、節の独立性が少し高まる、そういうことなのか。しかしそうなると「(☆」という符号になっているのは、どちらの場合なのか軽く混乱する。「〇、」などの符号の一種と考えられなくはないが、わざわざ見出し語を示すときにも使っている「(」を使っていることからして、独立性を高めたいが、見出し語はつけたくないくらいの位置にあるということなのか。「〇、」などは見出しの位置ではなく、「文中」ともいえる位置に入っていることもある。「、」もなく、かぎかっこの中の文中に入りこんでいるところもある。見出しの位置にある場合でも「〇△□、」という箇所も出てきている。「〇、」などを発話者としてとらえることが再浮上してくるのだが、発話というより、朗読劇とか卒業式の「呼びかけ」のように、各パートで違う人間が声を出しているようにも思え、「〇△□、」は三人一斉に声を出したということなのかとも思った。
さて、冒頭、いきなり、「(ノース、ポール」の見出しではじまる部分は、いまいったような「法則」でいったら、ゴシック体で区切られた「章」の中に入っていない、外側の「序文」のような部分ということになるのか。ただ、そもそもゴシック体の見出しのあとが一つのまとまりの「章」だという保証もないのだが、大方そういう枠で読むのが「ある程度の自然」と思うのにすぎない。そうしたものがはっきりしなくなる、というのはP62の「写真の水質」というゴシックの見出しのあるページで、それまでゴシック体はそれだけで独立したページを占めていたのだが、ここでは前の作品の本文と同じページに印刷されている。これは、やはり前の作品と次の見出しがそれぞれ半透明に重なっている、ということかもしれないし、「ゴシックの見出し」ということがすでにレイヤーのうちの一つであって、別の何かに従属しているのではなく、その膜は膜としてただ重ねあわされる働きしか持っていないということかもしれない(よってその膜をずらせば、全然変なところに「ゴシックの見出し」全体がずれる、ということもある)。後者はわかりにくい仮定だが、「法則」についての「軽い混乱」が「仮定の調整」を狂わせてくる、ということだ。
そして、「読めない」という方向に作りこまれているにもかかわらず、細部といったようなものが保持されていると思えることにおどろかされる。
ところで。森本孝徳は、座談会での発言や評論を読んでみると、ほかの人の詩に対して、恣意的なまでに「創造的」な読み方をしばしばしているように思われる。とすると、森本孝徳が自分の詩の中で作っているしかけは、やはり「読みとき」を待っているのではなく、「創造的」な読み方を誘発するための「きっかけ」として置かれていると見たほうがいいということになる。答えに至りつくための目印ではなく、そこから線を伸ばしていけば思いもよらぬ絵をえがくことができる、えがいていい、そういうポイントだ。それは空想とは違う。あくまでも線を伸ばしていったすえに、であり、しすぎであってもあくまでも「推論」、推論に推論をつみかさねることを誘っているのだ、としたい。
「読みとく」ための経路をたくみに抹消して、「読みはじける」(?)とでもいったような経路へと目印をつけかえる。そこでは「読むという範囲内」であれば、どんな読みも「排除」されないルールがひらけている。そのための経路といっていいのだが、しかし、読者というものは、「読みとく」ための経路(目印)と「読みはじける」ための経路(目印)との間で「指示の読みまちがい」を起こしてつまずくものだ。森本孝徳の詩を読んだときに起こる「ブレ」のような感覚はそのことから来る。そしてそのつまずき、「ブレ」の感覚こそ、ここで読んだ当のものとなり、中毒性を引き起こすことになっている。
柿沼徹『某日の境』(思潮社)。
冒頭の詩「とっぴんぱらり」について何がいえるか。「あんなこと」を言って何かを憎み、ひとりきりになった存在がいる。何を言ったのか書かれていない。ひとりきりになったのは「女」であるが、その女は「私」の中にいる。「女」は庭に立っている、「死んでいる」と書かれる、そして「ま新しい過去」をつぶやきつづけている、そのことが「とっぴんぱらりの/ぷう」ということばで受けられる。そして、「私」も「ひとけない嘘の/ほぼまん中に」立っている。「女」と「私」はイメージとして重なりつつも、同じ存在を指しているともいえず、この二つの存在の仕方がどう関係してくるのか、どういう状況にあるのか、十分な記述を意識的に避けることで、個別的な状況を保ちつつ抽象化された状況にあるというような描き方になっている(いろいろ想像はできる。「あんなこと」を言った存在が、生活世界ではなく「心の底」でひとりきりになった。「あんなこと」を言った存在の性別は不明だが、その心の底でひとりきりになったのは「女」である。「あんなこと」を言うことで「心の底」にひとりきりになった「女」が出てきた。「あんなこと」とは「嘘」なのか?)。「私」の中にいるとされる「女」に対して、「私」が現実の世界で実体を持っているかというと、そう単純な構図ではない。読みすすめると、むしろ、「女」は庭(「私」の中でもある?)に立っていて、「私」は嘘のまん中に立っていて、その意味で実体と観念の関係は逆転しているようにも感じられるのだ。しかし、「女」は死んでもいるわけで、それは、「私」の中にいる観念的な存在の仕方としては「過剰」でもある。ここでは、図式的な理解、整理をはみだすことばのしぐさが絶えず起こっている。そうしたことばの決定的な中心に「とっぴんぱらりの/ぷう」が置かれている。これはものごとを「台なし」にすることばであり、人間世界の中で「ひとりきり」になった存在の、存在の仕方を、軽みと謎の方へ解放的に押しひろげる力を持つ。