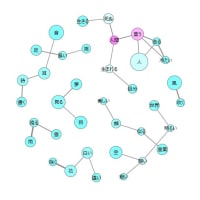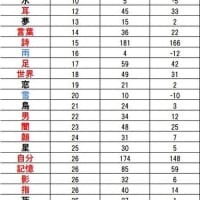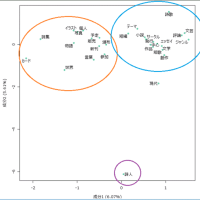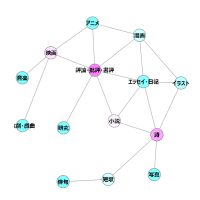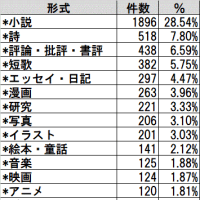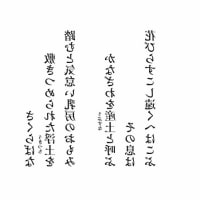きみとぼくの対象関係を書いているようでそうではなく、「きみ」にも「ぼく」にも実態はない。ラブストーリーを書いているわけでもない。最果さんのこの詩集の作品群からみえてくるのは、発話者不明の思念のようなものだ。
きみの中にある女の子像を殺すために、
あの子たちは女の子を名乗っているよ。
光が飛んできて、どれもこれも綺麗だけれど、
いつかこの地上をすべて燃やすために落ちてくる、
その瞬間もとても綺麗なはず。
(「誠実に女の子」)
「女の子」とはこういうものという時代による無意識の画一化に個性が殺されていく、その感覚は、生きていく一挙手一投足に100%迷いなく、時代に絡め取られていく人間には今ひとつピンとくるものではないだろうが、多かれ少なかれ誰もが持っている数%のメタ認知が警告を発するこの時代感覚への猜疑心を、この作品群は図らずも煽り、読者に認識させる。なにかこういうことを書いてやろう、云ってやろうという意図は作者にはおそらくなく、だからこの詩は押し付けがましくなく、渋谷駅から電車に乗るような日常的でカジュアルな感覚のまま、そのへんのOLや女子大生にもがんがん刺さっていく。
恋は冷凍庫の光
あたたかくもない眩しさが、何かを塗りつぶしたけれど、
誰もそのことについて語らない、
抱きしめられると不気味でならない、
愛を語ることが軽薄に見えない人などどこにもいない、
きみよりわたしはわたしが大切と、確かめることで生まれ
る恋があるのだと、子供のころは知っていました。誰もが、
きみをとても好きでいるはずだった。
ただひとり溶け損なったわたしは、恋人。
(「つめたくてあかるい」)
「恋人」とはなんなのか。当たり前だが人は恋人の定義をつきつめてからようやく恋をするというわけではない。なんとなくこういうものだと雰囲気で察して、年齢を重ねてやはりそういうものとして「恋人」を作り、暮らしていく。しかし、時にこの関係はなんなのだろうと、同じ文字を眺め続けてゲシュタルト崩壊を起こすように、これでいいんだっけ?と疑問がよぎる瞬間が、程度の差こそあれ誰にでもある。そのグラデーションにたぶん比例して、この詩は読者の無意識に重なっていく。共感、というよりも、あ、これは自分のなかにもある感覚だと発見できる能動性が、読み手に快感を与える仕組みになっている、そういう気すらする。
『恋人たちはせーので光る』というタイトルは傑出しているが、その光景自体、つまり「恋人たち」が「せーの」で「光っている」光景というのは、なんというか巷に溢れかえっている。現代に生きている人間がそれぞれグラデーションを帯びて持っている、せーので光る恋人たちへの違和へ働きかけるこの詩集は、おそらく作者の思いとは裏腹に、とある読み手にはとてつもないメッセージ性のある詩集として受け取られてしまうのかもしれない。
この詩集を読んでいて、自分が良いなと思った作品は、あまりそういう思念が見えてこない、ありそうなんだけどよく分からない作品たちだった。
壁だけが見える、空洞のなかで、手のひらのように壁
があり、反響を、くりかえす。そのたびに、ぼくの人
生も、きみの人生も、きっと増えていくはずだ、会え
ないことも、あるだろう、失うことも、あるだろう、
そのたび、ぼくは、このたった一つの体を思い出す。
世界の地図をかくように。
(「鉛筆の詩」)
記憶を辿るように朝を迎えて、この先すべては走馬灯。
いつから、死んでしまった者があらたな命に生まれ変わると、
ひとは思い込んだのだろう。
遡る雨のように、一人だけ生まれてくる、
未来の果てから、ぼくらに会いに。
(「人はうまれる」)
どの要素を良いと思ったのだろう、と改めて考えてみると、メッセージも意味も見えてこない景色のなかで出現する「会えないことも、あるだろう、失うことも、あるだろう、」「未来の果てから、ぼくらに会いに。」といった、分かってしまう表現、ある意味での紋切り口調に安心している自分がいることに気がついた。こういう詩の方が良いなと思う自分は、他の作品により惹起させられた、せーので光る恋人たちへの違和を意識にのぼらせることを、ただ回避したいだけなのかもしれない。