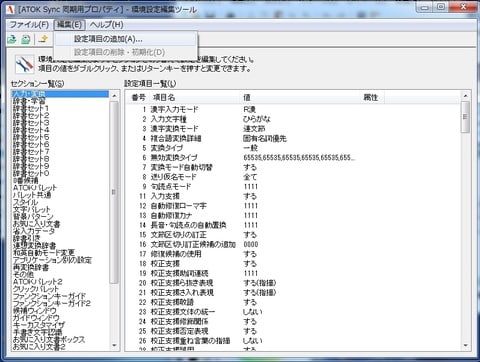Banana Pi Proを気に入って使っていましたが、LS-VLの故障時にサルベージ用に使っていたとき、突然、HDMIがおかしくなり、それ以来、全く起動しなくなってしまいまして。
最初はSD-Memoryのせいではないかと調べたんですが、そうではなくて、オンボードの何らかのチップが故障してしまったようです。
それ以来、ここ1年半ほど触ってこなかったんですが、ちょっと長い夏休みをもらえることになり、再挑戦とばかりに、Raspberry Pi 3 B+を購入してみました。
思っていたよりも性能もいいですし、使い勝手もRaspbianの品質も良いですね。
なによりも、ユーザが多いのでいろいろな情報が簡単に入手できるのが素晴らしい。
またしばらくは手探りで色々と試したいと思っています。
何点か問題もあり、特に標準のVLCはろくにビデオファイルを再生できないことがわかって、GNU Mplayerとかいろいろ試していますが、この数年で更に進んでいることもわかったので、キャッチアップしてみたいと思います。
ちなみに。。以前記事にしていたプリンタの件。なんと、MX893はGoogle Printの仕様変更に耐えられず、非対応になってしまい、常時起動のWindows PC経由で繋がないといけなくなってしまい、単体では使えない技になってしまっていました。そろそろ私の家のプリンタも世代交代が必要なようです。。。。
最初はSD-Memoryのせいではないかと調べたんですが、そうではなくて、オンボードの何らかのチップが故障してしまったようです。
それ以来、ここ1年半ほど触ってこなかったんですが、ちょっと長い夏休みをもらえることになり、再挑戦とばかりに、Raspberry Pi 3 B+を購入してみました。
思っていたよりも性能もいいですし、使い勝手もRaspbianの品質も良いですね。
なによりも、ユーザが多いのでいろいろな情報が簡単に入手できるのが素晴らしい。
またしばらくは手探りで色々と試したいと思っています。
何点か問題もあり、特に標準のVLCはろくにビデオファイルを再生できないことがわかって、GNU Mplayerとかいろいろ試していますが、この数年で更に進んでいることもわかったので、キャッチアップしてみたいと思います。
ちなみに。。以前記事にしていたプリンタの件。なんと、MX893はGoogle Printの仕様変更に耐えられず、非対応になってしまい、常時起動のWindows PC経由で繋がないといけなくなってしまい、単体では使えない技になってしまっていました。そろそろ私の家のプリンタも世代交代が必要なようです。。。。