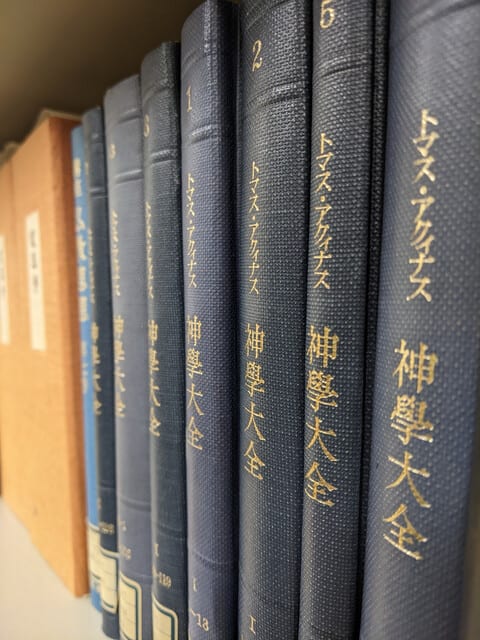
たいした事はないんだ。むかし日本の人に、キリストの精神を教えてくれたのは、欧米の人たちであるが、今では、別段彼等から教えてもらう必要も無い。「神学」としての歴史的地理的な研究は、まだまだ日本は、外国に及ばないようであるが、キリスト精神への理解は、素早いのである。
キリスト教の問題に限らず、このごろの日本人は、だんだん意気込んで来て、外国人の思想を、たいした事はないようだと、ひそひそ囁き交すようになったのは、たいへん進歩である。日本は、いまに世界文化の中心になるかも知れぬ。冗談を言っているのではない。
先日、或る外国の新刊本をひらいてみたら、僕の友人の写真が出ているのを見て、おどろいた。日本の代表的な思想家という説明文が附いていて、その友人は、八つ手の傍で胸を張って堂々と構えていた。僕は、この友人と酒を飲んで「おまえは馬鹿だよ」と言った事があるのを思い出して、恐縮した。馬鹿どころではない。既に、世界的な評論家なのである。あまり身近かにいると、かえって真価がわからぬものである。気を附けなければならぬ。
――太宰治「世界的」
この文章は、確か早稲田大学新聞にのったもので、相手が学生だからと言って、あまりにふざけている。馬鹿な読者はかの評論家が「馬鹿」であることがわからないじゃないか。文才がありすぎると、書くことがすべて余計な冗談となりがちだ。太宰治はコミュニケーションとしての語り口を十分に使いながら、それが十分にわからない読者も巻き込んで人気を得ようとするいやなやつであった。文人と文化人はものすごく違うものである。太宰は文人である。しかしいかにも文化人らしく振る舞うことも辞さない文人である。わがふるさとで大正時代に『木曽要覧』という本を書いた人がいて、なかなか愉快な文体で、木曽の温泉はいいねみたいなことを書いている。市井になかなかの文化人がいたのだ。しかしそのせいで、文人は、文壇にも市井にも居場所をなくしていった。









