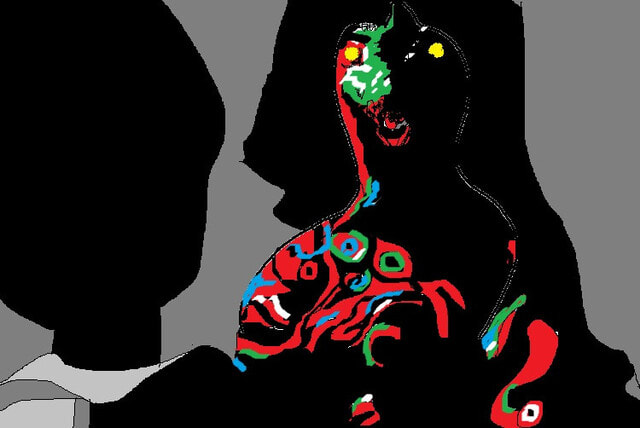鼠色の八重帯、肥前の忠吉二尺三寸、同作一尺八寸の指添へ、小刀ぬき捨て目釘をあらため、城下より一里離れし天神の松原に行きて、大木の楠を後に、蔦かづらに形をかくせし岩に腰を懸け、相待つくれに、はや人顔も見えぬ時、大息つきて権九郎かけ付け、「甚之介か」と言葉をかくる。 「腰抜けに近付きはもたぬ」といふ。 森脇泪を流し、「この節申し分けにはおよばず。後の世の渡り川にて心底を語らん」と申せば、「無用の助太刀頼まじ」 と論ずるうちに、半沢伊兵衛、家中荒物を十六人かたらひ来る。
「男色大鏡」のなかでも人気の「玉章は鱸に通はす」である。横恋慕をしかけられた弟分に「お手紙でも出したら」と言ったら、本気で兄貴に惚れている弟分は恨み、長大な恨みの恋文を執筆したあと、横恋慕しかけた下級武士(伊兵衛)を切り捨てて、そのあと兄貴も殺すつもりであった。そこにかけつけた兄貴に対し「腰抜けは近づくな」「無用の助太刀はいらん」と言い争っていると、あちらから荒くれ者を従えた伊兵衛が近づいてくる。これが上の場面で、そのあとはなんかよくわからんが激しいチャンバラである。考えてみりゃ巻き込まれた荒くれ者たちが気の毒であり、伊兵衛も、――このひとほんとに悪いのか、と思う暇もなく、愛する二人は生き残り、いざ彼らが切腹しようとすると、寺の坊主がお上に話してみなさいと言いい、当然のようにお上も許すのであった。で、こんな素晴らしい話はあるかと下々も言って、「恋は闇、若道は昼にな」ったというのである。
わたくしのへたくそな紹介だと、そりゃないぜと感じるが、西鶴の本文でよむとなんだか素晴らしい話のように思え、美少年の盛りあがることしかない兄貴への愛が忘れていたもののように読者の心をうつのかもしれない。「ロメオとジュリエット」は、最初から破滅の予感しかないが、この話は最初からなんだか陰惨さがまったく感じられない。
思うに、近代文学の世界になってから、殺伐とした三角関係が命を賭けたものであることを許されず、そのくせ、姦通は許さないなどと国家が出張ってくるようになってから、我々は人間関係全般が男色的な「昼」性を失い、闇討ちOKみたいな憤然とした意地汚いものになったような気さえする。実際、封建時代の身分の差よりも、巨大な国家と我々の存在の差のほうが遙かに大きいのであって、しかもそれを我々は庇護される関係として肯定し、自己の生の責任を半ば放棄している。我々は「無用の助太刀はいらん」と国家に対して言えるであろうか。
だから、評論家や文学同士の戦いに於いても、なんか武士の決闘みたいなものは、サルトルとカミュとか、花田=吉本以降、なにか他の目的が付随した、お互いに誰かに庇護されたがっている三角関係のようになりがちである。このあいだ、鮎川信夫と吉本隆明の『全否定の原理と倫理』読んでて、いまのひとたちは、論破とか**すとか言っているから駄目なんで、全否定のほうがいいんじゃねえかな、――と一見思ったわけだが、鮎川の吉本の関係に何か燃えあがるパッションがなくてお互いに評論家だとも思ったのである。全否定とか言っている割には、その否定にパッションが中途半端である。むろん彼らの周りには殲滅だかなんとか言ってた連中がいたわけで、全否定も**すみたいな意味合いはあるわけだが、かれらが大概口先だけだったのはもう既に今風だったのである。彼らと吉本たちもそれほど違っているわけではない。吉本って、戦う前からもう勝ってる体の口調のくせに、全体としてみると内向的な愚痴の漫才みたいになってるのがいいといえば良いような気がするが、それは我々が吉本と鮎川に生きるか死ぬかの関係をそもそも想定しないからである。上の男色だったら簡単に恋する相手だって殺しかねないのである。
言論人でもある東京の大学の教師が、襲撃されたので我々の業界はかなり動揺したが、暗殺の時代という20世紀の反復だけでなく、それ以前から考える必要もある。とわたくしは思った。
夫は、革命のために泣いたのではありません。いいえ、でも、フランスに於ける革命は、家庭に於ける恋と、よく似ているのかも知れません。かなしくて美しいものの為に、フランスのロマンチックな王朝をも、また平和な家庭をも、破壊しなければならないつらさ、その夫のつらさは、よくわかるけれども、しかし、私だって夫に恋をしているのだ、あの、昔の紙治のおさんではないけれども、
女房のふところには
鬼が棲むか
あああ
蛇が棲むか
――太宰治「おさん」