「何をどう変えて、新しい社会を作るのか」という
問いに答えなければならない
山田 宏明 (フリーライター)
【水谷保孝・岸宏一『革共同政治局の敗北 一九七五~二〇一四 あるいは中核派の崩壊』(白順社、二〇一五年)】
2015年7月3日
『流砂』2015年第9号 【書評】から転載
革共同中核派の四五年の歴史とその帰結
かつて「中核派」という言葉が「魔法の響き」だった時代があった。一九六〇年代後半の新左翼運動・全共闘運動を体験した人なら、何を言っているのか、ピンと来る話だと思う。ベトナム反戦を旗印に、数十万の学生、青年労働者、市民が首都東京で、集会やデモを展開、当時の佐藤首相の南ベトナム訪問や訪米に反対して、機動隊と激しくぶつかった。
この「新左翼の時代」の到来を告げたのは一九六七年一〇・八の「佐藤訪ベト阻止闘争」だった。再建された中核派などの三派全学連が羽田空港近くで機動隊と激しくぶつかり、中核派の活動家だった京大生、山崎博昭君が亡くなった。大衆闘争での死者は、一九六〇年安保闘争の樺美智子さん以来だった。ブント、解放派を凌いで中核派が三派全学連の主力として、一九七〇年の安保改定までの三年間の激しい街頭実力闘争の「先頭」にいた。
以来、まもなく半世紀。世の中は変わって、「左翼はキチガイ」と公言する人も珍しくない時代風潮になった。一九六〇年代末の闘争を担った「学生たち」も還暦をとうに過ぎ、人生の終盤を迎えている。
あの「闘争の日々は何だったのか」「我々はなぜ、敗北したのか」を自問自答している人も少なくない。「固い団結」を謳っていた中核派も、何度も分裂を重ね、安部極右政権の登場と、戦争国家への突進にも拘わらず、中核派の姿はよく見えない。一九六〇年代後半の闘いの「中核派の主要闘士」だったふたりが、この四五年間に革共同の中では何があったのか、を詳細にまとめた本書を出版した。「非合法・非公然」の「非非」体制に移行して以降、外部からはほとんど見えなくなっていたこの組織の権力(公安警察)や対立党派だった革マル派との闘い、退潮期だったにも拘わらず激しく闘われた成田闘争や国鉄民営化阻止闘争、そして組織内部での対立、路線闘争、なかんずく同派の創始者で、しかし、一九七五年に革マル派に暗殺された本多書記長の後を継いで、同派の最高指導者となった清水丈夫氏の政治路線と指導方針を巡っての組織内論争が具体的かつ詳細に描かれている。「高度に発達した資本主義国」での「レーニン主義革命」は可能か、という難問に挑んだ同派の「軌跡と現在」がここにある。著者たちの結論は「完全な敗北」であり、その責の大半は最高指導者の清水氏が負うべきものだ、である。日本の革命運動、新左翼の政治運動が、中核派に限らず、なぜ、かくも苦難と苦渋に満ちた道しか、たどれなかったのか、そのことを省みるためには、中核派に属さなかった人にも必読の「重い歴史証言」だろう。
著者ふたりは一九六〇年代後半に学生運動活動家として、当時、 日の出の勢いで組織的伸張を実現していた中核派に所属し、中核派全学連幹部や全国全共闘幹部を経て、二〇〇六年には革共同政治局員だった。しかし、千葉動労を中核とする「労働者党員と学生運動出身者との対立」が深まる中で、党外に「放逐」された。
一九六〇年代後半の中核派やその他の新左翼各セクトの伸張は何と言っても、当時、熾烈さを増すばかりだった「ベトナム戦争」への反戦闘争の高揚だったろう。戦後最大の反政府大衆運動だった一九六〇年安保闘争の敗北で三分解した共産主義者同盟(ブント)の一部メンバーが、日本共産党に代わる革命党の建設を目指して地道な学習会活動を続けていたごく小さな組織「革命的共産主義者同盟(革共同)」に合流して、ブントと並ぶ新左翼の一大潮流が生まれたのは周知のことである。しかし、大衆運動の進め方と組織建設を巡って、革共同全国委員会は一九六三年に革共同全国委員会(中核派)と日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義者同盟(革マル派)に分裂した。
中核派は一九六〇年代後半のベトナム反戦闘争の大衆的高揚の頃から「党のための闘争」と「党としての闘争」の統一をアビールし続けてきた。これは革共同第三次分裂のきっかけにもなった「党建設・組織建設」を最重視する革マル派へのアンチで、「権力闘争を激しく展開する中で、党建設・組織建設を進める」という革命組織観だ。革マル派を除く新左翼各セクトが、大衆運動の高揚を最重視して、組織建設を軽視する傾向があり、これが一九六〇年の安保ブントの崩壊の原因でもあったわけだが、中核派はこの困難な課題に真っ向から挑む姿勢を初期段階から明言して来た。一九七〇年前後の激しい対権力闘争で大量の逮捕者を出し、破防法の適用を受けたにも関わらず、党組織の分裂をきたさなかったのは、この「テーゼ」の力だったろう。しかし、一九七〇年代半ばからは、大衆運動の退潮によって、対権力闘争の高揚が困難となったことをひとつの背景として、革マル派との党派闘争が前面化、一九七五年には最高指導者だった本多書記長(当時)が革マル派に暗殺される。
革マル派との党派闘争もあってか、同派は本多氏の後継者を公表せず。「集団指導体制」を取っていたと見做され、また、野島三郎政治局員が『革共同の内戦論』など「反ファシズム解放闘争」という対革マル派闘争の理論化を行った著作を発表し、機関誌にも政治路線についての論文を掲載していたことから、同氏がリーダーと見做す向きもあったが、本書によると「後継は清水氏」であり、以来、今日まで、最高指導者だという。一九九〇年代初頭には、同派も清水氏を「革共同議長」と表記し、最高指導者であることを公表した。本書では、清水氏の長期間に渡る独裁とさまざまな組織的歪みは、対革マル戦に対処するための、「非公然・非合法」体制によつて党内民主主義が封殺され、党大会も開けず、清水氏の通達によって重要事項がトップダウンで決定していたためだ、としている。スターリン体制の旧ソ連で、世界大恐慌による世界大戦勃発の可能性に怯えて、「兵営共産主義」とのちに呼ばれるスターリン独裁が深化していった事例をほうふつとさせる話だ。
「輝ける安保全学連書記長」の経歴を有し、カリスマ性のあった清水氏が本多氏の後継になつたのは当然だったのかも知れない。また、一九六〇年代半ばに、三派全学連がブントの主導で、「ベトナム反戦」をメインスローガンに一九七〇年に向けての闘争を組織しようとしていた時に、当時、中核派の学対だった清水氏が、「反帝反スタ」という「空疎」な立場、「ベトナム戦争は米ソの代理戦争」という空疎な立場を捨てて、党内を「反米帝」に三日間で塗り替えた、というエピソードを『聞き書き〈ブント〉一代』で、医学連の創始者の安保ブントの石井暎禧氏が紹介していて、清水氏の「政治的センスの鋭さ」を称賛していたが、そういう才能は卓越していたのだろう。しかし、総合的に見て、清水氏が本多氏をしのぐ指導者だ、という声は新左翼関係者の間でも少なく、「レーニン主義の継承か、解体か」「戦争と革命の基本問題」など、マルクス・レーニン主義革命論に一時代を画する論考を書いた本多氏に比べて、清水氏にそういう著作はない。しかし、それでも半世紀に渡り、革共同に君臨し、政敵を寄せ付けなかったのは、この「非非」体制のせいだ、と著者ふたりは言う。(この点は一九九〇年代にやはり革共同から「放逐」された元政治局員の白井朗氏=山村克氏、故人=も以前、指摘していたことはあったが)。
一九九〇年代前半に、二〇年近くに及んだ革マル派との党派闘争は(はっきりとは宣言されないまま)停止される。革マル派と権力への武装闘争もトーンダウンし、革命軍という非公然武装組織もほぼ解体されて、中核派は一九六〇年代以来、久し振りに「公然大衆闘争」(全人民的政治暴露)に全面転換する。清水氏はこの転換を「敵の目の前でわき腹をさらしながら旋回したようなもので、この大転換で党が割れなかったのは世界史上に例のない奇跡」と称賛した。党組織の比類なき強靭さを称えたのだろうが、二〇〇七年の革マル派議長、黒田寛一氏の病死の際にも、機関紙『前進』でわずかな取り上げ方しかしていなかったのは、中核派メンバーだけでなく、この戦争に関心を寄せていた人々にも奇異な感じを抱かせた。「三頭目処刑」などと毎週のように『前進』に書いていた時代に比べれば、仰天するほどの違いだった。もちろん、対革マル戦の開始は本多氏の決断だったのだろうが。しかし、この決断もかつてのような「大衆闘争の革命的高揚」はもたらさず、これが現在の同派の「労働者の力で革命を」路線につながっているのではないか、と思われる。市民や学生、左翼知識人への一種の「絶望」があるのではないか、ということだ。
本書で詳細に述べられている党内での対立、軋轢、清水氏の対応については、当事者でないので、コメントしにくい。ただし、幾つかの新事実は披瀝されている。一九七〇年代に横須賀で起きた中核派アジトでの爆弾破裂事件と三人の中核派メンバーの爆死は、当時、革命軍を指導していた清水氏が深く関与していたこと、革命軍の索敵活動で革マル派の黒田氏と、ナンバーツーだった動労の松崎氏の「所在」をほぼつかみ、「革命的処刑」を実行できる状態にあった時期があったが、清水氏は、戦争の激化を怖れて、作戦にゴーを出さなかったこと--などだ。著者によれば清水氏は「投獄、収監や党派闘争での死」を何よりも怖れており、それが現在も続く「非公然」生活に繋がっているのだ、という。まあこの点は事実というよりは著者たちの「見方」ではあろうが。
長く長く、予想を超えてとてても長く続いた「後退局面」で「過激派(革命的左翼)が直面した困難(アポリア)」との格闘の記録でもあり、読後感は重苦しく、しんどい。しかし、困難の中で「職業革命家」の生き方を貫こうとした著者ふたりの「誠実さ」は疑いない。
なぜ、先進国革命はかくも「大きな困難」に直面
し続けるのか
「日本革命に不可欠の道」として未だにレーニン
主義を続けていることに根本問題がある
それでは、中核派を離れて、「先進国(帝国主義本国)の革命運動はなぜ、かくも「大きな困難」に直面し続けるのか」について、少し私見を述べてみたい。
新左翼が領導していた大衆運動が高揚し続けていた一九六〇年代には、「現代における先進国(帝国主義本国と言ってもいい)革命とは何か」が問題だった。中核派だけでなく、新左翼総体が直面していたアポリアだった。
しかし、今では、レーニン主義によるプロレタリア革命などあり得るのか、という問題が重くのしかかっている。通信産業、IT産業、サービス業などの拡大は、機械制大工業の労働者の蜂起によるプロレタリア独裁というレーニン主義の構図をとても古めかしいものにしてしまった。
イタリアのネグリとフランスのガタリは、プロレタリアに代わる革命主体として、こういう知識労働者やフリーターなどを取り込んだ「マルチチュード」を提起している。米国のウォールストリート占拠のような、「マルチチュードの総叛乱」による権力機構の麻痺を通じて、新しい「権力奪取の主体」が登場して来るというのだ。
レーニン主義を死守して来た中核派は、一九六〇年代は学生の総叛乱による日帝打倒を夢見た。しかし、ブントや革命的労働者協会[革労協](解放派)なども含め、この学生叛乱路線は、機動隊の壁を破れなかった。武装闘争で、権力の暴力装置を破壊しようという試みも、武装闘争を組織する過程での「重圧」を撥ね退けられず、権力奪取に手もかけられないまま、連合赤軍事件などで「爆砕」してしまった。
中核派の場合は、路線の行き詰まりは、内訌し、武装闘争を否定する革マル派との果てしない「内ゲバ」に結実し、大衆的な支持基盤をほとんど喪失してしまった。成田闘争や国鉄民営化阻止闘争という「シングルイシュー」に党組織の力を集中して、いわば「一点突破」的に局面を切り開こうという試みも行われたが、「一〇・八」のような波及力は生まれなかった。本書で描かれているのは主要には、こうした「冬の日々」の党活動、政治路線を巡る政治局の苦悩と路線対立、分派の発生の中での幹部党員の苦闘と挫折である。路線選択の間違いがこういう「未来」に逢着したとはちょっと思えない。
共産主義者同盟と同様に、日本共産党という革命組織への疑問から革命的共産主義者同盟という組織が生まれたわけだが、本多書記長のような優れたオルガナイザーは、黒田理論という「特異な革命理論」に頼る必要があったのか、という疑問は今の時点では消えない。一九五〇年代に形成された理論体系なので時代的制約があるのは当然だが、「認識論は素朴反映論」「マルクス主義の根底は疎外論」「唯物論とは物質の自己運動論」というとても古めかしい理論に依拠しないと、日本共産党の理論体系に対抗できなかったのか、という疑問は消えない。この黒田理論の独得の観念体系が、権力との衝突を重ねていた中核派にとって重荷になり、党派闘争で「革マル的偏向」を振り切ろう、という流れになったのではないのだろうか。
「レーニン主義の継承か解体か」「戦争と革命の基本問題」という優れた論文を書き上げる能力のあった本多氏は、黒田理論に依存しなくても革共同を作り出し、一九七〇年闘争を領導出来たのではないか。そうすれば、革マル派との党派闘争という泥沼に足を救われることはなかったのではないか。
死んだ子の歳を数えるような話ではあるが。安保ブント創設に関与した老理論家は「ブントの崩壊の仕方がまずかった」と革共同誕生の背景を、安保ブントの無様で異様な「潰れ方」に起因させている。一九六〇年安保闘争はブントが担ったのであり、革共同など何の関係もなかった、という安保ブント関係者の見解からすれば、その通りであり、「革共同とは何者なのだ」というところだったろう。
革共同とは違う一九七〇年闘争実現を目指して、安保ブントの活動家だった人たちや三派全学連の関係者は、第二次ブント(統一ブント)を一九六〇年代半ばに結成して戦うが、こちらも一九七〇年決戦で敗北して、再び七花八裂となってしまう。
ただ、特に清水体制に移行してからの革共同(中核派)は、路線論争などを巡って登場した「反対派」をことごとく「スパイ」「反革命」「階級敵への移行者」と決めつけ、「革命軍」を振り向けて、物理的・肉体的に打撃を与える党内闘争スタイルを取っているのはどうしてなのか。反対派を党外に「放逐」した結果として、現在に至る清水議長独裁体勢が存続しているわけだが、その結果として、この本の著者たちのように、「非公然・非合法」体制時代の「内幕」を公表して、どちらに非があったのか、を問う人たちが登場するのは必然であったろう。
ただし、著者ふたりも「自分たちは被害者で有責ではない」と思っているわけではないようだ。ふたりは一時期まで清水議長体制を支えた同派の政治局員で、成田空港反対闘争や国鉄民営化反対闘争の指導的立場にいた。「われわれの尽力があって初めて、清水議長体制は成り立ったのだ」と深く反省しているようだ。また、自分たちの政治的責任も含め、こうした「総括文書」を公表するのに、中核派を離れて九年間もかかったことについても「清水体制と戦って傷つき、党を離れた幾多の同志に深くおわびしたい」とのべている。
「党建設の失敗、挫折」と清水氏は言うのかも知れないが、そうではなく、「間口の狭いレーニン主義」を未だに「日本革命に不可欠の道」とし続けていることに根本問題があるのではなかろうか。党派闘争で倒れた多くの活動家に対しても、この点について、清水氏は答える責務があるのではないだろうか。非公然と言うことで曖昧化することはもはや許されないのではなかろうか。革マル派に圧倒的な非があるとは言え、二〇年近くも続いた党派闘争で、素朴に社会改革を夢見て立ち上がった人々を絶望の淵に叩き込み、公安警察の跳梁と、過激派攻撃をはびこらせたことの責任も明確にされなければならないだろう。
「現代において革命は可能か」という問いは今では「何を革命するのか。何をどう変えて、新しい社会を作るのか」という問いにも同時に答えなければならないだろう。前述したように、「プロレタリア革命」「プロレタリア独裁」といった言葉がもはやほとんど現実性のある言葉として、受け止められることがないのだから。
しかし、それは現時点で言えることであって、一九六〇年代からそうだったわけではない。ロシア革命が一瞬、示したプロレタリア世界革命の可能性を信じて、全てを懸けてボルシェビキたらんとしたふたりの革命家の「長い苦闘の歴史」は、これからも登場してくるであろう「社会変革を目指す若者」にとって、決して明るくはないが、ある時代を誠実に生き抜こうとした社会運動家の「生涯の闘い」が何であったのかを雄弁に語る「歴史の証言」なのだ。
『流砂』第9号(2015年9月25日刊)所収
問いに答えなければならない
山田 宏明 (フリーライター)
【水谷保孝・岸宏一『革共同政治局の敗北 一九七五~二〇一四 あるいは中核派の崩壊』(白順社、二〇一五年)】
2015年7月3日
『流砂』2015年第9号 【書評】から転載
革共同中核派の四五年の歴史とその帰結
かつて「中核派」という言葉が「魔法の響き」だった時代があった。一九六〇年代後半の新左翼運動・全共闘運動を体験した人なら、何を言っているのか、ピンと来る話だと思う。ベトナム反戦を旗印に、数十万の学生、青年労働者、市民が首都東京で、集会やデモを展開、当時の佐藤首相の南ベトナム訪問や訪米に反対して、機動隊と激しくぶつかった。
この「新左翼の時代」の到来を告げたのは一九六七年一〇・八の「佐藤訪ベト阻止闘争」だった。再建された中核派などの三派全学連が羽田空港近くで機動隊と激しくぶつかり、中核派の活動家だった京大生、山崎博昭君が亡くなった。大衆闘争での死者は、一九六〇年安保闘争の樺美智子さん以来だった。ブント、解放派を凌いで中核派が三派全学連の主力として、一九七〇年の安保改定までの三年間の激しい街頭実力闘争の「先頭」にいた。
以来、まもなく半世紀。世の中は変わって、「左翼はキチガイ」と公言する人も珍しくない時代風潮になった。一九六〇年代末の闘争を担った「学生たち」も還暦をとうに過ぎ、人生の終盤を迎えている。
あの「闘争の日々は何だったのか」「我々はなぜ、敗北したのか」を自問自答している人も少なくない。「固い団結」を謳っていた中核派も、何度も分裂を重ね、安部極右政権の登場と、戦争国家への突進にも拘わらず、中核派の姿はよく見えない。一九六〇年代後半の闘いの「中核派の主要闘士」だったふたりが、この四五年間に革共同の中では何があったのか、を詳細にまとめた本書を出版した。「非合法・非公然」の「非非」体制に移行して以降、外部からはほとんど見えなくなっていたこの組織の権力(公安警察)や対立党派だった革マル派との闘い、退潮期だったにも拘わらず激しく闘われた成田闘争や国鉄民営化阻止闘争、そして組織内部での対立、路線闘争、なかんずく同派の創始者で、しかし、一九七五年に革マル派に暗殺された本多書記長の後を継いで、同派の最高指導者となった清水丈夫氏の政治路線と指導方針を巡っての組織内論争が具体的かつ詳細に描かれている。「高度に発達した資本主義国」での「レーニン主義革命」は可能か、という難問に挑んだ同派の「軌跡と現在」がここにある。著者たちの結論は「完全な敗北」であり、その責の大半は最高指導者の清水氏が負うべきものだ、である。日本の革命運動、新左翼の政治運動が、中核派に限らず、なぜ、かくも苦難と苦渋に満ちた道しか、たどれなかったのか、そのことを省みるためには、中核派に属さなかった人にも必読の「重い歴史証言」だろう。
著者ふたりは一九六〇年代後半に学生運動活動家として、当時、 日の出の勢いで組織的伸張を実現していた中核派に所属し、中核派全学連幹部や全国全共闘幹部を経て、二〇〇六年には革共同政治局員だった。しかし、千葉動労を中核とする「労働者党員と学生運動出身者との対立」が深まる中で、党外に「放逐」された。
一九六〇年代後半の中核派やその他の新左翼各セクトの伸張は何と言っても、当時、熾烈さを増すばかりだった「ベトナム戦争」への反戦闘争の高揚だったろう。戦後最大の反政府大衆運動だった一九六〇年安保闘争の敗北で三分解した共産主義者同盟(ブント)の一部メンバーが、日本共産党に代わる革命党の建設を目指して地道な学習会活動を続けていたごく小さな組織「革命的共産主義者同盟(革共同)」に合流して、ブントと並ぶ新左翼の一大潮流が生まれたのは周知のことである。しかし、大衆運動の進め方と組織建設を巡って、革共同全国委員会は一九六三年に革共同全国委員会(中核派)と日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義者同盟(革マル派)に分裂した。
中核派は一九六〇年代後半のベトナム反戦闘争の大衆的高揚の頃から「党のための闘争」と「党としての闘争」の統一をアビールし続けてきた。これは革共同第三次分裂のきっかけにもなった「党建設・組織建設」を最重視する革マル派へのアンチで、「権力闘争を激しく展開する中で、党建設・組織建設を進める」という革命組織観だ。革マル派を除く新左翼各セクトが、大衆運動の高揚を最重視して、組織建設を軽視する傾向があり、これが一九六〇年の安保ブントの崩壊の原因でもあったわけだが、中核派はこの困難な課題に真っ向から挑む姿勢を初期段階から明言して来た。一九七〇年前後の激しい対権力闘争で大量の逮捕者を出し、破防法の適用を受けたにも関わらず、党組織の分裂をきたさなかったのは、この「テーゼ」の力だったろう。しかし、一九七〇年代半ばからは、大衆運動の退潮によって、対権力闘争の高揚が困難となったことをひとつの背景として、革マル派との党派闘争が前面化、一九七五年には最高指導者だった本多書記長(当時)が革マル派に暗殺される。
革マル派との党派闘争もあってか、同派は本多氏の後継者を公表せず。「集団指導体制」を取っていたと見做され、また、野島三郎政治局員が『革共同の内戦論』など「反ファシズム解放闘争」という対革マル派闘争の理論化を行った著作を発表し、機関誌にも政治路線についての論文を掲載していたことから、同氏がリーダーと見做す向きもあったが、本書によると「後継は清水氏」であり、以来、今日まで、最高指導者だという。一九九〇年代初頭には、同派も清水氏を「革共同議長」と表記し、最高指導者であることを公表した。本書では、清水氏の長期間に渡る独裁とさまざまな組織的歪みは、対革マル戦に対処するための、「非公然・非合法」体制によつて党内民主主義が封殺され、党大会も開けず、清水氏の通達によって重要事項がトップダウンで決定していたためだ、としている。スターリン体制の旧ソ連で、世界大恐慌による世界大戦勃発の可能性に怯えて、「兵営共産主義」とのちに呼ばれるスターリン独裁が深化していった事例をほうふつとさせる話だ。
「輝ける安保全学連書記長」の経歴を有し、カリスマ性のあった清水氏が本多氏の後継になつたのは当然だったのかも知れない。また、一九六〇年代半ばに、三派全学連がブントの主導で、「ベトナム反戦」をメインスローガンに一九七〇年に向けての闘争を組織しようとしていた時に、当時、中核派の学対だった清水氏が、「反帝反スタ」という「空疎」な立場、「ベトナム戦争は米ソの代理戦争」という空疎な立場を捨てて、党内を「反米帝」に三日間で塗り替えた、というエピソードを『聞き書き〈ブント〉一代』で、医学連の創始者の安保ブントの石井暎禧氏が紹介していて、清水氏の「政治的センスの鋭さ」を称賛していたが、そういう才能は卓越していたのだろう。しかし、総合的に見て、清水氏が本多氏をしのぐ指導者だ、という声は新左翼関係者の間でも少なく、「レーニン主義の継承か、解体か」「戦争と革命の基本問題」など、マルクス・レーニン主義革命論に一時代を画する論考を書いた本多氏に比べて、清水氏にそういう著作はない。しかし、それでも半世紀に渡り、革共同に君臨し、政敵を寄せ付けなかったのは、この「非非」体制のせいだ、と著者ふたりは言う。(この点は一九九〇年代にやはり革共同から「放逐」された元政治局員の白井朗氏=山村克氏、故人=も以前、指摘していたことはあったが)。
一九九〇年代前半に、二〇年近くに及んだ革マル派との党派闘争は(はっきりとは宣言されないまま)停止される。革マル派と権力への武装闘争もトーンダウンし、革命軍という非公然武装組織もほぼ解体されて、中核派は一九六〇年代以来、久し振りに「公然大衆闘争」(全人民的政治暴露)に全面転換する。清水氏はこの転換を「敵の目の前でわき腹をさらしながら旋回したようなもので、この大転換で党が割れなかったのは世界史上に例のない奇跡」と称賛した。党組織の比類なき強靭さを称えたのだろうが、二〇〇七年の革マル派議長、黒田寛一氏の病死の際にも、機関紙『前進』でわずかな取り上げ方しかしていなかったのは、中核派メンバーだけでなく、この戦争に関心を寄せていた人々にも奇異な感じを抱かせた。「三頭目処刑」などと毎週のように『前進』に書いていた時代に比べれば、仰天するほどの違いだった。もちろん、対革マル戦の開始は本多氏の決断だったのだろうが。しかし、この決断もかつてのような「大衆闘争の革命的高揚」はもたらさず、これが現在の同派の「労働者の力で革命を」路線につながっているのではないか、と思われる。市民や学生、左翼知識人への一種の「絶望」があるのではないか、ということだ。
本書で詳細に述べられている党内での対立、軋轢、清水氏の対応については、当事者でないので、コメントしにくい。ただし、幾つかの新事実は披瀝されている。一九七〇年代に横須賀で起きた中核派アジトでの爆弾破裂事件と三人の中核派メンバーの爆死は、当時、革命軍を指導していた清水氏が深く関与していたこと、革命軍の索敵活動で革マル派の黒田氏と、ナンバーツーだった動労の松崎氏の「所在」をほぼつかみ、「革命的処刑」を実行できる状態にあった時期があったが、清水氏は、戦争の激化を怖れて、作戦にゴーを出さなかったこと--などだ。著者によれば清水氏は「投獄、収監や党派闘争での死」を何よりも怖れており、それが現在も続く「非公然」生活に繋がっているのだ、という。まあこの点は事実というよりは著者たちの「見方」ではあろうが。
長く長く、予想を超えてとてても長く続いた「後退局面」で「過激派(革命的左翼)が直面した困難(アポリア)」との格闘の記録でもあり、読後感は重苦しく、しんどい。しかし、困難の中で「職業革命家」の生き方を貫こうとした著者ふたりの「誠実さ」は疑いない。
なぜ、先進国革命はかくも「大きな困難」に直面
し続けるのか
「日本革命に不可欠の道」として未だにレーニン
主義を続けていることに根本問題がある
それでは、中核派を離れて、「先進国(帝国主義本国)の革命運動はなぜ、かくも「大きな困難」に直面し続けるのか」について、少し私見を述べてみたい。
新左翼が領導していた大衆運動が高揚し続けていた一九六〇年代には、「現代における先進国(帝国主義本国と言ってもいい)革命とは何か」が問題だった。中核派だけでなく、新左翼総体が直面していたアポリアだった。
しかし、今では、レーニン主義によるプロレタリア革命などあり得るのか、という問題が重くのしかかっている。通信産業、IT産業、サービス業などの拡大は、機械制大工業の労働者の蜂起によるプロレタリア独裁というレーニン主義の構図をとても古めかしいものにしてしまった。
イタリアのネグリとフランスのガタリは、プロレタリアに代わる革命主体として、こういう知識労働者やフリーターなどを取り込んだ「マルチチュード」を提起している。米国のウォールストリート占拠のような、「マルチチュードの総叛乱」による権力機構の麻痺を通じて、新しい「権力奪取の主体」が登場して来るというのだ。
レーニン主義を死守して来た中核派は、一九六〇年代は学生の総叛乱による日帝打倒を夢見た。しかし、ブントや革命的労働者協会[革労協](解放派)なども含め、この学生叛乱路線は、機動隊の壁を破れなかった。武装闘争で、権力の暴力装置を破壊しようという試みも、武装闘争を組織する過程での「重圧」を撥ね退けられず、権力奪取に手もかけられないまま、連合赤軍事件などで「爆砕」してしまった。
中核派の場合は、路線の行き詰まりは、内訌し、武装闘争を否定する革マル派との果てしない「内ゲバ」に結実し、大衆的な支持基盤をほとんど喪失してしまった。成田闘争や国鉄民営化阻止闘争という「シングルイシュー」に党組織の力を集中して、いわば「一点突破」的に局面を切り開こうという試みも行われたが、「一〇・八」のような波及力は生まれなかった。本書で描かれているのは主要には、こうした「冬の日々」の党活動、政治路線を巡る政治局の苦悩と路線対立、分派の発生の中での幹部党員の苦闘と挫折である。路線選択の間違いがこういう「未来」に逢着したとはちょっと思えない。
共産主義者同盟と同様に、日本共産党という革命組織への疑問から革命的共産主義者同盟という組織が生まれたわけだが、本多書記長のような優れたオルガナイザーは、黒田理論という「特異な革命理論」に頼る必要があったのか、という疑問は今の時点では消えない。一九五〇年代に形成された理論体系なので時代的制約があるのは当然だが、「認識論は素朴反映論」「マルクス主義の根底は疎外論」「唯物論とは物質の自己運動論」というとても古めかしい理論に依拠しないと、日本共産党の理論体系に対抗できなかったのか、という疑問は消えない。この黒田理論の独得の観念体系が、権力との衝突を重ねていた中核派にとって重荷になり、党派闘争で「革マル的偏向」を振り切ろう、という流れになったのではないのだろうか。
「レーニン主義の継承か解体か」「戦争と革命の基本問題」という優れた論文を書き上げる能力のあった本多氏は、黒田理論に依存しなくても革共同を作り出し、一九七〇年闘争を領導出来たのではないか。そうすれば、革マル派との党派闘争という泥沼に足を救われることはなかったのではないか。
死んだ子の歳を数えるような話ではあるが。安保ブント創設に関与した老理論家は「ブントの崩壊の仕方がまずかった」と革共同誕生の背景を、安保ブントの無様で異様な「潰れ方」に起因させている。一九六〇年安保闘争はブントが担ったのであり、革共同など何の関係もなかった、という安保ブント関係者の見解からすれば、その通りであり、「革共同とは何者なのだ」というところだったろう。
革共同とは違う一九七〇年闘争実現を目指して、安保ブントの活動家だった人たちや三派全学連の関係者は、第二次ブント(統一ブント)を一九六〇年代半ばに結成して戦うが、こちらも一九七〇年決戦で敗北して、再び七花八裂となってしまう。
ただ、特に清水体制に移行してからの革共同(中核派)は、路線論争などを巡って登場した「反対派」をことごとく「スパイ」「反革命」「階級敵への移行者」と決めつけ、「革命軍」を振り向けて、物理的・肉体的に打撃を与える党内闘争スタイルを取っているのはどうしてなのか。反対派を党外に「放逐」した結果として、現在に至る清水議長独裁体勢が存続しているわけだが、その結果として、この本の著者たちのように、「非公然・非合法」体制時代の「内幕」を公表して、どちらに非があったのか、を問う人たちが登場するのは必然であったろう。
ただし、著者ふたりも「自分たちは被害者で有責ではない」と思っているわけではないようだ。ふたりは一時期まで清水議長体制を支えた同派の政治局員で、成田空港反対闘争や国鉄民営化反対闘争の指導的立場にいた。「われわれの尽力があって初めて、清水議長体制は成り立ったのだ」と深く反省しているようだ。また、自分たちの政治的責任も含め、こうした「総括文書」を公表するのに、中核派を離れて九年間もかかったことについても「清水体制と戦って傷つき、党を離れた幾多の同志に深くおわびしたい」とのべている。
「党建設の失敗、挫折」と清水氏は言うのかも知れないが、そうではなく、「間口の狭いレーニン主義」を未だに「日本革命に不可欠の道」とし続けていることに根本問題があるのではなかろうか。党派闘争で倒れた多くの活動家に対しても、この点について、清水氏は答える責務があるのではないだろうか。非公然と言うことで曖昧化することはもはや許されないのではなかろうか。革マル派に圧倒的な非があるとは言え、二〇年近くも続いた党派闘争で、素朴に社会改革を夢見て立ち上がった人々を絶望の淵に叩き込み、公安警察の跳梁と、過激派攻撃をはびこらせたことの責任も明確にされなければならないだろう。
「現代において革命は可能か」という問いは今では「何を革命するのか。何をどう変えて、新しい社会を作るのか」という問いにも同時に答えなければならないだろう。前述したように、「プロレタリア革命」「プロレタリア独裁」といった言葉がもはやほとんど現実性のある言葉として、受け止められることがないのだから。
しかし、それは現時点で言えることであって、一九六〇年代からそうだったわけではない。ロシア革命が一瞬、示したプロレタリア世界革命の可能性を信じて、全てを懸けてボルシェビキたらんとしたふたりの革命家の「長い苦闘の歴史」は、これからも登場してくるであろう「社会変革を目指す若者」にとって、決して明るくはないが、ある時代を誠実に生き抜こうとした社会運動家の「生涯の闘い」が何であったのかを雄弁に語る「歴史の証言」なのだ。
『流砂』第9号(2015年9月25日刊)所収
















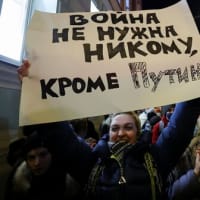


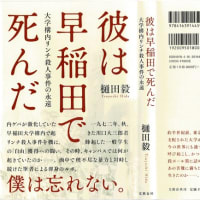
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます