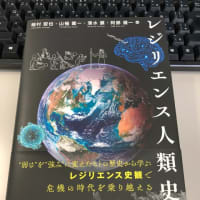地球研内の可視化高度化事業に私の案「TD研究による「異なる回路」の発見プロセスの可視化―環境トレーサビリティープロジェクトホームページ作成の現場から」が、紆余曲折を経て採択された。とりあえず、ほっ♡・・・5月の終わりにプレゼンがあり、地球研内の事業だし、環境トレーサビリティは地球研の目玉事業だし、たぶん採択されるだろうと甘い考えでいたら、翌日に「採択見合わせ」のお知らせが届いた。。。その後ヒアリングがあり、なんとか採択にこぎつけた。当初の予定よりかなり縮小してしまったけど、本当にやりたいことに集中できる事業に変更することができたように思う。公開プレゼンでコメントくださった方、審査委員の方々、ありがとうございます。
私がやりたいのは、ずばり、同位体比を使った測定に対する理解がどのように進むのか、ということだ。それをサイエンスコミュニケーションの枠組みで考えることができないかなと考えている。
そもそも、私が同位体測定と出会ったのは、10年ほど前、ひどいアレルギー症状を発症し、医者に駆け込んだら、「原因は黄砂か花粉かどちらかです」と言われたことだ。すぐに黄砂に興味を持ちいろいろ調べていると、黄砂が運ばれてくる経路を特定する研究では、放射性同位体比を使っていた。いろいろ論文を読んでいると、中国の核実験だけではなく、イギリスの再処理工場から飛んでくる核物質も日本で検知されていた。
ちなみに同位体比というのは、元素を構成する粒子の構成が若干異なっているものの比率。地球上には、炭素とか水素とか鉄などたくさんの異なる元素がある。どの元素も、陽子、電子、中性子で構成されるが、どうして鉄になったり、水素になったりするのかというと、陽子の数が違うから。元素の陽子の数が同じなら同じ元素で、違えば違う元素になる。でも、同じ元素(つまり陽子の数が同じ)でも、中性子の数が異なるものが存在している。これが同位体だ。炭素だけど、中性子の数が異なる炭素元素が集まっているのだ。この中性子の異なる炭素の割合が同位体比だけど、この同位体比を用いることによって、自分の家の井戸の水がどこから来ているのかとか、ミルクの産地とかのトレースやほんもののはちみつかどうかなどが分かるのだ。
さてさて、話を元に戻すと、その後地球研叢書で、『安定同位体というメガネ―人と環境のつながりを診る』と言う本を読み、同位体にますます興味を持った。
これから一年間、同位体のホームページを作る作業に参加し、同位体のことをよく知らない人にも入ってもらって、ホームページ作りのワークショップを開催し、ファシリテートも務めながら、ホームページ作りに参加する人の考え方がどう変わるのか、同位体をどういう風に理解していくのか、それがどう生かされていくのか、見ていきたいと思っている。
とても楽しみだけど、忙しくなりそう!いや、忙しいけど、楽しい作業になりそう、と書いた方がいいだろうか?(写真は、左から環境トレーサビリティプロジェクトの藤吉研究員、陀安リーダー、わたし)