山田ときさんを偲ぶー6
〈2 つぎの一年――原っぱの子らと〉
流されて
こうして、つたない第一歩を歩みはじめていた私に、思いもかけぬことがおこってしまっ た。
一年近い交際のあいだに、校長先生もなかにはいって、進みかけていた国分先生との婚姻 ばなしを、二・三年間、両親のひざもと近くで、勤めていく間に具体化してゆこうという、 理解深い校長先生の厚意が、かえって逆効果となり、翌年三月末に、私はふいに同郡亀井田 尋常高等小学校に転任の辞令をうけとったのだ。
実家の町の学校にはゆけなくても、もしかしたら、その近くにはいかれるでしよう、そし たら、おとうさん、おかあさんに親孝行できるでしよう、といってくれた校長先生のあっせ んとは反対に、いままでよりはもっと北の方の最上川のほとりに流されてしまったのだ。
その村には分校あわせて四つあり、私がいったところは、尋常高等小学校で本校と呼ばれていた。あとの三つは尋常小学校だった。雪の名所として、また『奥の細道』で名高い大石 田から北方に約一里(学校まで)、八学級、校長あわせて九人の小さな学校だった。ここも全くの知らない、はじめて聞き、はじめて見た村だったが、女三人のうち、私より六年ばかり先輩の溝川先生がおられることは、たったひとつの慰めだった。
それで溝川先生とは、学校の往復に、寄宿舎の思い出ばなしを語ったり、たま.には読んだ本の話などをすることもできた。
ここで、私を待っていてくれたのは、三から集ってきた、新しい七十二人の一年生た ちだった。
ようやく、子どもとともに生きる線に浮びあがったばかりで、五十人の長瀞の子どもと別 れなければならなかった私は、若い時代の感傷もあり、包みきれぬ悲しさに、子どもたちと いっしよに泣き、もう一度必ず長瀞にもどることを約束して別れた。校長先生も国分先生も、 「どこにいっても、同じ日本の子どもを教えるのだ、元気をだしてやりなさいよ」と励ましてくださったが、やっぱり悲しかった。しかし、七十二人の子どもたちの前に立ってみると、こんな感傷におぼれていることは許されなかった。
二年目とはいえ、男女合わせて七十二人の一年生に向っては、全く新しいことばかりで、 何も考えるひまがなかった。国分先生は、「子どもを見つめなさい。教室の記録をもちなさい。そこから問題をつかみなさい」と、常に励ましてくださった。私は夢中になって、子どもたちととりくんだ。授業が終わり、子どもたちを見送ると、忘れないうちに、すぐに教室で、その日の子どもたちの会話のなかから、子どもたちのおどろき、欲求、悲しみ、喜び、家庭でのできごと、登校下校時のできごとなどを書き込んだ。宿に帰ってからも、また、思いだしながら書き落しのところをつけ加えた。日記をつけることによって、子どもたちと語り、その母たちと語り、自分を叱り、また慰めた。
こうして一週間ぐらいたまると、私はそれを国分先生におくり、先生はそれに批評を加え たり、自分のやっているしごとを知らせてくださった。それが文通であった。私はこの手紙 を何よりも待ち、自分の手紙も空虚にならないように、この子どもたちのために専心没頭し た。
私は若かった。今考えてみると、ミスもいっぱいあった。この年の七月からは、日中戦争 がぼっ発し、教育界にも、いよいよ軍国調がのしかかってきていたので、この小さい一年生 たちのいたいけな教室経営にも、遠慮なくその波はおしよせてきた。今考えてみても、はず かしくてたまらないことがいっぱいだ。そのときの日記をひらいてみよう。
山田とき著『路ひとすじ』(東洋書館・1952年・P23~P25)より










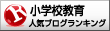








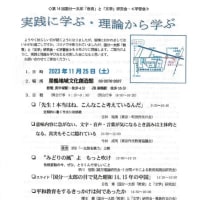




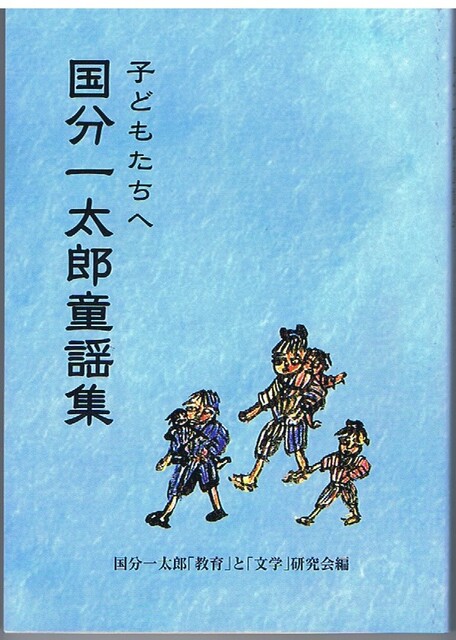

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます