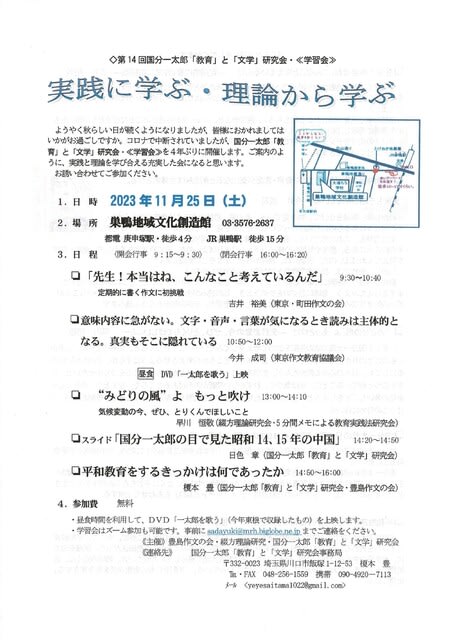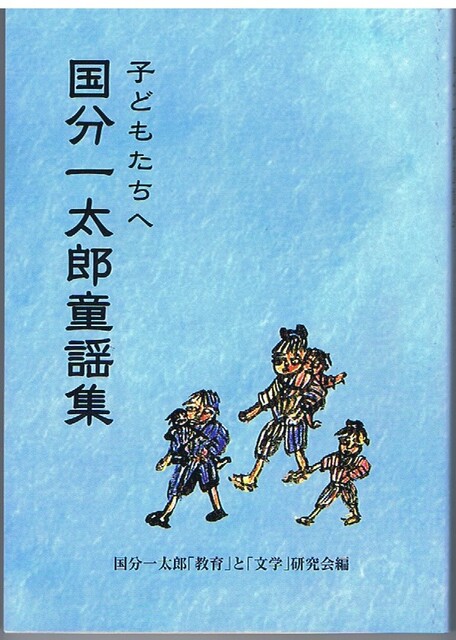第19回国分一太郎「教育」と「文学」研究会のご案内-4
オンライン参加のおすすめ
すでにご承知のことと思いますが、今回の、国分一太郎没後40年の集いも、オンラインでの参加が可能です。そこで、メールでご案内できる方には、下記のように、ご都合がよいときにご参加いただければと思い、それぞれの開始時刻をご案内しました。そのご連絡を、このブログにも転載します。
ご覧になって、ご都合がよいときにご参加いただければさいわいです。
◎
新緑の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
6月上旬に本研究会のご案内を差し上げましたが、7月12日(土)、13日(日)の研究会まであと2週間ほどとなりましたので、再度お誘い(ズーム参加)のご案内を送らせていただきます。
12日、13日の2日間、会場においでいただけない方には、ズーム参加(無料)をお勧めいたします。ズーム参加をしてみたいという方がいらっしゃいましたら、チラシのQRコードか、
https://ichitaro.higashine.org
上記の「申し込みサイト」にアクセス、参加申し込みをしてください。
* 申し込みフォーム内の「役職」(肩書)の欄には、所属(例:カクコサークル、 山形童話の会等)をお書きください。
*「申し込みサイト」には、詳しい案内ビラが載っていますので、そちらもご参 照ください。
皆様のズーム参加、心よりお待ち申しております。
2025年(令和7年)7月1日(火)
国分一太郎「教育」と「文学」研究会
会長 田中 定幸
◎
☆第19回 国分一太郎「教育」と「文学」研究会
没後40年の集い 日程のご案内
◎7月12日(土)
◆開会式 (13時30分~)
◆一太郎・綴方・想画 (13時50分~)
ビデオ上映「故郷へのメッセージ」
「生活綴方 国分一太郎」
◆一太郎を歌う (14時50分~)
ビデオコンサート
東根混成合唱団アップルコーラス
けやきジュニア合唱団
斎藤文四郎 渡邉ゆき子 他
北東村山レインボー合唱
◆記念講演 (15時00分~)
「想画とブリューゲル」
講師 岡田匡史 (信州大学名誉教授)
◎7月13日(日)
◆報告1 ( 9時00分~10時20分)
「デジタル化隆盛の今、子どもに文章を書かせることの意味と課題」
早川恒敬(「5分間メモ」による教育実践法研究会)
◆報告2 (10時30分~11時50分)
「綴り、つながり、巡り合う」
菅野恵子(福島 カクコサークル)
共同研究 安部貴洋(山形県立米沢栄養大学)
◆報告3 (13時00分~14時30分)
「国分先生から学んだ作文の書き方・書かせ方」
田中定幸(国分一太郎「教育」と「文学」研究会)
◆閉会集会 (14時30分~15時00分)
毎日、暑いですね。でも、研究会に向けてがんばります。お目にかかれるのを楽しみにしています。(田中定幸)
オンライン参加のおすすめ
すでにご承知のことと思いますが、今回の、国分一太郎没後40年の集いも、オンラインでの参加が可能です。そこで、メールでご案内できる方には、下記のように、ご都合がよいときにご参加いただければと思い、それぞれの開始時刻をご案内しました。そのご連絡を、このブログにも転載します。
ご覧になって、ご都合がよいときにご参加いただければさいわいです。
◎
新緑の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
6月上旬に本研究会のご案内を差し上げましたが、7月12日(土)、13日(日)の研究会まであと2週間ほどとなりましたので、再度お誘い(ズーム参加)のご案内を送らせていただきます。
12日、13日の2日間、会場においでいただけない方には、ズーム参加(無料)をお勧めいたします。ズーム参加をしてみたいという方がいらっしゃいましたら、チラシのQRコードか、
https://ichitaro.higashine.org
上記の「申し込みサイト」にアクセス、参加申し込みをしてください。
* 申し込みフォーム内の「役職」(肩書)の欄には、所属(例:カクコサークル、 山形童話の会等)をお書きください。
*「申し込みサイト」には、詳しい案内ビラが載っていますので、そちらもご参 照ください。
皆様のズーム参加、心よりお待ち申しております。
2025年(令和7年)7月1日(火)
国分一太郎「教育」と「文学」研究会
会長 田中 定幸
◎
☆第19回 国分一太郎「教育」と「文学」研究会
没後40年の集い 日程のご案内
◎7月12日(土)
◆開会式 (13時30分~)
◆一太郎・綴方・想画 (13時50分~)
ビデオ上映「故郷へのメッセージ」
「生活綴方 国分一太郎」
◆一太郎を歌う (14時50分~)
ビデオコンサート
東根混成合唱団アップルコーラス
けやきジュニア合唱団
斎藤文四郎 渡邉ゆき子 他
北東村山レインボー合唱
◆記念講演 (15時00分~)
「想画とブリューゲル」
講師 岡田匡史 (信州大学名誉教授)
◎7月13日(日)
◆報告1 ( 9時00分~10時20分)
「デジタル化隆盛の今、子どもに文章を書かせることの意味と課題」
早川恒敬(「5分間メモ」による教育実践法研究会)
◆報告2 (10時30分~11時50分)
「綴り、つながり、巡り合う」
菅野恵子(福島 カクコサークル)
共同研究 安部貴洋(山形県立米沢栄養大学)
◆報告3 (13時00分~14時30分)
「国分先生から学んだ作文の書き方・書かせ方」
田中定幸(国分一太郎「教育」と「文学」研究会)
◆閉会集会 (14時30分~15時00分)
毎日、暑いですね。でも、研究会に向けてがんばります。お目にかかれるのを楽しみにしています。(田中定幸)