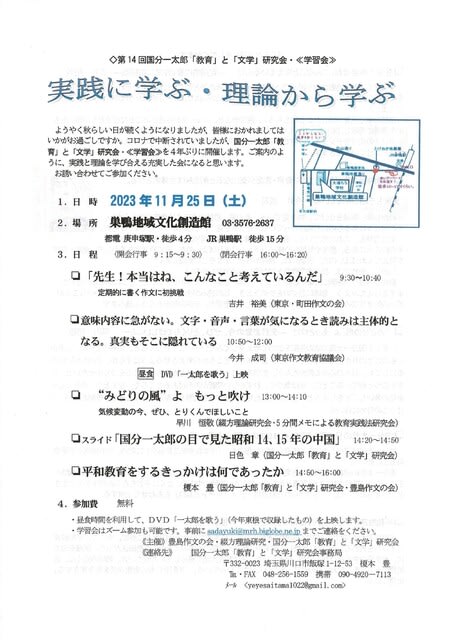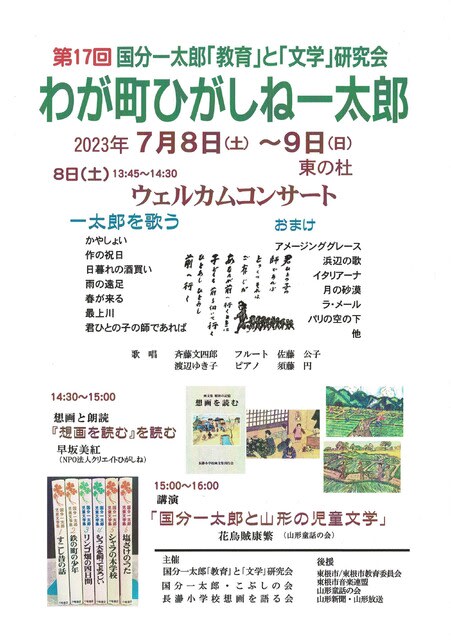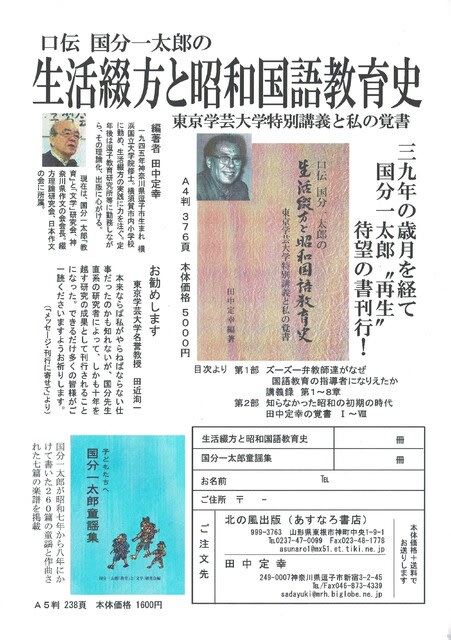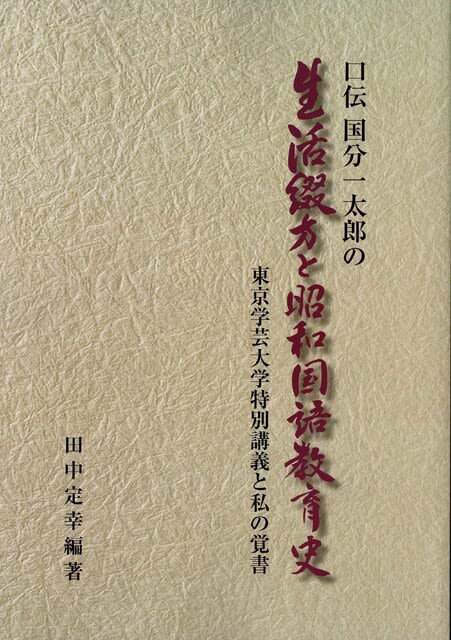すでに第15回国分一太郎「教育」と「文学」研究会《学習会》のご案内を差し上げていますが、池上善彦さんから、上記のように報イトルイトルを変更したいというご連絡をいただきました。
当時、綴方にも、版画にも、そして、図画にも「生活」という言葉がそえられていたことの意味を語ってくれるのではないかと私も期待してもります。
前回のチラシのコピイでのお知らせでは、見にくかった方もいらっしゃるのではないかと思いますので、池上さんの部分をあらためて紹介させていただきます。
❏「生活綴方・生活版画・生活画」 13:00~14:30
池上 善彦(『現代思想』誌(青土社)元編集長)
1956年岡山県生まれ。1991年から2010年まで『現代思想』誌(青土社)編集長。
初期の『作文と教育』ではほぼ毎号と言っていいくらいに版画が表紙になっていて、岩波文庫版『山びこ学校』には「炭やきものがたり」と題された詩と版画が掲載されています。また恵那の石田和男さんによる『夜明けの子ら』は「生活版画と綴方集」とサブタイトルがつけられていました。
戦前長瀞小学校で実践されていた「想画(生活画)」と国分一太郎さんのことはよく知られています。しかし戦後に綴方と強く結びついて現れた美術は絵画ではなく、版画でした。それは一体どのようなもので、どのような意図を持って教師達に実践されたのでしょうか? またその背景にあるものは何だったのでしょうか? 従来とは少し別の角度から見てみることで、綴方運動の広がりのお話が出来ればと思っています。よろしくお願いします。
私がはじめて、毎年夏に開かれる、日本作文の会主催の”全国作文教育研究大会”に参加したのが、1967年に静岡の駿府会館と静岡大学で開催された、第18回大会でした。
この時、会場にはられていた「教室はまちがうところだ」の詩と初めて出合い、それをうつしとって、学級の子でもたちと毎朝、暗唱しました。
この詩を書いたのが版画教育も実践されてきた蒔田晋治さんだったということを後で知りました。
そして、私もいつの間にか、版画に興味をもち、年に3回発行する文集のそれぞれの子が保管する文集の表紙には、その子描いた版画を載せるようになっていました。綴方も版画も、そして図画教育にも「生活」がつながっていったように思います。
蒔田晋治さんは『生命を彫った少年』(エミール社 1993年12月)という本のなかで、「版画と作文、あるいは詩、直接なんの関係もないようだが、生活を彫る版画も、生活を綴る作文も根っこひとつである」と書いています。そして、その後には、
綴る/人間を綴る/人間の生きる姿を綴る/人間の喜びや悲しみや/怒りや苦しみを綴る/心のひだを綴る/深く深く綴る/
あるがままに綴る/自然を綴る/自然のいのちを綴る/自然の喜びや悲しみや/怒りや嘆きを綴る/自然の心を綴る/あるがまま
に綴る /心をこめて綴る/綴る
という詩を載せていました。
私は、そのころ、3つの関係なんて、それ程意識していませんでしたが、なんだか若い頃にもどれるような気がして、池上さんのお話がますます楽しみになってきました。(田中定幸)

当時、綴方にも、版画にも、そして、図画にも「生活」という言葉がそえられていたことの意味を語ってくれるのではないかと私も期待してもります。
前回のチラシのコピイでのお知らせでは、見にくかった方もいらっしゃるのではないかと思いますので、池上さんの部分をあらためて紹介させていただきます。
❏「生活綴方・生活版画・生活画」 13:00~14:30
池上 善彦(『現代思想』誌(青土社)元編集長)
1956年岡山県生まれ。1991年から2010年まで『現代思想』誌(青土社)編集長。
初期の『作文と教育』ではほぼ毎号と言っていいくらいに版画が表紙になっていて、岩波文庫版『山びこ学校』には「炭やきものがたり」と題された詩と版画が掲載されています。また恵那の石田和男さんによる『夜明けの子ら』は「生活版画と綴方集」とサブタイトルがつけられていました。
戦前長瀞小学校で実践されていた「想画(生活画)」と国分一太郎さんのことはよく知られています。しかし戦後に綴方と強く結びついて現れた美術は絵画ではなく、版画でした。それは一体どのようなもので、どのような意図を持って教師達に実践されたのでしょうか? またその背景にあるものは何だったのでしょうか? 従来とは少し別の角度から見てみることで、綴方運動の広がりのお話が出来ればと思っています。よろしくお願いします。
私がはじめて、毎年夏に開かれる、日本作文の会主催の”全国作文教育研究大会”に参加したのが、1967年に静岡の駿府会館と静岡大学で開催された、第18回大会でした。
この時、会場にはられていた「教室はまちがうところだ」の詩と初めて出合い、それをうつしとって、学級の子でもたちと毎朝、暗唱しました。
この詩を書いたのが版画教育も実践されてきた蒔田晋治さんだったということを後で知りました。
そして、私もいつの間にか、版画に興味をもち、年に3回発行する文集のそれぞれの子が保管する文集の表紙には、その子描いた版画を載せるようになっていました。綴方も版画も、そして図画教育にも「生活」がつながっていったように思います。
蒔田晋治さんは『生命を彫った少年』(エミール社 1993年12月)という本のなかで、「版画と作文、あるいは詩、直接なんの関係もないようだが、生活を彫る版画も、生活を綴る作文も根っこひとつである」と書いています。そして、その後には、
綴る/人間を綴る/人間の生きる姿を綴る/人間の喜びや悲しみや/怒りや苦しみを綴る/心のひだを綴る/深く深く綴る/
あるがままに綴る/自然を綴る/自然のいのちを綴る/自然の喜びや悲しみや/怒りや嘆きを綴る/自然の心を綴る/あるがまま
に綴る /心をこめて綴る/綴る
という詩を載せていました。
私は、そのころ、3つの関係なんて、それ程意識していませんでしたが、なんだか若い頃にもどれるような気がして、池上さんのお話がますます楽しみになってきました。(田中定幸)