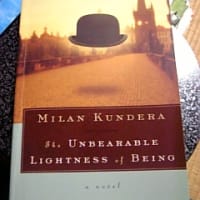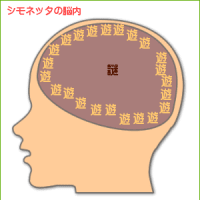劇団桟敷童子の『軍鶏307』を観ました。この劇団の舞台を観るのは、昨年の『海猫街』に続いて2度目です。今回は、鈴木興産という会社の中の倉庫での上演でした。ケツ痛かったっす、勘弁してくださいよ。
2作観て感じたのは、この劇団の作品が、ストレートで古典的な傾向を持つということでした。直情的に訴えてくることを指しているのではありません。虐げられる者の描き方や、軍鶏307という希望の象徴の使い方のことです。それとも、「九州○部作」みたいに、たまたまそういう傾向の作品が続いているだけなのでしょうか。
ここで、ミラン・クンデラの『存在の耐えられない軽さ』の一節を引用します。時は1968年、「プラハの春」に対するソ連の軍事介入を描いた場面の一部です。これはまさに「飛ベナイ鳥ハ鳴クシカネエ」ですが、ずっとドライな「鳴き方」です。
それにセックスに飢えている、かわいそうなロシアの兵隊たちの感情を刺激する信じがたいほど短いスカートをはいていた女たちがいて、彼らの前で誰かれとなくあたりを通る人とキスをしていた。(第2部-23)
もう少し例を挙げましょう。カミュの『ペスト』はメルヴィルの『白鯨』にインスパイアされて書いたものだそうですが、架空の都市における緊迫感あふれるスペクタクルに置き換えることに成功していますし、突然逮捕されて裁判にかけられる主人公の境遇を描いたカフカの『審判』は、何らかの虐げられた境遇の比喩だと解釈することもできるでしょう。もう数十年もすれば古典とみなされるようなこれらの作家ですら、すでに比喩化された舞台を使っているのです。
また、いわゆる現代劇というやつでも、軍鶏307などの何かを象徴するものは、穏喩として現れるか、もしくは現れることさえないのではないでしょうか。たとえわかりやすいものでも、軍鶏307のようにセリフで説明してしまうのは、かなり珍しいのではないかと感じました。
そういった表現の多様さを踏まえた上で、桟敷童子における古典的手法の必然性ということを考えてみるのも、ファンの方にとっては楽しいのかもしれません。多少の流行はあるでしょうが、表現の新旧が作品の良し悪しを決めるものでもないでしょう。新しくてもクソみたいな作品はたくさんありますしね。そして古典的でストレートなのがこの劇団の特徴なのではなく、全編を通して貫かれる力強さこそが最大の「売り」なのだとしたら、そのテイストは残した上で、現代的な作品を一度観てみたいと思うのです。古いからダメだと批判するつもりは毛頭ないのですが、日露戦争後の次は大戦直後という設定が続くと、申し訳ないですがちょっとね…
2作観て感じたのは、この劇団の作品が、ストレートで古典的な傾向を持つということでした。直情的に訴えてくることを指しているのではありません。虐げられる者の描き方や、軍鶏307という希望の象徴の使い方のことです。それとも、「九州○部作」みたいに、たまたまそういう傾向の作品が続いているだけなのでしょうか。
ここで、ミラン・クンデラの『存在の耐えられない軽さ』の一節を引用します。時は1968年、「プラハの春」に対するソ連の軍事介入を描いた場面の一部です。これはまさに「飛ベナイ鳥ハ鳴クシカネエ」ですが、ずっとドライな「鳴き方」です。
それにセックスに飢えている、かわいそうなロシアの兵隊たちの感情を刺激する信じがたいほど短いスカートをはいていた女たちがいて、彼らの前で誰かれとなくあたりを通る人とキスをしていた。(第2部-23)
もう少し例を挙げましょう。カミュの『ペスト』はメルヴィルの『白鯨』にインスパイアされて書いたものだそうですが、架空の都市における緊迫感あふれるスペクタクルに置き換えることに成功していますし、突然逮捕されて裁判にかけられる主人公の境遇を描いたカフカの『審判』は、何らかの虐げられた境遇の比喩だと解釈することもできるでしょう。もう数十年もすれば古典とみなされるようなこれらの作家ですら、すでに比喩化された舞台を使っているのです。
また、いわゆる現代劇というやつでも、軍鶏307などの何かを象徴するものは、穏喩として現れるか、もしくは現れることさえないのではないでしょうか。たとえわかりやすいものでも、軍鶏307のようにセリフで説明してしまうのは、かなり珍しいのではないかと感じました。
そういった表現の多様さを踏まえた上で、桟敷童子における古典的手法の必然性ということを考えてみるのも、ファンの方にとっては楽しいのかもしれません。多少の流行はあるでしょうが、表現の新旧が作品の良し悪しを決めるものでもないでしょう。新しくてもクソみたいな作品はたくさんありますしね。そして古典的でストレートなのがこの劇団の特徴なのではなく、全編を通して貫かれる力強さこそが最大の「売り」なのだとしたら、そのテイストは残した上で、現代的な作品を一度観てみたいと思うのです。古いからダメだと批判するつもりは毛頭ないのですが、日露戦争後の次は大戦直後という設定が続くと、申し訳ないですがちょっとね…