娘がまだ1歳になる前のこと、嫁さんと二人で「娘が将来どんな職業に就くか」話したことがあります。真剣に予想したわけではなく、車中の雑談で思い付きを出してみただけ。現実にはたいてい、予想もしてなかったものを選ぶものでしょう。ちなみに父はフォトジャーナリスト、母はヘアデザイナー。
自分の記憶をたどると、聞かれてうれしいものでもなかったので、「大きくなったら何になる?」と聞くことはないのですが、じいちゃん、ばあちゃんなど周囲の大人は聞きたがるもの。といっても答えはたいてい、『プリキュア』など、ファンタジーの世界。ところが一月ほど前、本人から、具体的な希望が出てきました。イルカの飼育員だそうです。
NHKの「ダーウィンが来た!」を欠かさず視聴、土岐川観察館主催の川の生き物探索、「ガサガサ探検隊」も大好き、水族館やプールも大好きな彼女の希望としては、なかなか筋が通ってるかも。そんなわけで、幼稚園で作った凧もその絵。よく見ないとわかりませんが、真ん中の青いのは水槽で、中にイルカ。左は飼育員になった本人でしょう。
このまま本当にその職業に就く、あるいはそれを目指す可能性はとても低いでしょうが、本人から初めて出た具体的・現実的な希望は覚えておきたい。ちなみに、イルカじゃなかったらウマでもいいそうです。
自分の記憶をたどると、聞かれてうれしいものでもなかったので、「大きくなったら何になる?」と聞くことはないのですが、じいちゃん、ばあちゃんなど周囲の大人は聞きたがるもの。といっても答えはたいてい、『プリキュア』など、ファンタジーの世界。ところが一月ほど前、本人から、具体的な希望が出てきました。イルカの飼育員だそうです。
NHKの「ダーウィンが来た!」を欠かさず視聴、土岐川観察館主催の川の生き物探索、「ガサガサ探検隊」も大好き、水族館やプールも大好きな彼女の希望としては、なかなか筋が通ってるかも。そんなわけで、幼稚園で作った凧もその絵。よく見ないとわかりませんが、真ん中の青いのは水槽で、中にイルカ。左は飼育員になった本人でしょう。
このまま本当にその職業に就く、あるいはそれを目指す可能性はとても低いでしょうが、本人から初めて出た具体的・現実的な希望は覚えておきたい。ちなみに、イルカじゃなかったらウマでもいいそうです。











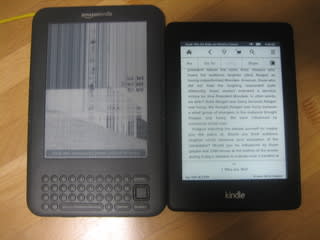

 」
」