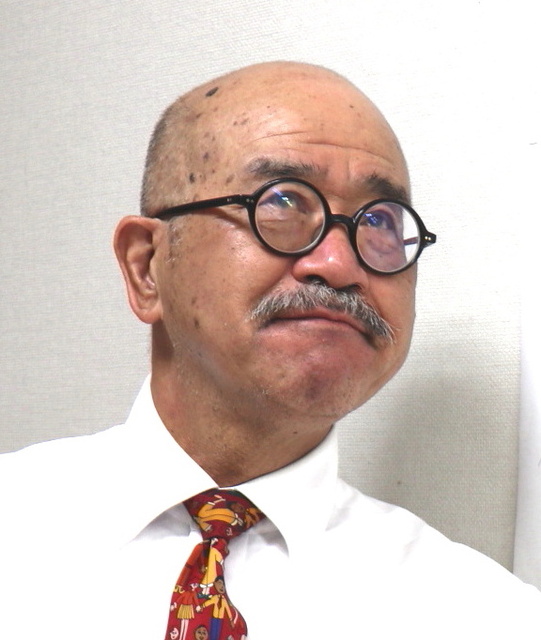暑い月曜日。まったく、梅雨が…ブツクサ。
そこで、涼しい水草の話を書きます。読むと涼しくなります…か。
写真の白い花、何かわかりますか。オオカナダモです。
自転車で走り回っていたら、用水路で見つけました。
理科の光合成のところで登場する植物です。
試験管に入れて、日光を当てるぞ。
こっちはアルミ箔で包んで、日光が当たらないようにするぞ。
こっちの試験管には何も入れませんよ。
さあどうなりますか。
と、色々な苦労をさせられている植物です。
理科の実験でお馴染みのオオカナダモは、南米原産の帰化種、多年生沈水植物。日本には、植物生理学の実験植物として導入された。
北海道を除く各地のため池,湖沼,河川,水路に侵入・定着している。
これまでの観察によると、富栄養な水域でも貧栄養な水域でも分布がみられる。
花期は5~10月で、1日に1花ずつ水面上に出て開花する。
雌雄異株であるが、日本には雄株のみが帰化しているため、結実しない。日本で見ることのできるオオカナダモは、切れ藻などの無性生殖によって増えた個体である。
*岡山理科大学 生物地球システム学科 時光さんの研究発表から一部を引用。
オオカナダモは、1910年代に植物実験用として日本に持ち込まれたものが野生化したアルゼンチン原産の帰化植物。
特徴は後ろの文字が透けるほど薄い半透明の葉。
特別な処理をしなくても細胞や葉緑体の様子を観察できるため、現在でも理科の実験材料として重宝されています(もしかしたら中学校の教科書にも載っているかもしれません)。
日本生態学会が定めた「日本の侵略的外来種ワースト100」に指定されるほど、生態系や人間活動を脅かす存在としても知られています。
オオカナダモには雄株と雌株があり、それぞれが雄花と雌花を咲かせ受粉を行うことで繁殖します。
しかし日本で野生化しているオオカナダモは雄株だけだそうです。確かに桃山高校の池で見られるのも黄色い花粉が特徴的な雄花だけでした。雌花がなければ受粉は行えません。では日本に生育するオオカナダモはどうやって繁殖しているのでしょうか?植物には何か特別な繁殖方法があるのでしょうか?
後編へつづく(5月28日公開予定)
*こちらは、京都府立桃山高校の研究発表のページから一部を引用しました。オオカナダモで検索したら、前のほうの順番で出てきて、大学の理学部のような立派なページで、驚きました。
この高校は文部科学省に、SSHスーパーサイエンスハイスクールに指定されています。
まず生徒たちの観察、研究がすごい。そして、こんな生徒たちをサポートしている桃山高校の先生たちは、うむ、さすがです。
そういえば河合塾マナビスの伏見桃山校には桃山高校の生徒たちが。
Y先生へ。桃山高校の生徒たちに、福井クンが科学系のホームページに感激していたとお伝えください。大学に負けない研究です。
こんなホームページを運営するハイレベルな生徒たち&先生たち。
なお、滋賀県で文部科学省のSSHに指定されているのは、膳所高校、虎姫高校、立命館守山高校の3校です。
京都でも、滋賀でも、高校生と先生たちは頑張っているなあ。頼もしい♪
ホームページで科学の甲子園。がんばれー♪
中学の理科の「無性生殖」のところでも使いやすいのですが、教材には登場しませんね。
①オオカナダモというけれども、カナダじゃなくてなくて、南アメリカのアルゼンチンから日本に来たらしい。
②モ(藻)というけれども、藻類じゃなくて、れっきとした種子植物、被子植物、単子葉植物。イネ、トウモロコシなどとは分類上の住所が近い。
③はるばる日本まで来たのに、男子ばっかり。女子は来てくれなかったのですね。
雄株だけしかいないから、花が咲いても無駄なことで、無性生殖で増えている。
ちぎれて、流れて、そして根を出してふえていく。
ここで一句。
水面に白く咲いて ちょっと寂しいか オオカナダモ
今、琵琶湖に注ぎ込む小川や、水田地帯の用水路で白い花を咲かせています。実物を見るチャンスですよ。ただし、川に落ちたり、遅刻したりせぬように。