物語作品は、現在でも登場人物たちの振る舞いや内面の描写だけでなく、必ず舞台となる土地や風景が登場し、描写される。太古において物語を聴衆に語る場合は、狭い集落を想定すれば、現実界であれ異界であれ、同じ集落あるいは近隣の集落に住む話者が、ある土地や場所を語ると、ははあ、あそこだな、そういうことだな、という風に聴衆はすぐに了解できたのではなかろうか。そういう舞台を背景として、聴衆に受けるような不思議な語りがなされていたのかもしれない。
そこから世界や交通が発達したこの次の段階として、同じ集落出身ではない、遠い他所からやってきた話者の場合、聴衆は自分たちの知らない遠い地方の物珍しい土地や風物を背景とした物語を聞くということが想定される。この場合、聴衆の集落との同一性もあれば異質な面もあるだろう。物語の舞台が都などの大きな都市の場合は、聴衆に物珍しさを与える面が強かったかもしれない。柳田国男はこうした各地を漂泊していく語り部の存在を何度か追究していた。そして、そういう語りは、語り手の脚色もいくらか付け加えられていったとしても、語り手の独創というより、ある物語の定型が主要には聴衆の興味関心に沿って語られていったと記している。つまり、民衆に受けるような語り物であったということである。
明治になると、個の内面描写を獲得した西欧近代の波をかぶり、わが国にも近代小説の形式や表現が浸透してくる。現在から見渡すと、二葉亭四迷の『浮雲』辺りは当時としては斬新だったとしても表現としてまだ十分こなれていないし読みづらいが、夏目漱石の『こころ』辺りでは、現在の読者にとっても割と自然な表現になっている。そして、そうした物語の世界は、わたしたちが現実の様々な場所で活動し、生活しているのと同じように、物語世界の登場人物たちに関しても単に内面の描写に終始することなく、彼らの活動する物語世界の舞台背景や風物の描写を必要とし、伴っている。そして、そのことは地方と都市の落差から来る、聴衆(読者)のもの珍しさという興味・関心に答えるという面も併せ持っていた。
現在に近づくにつれて、このもの珍しさは薄れてきている。つまり、大都市や地方都市という都市の規模の違いはありつつも、この列島全体が都市化されて均質化されてきているからである。もちろん、現在でも大都市を中心にして新たなもの珍しさは絶えず生み出され、更新されてはいる。
遠い遙か太古から近代以前は、物語の舞台となる土地や風景の描写は聴衆(読者)に対してある強度を持っていたとすれば、それ以降現在に近づけば、物語の舞台となる土地や風景の描写は、無意味だと消失してしまうことはなく作品の中に相変わらず存在しているが、その強度はずいぶん薄れてきている。言い換えれば、わたしたちが作品を読むとき、そういう土地や風景の描写は流し読みのように読まれているのではないだろうか。
例えば、わたしの読書経験から言えば、よく知らない街の描写などは読み飛ばすことが多い。おそらく作者たちが東京などの大都市に居住していることが多いせいか、詩や物語の中でよく東京の街々などが描写される。わたしはそれらの街をほとんど知らない場合が多いから、熱心に読みたどるという気分になれない。また、文学にも村上春樹や吉本ばなななど極わずかながらグローバル化の波に乗って世界中に読者を持っている作者たちもいる。この場合、作者たちは、読者のわたしが作品の中の東京などの知らない街の描写を読み飛ばしたというようなことを表現の問題として繰り込み、今度は世界中のファンに対する配慮として描写の有り様を考えていくことを強いられているのではなかろうか。これ以外にも先端を行く作者たちは、様々な具体的な自己配慮と表現の工夫を促されているのではないだろうか。
ここで、現在の二つの作品から土地や風景の描写に当たるところを取り出して考えてみる。
① (引用者註.名古屋から東京の大学へ出て来て)
しかしつくるのまわりには、個人的に興味を惹かれる人物が一人も見当たらなかった。高校時代に彼が巡り合ったカラフルで刺激的な四人の男女に比べれば、誰も彼も活気を欠き、平板で無個性に見えた。深くつきあいたい、もっと話をしたいと思う相手には一度も出会えなかった。だから東京では大方の時間を一人で過ごした。そのおかげで前より多く本を読むようになった。
「淋しいとは思わなかったの?」と沙羅は尋ねた。
「孤独だとは思ったよ。でもとくに淋しくはなかったな。というか、そのときの僕にはむしろそういうのが当たり前の状態に思えたんだ」
彼はまだ若く、世の中の成り立ちについて多くを知らなかった。また東京という新しい場所は、それまで彼が生活していた環境とは、いろんなことがあまりに違っていた。その違いは彼が前もって予測した以上のものだった。規模が大きすぎたし、その内容も桁違いに多様だった。何をするにも選択肢が多すぎたし、人々は奇妙な話し方をしたし、時間の進み方が速すぎた。だから自分とまわりの世界とのバランスがうまくつかめなかった。そして何より、そのときの彼にはまだ戻れる場所があった。東京駅から新幹線に乗って一時間半ほどすれば、「乱れなく調和する親密な場所」に帰り着くことができた。そこは穏やかに時間が流れ、心を許せる友人たちが彼を待っていてくれた。
(『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』P27-P28 村上春樹 文藝春秋 2013年)
この簡潔な描写から、外国の読者が読んでも地方の名古屋から大都会の東京に出て来た「つくる」という主人公の境遇や内面に引き起こされる戸惑いなどの波紋はすっと理解できるだろう。むしろ、作品の重力の中心は、夏目漱石の『こころ』と同様に、主人公つくるを巡る人と人とが関わり合う世界の物語に置かれていて、その地平では色合いや感触の違いがあっても、現在を共有する世界共通性として外国の読者にも受け入れられるのかもしれない。普遍的に語れば、この作品のモチーフは、利害関係を意識する以前の無償性の少年期、その関係の有り様から大人の世界に入り込んでいく時期の、誰にも訪れるある喪失と移行に置かれているものと思われる。
(引用者註.主人公多崎つくるは、東京の大学を出て、東京の鉄道会社(設計の仕事)に勤めて十四年ほどになる。この日沙羅と出会って用件を済ました後)
さて、どこに行けばいいのだろう?
結局、行くべき場所はひとつしかなかった。
彼は大通りを東京駅まで歩いた。八重洲口の改札から構内に入り、山手線のホームのベンチに座った。そしてほとんど一分おきに次々にやってきて無数の人々を吐きだし、また無数の人々を慌ただしく呑み込んで去っていく緑色の車両の列を眺めて、一時間あまりを過ごした。彼はそのあいだ何も考えず、ただその光景を無心に目で追っていた。その眺めは彼の心の痛みを和らげてはくれなかった。しかしそこにある反復性はいつものように彼を魅了し、少なくとも時間に対する意識を麻痺させてくれた。
人々はどこからともなく引きもきらずやってきて、自主的に整った列を作り、順序よく列車に乗り込み、どこかに運ばれて行った。かくも多くの数の人々が実際に(「実際に」に傍点)この世界に存在していることに、つくるはまず心を打たれた。そしてまたこの世界にかくも多くの数の緑色の鉄道車両が存在することにも、同じように心を打たれた。それはまさに奇跡のように思えた。それほど多くの人々が、それほど多くの車両で、なんでもないことのようにシステマティックに運搬されていること。それほど多くの人々が、それぞれに行き場所と帰り場所を持っていること。
ラッシュアワーの波がようやく引いた頃、多崎つくるはゆっくり腰を上げ、やってきた列車の一台に乗り、うちに帰った。心の痛みはまだそこにあった。しかしそれと同時に、彼にはやらなくてはならないことがあった。
(『同上』 P149-P150)
引用した部分の「彼は大通りを東京駅まで歩いた。八重洲口の改札から構内に入り、山手線のホームのベンチに座った。」は、途中の道筋や風景を細々と描写することなく、とても簡潔な描写になっている。そして、描写の中心は、その後の「心の痛み」を抱えた主人公つくるが、駅のベンチに座りながら眺める光景や、そこからこの世界の有り様に思いめぐらすということに置かれている。この描写は、東京駅でなくて外国のどこかの駅でもいいし、そういう場面で人がある思いを抱えていて、もの思いするということは、世界普遍性を持っているのではないか。つまり、外国の読者でも自分の生活する地域に変換して十分に読み味わえると思われる。ただし、この作品の場合、時間を持てあました主人公つくるがなぜ東京駅にやってきたのかは、この日沙羅と出会って用件済ました場所が東京駅に近かったということや、余り遊び歩くこともなく割と内向的なつくるの性格や電車や鉄道に愛着を持ちつつその種の仕事していることから、必然的に東京駅に吸い寄せられたということであろう。
② (引用者註.教育実習生で熊本にやってきたあや子先生に、構って欲しくて仲良し三人の二人が悪戯したり無礼を働いたりしたので、中一の春休みに謝りがてら大牟田に住む先生に会いに行く話。本心としては、友達三人で遠出する心躍りのある、久しぶりに先生に会うのを楽しみとした旅行であった。)
銀水行きの普通電車は、午前一〇時半すぎに熊本駅を発車した。日帰りとはいえ中学生だけで県外に出るのは初めてだった。気持ち弾んで、浮かれるのがあたりまえだのに、どうしたことか三人とも言葉少なだった。たまらずぼくは車窓を引っ張りあげて、外の風を迎えいれた。ここは無人駅だろうか。ひとけのないホームに〈田原坂〉の駅名を掲げた看板がぽつねんと立っている。西南の役の古戦場。各停が大牟田に到着するまであと三十分はゆうにかかるだろう。
大牟田の景色は熊本とはずいぶんようすが違った。
白っぽい色あいの町並みを縫うように国鉄の引込み線が何本も走っている。鋳物かなにかの工場だろうか、煉瓦造りの古い建物が目立つ。とくに赤白だんだらに塗られた集合煙突は熊本ではお目にかかれないものだった。
(『春休みの友』【Ⅱ】イワシ タケ イスケ
http://kp4323w3255b5t267.hatenablog.com/entry/2015/03/24/%E3%80%8E%E6%98%A5%E4%BC%91%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8F%8B%E3%80%8F )
特急の通過待ちで停車中の窓を開いて、ぼくは水気をたっぷりと含んだ風に顔をさらした。福岡の雨が熊本まで追いついた。ただしいまは霧雨だ。ホームの看板に〈木葉〉と記されている。駅のすぐ裏手に小高い山が迫り、石灰質の山肌をあらわにしている。午後五時過ぎの空には夜の帳が降りて、稜線との境目は判然としない。
(『同上』【Ⅴ】 )
この二つ目の作品は、村上春樹の対象とした少年期から青年期への移行の時期より前の、誰も通り過ぎてきた、また時折その時期を思い起こし反芻したりする、少年期を対象としている。
わたしは熊本に数年居たせいでこの路線の電車には何度か乗ったことがある。降りて歩き回ったわけではないけど、〈上熊本〉や〈田原坂〉などの駅名もわたしの耳には親しい。しかし、鈍行の普通列車じゃないから、あれと思う駅名があった。〈木葉〉(このはえき)もその一つで、調べてみると「熊本県玉名郡玉東町大字木葉にある」らしい。またわたしの奥さんの実家が熊本であるから、この玉名の町並みは車でも何度も通り過ぎていて、玉名という名前には少しなじみがある。しかし、〈木葉〉からの眺める風景はわからない。
このように読者に親しい街や駅や地名の描写があれば、作品はいっそうその読者に身近になるような気がする。肌合いの感覚として描写が具体性を帯びて感受されるはずである。作品というものは、作者が紡ぎ出す幻の物語世界であるけれども、それを肌合いの感覚として現実化するのは、作者の表現力であり、また他方では読者の感受する力である。わたしが読み飛ばすことの多い、作品の中の東京の街の描写に感じることと同じことを、この熊本からその県境にある福岡県の大牟田に渡る地域を物語の舞台にしたこの作品に対して、これらの地を知らない読者たちは感じるのではないだろうか。もちろん、このような街や風景の描写は、現在にあっては特にささいなことかもしれない。つまり、作品世界の本質にはそれほど深く関わっているわけではない。しかし、そういう街や風景などの場(舞台)がないと、物語世界は十分に駆動したり、展開したりできないことも確かである。
この作品は、少年たちの、「気持ち弾んで、浮かれ」たり、気持ちが沈んだり、また立ち直ったりと、それぞれの性格の違いはあっても、少年たちの関わり合う世界とその固有の曲線を描いていく。大人より、低い視線の見つめる世界。通り過ぎてしまったら、その現場の鮮度が色あせてしまってもはや生き生きとは出会えないような世界。こんな少年期には、汲み尽くせない何かがあるから、作者たちはくり返し発掘を試みるのだろう。
この作品では、残念なのは、おそらく作者は読者へのもてなしとしてそこに力こぶを入れたのだと思われるが、芥川龍之介の「羅生門」などのように作者たちが作品世界に登場したりして、作品の舞台裏が明かされながら物語が進行することである。わたしにとっては、物語の進行と起伏をはぎ取るような、ちょっと邪魔くさい感じで受けとめられた。むしろ、虚構の作品として、物語の舞台の中枢に降り立って、少年たち固有の曲線を描いていき、そこから浮かび上がるものに作品世界を絞り込んでほしいと思われた。
もう今では「車窓を引っ張りあげて、外の風を迎えいれた」りできる電車ではないかもしれない。時代は変貌し風物も変化していく。しかし、人が生まれ育ち成人となり老いてゆくという固有の曲線は、時代や風物が変貌してもある不変な相であり続けている。
最新の画像[もっと見る]
-
 最近のツイートや覚書など2024年3月
2週間前
最近のツイートや覚書など2024年3月
2週間前
-
 最近のツイートや覚書など2024年3月
2週間前
最近のツイートや覚書など2024年3月
2週間前
-
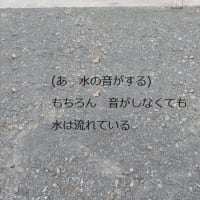 水詩(みずし) #1
3週間前
水詩(みずし) #1
3週間前
-
 農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前
農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
2ヶ月前









