「男と男の約束だ」
【武士道 新渡戸稲造】 なぜ「武士に二言はない」のか?
テーマ:武士道の言葉
武士にとっての「言葉」は、
一言一言に命が宿り、軽はずみな発言は、
武士としての弱さと思っていたようです。
だから、武士の言葉はかっこいいんですね。
■武士道 新渡戸稲造
「誠」 ――なぜ「武士に二言はない」のか?
・真のサムライは「誠」に高い敬意を払う
嘘をつくこと、あるいはごまかしは、等しく臆病とみなされた。
武士は自分たちの高い社会的身分が商人や農民よりも、
より高い誠の水準を求められていると考えていた。
「武士の一言」、
あるいはドイツ語でこの言葉の同義語にあたる「リッターヴォルト」は、
断言したことが真実であることを十分に保証するものであった。
このような語句があるように、
武士の言葉は重みをもっているとされていたので、
約束はおおむね証文なしで決められ、かつ実行された。
むしろ証文は武士の体面にかかわるものと考えられていた。
「二言」、つまり二枚舌のために死をもって罪を償った武士の壮絶な物語が数多く語られた。
(中略)
偽りの証言をすることに対する何らかの積極的な戒めがない中で、
嘘をつくことは罪悪として咎められたのではなかった。
むしろ弱さとして批判された。
そして、弱さは大いに不名誉であった。
言葉に重みがあるというのは、
約束を守るということであり、
有言実行するということ。
そして、余計なことは言わない。
武士としての自覚が、このような誇り高い精神を育んだのでしょう。
自覚が言葉になって現れ、
言葉が自覚を深めます。









----------------------------------
「腰の骨を骨折してね。これまでの人生を色々振り返ってね」
「そうでしたか。大変でしたね」
「君には、色々お世話になったね。何とか恩返しもしたいと思っているのだけれど、こんな身になって、それどころではない」
「恩返しなど、必要ありません。1日も早く腰を治して、復帰してください」
「そのことなんだが、娘にも言われてね。引退しようと思ってね」
「引退ですか!まだ、引退は早いですよ。これかま協力は惜しみませんから、一緒にがんばりましょうよ」
「ありがとう。そんなふうに言ってくれるのは、君だけだ。ありがとう。本当にこれまで、ありがとう。助かったよ。取材先の日程を毎回、知らせてくれたのは君だからね。本当に、本当に感謝しているんだよ」
「いいえ、たいしたことはしていません」
「君がいたから、今日まで来られた。本当に感謝している」
「いいえ。大したことはしていません」
「そうじゃない。ありがたかったよ。逐一、取材の日程を知らせてくれて、君以外はとてもできないことだったよ」
「・・・・」
「娘は“お父さん、もう十分でしょ”と言うんだ。確かにもう無理はできない。歯科記者会も引退届けを出そうと思っているんだ」
「引退ですか?もったいないですよ!」
「そんなふうに言ってくれるのは、ありがたい。だが、もう私は年なので引退だ」
「伝統ある社歴が消えるのは、もったいないですよ」
「結局、後輩が育たずだ。消えるもの仕方ない」
「もったいないですね」
「もったいないなどと、言ってくれるのは君だけだ。消え去っても仕方ないことだ」
「社名を残せませんか?」
「残す?」
「そうです。私が会社を継承できませんか?」
「君が?」
「そうです」
「そうか、君が継承してくれるのか!ありがたい!そんなことまで今まで、考えてもみなかったことだ。君がやってくれるのか?」
「ハイ!譲ってくださるのなら是非、継承したいです」
「そうか!継承してくれるのか?本当なんだね?!」
「本気です!」
「では、好きなようにやりなさい。日本歯科医師会、東京都歯科医師会、日本歯科技工士会へは、私から君が継承者だと電話で伝えておくからね。好きなようにやりない」
「あくまで私は編集の責任者であり、生涯、大坂さんが社長です」
「私のことは、もういいから、君は社長でも編集長でも名乗りなさい。まず、名刺を作り挨拶回りが先決だよ」
「いいえ、あくまで大坂さんが社長であることに変わりはありません」
「好きなようにしない」














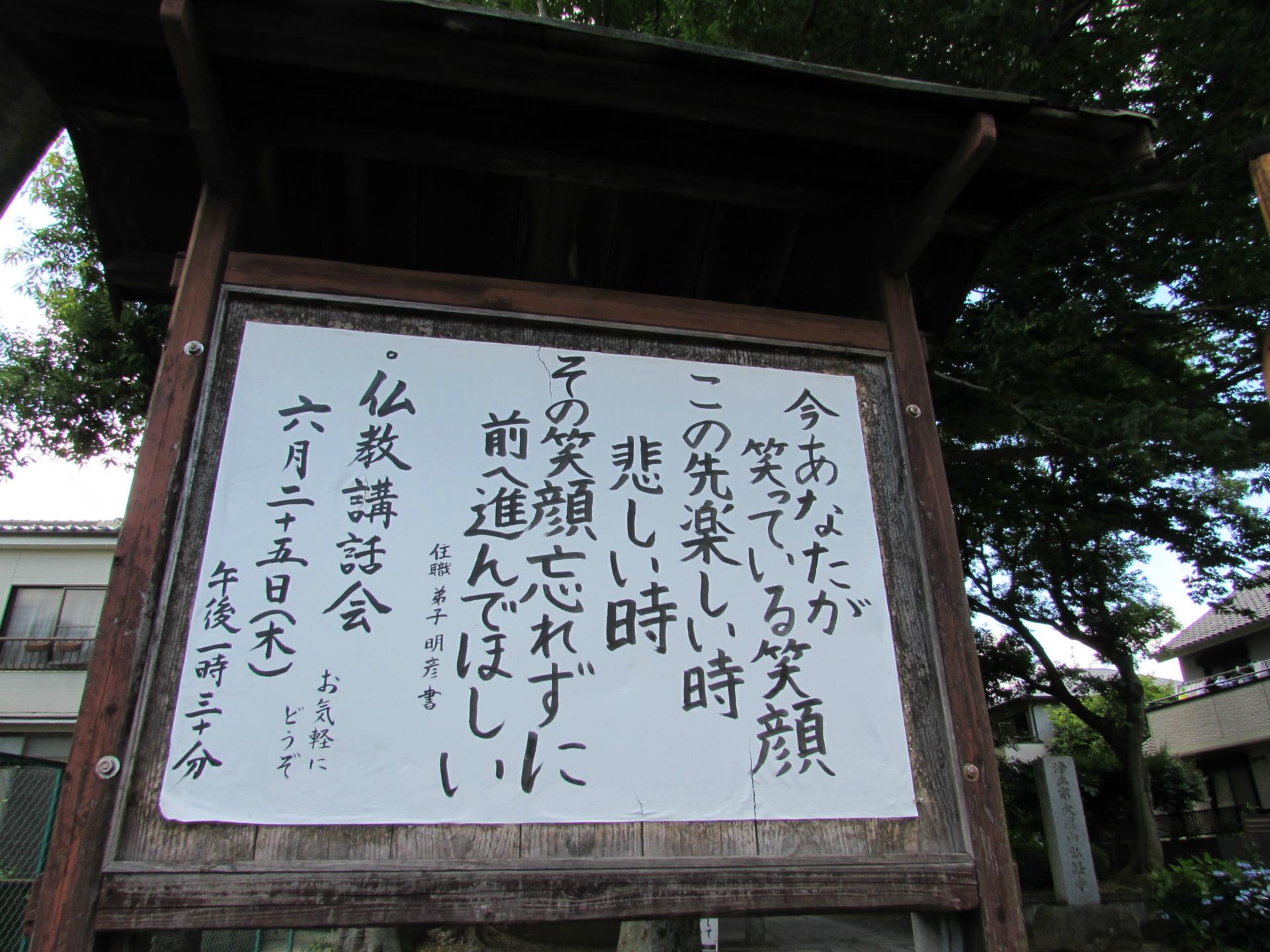















 近現代の沖縄の歩みは、自立を求めて苦闘する不断の歴史だ。
近現代の沖縄の歩みは、自立を求めて苦闘する不断の歴史だ。














































