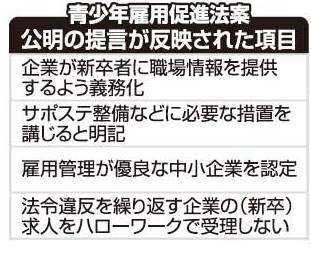「地方創生」は、国替えともいえる大転換事業。
国民もどれだけ当事者として関われるかが問われる。
「地方分権推進法」ができたのが1995年。
地方が国に逆らえたのは、この法律ができたこと。
地方への権限委譲が形式的には進んだが,
「住民自治」がごこまで進んだかである。
“依存から自立へ”という地方自治の時代を迎える。
2008年から日本の人口が減少に転じた。
このため地方自治の力が本当に問われてくる。
地方自治体の首長、議会、公務員である職員、彼らの考え方が本気で依存型から自立型のかわらないとダメだ。
本質的に変わったとことこそが生き残り、将来を展望できる。
成長時代は中央集権体制でもよかった。
しかし、もう成長による果実で社会福祉や地方政策が賄えなくなってきている。
超高齢化社会に突入し、医療、介護、福祉を包括した地域でのケアを自治体で回していかなければならない。
国には国の役割がある。
県や市町村がどういう負担をしていくか。
そういった具体的な積み上げが「地方創生」で問われ始める。
もはや財政に頼った行政というのは困難。
必要なことは地域の知恵や民間の力をどう引き出すかだ。
特に東京の一極集中に歯止めをかけ是正する。
今や貧困率が若い世代で16%くらい。
6人に1人は貧困家庭で育っている。
若者や片親の家庭がそれなりの所得が得られる仕事場を、地域にどう作りだしていくか。
これらは「地方創生」の本質につながる。
一人でも能力を持った人間がたくさ増えれば行政も変わっていく。
人材募集、選別、訓練が必要。
「地方創生」には、利益誘導から政策優先の選挙への転換が求められる。
地方政治は「実績重視」の時代へ。
予算配分は、従来の「陳情型」から「企画提案型」になってきた。
東日本大震災を経て、有権者の地方議員を見る目も変化した。
「期待重視」から「実力重視」「実績重視」へ確実に変わってきた。
「地方創生」のためには、地方議会、地方議員が旧態依然の議員像を脱却して、高度な政策提案を行える存在へと成長しなければならない。